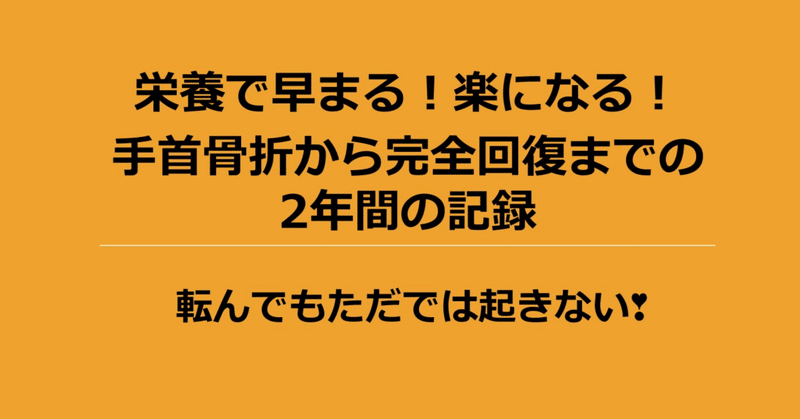
手首骨折完全回復までの2年間の記録 ―転んでもただでは起きない❣️―
2022年の1月6日から7日にかけての雪で、アイスバーンになった自宅前で滑って転んで右手首を骨折(全治3か月:実質2か月と10日)しました。橈骨遠位端骨折と言うみたい。
骨折をして改めて気づいたり感じた体のことや栄養のことがたくさんありました。
アラ還で、利き手首の骨折をどのように回復させたかまとめた2年間の備忘回復記録です。
リハビリの状態など、追記しながら記録してあります。(長文です笑)
なぜこんなブログを書いたかと言うと、整形外科的な栄養療法(分子整合栄養医学)の視点の書籍やブログ、アドバイスを探しても、ほとんど見つけられなかったからです。
アラ還でも、骨折から早期に回復させることができる。回復を早めるにはコツがあると、実体験から感じたので、まとめておこうと思った次第です。
どうせなら、早く治したいですものね、骨折を早く治したい方のお役に立てれば幸いです。
※途中レントゲン写真あり、閲覧注意です❣️
骨折の経過
1.骨折
生まれて初めて骨折したため、折れたのか捻挫かわからない。骨折すると腫れると聞いていたので、様子を見ていました。
雪の明日は裸で洗濯ってくらい、翌日は晴れると相場が決まっているので洗濯を済ませており、あとは干すだけだったので、右手首をかばいながら洗濯物を干していたのですが、だんだん手首がぶらーんとしてきて痛みが出てきて腫れてきました。あ、これ絶対折れたなと、整形外科へ。
骨が折れてズレていたので、先生が手とひじを両方から引っ張ってズレを治してくれました。痛いのなんの。
竈門炭治郎ではないけれど、ゆっくり吸って、吐いて~とここで深呼吸が役立ちました。
でも、「人間の体って伸びるんだ~・・・」なんてどこか冷静に感心している自分もいました。
安静1か月、全治3か月という診断でした。ギブスをして、痛み止め1週間分いただきました。トホホ。
指先だけは、ぐーぱーよく動かすように、腕を心臓より上にあげておくようにという注意を受けました。
利き手の手首が使えないショックね。正月はタップリ休んで明けに始めようとパソコン作業をたくさん溜めてあったけれど、できません・・・
ショックとか、妙な疲れでぐったり眠くなり、2~3日は抑うつ状態。
キューブラー・ロスの五段階 (「否認」→「怒り」→「取引」→「抑うつ」→「受容」という5つの心理的段階を経て、人は死を迎えるという説)のような心理状態を短期間でやった気がします。
数年前(栄養を学ぶ前)までは、痛みに異常に弱く、すぐに痛み止めを飲んでいた自分からは想像できないけれど、骨折当日医者から帰宅後、一錠痛み止めを飲んだきり(ひどい痛みで飲むというより、これから痛みが来るのかなと予防で一粒)。でも、その1粒だけで、それ以降痛み止めいらずでした。
翌週の診察時、先生に「1週間、痛かったでしょう。」と言われたけれど、「いえ、全然大丈夫でした。痛み止めも一錠飲んだだけで、あとは飲まずに生活できました。」と伝えると、結構驚かれました。
4年ほどタンパク質をしっかり摂るよう、栄養に気をつけてきて、どうも痛みに強くなってきているようなのです。
2.足湯と手浴
骨折2~3日後、高齢者施設を営んで、看護師でもある姉から「足湯が命を救うってよ!」と連絡があり、東洋医学では骨を打つと臓器に影響するという視点があることを教えてもらいました。「転倒のショックで自律神経が緊張して、臓器や体温や血圧に異常がなどがおこったり、認知症を発症したり、生命にかかわることもある」とのこと。そして足湯が命を救うというのです。この情報を教えてもらってから即座に足湯を始めたというわけです。
高齢者はよく転ぶから、いろいろな情報を持っているようなので、速攻足湯を始めました。
足湯は体全体が温まり、緩みます。ショックや脳、腎臓の働きに良いというので外せません。手浴はダイレクトに骨折部分の痛みや違和感軽減している感じがしました。
【足湯】
朝,足湯20分してみたところ、効果絶大でした。体全体が温まり,緩みます。体が動くので気分もよくなりました。
最初1か月は,ラベンダーのアロマオイルを入れてリラックスして足湯をしました。
その後,塩化マグネシウムを入れて足湯・手浴するようになりました。


【手浴】
手浴は、足湯をしているバケツに、足と一緒に手を温めたり、手だけお湯につけたりして手浴です。
手浴ができない忙しい日は,洗面所の蛇口のお湯を手首にかけ流してあたためました。
手浴は、骨折部分の痛みや違和感軽減に役立ちました。

足湯を始めたことで、自分で治す意識が強く芽生えました。そして、抑うつ状態から抜け出し、骨折を自分の中で受容できるようになりました。
3.驚異的に回復させるぞ!という意識
受容できるようになると、「驚異的に回復させるぞ!!」と意識が芽生え、回復のための情報を探しだしたり、せっせと栄養を盛り込み始めました。
栄養療法で整形外科的な発信している医師はほとんどおらず(知る限り)、書籍を探しても見つからないの。トホホ。
整形外科的な栄養療法の本は「寝たきりを防ぐ『栄養整形医学』骨と筋肉が若返る食べ方」[1]だけ持っていたから、もう一度読み直してみました。まさに「ビタミンCが骨折に効く!」[1]って章があるじゃない!骨折はビタミンCで回復が早いんだ~🥰

大友先生の講演ビデオも再視聴。
やっぱりビタミンCとタンパク質じゃん!ということで、改めて骨折のための栄養補給。
骨の材料がなければ、骨がくっつかないだろうから、主にコラーゲンや骨になる栄養盛り盛り。
プロテインも少しずつ入れてタンパク質を盛りました。プロテインは腸内環境を荒らす人もいるから、使うなら少しずつ薄めにするのが吉。
高濃度ビタミンC点滴やっているところが近所にないのよね。残念。ビタミンCはサプリを活用。
マグネシウムや骨を強くするのはビタミンD。抗酸化の栄養もね
あとはマグネシウム風呂(後述)で緩むこと。足湯も頻繁にしました。
【3週間目】
相当骨折したあたりが炎症を起こして内出血しているのか、3週目くらいにめまいやふらつきがあったので、血液検査もしていただきました。フェリチンも赤血球も鉄も下がっていました。
貧血を感じてからは、炎症もあるため、鉄は食事でカバーしようと赤身肉やレバー、カツオなどをせっせと食べました。
ちなみに、骨折から2週間で鉄の指標の一つであるフェリチンがめちゃくちゃ下がっていました。びっくり!!
4.へバーデン結節
指が腫れたり、ギブスをしている腕が重く、肩が痛くなったり、いろいろ体への影響や変化も感じました。
右手の中指、薬指あたりの第一関節がふくらんで痛かったので、もしかしたらリウマチか。それともプロテインに含まれるカルシウムが多いからマグネシウム不足になっているのが原因かと思って診察時に先生に聞いたら、ヘバーデン結節ということでした。確かに第一関節のあたりのふくらみが大きかった。
炎症が起きているときは、テーピングして動かさない方がよいとのこと。女性ホルモンの影響もあるらしいので豆乳がおすすめとのことでした。
豆乳は、豆腐を摂っているからよいとして。
たぶん、カルシウムとマグネシウムの比率が崩れているのだろうと推測しました。カルシウムとマグネシウムの比率(カルマグ比)は2:1と言われていましたが、最近では、マグネシウムの摂取が大幅に不足しているため、1:1とも言われています。
そこで、牛乳を摂ることになるカフェラテはやめて、紅茶やアーモンドミルクラテにしました。さらに、マグネシウムをいつもより多く摂取するように心がけました。グルテンフリーはやっているので、小麦の問題はクリア。
ご飯ににがりやぬちまーす塩を入れて炊くことはもちろん。マグネシウムのサプリのほか、にがりを白湯に垂らして飲んだり、にがりで歯磨きしたり。口からも摂取し、お風呂で経皮からも摂取するようにしました。
ドイツの友人もカゼインとグルテンフリーでへバーデン結節のような関節の痛みが良くなったと教えてくれました。
一週間もすると、テーピングは不要になり、現在はヘバーデン結節だった?というくらい、第一関節の痛みはまったくないし、腫れもありません。
マグネシウム湯やお湯で温めてから、マグネシウムクリームを塗って、グーパーや、やっていい動きはゆっくり丁寧に行って自分でリハビリを進めました。
マグネシウムクリームについては以下のnoetにまとめています。
5.ギブスがとれる
【1か月目(4週間目)】
骨折4週間目でギブスがとれました。
「栄養をいくら入れても、日柄が必要ですよ」と先生に言われ、ちょっとがっかり。でも、絶対材料になる栄養がなければ、治りは早くならないはずと思って、さらにしっかり食べて、せっせと栄養盛りました。
映画「ホノカアボーイ」観たことがありますか?
映画館のおじさんが骨折して、ギブスがとれて大喜びしていたら、また骨折してしまったのですね。映画館のおじさんみたいににならないように、大喜びしすぎず落ち着いて喜ぶよう、ちょっと気をつけました笑
【1か月と1週間目】
ギブスを外して不安なので、サポーターを付けてみたけれど、サポーターをしていると手を使わなくなってしまい、2日間使わないと腕が固まる感じがしたので、サポーターは外出時だけにしました。
小学生の子どもたちのお勉強をサポートしているため、小学生との接触が多く、久しぶりに会った子が飛びついてきて、一緒に転びそうになるとか、「ここどうしたの?」なんてギブスを触られる、なんてことも頻繁でしたので、サポーターで怪我していることを可視化しておく必要もありました。笑
右手の爪が伸びません!!。特に薬指。こんなことがわかったのは初めてです。
きっとタンパク質も鉄もビタミンもミネラルも爪まで行き届かないのだろうな。こういう観察が栄養を盛るバロメーターになりました。
6.マグネシウム風呂
ギブスがとれて、お湯に右手を付けられるようになって初めて塩化マグネシウム入りのお風呂に入ったとき、ぱちぱちと皮膚からマグネシウムが入るような感覚がありました。痛かった関節もマグネシウム湯に入ると痛みが軽減するのがわかりました。
マグネシウムすごい!

手首を前に曲げたり後ろに曲げたり、左右に曲げるなど、自分でリハビリして回復に向けました。これもただのお湯のお風呂より、マグネシウムのお風呂に入りながらが一番楽ちん。
ちなみに、マグネシウム風呂にするためには、バスタブにカップ2杯~3杯くらい、たっぷりの塩化マグネシウムを入れました。
冬は、特にお風呂は7分×2回くらいマグネシウム湯につかっていると、就寝中の痛みが違う気がします。
「塩化マグネシウム」や、「エプソムソルト」、「死海の塩 Dead Sea Salt 塩化マグネシウム」等、色々試しました。コスパが良いのは塩化マグネシウムの大袋。
死海の塩 Dead Sea Salt 塩化マグネシウムは、とても温まるので冬にお薦め。
温まり方が半端でないのは「薬用浴剤マグマオンセン 別府(海地獄)」です。色もマリンブルーで香りも良く、残り湯を洗濯にも使えるという優れもの。これは本当にポッカポカに温まって、温泉に行った気分。これホントお薦めです。

お風呂上がりや痛いとき、痛みがあるところに、にがりやマグネシウムオイルをぬりました。マグネシウムオイルは塗るとチクチクするので、マグネシウムクリームの方が個人的には良かったです。

マグネシウムの効果やカルシウムとマグネシウムの関係[2]もいろいろ情報を探して読みあさりました。
7.胃腸炎と花粉症vs骨折
ギブスを取ったら、腕が痩せてガリガリになっていました。
花粉症と血糖値スパイク防止策として糖質を少しコントロールしていましたが、怪我からの回復には、肉も筋肉もつけなければいけないので、糖質(ご飯)もしっかり食べました。
花粉症より骨折の回復が最優先事項。
でも、結局、糖質もパンやスイーツなど主に小麦や砂糖が入ると花粉症が悪化していることを感じました。
また、コーヒーやアルコールも刺激になりました。また、ビタミンDを摂っていなかったことが花粉症悪化させていたのだと思い当たりました。
だから、糖質は、小麦ではなくお米が吉。
そして、糖質(ご飯)は一度に食べずに頻回にしたり、べジファ―ストで野菜を先に食べたり、ボーンブロススープやタンパク質を食べてからご飯を食べるようにすれば、血糖値の問題もクリア。
花粉症が酷いときはビタミンD+Kで対応。ビタミンDもKも骨の強化にも関係するから、骨折にも外せない栄養素なのだ。
ビタミンDを多く摂るとカルシムが沈着して石灰化するという情報があり、花粉症で調子に乗ってビタミンDをたくさんとったら、へバーデン結節のように関節が痛くなったことがあり、その時はマグネシウムを摂って良くなったことを思い出し、マグネシウムはサプリも使い、マグネシウム風呂で経皮からも摂るよう気をつけました。
腕は動かせないから腕以外から筋肉つけていこうと思い、運動はスクワットをしたり歩いたりして少しずつ行いました。
回復途中、一回胃腸炎にもなりました(冬だから仕方ないね)。
胃腸炎はボーンブロスと少しずつのグルタミンやプロテイン、ビタミンCなどで回復。
食欲が落ちれば、栄養が落ち、怪我の回復も長引くことを感じました。
胃腸炎が治ってから、またしっかり栄養盛り盛りにしました。
8.骨がくっついて、通院終了
【2か月と10日】
もう普通の生活をしてOK、通院も終了となりました!

骨折線はアップにすればまだ見えるものの、骨と骨をつなぐ橋のように見える線(仮骨形成というのでしょうか?)がたくさん走っているのが見えるので、もう大丈夫なのだそう。
7.5キロのファンヒーターを持ち上げて、数日間違和感があったことを伝えると、重いものをもって違和感があったら、少し使わず静かにしてあげると治るとのアドバイス。2~3日たっても痛みが取れずおかしいようだったらまたいらっしゃいとのことでした。
重いものを持つとどうしても手首をかばうため、肩や二の腕が痛むので、そういうときは、休めてあげて徐々に慣らしていきました。
手首の骨折完治まで2か月と2週間は、私くらいの年齢(アラ還)では、かなり驚異的に完治させた方だと主治医に言われました。☺
そういえば、ギブスをしているとき、駅のお掃除のおばさん(たぶん同じくらいの年齢の方🥰)に「私も去年の7月に左手首骨折したのよ。」と声をかけられました。その日は「お互い気を付けて頑張って治しましょう!」と別れました。たまたま3月に再会できたときには、まだリハビリに通っているけれど、中指が曲がらないし、まだとても痛いとのことでした。8カ月も痛いのはつらいですね。
おばさんに、栄養のことを少しお話したら、「私は、マグネシウムもタンパク質もビタミンCも、全部足りていないわ。」っておっしゃっていました。
そう考えると、やはり日柄だけではなく、栄養の入れ方と、リハビリのコツも回復大事な要因だったと思います。知っていてよかった!分子栄養学(栄養療法)。
【2か月と2週間目】
使わない腕は重いし、リハビリはゆっくり時間がかかるのだな。
パソコンをしていても、右手が重くてだるくなるときがしばしばあります。
腕って重いのよね。肩と二の腕に、筋肉痛や慢性炎症的な痛みがある。
炎症があると感じているときは、右手で重いものをもったり、あまり無理をしないようにしていました。肩に湿布を貼って、この頃は、ビタミンCやスカベンジャー(抗酸化)のアスタキサンチンなどを気を付けてとっていました。
DHAは痛みを抑える物質の材料にもなるというので、魚も大事。痛みを抑える物質は、春菊にも多いそうです。魚+春菊=お鍋。最強ですね。
「EPAには炎症を抑える作用」[1]があるのだそうです。大友先生によると、EPAが少なくなれば、炎症を起こしやすくなったり、治まりにくくなるのだそうです。だからEPA不足が「長引く痛みやけがの治りにくさ」につながっているのだそうですDHAにも抗酸化作用があるとのこと。
DHAとEPA、オメガ3系脂肪酸なども必要なのですね。
夜寝ていても、腕が重だるくなって眠りが浅くなる日々。そのたびに手をグーパーしたり、寝返りを打って、体勢を変えます。
痛みのある箇所を触るとそこだけ不思議に冷たいので手を当ててみました。冷たい箇所が温まるととまた眠れました。お手当てもやっぱり大事❣️
冷えると痛いから、1日ホカロンをあてた日もありました。やはり温めると痛みが楽になりました。
寝ていても肩が冷えないよう、肩用の半そでのウールのボレロみたいな肩当て(肩ウォーマー、肩サポーター)のを母が貸してくれたので、夜はパジャマの下にそれをして寝て、肩を冷やさないようにしています。
なんとなくしびれて、重い、だるい腕には、マグネシウムクリームを塗ったらだいぶしびれが良くなりました。お風呂上りや朝など、気になったときに塗っています。

眠りが浅い翌日はナイアシンアミド(ビタミンB3)で、結構ぐっすり眠れる日も増えてきました。
掃除のときに、またファンヒーターを右手で持ち上げてみました。今回は違和感1日。回復していることを感じます。念のため湿布を貼って、違和感のある間は少し大事にしました。
真綿を剥ぐようにじわじわよくなっていくことを感じていました。
9.仕事と食事
小学生の子どもたちにお勉強をサポートする仕事もしていますが、ギブスの上からデコピンされたり、走り回ってぶつかったり、骨折の身にとっては、体張る仕事笑。結局骨折4日後の一度だけお仕事お休みしてしまった。

みんな、お見舞いのお手紙くれたり、いろいろお手伝いしてくれて助かりました。ありがとう💛
利き手首の骨折のおかげで気づいたことも多かったです。
引っ張る、押す、ふたを開けるときに使っている力、鍋や水をはじめさまざまな物の意外な重さ。体の部位の連携、化粧(アイラインなど)の細かい作業の難しさ、けがや病気のときのメンタルの変化、人の親切、家族のありがたさなどなど。
買ってくれば楽だけれど、この状態で添加物やら糖質入れて、回復を遅らせたくないなと思っていたら、週末になると、子どもがめいっぱい常備菜の作り置きしてくれて、早く回復するようサポートしてくれました。あとは魚やお肉をさっと焼くだけ。楽チン楽チン。
いつも以上に(笑)、とっても優しくされて嬉しかった☺


冷蔵庫には常に卵をたっぷりストック。
朝昼晩とお待ちかねで卵も食べました。味玉にしたり、温泉卵にしたり、完全栄養食の卵の栄養とタンパク質をたっぷり摂れるようにいろいろ工夫してくれました。

毎日のように、子どもにも食や栄養の話を毎日のように話し続けてきてよかった♪

いろいろ工夫して作り置きしていたおかげで子ども自身、料理の手際がよくなって、腕も上がりました。素晴らしい!
掃除、洗濯と料理と仕事、いろいろこなしてくれて本当にありがたかった💛
10.三浦雄一郎さんから学ぶ回復力
そういえば、三浦雄一郎さんの「65歳から始める健康法―心と体のメタボからの脱出(p.102)」[3]という書籍にも、骨折からの回復について書かれていたことを思い出しました。

76歳で骨盤と大腿骨の付け根を骨折した病院で、骨折の回復を早めるために、奥様に鮭の頭と身と骨を、こぶや生姜、クコの実など一緒に煮込んだ料理を作ってもらって病院まで届けてもらったとのことでした。
鮭の頭を一日一匹分ずつ食べて、サプリもとり、驚異的な回復を見せたそう。
鮭はアスタキサンチンという抗酸化の栄養素を持つ魚ですし、魚の骨から摂ったボーンブロスやサプリでミネラルがしっかり摂れたということなのね。
普段から骨密度を高めるために負荷をかけたトレーニングをしていた効果もあったとのことです。私たちなら、ビタミンD合成のために、日ごろからお日様たっぷり浴びてお散歩して日常的に骨を強くしておくことは必須ですね。
そして、「『病は気から』といいますが、気を強く持って、何が起こっても絶対に前向きに捉えることが大きな力を生むのだと思います。」[3]とも書かれていました。この辺りは胆力とレジリエンスに繋がりますね。
11.回復のための、胆力とレジリエンス
私が栄養を学ぶきっかけとなった、身内の怪我の時のペインクリニックの先生の言葉を思い出しました。
痛みでほとんど歩けない状態の時に、先生から「杖を使わず、足も引きずらず、ゆっくりでいいから、できるだけ今まで通り普通に歩く練習をするように」と言われていました。また「痛みに負けるな!」とも言われていました。「痛みに負けて歩けなくなった人をたくさん見てきた」とのこと。頑張って痛みに負けずにリハビリをすることが大事なのだ、その時に知りました。
肝心な時に甘やかすと体も易きに流れるということなのね。
最初に杖を使ったり、痛い方をかばって変な歩き方をすると、杖を持たないで歩けなくなるし、普通の歩き方に戻れなくなるのだそう。
「最初が肝心だから、きちんと歩きやすい運動靴をはいて、痛くても、ゆっくりでいいから、できるだけ普通に歩きなさい。」とのことでした。
「多くの人がこれをできずに、怪我の後、足を引きずるような歩き方になってしまったり、杖が必要になってしまう。」とも。
体を治すには、自分で治す!という気力や胆力が必要なのだと、そのときに思ったのです。
治すのは医者でも薬でもなく、自分なのです。自分で治すんだ!という胆力。大事。
また、落ち込んでいるときに急に流れてきた動画[4]が、奮起して頑張るきっかけになりました。
手足がなくてもあふれる笑顔で美しくお化粧して、お洒落して活動している女性の姿に勇気をもらいました。利き手が使えず、いろいろなことができないなどと甘えている場合ではないと反省。
できない理由ではなく、できる理由を考えるのだった!
落ち込んでもまた立ち上がる、これがレジリエンスです。
12.”レントゲンカーター(宿酔)” 放射線を浴びたときのだるさ対策
食にも気をつけて体調管理をしてきたここ数年なのに、今回の骨折でレントゲンを何度も撮ることになってしまいました。
最悪の時期の最優先は、骨をくっつけることだったので、そんなことも気にならなかったけれど、今、右手のだるい重いとか、骨折当初のだるさは、もしかしたらレントゲンで放射線浴びたからなのかもしれないと思うようになりました。
レントゲン・カーター(宿酔)放射線を浴びたときのだるさ対策[5]については、鍼灸マッサージ師で、栄養療法執筆家の鈴木加菜先生[6]が情報をシェアしてくださいました。
レントゲン・カーター(宿酔)は「レントゲン技師が、放射能を浴びたときにからだがだるくなる症状で、その際、生理食塩水より少し多くの塩分を含んだ水を飲ませる」[5]ということ。
対策としては、「塩、味噌」をとり、「そして甘いもの特に砂糖を避ける」[5]とのことらしい。
そんな話を母にしたら、胃腸科の医師をしていた母の友人のご主人は、レントゲンを撮ることが多いから、毎朝必ず10時に利尿作用があるコーヒーを飲むと言っていたと話してくれました。解毒を意識されていたということ。
毎日ご飯にぬちまーす塩やにがりなどを入れて炊き、しっかり海塩を摂っているし、味噌汁も必ず1日一回は飲んでいる。砂糖はもちろん、甘いものもほとんどとらない生活だし、利尿作用はお茶でとっているので、まずは、このまま続けて、腕のだるい重いを観察していきたいと思います。
やっぱり食と栄養の観点は、体の回復に外せない。
とりあえず、3か月近く経ち、まだ肩や腕、手首に違和感がある日もあります。スッキリと何事もなかったようになるには(なるのかな?笑)きっと時間が必要でしょう。
でも、あれこれ気を配るポイントをおさえると、よりよい回復につながることがわかりました。
13.裸足とアーシング
体に意識を向け始めると、レントゲン・カーターや電磁波も体に関係していると感じるようになります。
少しでも良い環境で、体を回復させたいものだと、アーシングもよく行うようになりました。


不思議なことに砂浜を歩いていたり、波に足を浸しているだけで体が楽になるのです。だから、できるだけ裸足になって、土や自然と触れ合うことも意識するようになりました。
2024年には、血流を上げるというマンサンダルも作ってみました。
現代社会では、避けることができない電磁波や自然からの距離。
人間も動物だからできるだけ土に近く、自然の中で自然に触れ合うのはとても重要なことだと、骨折をして改めて強く思いました。

14.療育整体で血流をあげ、自律神経を整える
療育整体[7]を学んで、基本の手技で、血流を上げることができるようになりました。そして次のステップである、自律神経を整えるセルフの手技も学びました。
血流が滞ると痛みが強くなるように感じましたので、血流を上げる手技は役立ちました。

また、どうしても骨折のストレスで、交感神経優位になりがちなので、副交感神経を上げて、自律神経を整えるのも、リハビリ中などにとても有効でした。
これもセルフでできるのが嬉しいです。
松島先生[7]は、施術もしてくださるし、療育整体師としてのトレーニングもしてくださるので、詳細は、発達キッズ協会[9]に問い合わせてみてくださいね[8]。
療育整体って何?って思ったら、以下のnoteを読んでみてくださいね。
他にも、自律神経を整えるのには、呼吸や瞑想もお薦めです。
心も体も脳も繋がっているので、緩めて楽にしていくと回復が早いと思います。
リハビリの経過
15.骨折後3か月からのリハビリの経過と食事や栄養
【3か月と1週間目】
日中、腕の重いだるいがなくなってきました。
朝はストレッチしてから起きるけれど、体が固まっていることがよくわかります。
肩の痛みもよくなってきたので、PCなどを入れて少々重いリュックサックも背負えるようになりました。
マグネシウム風呂で可動域を広げる動きを20秒ずつ2~4セット継続中。
お風呂上りのマグネシウムクリームも継続中。
湿布は不要にな日も出てきました。
夜、痛みや重みで目が覚めることはなく、ぐっすり眠れ日も出てきました。
怖くてできなかった、うつぶせになって体重をのせて手をつくことも、徐々にできるようになってきました。日柄とリハビリの大切さを感じています。
【3か月と3週、4週間目】
腕のだるい重いはなくなりましたが、まだ肩の痛みが時々あります。
痛みの頻度は、たぶん以前よりずっと少なくなってきていると思うのですが、治れば治るほど、以前の普通の状態と比べているのだと思います。
寝付いても何度か痛みで目が覚める日も、まだあります。肩の血流が悪そうです。
寝返りをうち、肩をマッサージしたり手を当ててあたためると、又眠れるので、寝不足になるほどではありません。
朝は、相変わらず少しストレッチして、上下左右に腕をのばしてから起き上がります。最初は肩が痛くて、顔をしかめるほどですが、起き上がって、顔を洗ったり朝食の支度をしているうちに、徐々に痛みを感じなくなります。無理な動きをしなければ大丈夫。痛みがある日は、湿布を貼っています。
でも湿布はかえって血流を悪くするという情報を聞いてから、湿布は貼らなくなりました。
シャツやカーディガン、ジャケットなどは、骨折した腕から袖を通します。逆から入れると、痛くてまだ着れません。
行ったり来たり、真綿を剥ぐようにじわじわ良くなっているのでしょうね。
【4か月と1週目】
4か月目に入ったけれど、肩の痛み、ひじから下の重いだるいは相変わらず。
ヨガの、腕を前に伸ばしたチャイルドポーズができないことに気づきました。普段しない動きをしたときに、痛みがあり、あー骨折したんだなと改めて思います。
ヨガのチャイルドポーズは手を頭の下においてもよいと聞き、それならできるからちょっと安心。
他にも、胸式呼吸ができているかチェックする動き(前ならえの先頭さんの動き)が痛い!この動きも普段しないからわからなかった。肋骨まで手首と腕を上げるなんて、とても無理。
腕を振って走るとか、普段しない動きをしたときに、リハビリが長期にわたる意味が分かります。
腕を前に伸ばすストレッチや、前ならえの腕、後ろで手を組むなどもスムーズに行うため、お風呂でのマグネシウム湯内でのストレッチに加えました。
ごまとくるみと松の実ペーストを食べ始めて、少し痛みが楽になった気もします。
【4か月と2週目】
4か月と2週目、肩に湿布がいらなくなりました。肩の痛みが取れました。筋肉がついてきたのでしょうか。時々手首だけに湿布を貼っています。
変わらず、タンパク質しっかりの食事、ボーンブロススープを毎日飲んでいます。炭水化物は麦ごはん、甘いものはほとんど食べません。
お昼のお弁当はこんな感じ。夕方4時には帰宅できる日のお弁当なので、帰宅してから捕食の小さなおにぎりを食べていました。

タンパク質は、ガングロ卵(卵のしょうゆ漬け)2つ、ローストビーフ3~4枚、豚肉生姜焼き。野菜はブロッコリーとスナップえんどう、ミニトマト。ゴマクルミ松の実ペーストも入れました。おにぎりは、鮭と梅干入り。小腹が空いた時用のプロテイン(5gくらい)+MTCパウダー(小さじ1)も持っています。
ビタミンCやDHA・EPA、マグネシウム、コエンザイムQ10 、アスタキサンチンなども適宜摂っています。
関係あるかわからないけれど、CMCスーパーバンドという、水道水を活性化させるというバンドも水道メーターの横に取り付けてみました。心なしか、水がさらさらと柔らかく軽くなったような気がします。お風呂のお水も活性化しているのかもしれません。
ストレッチが効いているのか、ゴマとクルミと松の実ペーストもよかったのか。いずれにしても、諦めず、コツコツとよいと言われることを続けることなのかなと改めて思っています。
【4か月と3週目】
4か月と3週目に入ると、ふろ上がりのマグネシウムクリームを塗り忘れました。いろいろ忘れるということは、骨折前の状態に近づいているのだと思います。
でも、できない動きもいろいろあることに気づき、リハビリ方法を教えてもらおうと、2か月ぶりに整形外科に行きました。
整形外科のリハビリは温めることだけなのだそうです。やっぱり自分の体は自分で主体的に治していくしかないのだな。
ということで、先生から直々にリハビリ方法をご教示いただき、自分でやることになりました。
まず、骨折すると、折れたところに血がたくさん出て、血で固めるのだそう。その時に組織も固めているのだそう。だから、今は、骨は完全にくっついたけれど組織の方が固まってしまっている状態なのだそう。
骨折が酷ければひどいほど、固めている時間が長ければ長いほど、リハビリに時間がかかるそうです。
お風呂の中やお風呂上りに体が柔らかい時に特に、できる限りいろいろな動きを何度も何度も繰り返して行うのが吉とのこと。
①机に手をのせ、体重をかけて手首を曲げる

この動きはなかなか怖くてできないのと、痛いので頻度が少なくなっていました。
最初からこの動きは大事だと先生がおっしゃっていたのを思い出し、まずはしっかり体重をのせて直角に曲がるまでやってみます。
お風呂洗いがいいですね。
②手首を反対に曲げる

この動きも普段なかなかやる機会がない動き。
左手を見ながら、左手と同じように曲がるよう、折曲げます。
③手のひらに置いたお金が落ちないように手のひらを上に向ける
気づくと小指側が低く、親指側が高く斜めになっています。
斜めになっていては手のひらのお金が落ちてしまいますね。
お金を落とさないよう、ねじりましょう。
④両手を組んで手首を左右に折り曲げる
⑤雑巾を絞る。これも台所で台布巾を絞ったり、雑巾絞ったり、普段の生活の中でできる動作。
⑥握力は強いものを数回というより、軽いものを何度も握る
痛くなったら休み、熱を持ってきたら、湿布を貼って休ませましょうとのこと。
そして、まだ骨折して4、5か月だから、このくらいでも全然大丈夫。12月ごろまでリハビリ続けるつもりでとのこと。
医師からは、諦めずにリハビリを続けた人はちゃんと動くようになるから、諦めないで頑張ってください。と言われました。
家事がリハビリになる一石二鳥はありがたい。
諦めずコツコツリハビリ続けます。
【5か月目】
どこかに急に右手がぶつかると恐ろしく肩のあたりが痛いけれど、普段は痛みがなくなってきました。しびれもなくなってきました。
ふと、最近楽になったなと思うと、一か月経過していて、不思議だなと思います。ひと月ごとに楽になってきています。
マグネシウム湯でのリハビリ運動は、金魚体操(湯の中でゆらゆら揺れる)して緩んでからやると後ろ手に組むのが深く組めるし、痛みが少ないので、体を温めて緩めてからリハビリの動きに入っています。
腕は動かした方が翌日楽な気がします。
手首の湿布はまだ貼っていましたが、湿布が血流を悪くするという情報を見たので、癖になっていた湿布を貼らなくなりました。そして、湿布よりマグネシウム風呂やマグネシウムクリームの方が有効だと感じたためでもあります。
一週間くらいで、しびれも軽くなり、またまた、だいぶ腕が楽になってきています。
【5か月と2週目】
気づくと手のしびれがなくなっています!
素晴らしい!!人間の体はいくつになっても少しずつ回復していくのですね。
改めて実感。
湿布も貼っていないので、マグネシウムのお風呂から上がったら、マグネシウムクリームは塗っています。
昨日読んだ、「薬に頼らない 新時代の医学」[9]に、皮膚の触覚の第一人の山口創先生が「セルフマッサージ」についてお話しています。セルフマッサージでもオキシトシンが出るので、肩から手の甲にかけて、寝る前に手のひら全体でしわを伸ばす程度の圧で優しい刺激を与えるとリラックスして眠れる。それが自律神経を整えたりストレスを癒すというのです。「副交感神経が優位になると血圧が下がったり、よく眠れるようになったりする効果も出て」[7]来るそう。
マグネシウムクリームを塗るときに、肩から手首まで、ゆっくり撫でて塗っているのは、自律神経を整えていたのですね。やっぱりお手当、大事❤
ということで、諦めたらそこで試合終了です!って、すごく納得しています☺
引き続き、もう少しリハビリ頑張ります!
【6か月目】
出張でかなり重い荷物を引いたり、背負ったり、長時間運転をして、カステラやフルーツ、麺類など糖質も許容していたら、4日後ぐらいからじわじわ右腕全体に痛みを感じるようになりました。
EPA が疼痛を和らげるという情報を教えていただきました。
大友先生は「EPAには炎症を抑える作用」[1]がある。EPAが少なくなれば、炎症を起こしやすくなったり、治まりにくくなる。だからEPA不足が「長引く痛みやけがの治りにくさ」につながっている。そして、DHAにも抗酸化作用があると既に書籍に書いています。
以下の研究[10]では、「神経障害性疼痛や炎症性疼痛、インスリン抵抗性予防」「高脂血症や動脈硬化症の治療」などには、EPA+DHA よりも EPA単体の方が有効とも報告されているとのこと。EPAとDHAは別で摂取した方が良さそうですね。
「魚油や亜麻仁油に含まれるオメガ3系多価不飽和脂肪酸のエイコサペンタエン酸が痛みに効く分子メカニズムを解明~慢性痛の新規医薬品の開発に期待~ 」[10]
私の場合は、炎症性疼痛というやつですかね.
EPA単体では摂っていないのですが、いろいろな抗酸化サプリを摂ってみると、抗酸化だけではあまり痛みがとれず、DHA+EPAが良い感じでした。
そして、リハビリは続く☺
【7か月目】
7か月目からヨガを始めました。週に4~5回、20分~30分ほど。
一週間ごとに別の動きをするのですが、最初の1回目は全然できないのですが、同じ動きをして3回目くらいになると、言われた動きができるようになるから不思議です。腕立ての姿勢など、骨折の腕が痛くてできなかったのに、3回目からできるようになります。できるようになると、逆に痛みが取れて可動域が広がるようです。
リハビリにヨガは非常に有効です。
マグネシウム風呂とマグネシウムクリームも継続しています。
気がつけば、半年以上リハビリを続けているわけで、マグネシウムクリームは1つ空っぽになりました。継続は金。
今度はメイドインジャパンのマグバームにしてみました。

【8か月目】
EPAやDHA、MCTオイル、アマニ油、えごま油などは積極的に摂るようにして、できるだけお惣菜の揚げ物や、加工食品などで油を摂らないように気をつけています。

7か月目の頃は背中で左手を上から、右手は下から手を結ぶ動きが全くできず、右手が腰から上に上がらなかったのですが、8か月目で、マグネシウムのお風呂の中でようやく指と指が触れるようになりました。11か月目には、背中で手が結べるようになりました。
【山手のドルフィンでソーダ水】
久しぶりに山手のドルフィンに行ったので、ソーダ水(果糖ブドウ糖液+炭酸水)を頼んだのです。
オーダーしてから、ふと、ジュースなんてもう何年も飲んでいないことに気づき、100ccくらいで飲むのをやめたのですが、翌日から2日間くらい、また、骨折した部分や腕にしびれ、しくしく痛みが出て、糖化(?)を感じることになりました。
ようやく痛みのない生活をしていたのに、ソーダ水でまたぶり返し。果糖ブドウ糖液の怖さを実感しました。とりあえず2日で痛みやしびれがひいたのでほっと一安心しました。
諦めなければ、必ず動くようになると言われた整形外科の先生の言葉を思い出しました。
こうして、まだまだリハビリは続きます。
山手のドルフィンとソーダ水のお話はこちら。
【10か月目】
とうとう完治❣
もう、大丈夫。まったく痛くない🥰 ルンルン♪
アラ還の手首の骨折。10か月で完全に完治でよいでしょう。
【1年2か月目】
2023年3月。
もう、何事もなかったように生活しておりましたが、なんと、骨折から1年2か月経過時点で、またできない動きが見つかりました。
療育整体で自律神経のチェック項目で行った動きです。
左腕はこのように手首を裏返して足の付け根においてひじを伸ばせます。

ところが、右手はまず、手首で裏返すことが困難です。さらに、足の付け根に指を合わせると、手首が浮き上がって、ひじも満足に伸ばせません。

普段特にここまで必要のない動きなので、できないことすらわからなかったのです。

こんなに浮き上がってしまうし、真上に肘を返すことができないのです。
さて、またマグネシウム湯とマグネシウムクリームでリハビリです。
だいぶ手首が固くなってしまっているから、時間がかかりそうですが、続けてみます。
【2年1か月目】
2024年2月
肩が冷えた時の痛みも、去年出来なかった手首をひっくり返す動きも、あー、みんなできるようになったな。本当に完治して、元に戻ったのだなとふと思った2024年。
血流を良くして、体をあたためること。朝からタンパク質をしっかり摂ること、血糖値を安定させること、散歩やアーシング、療育整体で自律神経を整えるセルフ施術、マグネシウム風呂やマグネシウムクリームなどは現在も続けています。
おやつは煮干しやナッツ、ボーンブロススープ、ウズラの卵など。
お金がかからないし、時間もかからない、家庭でできる、自分でできることばかり。
極力摂らないものは、小麦やケーキやチョコレートや甘いお菓子。
パンは米粉パンにして、小麦粉はほとんど食べません。
ケーキやスウィーツはお誕生日や特別な日にすこしいただくとか、グルテンフリーのケーキやさん見つけた時に食べるくらいかな。
ヤクルトなども含め、ジュースやソーダ水は一切飲まない。
コーヒーは飲まない。たまに飲むときはノンカフェイン(それでもカフェインは入っているそう)にアーモンドミルクや豆乳やMTCを入れて、ランチまでに一杯飲むくらい。
アルコールもたまにしか飲みません。
フルーツもできるだけ甘くないものを選び、たまに食べるくらい。
心も体も脳も繋がっているから。そして、結局痛みや花粉症ででつらくなるのは自分だから、こんな調子で続けています。
食やメンタルについて、Instagramの@smile_remies[11]でもいろいろ発信しています。見に来てくださいね🥰
ということで、アラ還の骨折でも食と栄養と運動で痛みも抑え、驚異的に回復させることも可能だということ。2年間で固まってできなかった動きまでできるようになり、完全に治ることを(n=1)、体を張って学んだ回復記録でした🥰
長々お付き合いいただき、ありがとうございました。
骨折された際には、ご参考にしていただければ幸いです。
骨折って、辛くて痛いし、先が見えずに不安になりますよね。
サプリなどは個人差があると思いますが、やめた方が良いものはたぶん同じだと思います。ご自身のお体に合わせていろいろ試してみてください。
必ず回復するし、今まで以上に元気な骨になります。頑張ってくださいね!!🥰
参考文献
[1]大友通明(2018)『寝たきりを防ぐ「栄養整形医学」骨と筋肉が若返る食べ方』青春出版社
[2]精神科医こてつ名誉院長のブログ(2022-04-05)「Mgが欠乏するとCaを溶解状態に維持できない」
https://ameblo.jp/kotetsutokumi/entry-12735710889.html
[3]三浦雄一郎(2014)『65歳から始める健康法―心と体のメタボからの脱出―』致知出版社
[4]世界☆最強の勇者たち11 手足のない女性の挑戦 母と歩んだ感動実話
[4] そこまでやるかマン 世界最強の勇者たち 「歩き続けよう」
https://kakaku.com/tv/channel=4/programID=22833/
[5] うえぞの整骨院「レントゲン・カーター(宿酔)」2012.06.22
https://www.uezono-seikotsuin.com/archives/923?fbclid=IwAR1T0i9SiLpsnTo47UERRQPOEXC-fd7CEelH2x6Wwa9EgBnP9qaIc1nG88g
[6]鈴木加菜『予防栄養学と自己治療法―病しらずの一人暮らし―』かな太書庫
[7]療育整体
https://www.kafusha.com/products/detail/58
[8]発達キッズ協会
https://devkids2020.wixsite.com/my-site
[9]今井一彰『薬に頼らない 新時代の医学―12人の達人に訊いた!―』マキノ出版
[10]「魚油や亜麻仁油に含まれるオメガ3系多価不飽和脂肪酸のエイコサペンタエン酸が痛みに効く分子メカニズムを解明~慢性痛の新規医薬品の開発に期待~ 」日本の研究.com 20220719
https://research-er.jp/articles/view/112662
[11]@smile_remies
https://www.instagram.com/smile_remies/
#骨折 #分子栄養学#マグネシウム#ビタミンC#回復記録#復活#栄養#栄養療法#レジリエンス#リハビリ#諦めなければ動くようになる
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
