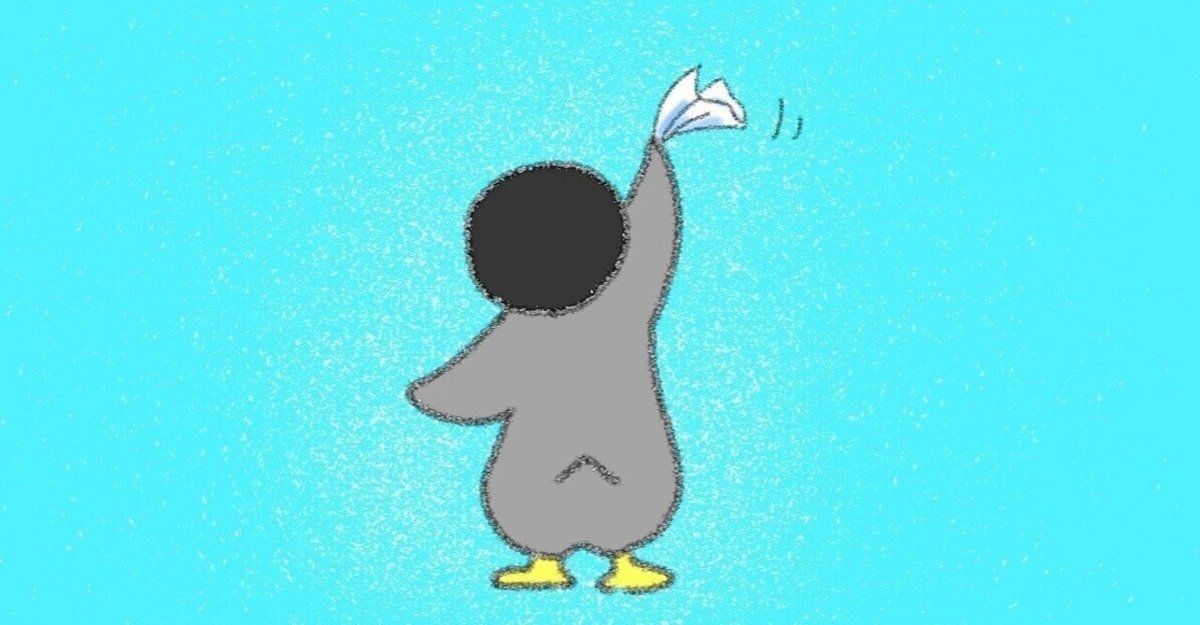
推しとの「離れかた」 ―私淑、 "Therefore I am"、そして忘却—
先日、芥川賞を取った宇佐見りん『推し、燃ゆ』を読んだ。
読んでいる途中、たびたび身につまされる思いに襲われた。私には、一般的にはアイドルとして見られているだろう「にじさんじ」というVirtual YouTuberの事務所を箱推ししている。この集団は、100人以上のライバーがほぼ毎日雑談やゲーム、歌などの放送をしている。そして、この集団も現代のネット環境下では、残念ながら炎上やコミュニケーション上のトラブルとは無関係ではない。
そんな時、次のような記事をnoteで発見した。
にじさんじに所属する弦月藤士郎くんという、ピアノがべらぼうに上手いVtuberの子が、リスナーとの距離感に悩んでいる話が綴られている。ポイントは、彼が悩んでいるのが「自分を肯定する言葉が作る、同調的な空気感」だという点だ。「僕は自分の生活があるので、僕が自分の生活をしている時にみんなはみんなの生活をしていてほしい」という言葉に彼の気持ちが込められている。
にじさんじだけの問題ではない
00年代以降、情報機器の発達とともに、インターネットでMP3やYouTube等の視聴覚メディアに触れやすくなった。ひと昔前、人はラジオやテレビに人々が熱狂した。そういう強い刺激を作り出すメディアが一般化した。そして10年代、SNSが出てくると常時相手の情報に接続可能となった。
月並みな物の書き方だが、これにより人は即座に欲しい情報にアクセスできる(かもしれない)権利を手に入れた。しかし一方でSNSなどで書き込むことには、常に「誰かに+であれ-であれ評価されてしまう」欠点があった。『推し、燃ゆ』の主人公も、アイドルである推しの情報を一点たりとも逃さず解釈することに心血を注いでいた。
この問題は、単ににじさんじだけにとどまらない。海外の音楽の世界では、SNS上のやりとりを避けるようになった人(Ed Sheeranが筆頭)も数えきれないほどいる。特に、2019年に「Bad Guy」で一躍時の人となったBillie Eilishの新曲「Therefore I am」も、SNSやニュース記事が彼女に向ける好奇の目線を一蹴するものだった。Therefore I amとは、哲学者デカルトの「われ思う、故にわれあり」の英語訳である。
つまり、こうした+であれ、-であれ、「自分に目線を向けられる」状態は、時に負荷になるのである。このあたりは、哲学的にはミシェル・フーコーのまなざしの問題にもなるだろう。
では、どうしても人間として、相手を勝手に解釈してしまうような「推し」がいる人は、「推し」と付き合うのがいいのだろう?いくつか方法を考えてみた。
「私淑」「ゲートキーパー」を推しから離れるための道具として使う
読書猿さんの『独学大全』には、他人を頼る勉強の方法として「私淑」「ゲートキーパー」という二つの方法がある。この勉強法をあえて推しから距離を取る方法に使ってしまう方法がある。
「私淑」とは、実際に出会えない人を師として仰ぎ、その人の情報を集める。そして集めた情報を基に、問題にぶつかった時に「この人ならどうするだろう」と想像する方法である。「ゲートキーパー」とは、来週までにやるべき事柄を紙に書きだして、繰り返し会うことの出来る人に手渡す。これにより、行動のグダグダを回避して、自らの勉強を進める方法である。
「推し」を持つ人の弱点は、「推し」のことを考えすぎるあまり、本人の一挙動全てに反応してしまったり、自分の想像の中の「推し」の解釈を進めすぎ、それが本人の元に届いてしまうことである。ならば、そのエネルギーを本人に向けるのではなく、「本人に喜ばれるような立派な人間になる」ことに注ぐことは、無益なことじゃない。
具体例は、にじさんじ初代の月ノ美兎さんに憧れるあまり、自らもにじさんじに入り、ライバーとして成功したリゼ・ヘルエスタさんだろうか。
「推しの推し」を推す
これは私がよく使う手である。日本音楽史一とも称されるバンド、はっぴいえんど。そのボーカルの大瀧詠一さんは、かなりの好事家だった。ビートルズと日本の音頭に共通点を見出して、イエロー・サブマリン音頭などという怪曲を生み出した。ありとあらゆるジャンルの音楽を聞き漁り、音楽評論家としての活動も積極だった。
①あらゆるものには前史がある
②傑作は単独では存在しえない
③あらゆる作品にはそれを作った人たちがいる
これは、ある程度までは人間にも当てはまるのではないかと私は考えている。冒頭述べたように、今の時代ほど人がどのように人に影響を与えているかが、SNSによって可視化された時代はない。ならば、「推し」の好きなものを探しにいくことは、推し本人に迷惑をかけない形で出来る推しへの貢献である。
想像してほしい。「あなたのことが好き」というと重い。しかし「僕も○○が好き!」ならば受け止めやすいのではないだろうか。
ちなみに大瀧詠一の志を継いだ、音楽的探求を行っている人にみのミュージックさんがいる。
推しを忘れる
この方法は、合わない人には合わない。しかし、推しにとって自分も「合わない」ことがあるかもしれない。そんな時は、ただ単に「推し」から離れてしまうのもよい。
スピノザなら「コナトゥス」というのかもしれないが、「推し」が好きな人は、当然ながら「推しを好きと思う自分」を壊したくないと考える。しかし、心理学では「好き」という感情は容易に憎悪に反転することがある。スキキライの反対は、「無関心」あるいは「忘却」なのである。
ここ数年、BUMP OF CHICKENは「忘れる」ことを静かに、肯定的に歌う曲を数多くだしている(Firefly、RAY)。その最たるものが「話がしたいよ」である。
この曲には「ボイジャー」や「お薬」「ガム」「バス」など、歌の文脈とは一見関係ないような単語が散りばめられている。もしも、この曲が別れて他人になった友達や恋人に向けて歌われているとしたら、それは別れた自分が見て来た景色のことである。
普通、勉強や思い出は多ければ多いほど良いと人は考える。でも、人はモノを忘れ、居つきから解き放たれることによって、目の前の物に新しい意味を見出すことがある。時には、そんな離れ方をするときも、あっていいだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
