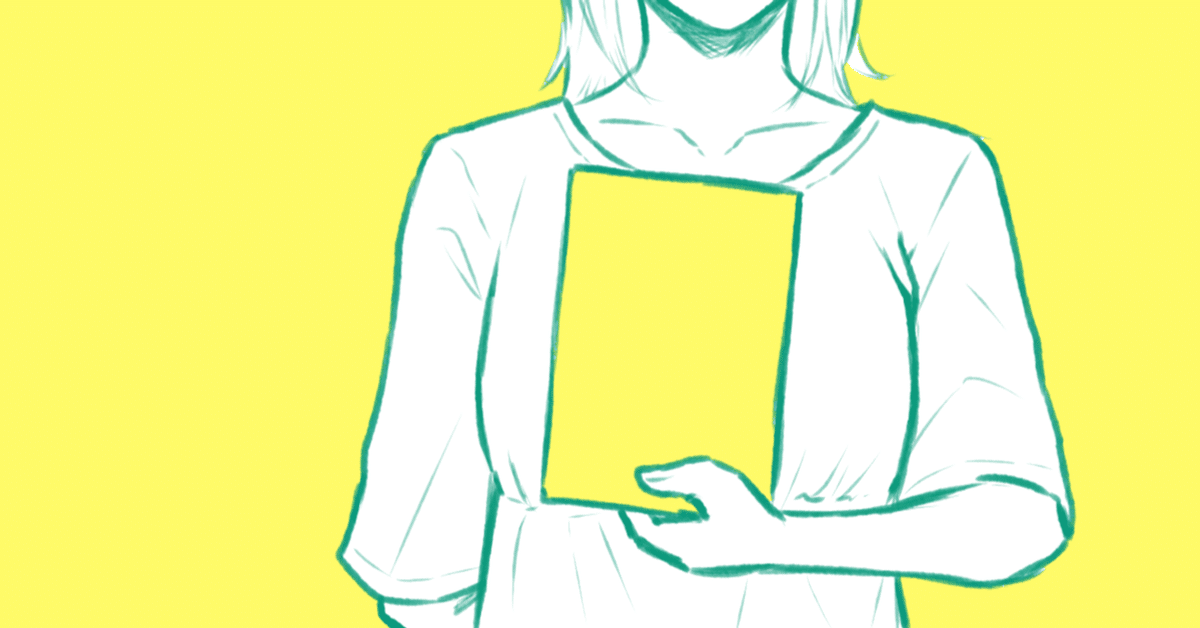
【100冊後に教養が身につく中公新書】ーー2冊目『詭弁論理学』
野崎昭弘『詭弁論理学』(通巻番号448)
めちゃくちゃおもしろい本ですが、タイトルだけを見ても内容がイマイチ想像できないかもしれません(私自身がそうでした)。
この本は議論のなかで用いられる「詭弁」「強弁」についてフォーカスし、それらの代表的な型について、具体的な例と対応策を解説しています。
ただしこの本の目的は、「議論に強くなるためのハウツー」を示すことではなく、相手の詭弁術を理解することで議論を楽しむ・人間観察を楽しむための「ゆとり」を持つことに置かれています。(私は本書のはしがきに書かれているこの前提がとても気に入っています)
本書のイメージをもう少し具体的に持っていただきたいので、内容を少し紹介します。
まず著者は相手を議論で丸めこむ(ごまかす)際の手法として、「詭弁」と「強弁」とを区別しています。どちらも正確な論理性を欠いたものですが、「詭弁」が多少は論理や常識をふまえたものであるのに対し、「強弁」は理屈無視のゴリ押し戦法です。
「強弁」は理屈無視の戦術とはいえ、実際に日常のなかではある意味効果的に使われているものです。下記にいくつか例を紹介しますが、普段自分が苦しめられている戦術の型を知るだけでも、いくぶんか精神的な余裕が生まれると思います。(対応策が気になる方はぜひ本書を読んでみてください)
二分法
人々や考え方を、ある原理的な基準で二分する考え方。
例 「おまえたちにおれの気持ちがわかってたまるか!」
相殺法
相手の意見に賛成しておきながら、重箱の隅をつつくようなことをいい出して、相手のいい分を帳消しにしてしまおうとする作戦
例 「ミネオちゃん、宿題すんだ?」「ママ、洗濯すんだ?」
強弁はすぐにおかしいと指摘できるものもありますが、詭弁になると論理のおかしいポイントを指摘するのが難しくなってきます。詭弁術の論理破綻を解き明かしていくというアプローチで、論理学の世界を楽しめるというユニークな本書は、「議論べた」な方におすすめの一冊です。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
