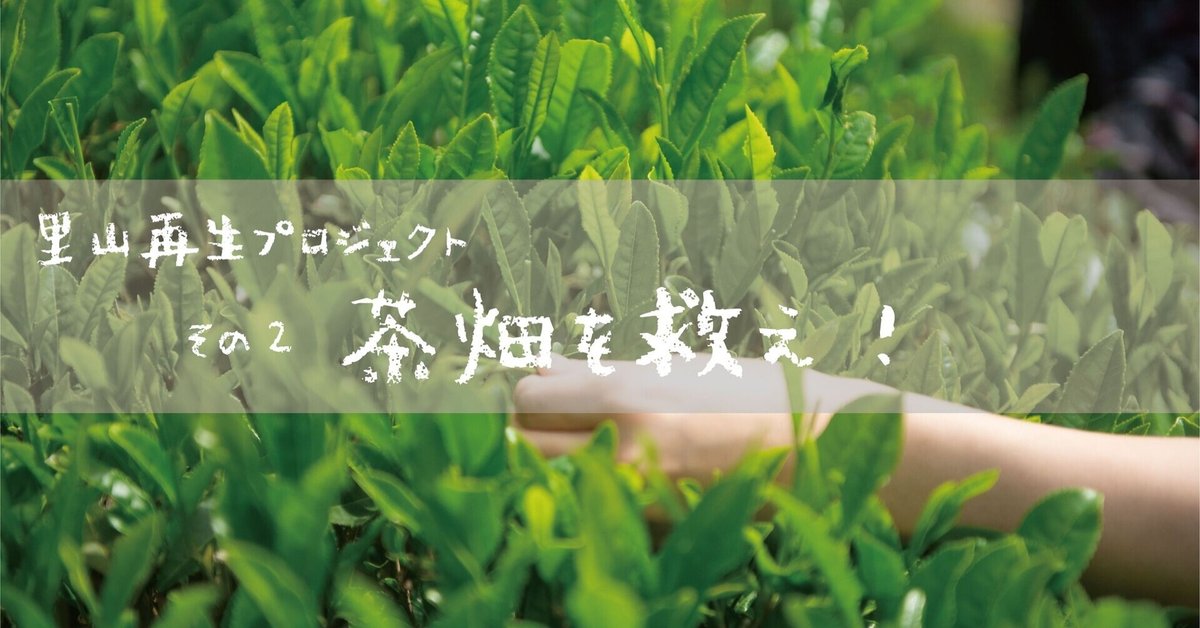
茶畑を救え!:里山再生プロジェクト②
この茶畑、もう潰そうかな
私たち家族が引っ越してきたのは、
森町の西亀久保という山あいの集落。
国指定重要文化財の友田家住宅がご近所さん。
10軒あるうち5軒しか住んでいない。
苗字はみんな友田さん。
友田家の目の前には、友田の人々が営んできた茶畑が広がっている。
一つはすでに茶の木が抜かれ、代わりに栗の木が植えられている。
が、残りまだ一反ほどの茶畑が残っており、
その茶畑を営んでいた友田さんも、とうとう昨年やめることを決意。
「この茶畑ももう誰もやらんで、潰そうかなぁ。
それか、佐野さんやるなら使ってくれていいで」
お茶って私みたいな素人がやってもいいの!?
考えたこともなかった選択肢。
手前から見ただけじゃ分からない、奥に続く茶畑を見てびっくり。
「意外と広いでねー」
およそ1000㎡。意外とっていうか、広い。
正直どうしたらいいか分からないけど、
潰されるのは止めたいので、手探りでやってみることに。
止まらない手摘み
一番茶には間に合わなかったので、
二番茶に照準を合わせ、一番茶は刈り落とすことに決めた。
せっかくの新芽がもったいないので、
自分たちで作れる分だけ、手摘みすることにして
GW明けに茶畑へ向かった。
これで良いのかなー?とチマチマ摘み始めると、
カネさん登場。
「私もちっと摘もうかね。懐かしいやぁ」
そう言って、すごいスピードで摘み始めた。
私たちの倍の速さで、二倍くらいの量を袋に詰め込んでいく。

「子どもの頃からお手伝いで摘んでたからね。
ひと芽、ひと芽、摘んでたら間に合わないよぉ。
昔は自分ちで飲む分は、みんな手摘みで手で揉んでたよ。
今は機械でたくさん摘めるけど、やっぱり機械は機械の味だって。
手の味が一番美味しいよ」

これが噂の『一芯二葉』!
次から次へ目が移って、手が止まらない。
自分たちで手揉み出来る量に限界があるので、
たった二列目が終わったところで終了。
自家製烏龍茶づくり
家に帰って、日なたで一時間。
日陰で二時間ほど干して、半発酵させます。

本当は、葉の先が黄色くなるまで発酵させるらしいけど、
今回は青臭さが消える程度で、次の工程に進みます。

中華鍋でお茶っ葉を炒って、パチパチ水分を飛ばします。
炒って熱々の葉っぱを手で揉んで、水分を出します。
そしてまた炒って、の繰り返し。
葉っぱの量が多かったので、二時間ほどかかって全部カリカリになりました。

さっそく淹れてみると、清清しい香りと優しい味。
釜炒り茶と烏龍茶の間のようなお茶になりました。
手前味噌ですが...ふつうに美味しい♪
自分で自分のお茶を作る
ふだん飲んでいるお茶のこと。
どんな姿の木で、
どんな葉っぱをしていて、
どんなふうに作られているか。
摘んでから炒るまで、変化していくお茶の香り。
目の覚めるような清爽な芳香に包まれる、至福の時間。
知らなかったことを知るのが楽しい。
自分で摘んだ葉っぱで、お茶を作り、飲む。
昔ここで住んでいた人たちの暮らしをトレースしていく。
これから、お茶畑の手入れをしていくにあたって、
勉強することは山ほどあるけれど。
今後、どんなことが出来るかワクワクしています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
