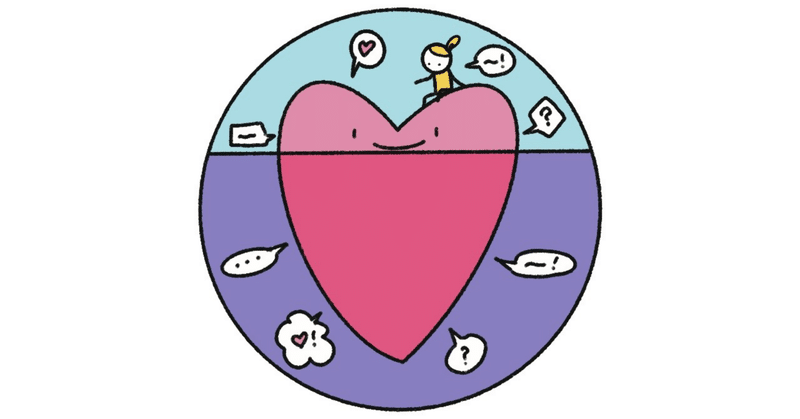
#101 「本当の自分」など存在せず、環境が自分の存在を規定する 24/3/6
みなさん、こんにちは。
自分とは何者か、源流を辿ることの意味と、自分探しは無意味さ、の一見すると相矛盾することについて考えてみます。
考えるきっかけは、現在25年度新卒採用の選考で学生さんとお会いしていると感じることがあったことです。
自己分析に多くの時間を使って自分と向き合うのは、就職活動のときが初めての方も多いのではないでしょうか。わたしもそうでした。
その自己分析は、有象無象で、上手に自分の原点・源流を辿ることができる学生もいれば、いわゆる自分探しに迷走してしまっている学生と、両極端に分断される印象を強く感じます。
自分探しに陥る環境的要因は、10数年前に私が就職活動をしていた頃も、今も、根本的には変わっていないように感じます。
しかしながら、昨年から今年の選考、つまり4年制大学卒でいえば24年度・25年度に就職する方々には顕著かもしれません。その要因の1つは、コロナ禍で4年間ほぼすべてがオンライン授業で、リアルな場で人間関係を作る量的体験が、圧倒的に少なくなってしまった2世代ではないかと推察します。
それはどういうことか、です。
他者と交わる中で、意見や価値観の異なる人と多く触れ合います。その直接的な身体体験を通じて、自分にセルフフィードバックが働き、内省する機会が少ないことが1つです。
一方、外出が制限された環境に置かれたが故に、自分自身と向き合う時間は多く、内省はそれまでの世代より深いことも確かです。
もう1つは、他者から直接的にフィードバックをもらう機会が少なかった点です。
このフィードバックが機能する機会が少なかったことにより、自分を客観視することが少なく、自分の源流を辿ることを一層困難にしたのではないか、と推察します。
ジョハリの窓でいうと、自分は知らない×他者が知っている、のセグメントです。この領域を中心とした「自分」を知ることが困難だった可能性があると考えています。
次に課題になるのは、その機会がそこそこに存在したとしても、そのフィードバック情報との向き合い方次第で、自分探しに留まるか、自分の源流を辿れるか、自己分析の程度が変わってきます。
そこに影響を与えるのは、自分の経験を俯瞰して感じた感覚を、言葉にすることから逃げずに向き合えるかです。
言語化することがは難しくとも、言語化し可視化することに時間と労力をかけたかどうかでしょう。それだけでも差が生まれます。
さらには、そのときに、問いかけを投げかけてくれる友人や先輩など、周辺のサポーターがいるかも、大きな要素になります。
いわゆるフィードバッカーです。
このフィードバッカーの存在を確保することは、よりハードルが高い課題です。
それでもなお、インターンで知り合った人、あるいはインターンをした会社の人事担当者、アルバイトや課外活動などでの年齢や性別の異なる他者の助けを借りたいところです。
自分をよく知っている友人のほかに、ゆるい人間関係のパスがあると、それはスムーズにできると考えます。弱いつながりと言われる人的リソースの確保です。
最後に、わたしの究極的な結論です。
そうはいってしまうと詰んでしまうのですが、最終的にはこう考えています。
「私は、自分は」と自分を探しに行っても「本当の自分」などは存在しません。
今この瞬間、置かれている環境や状況をあるがままに受け入れたときに、そこに存在するのが「本当の自分」と幻想的に言われる自分の、正体です。
ごく稀に、このことを無意識かつ自然に自覚している存在がいます。
それが「天才」と考えます。
それでは、また。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
