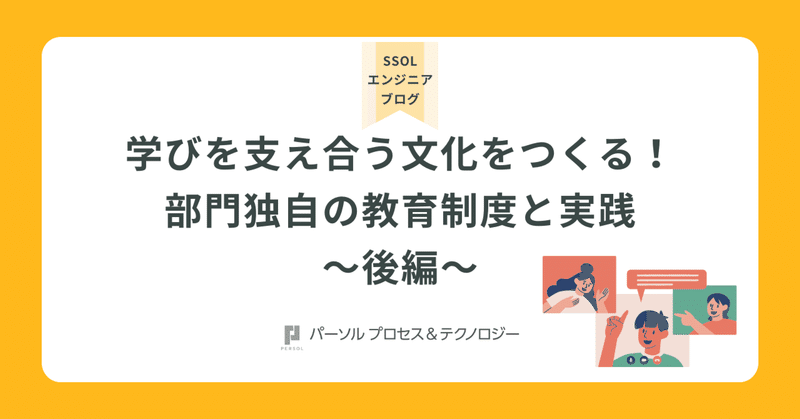
学びを支え合う文化をつくる!部門独自の教育制度と実践〜後編〜
こんにちは、パーソルプロセス&テクノロジー(以下、パーソルP&T)の藤谷です。
前回「部門独自の教育制度があるよ」というブログを書きました。
後編の今回は「独自の教育制度のもとでメンバー同士が学びを支援する(≒教育する)取り組みが実践されている」という事例を紹介したいと思います。
パーソルP&Tやリクルートメントソリューション部に興味いただけたら嬉しいです。
■事例1:座学と実践で学ぶAWS
1つ目の事例はAWSに関するものです。PERSOLグループではクラウド移行が推進されています。
私たちのミッションは「グループ会社のサービスをITの力で支える」こと。メンバーにはクラウド基盤上でシステムを構築・運用するスキルが必要とされます。
今回は若手~中堅の3名にそれぞれの取り組み内容を教えてもらいました。順を追ってご紹介します。
●手を動かしてAWSを学ぶ(2022年度1Q~2Q)

藤谷:手順書の作成は、大変ではなかったですか?
中山さん:簡単なものではありましたけど、工数で1人月前後、工期で4ヶ月くらいかかりましたね。
藤谷:目的は達成できましたか?
中山さん:達成率は50%くらいです。予備知識のあった人は体験を通じて成長しましたが、一方で予備知識ゼロだった人は「手を動かす」だけでは実にならなかった印象です。企画者として課題は残りました。
藤谷:課題は残しつつ、一定の効果もあったと。知識と実践の相補性というおもしろい発見があったようですね。
●座学と実習でAWSを学ぶ(2021年度3Q~4Q)

藤谷:中山さんの企画と似ているようで、背景にはグループの色が出ていますね。やってみてどうでしたか?
藤江さん:中山さん同様、達成率50%程度でした。座学ではQAがあまりなく、演習の時間が足りず途中で終わりに……。お題やルール設定など、企画側できっちり決めるべきだったかと。
藤谷:難しい問題ですね。逆説的ですが「皆さんで自由にどうぞ」というのは参加者からすると窮屈になる。そこをうまく乗り切る術を学ばせるのが目的ならばよいのですが。とはいえ、企画側で全てお膳立てするのは準備の手間もかかりますしね。
●資格勉強で切磋琢磨(2022年度1Q~2Q)

藤谷:藤江さんの企画直後、同じグループで照沼さんが企画を進めてくれましたね。今度は主体的な参加を重視。アウトプットにより知識の精緻化・定着を図った結果、大きな成果が得られましたね。
照沼さん:はい。参加者全員合格でした!
藤谷:おめでとうございます!!
●企画推進の課題:どこまで参加者の主体性に任せるか
藤谷:企画推進の課題として、先ほど藤江さんから「どこまで縛りを設けるか」という趣旨の話がありましたが、他に課題と感じたことはあるでしょうか?
中山さん:教える側と教えられる側の距離感ですね。私の企画の場合、一方的教授に留まってしまったのが残念。もっと対話が生まれるようにしたかったなと。
藤谷:明確な答えがある問題であれば一方的教授が適していますが、明確な答えがない(答えが複数あり得る)問題では対話が鍵になりますよね。
中山さん:はい。あとは「モチベーションをどう引き出すか」にも対話が絡んできます。
照沼さん:「アウトプット会」での教え合いの時間は好評でした。参加者には教える嬉しさを味わってもらえました。教える前提で学ぶことで、きちんと理解もできる。教える側にも大きなリターンがあったんです。
藤谷:なるほど。
照沼さん:細かいことを言えば「もっと交流を多めにしてもよかったか?」「開催日時をもっと柔軟に、参加者の負荷を低減するようにしてもよかったか?」など思うところはいくつかあります。
藤谷:でも発散しちゃうリスクもありますね?
照沼さん:そうなんです。参加者ごとにご意見はあると思いますが、結局はこれでよかったのだろうと。
■事例2:参加者同士の対話で学ぶヒューマンスキル
2つ目の事例はヒューマンスキル。中でもプロジェクトマネジメントとリーダーシップに関するものです。
リクルートメントソリューション部にはPM、PL、TL、そしてその候補生たちがいます。組織力を強化する上で組織をつくる役割を担う方たちの育成は重要なテーマです。
数々のプロジェクトを経験してきた大ベテランの星野さんと、プロジェクトマネジメントはもちろん新人研修リーダーのご経験もある金子さんにお話を聞きました。
●意見交換を通じてPM/PL業務を学ぶ(2021年度1Q~2Q、2022年度1Q~現在)

▼星野さんの過去の記事はこちらから
藤谷:企画された勉強会はどちらも対話が重要なパーツですよね。参加密度が高くて、アンケート結果では満足度もかなり高かったです。
金子さん:私も参加者だったのですが、すごくよかったです! 直属の先輩や同僚以外の話を聞けて、良い刺激になりました。同じグループ内だと良くも悪くも同じ色になってしまいますから。
藤谷:PMについて本を読んだり先輩に聞いたりして得た知識をどう実践に活かすかは重大問題ですよね。組織によって取り扱うプロジェクトの規模も特性も変わってくる。そこでお互いが実践の中で知り得た知識の交換が意味を持ってきます。
星野さん:そうですね。中途入社組はとくにそうした機会を欲していたようです。前職とまったく異なる環境でチームやプロジェクトを運営しなくてはならないわけですから。
●ワークショップを通じてリーダーシップを学ぶ(2022年度1Q~現在)

▼金子さんの過去の記事はこちらから
藤谷:ワークショップを織り交ぜての企画の準備は、大変だったのでは?
金子さん:外部研修の一部を参考にしつつも、アレンジしたりカスタムメイドしたり。毎回悩みますね。ただ労力をかけた分、参加者から好評いただいています。
藤谷:参加者からはどんな感想が聞かれました?
金子さん:「他者のやり方や考え方を聞いて自分自身の振り返りができた」「自他の違いを知って学習目標の設定に繋がった」という声を聞きました。元々私が受講した外部研修も、異業種交流による刺激を得るもの。スケールは違いますが同じ効果が得られたわけです。
藤谷:参加者の振る舞い方に変化はありましたか?
金子さん:勉強会は1ヶ月置きの開催です。参加の都度、直近1ヶ月の自身の取り組みを振り返ってもらうんです。その内容を見ていると、だんだんと文量も増え、内容の多様性も増してきました。参加者各自がそれぞれのやり方で着実に学んでくれているようです。
●企画推進の課題:いろいろな正解を見つけられる場にしたい
藤谷:勉強会の企画を継続するにあたって、強化したいことはありますか?
金子さん:できることならば対面でやりたいですね。表情や身振り手振りがあると意見交換しやすいですし、運営側も参加者の感情や理解度などを把握しやすくなります。
藤谷:コロナ禍の制約ですね。もっともリモートだからこそ参加できるという人もいるはず。その意味ではより多様な意見を交換する機会にもなっています。トレードオフなところですね。
星野さん:形式はどうあれ、より多様な意見や多様な正解を持ち帰れる場がつくれればいいなと。ヒューマンスキルは複雑です。一筋縄ではいかないものが多い。だからこそ参加者同士で知恵を出し合って色々な場面で活用できる「型」をより多く学べる勉強会にしていきたいです。
■まとめ
今回は勉強会を開催してくれている5名のメンバーに、それぞれの実践ストーリーを聞きました。
ITスキル系かヒューマンスキル系かを問わず「対話をどう誘発するか」「参加をどう促すか」「参加をどう促すか、知恵をどう出し合うか」といった課題感が似ている点は興味深いですよね。
もちろん今回紹介したものの他にも多くの勉強会が企画されており、多数の参加がありました。詳しくは前回の記事をご覧ください。
こうした成果を踏まえて、今年度のリクルートメントソリューション部の注力ポイントは大きく次の2点です:
企画する側(教える側)になるメンバーを増やす。
より多くの教育コンテンツを提供するためには企画する側の人口が必要。
教える行為は教える側にこそ多くの効果をもたらす。自身の業務の枠を超えた学び、将来を見据えた学びが得られる。
学ぶ自分(個人の生産性) →教える自分(チームの生産性) →教える者を育てる自分(生産性の継続性)。このような成長ができる組織をつくりたい。
スキル観点で2・3年度を見据えた組織のビジョンを定義する。
学ぶ側と教える側。双方が取り組みの指針とできるものが必要。
前編でお話したAWSのスキルに関するKPIはこれの一部だが、それだけでは不十分。
他のITスキルやヒューマンスキルも含めたよりカバー範囲の広いターゲット設定をしていきたい。
引き続き、組織で、個人で、様々なレベルで取り組みをしてまいります。
「顧客のサービスをITの力で支えたい」そのミッションのために「チームを支えて貢献したい」「チームをつくり、チームを育てていきたい」。
そんな意思をお持ちの方といっしょに働きたいなと考えています。
