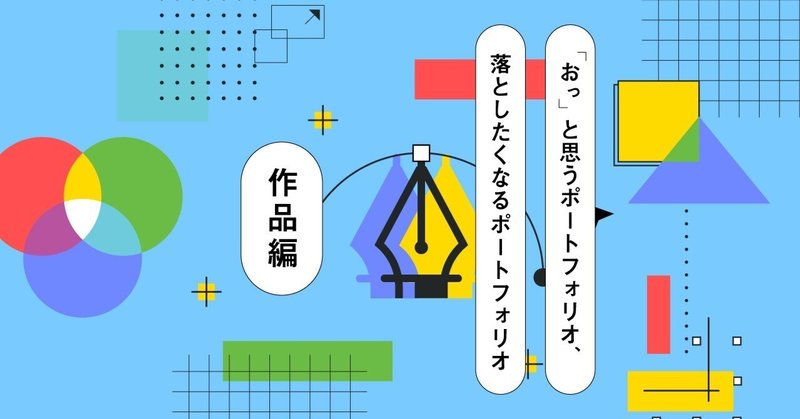
「おっ」と思うポートフォリオ、落としたくなるポートフォリオ【作品編】
デザイントーストというオンラインスクールをやっているほりです。
落としたくなるポートフォリオってなんやねん!と怒られそうなタイトルですいません。
今回は、ポートフォリオを始めとした、転職面談で聞かれるデザイン説明のコツについても触れてみたいと思います。
Webデザイナーやグラフィックデザイナーにとって、必須の「ポートフォリオ」を知ってますか?
ポートフォリオ=デザイン作品集、のことです。
デザイン独学or巷のスクール行った人の作品って9割「なんとなく作ったよ」感出てて実際なんとなく作ってる
— ぽり(ほり) (@polittlehori) January 4, 2023
・あなたはどうしたいと思ってこれ作ったの?に答えられる事
・大前提としてポートフォリオは超全力注ぐ(会ってもない誰かの目を引くアイキャッチ的期待を高めるものを)
は必須だよなと思った
先日、とあるSNS上の駆け出しデザイナーさん(転職活動中)のデザインを見て、感想として正直に思ったことがあります。
「デザインはダメじゃない…けど、よくSNSにいる典型的な駆け出しさん、という印象」
「正直、これだとちょっと難しいかもしれないな」
決して作品のクオリティ自体がめちゃくちゃ低かったわけではありません。その人なりにデザインをリサーチして、真似てみて、見た目のクオリティを上げたというのは伝わってきました。
ただ、面談でポートフォリオを今まで色々見て来た私には「決定的に欠けているもの」を感じました。
ずばり、それは
「この作品をなんで作ったのか、作った本人もはっきりと分かってないまま作ったデザイン」です。見る人の視点が意識されて作られていない。
私の受け取った印象としては、そこに芯が見えなくて、なんだかふわふわと実態のないものに見えるというか。
もう一度言いますが、責める意図はありません(指摘をどう受け止めるかはその人次第だと思うので)
もし、超毒舌な有名アートディレクターならこう言うかもしれない。
「目的もはっきりせずに作って何の意味があるの?趣味ならいいけど」
いちデザイナーの私が一目みただけでこう思うということは他にもおそらくそう思う面接官が沢山いると思います。
それを改善すればもっと受かるはずだし、デザインの作り方の視点も大きく変わると思います。
なので、私なりの意見としてこういう風にしてみたらどう?という、記事です。気づきやきっかけになったら嬉しいなあと思います。
ポートフォリオ送付に、返事が返ってこない原因4つ
ポートフォリオに返事が来ない!悲しいけど、よくある話です。
原因を4つに分けてみました。
1.作品がよくない(薄っぺらい、そこに熱や想いがないetc)
2.作品はよいが、見せ方が上手くない
3.他がよくない(履歴書・職務経歴書を見て、キャリア経験の不一致)
4.企業側の原因(タイミング・募集環境の不一致etc)
私も未経験の頃の転職時はすごく悩みました。
実務デザイン実績が増えてくると、同ジャンルへの応募は受かるようになりました。が、経験のない他ジャンルに応募するとやっぱり落ちる。
未経験なら、なおさら信用がないので大変ですよね。
1.作品がよくない(薄っぺらい、そこに熱や想いがないetc)
これが実は、今まで見た限り、一番多い!
序盤で触れた、私がSNSで見た駆け出しデザイナーさんの作品はこれでした。
傾向として、以下のようなすごく頑張り屋さんの人たちが多い。
・普段、SNS上のデザインTipsで情報収集・配布課題をやっている人
・独学でUdemyなどでソフトは扱えるようになった頑張り屋さん
・作って終わり、プロデザイナーにがっつり添削や実務レベルの意見を貰っていない人
持論:中級以降でお金をケチって、いい学びは得られない
これは私の持論で、どんな学習にしても思うんですが、
お金をかけないでやってやる!って素晴らしい心意気だし、独学でできるならそれでいいと思う。というか独学でモチベ保ってできるの、偉い!巷のスクールさんはお高く、大手は特に、値段に質が伴っていないところもありますしね。
ただ、個人的に思うのは、無料でいいのは初級まで。中級以降はある程度お金かけないとなフェーズだと思う(知り合いとかコネクションがないのであれば)
重要なのは「ちゃんとしたプロに、がっつり厳しい本音のフィードバックをもらったことありますか?」ということです。
(だって、スキルがあればデザイナーは時給3000円で働けるのに、その勤務時間&収入を削ってまで、わざわざ無料で見知らぬ人にアドバイスくれるような人いたら、ちょっと怖くないですか?)
とはいえ、一般的なWebスクールなんかは大体、初心者しか受け入れていないのだけど…(デザイントーストは中級も受け入れてますが)
質問:「何でこのデザインにしたの?デザインの目的は?」
話を戻します。
「クオリティは低くないけど作品がダメって、どういうこと?」と思う人、では、一つここに作品を用意してください。
そして、この面談で必ず聞かれる質問に答えてみて下さい。
「あなたは、なんでこのデザインにしたの?この制作物の目的はなに?」
もう一つ、
「そして、この質問の意図は何だと思いますか?」
あなたの回答は、どうでしょう?
・
・
・
もし、これを聞かれて
デザインの見た目の話をしてしまったら、個人的にはアウトーー!!
なぜかというと、面談者の質問の意図は、あなたが
「誰にとって」
「どんな目的を叶えるために」
「どのくらいの思いの強さで」
「どう具体的に想像し、調べた上で制作したか」
が知りたいから。
デザインはクリスマスツリーの飾りつけではなく、パーティーの計画そのもの
デザインは、
見たユーザー目線に立ち、どういう心理状況で見て、何を感じ、どう行動し、その結果どう目的を達成するのか。という想像力が必要。
これを意識して制作していないと当然、説明することもできません。
デザインを例えるなら、クリスマスツリーではなく、クリスマスツリーを含むパーティーの計画そのものかもしれません。
【A. クリスマスツリーの飾りつけ】
これなら、子どもでもできますね。
計画なしに飾りつけして「なんかそれっぽくできた」でいいからです。
【B. 友人を家に招くクリスマスパーティーの計画】
これはどうでしょう。
「全員で10人来るから、料理はこのくらいの量かしら?」
「テーブルレイアウトは、〇さんは子どもを連れてくるから、赤ちゃん用の椅子も用意しよう。ドアの近くだと挟まるかもしれなくて危ないから、こちらに置こう」
「皆プレゼントを持ちよって大きな荷物だろうから、クリスマスツリーは玄関の近くだと邪魔かもしれないから奥へ置こう」
「〇さんと〇さんは仲が良くないから、あっちとこっちに座ってもらおう」
お客さんの具体的な行動を想像をした上で、「楽しめること」という目的に合わせ、危険を極力減らすなどの計画が必要です。
これは、経験がある事ももちろんですが「こうではないだろうか?」と沢山想定をする事が必要です。
そう、招くメンバーと関わり合いのない人にいきなり"レイアウトを考えてみて"と言っても、よい計画ができるはずがないんです。
デザインにおいても同じで、「お客さんを知る=リサーチ」から始めないと、彼らがあなたのWebデザイン上で、どんな思考回路から行動するのか想像がつかないはず。
もし何も考えなかったら、お子さんが怪我をしたり、誰かが喧嘩してしまい、「楽しむ」という目的が達成されなくなってしまいます。
デザイン=設計、という意味なのが、なんとなく伝わるでしょうか。
課題:ビーガンバーガーを売ろう
例えばあなたがお客さんに「うちのこだわりのビーガンバーガーを売ってほしい」と言われたとします。
「誰にとって」
「どんな目的を叶えるために」
「どのくらいの思いの強さで」
「どう具体的に想像し、調べた上で制作したか」
再び、以上の面接官の聞きたい内容を意識して答えるべく、解答するなら?
【よい回答例】
「誰にとって」→美味しいバーガーを見つけられないビーガンユーザー
「どんな目的を叶えるために」→ハンバーガーの売上を上げる
「どのくらいの思いの強さで」→リサーチし競合をこう調べ、ビーガンが美味しさ以上にバーガーの作られる過程やこだわりに共感して購入している事実に気づいた、等、努力の結果得た事
「どう具体的に想像し、調べた上で制作したか」→ユーザーが見て、オーナーの想いを知ってもらい、共感から購入につなげたい
【よくない回答例】
【良くない例①】言われないと制作者にしか分からない、画についての説明
「このデザインの黄色は、月をイメージして…」
「円を使った理由は、皆が繋がれる柔らかい雰囲気を表していて…」
見た目の説明は、正直どうでもいい。
その見た目が誰にどう作用する狙いがあるか?
が知りたいんです。
「ピンクにすることで柔らかさを表現した」より
「ピンクにすることで柔らかさを表現し、見る人に”ここに来たら意見が言いやすい”と思ってもらえるようにしようとした」
の方がいいということです。
個人的に、デザイン全体の構造や構成に意味があることは重要ですが、一つ一つの細かい詳細イメージへの意味は、いらないことが多い。
あとは「見る人がどういう気持ちになるか」という事に着地したい。
人に説明してみて、「アーティスティックだね」「なんかピンとこない」と言われたら、それは多分、表現から連想ゲームをして自己満足になってないか?を今一度振り返ってみるといいかも?
【良くない例②】頑張ったよアピール
「このデザイン作るのに、1ヵ月かかりました!」
「競合100社調べました!」
頑張ったんだね。結果は?と思われる可能性。
頑張ったかどうかは結果であり、判断するのは自身ではないんです。
なので、その結果、何を得たのかを必ずセットで言った方がいいです。
「ビーガンに何でなったのか?という背景を調べた事で、一部ビーガンの方たちの商品選びに、このような傾向があるという事がわかりました」
結論
「想像したか?」というのはデザインに如実に表れます。
ポートフォリオの見せ方だけでなく、作品自体が考えて作られていないとよくない、ということ。
じゃどうすればいいんだよ!という人、
少なくとも、一回目に現れなくても「ユーザー目線を想像して作るx3回」くらいで、視認性・情報整理・見せ方の意識が全然違うものが作れるようになってきます。
見る人の目線になっていると、見る人に親切なので、面接官にも伝わるんです。
その他、転職の裏側を含めた「理由2-4」も、次の記事で紹介していきますね!
うちのスクールです↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
