
こんな身近なところに、長い間、探していた事を知っている人がいた【本:窓ぎわのトットちゃん】
『窓ぎわのトットちゃん』1981年3月5日に第一刷発行。まだ自分が生まれていないときに出版されたこの本は、きっと自分が通っていた学校にも、街の図書館にもあったに違いないけれど、もうすぐ70歳になる元数学教師の方に「あなたの人生は、黒柳徹子さんに似ているから、『窓ぎわのトットちゃん』を読んでみてください」と言われ、すぐさま今いる場所の図書館で借りてきた。
今、偶然にもいる「学院」が、境遇や歴史、成り立ちは全く異なるのだけれど、トットちゃんこと黒柳徹子さんが恩師小林先生に出会ったトモエ学園にある「エネルギー」「可能性」といったものと重なる点が多くて、私は、これについて、こんどの「発表会」にでもみんなに話したいと思っているくらい。
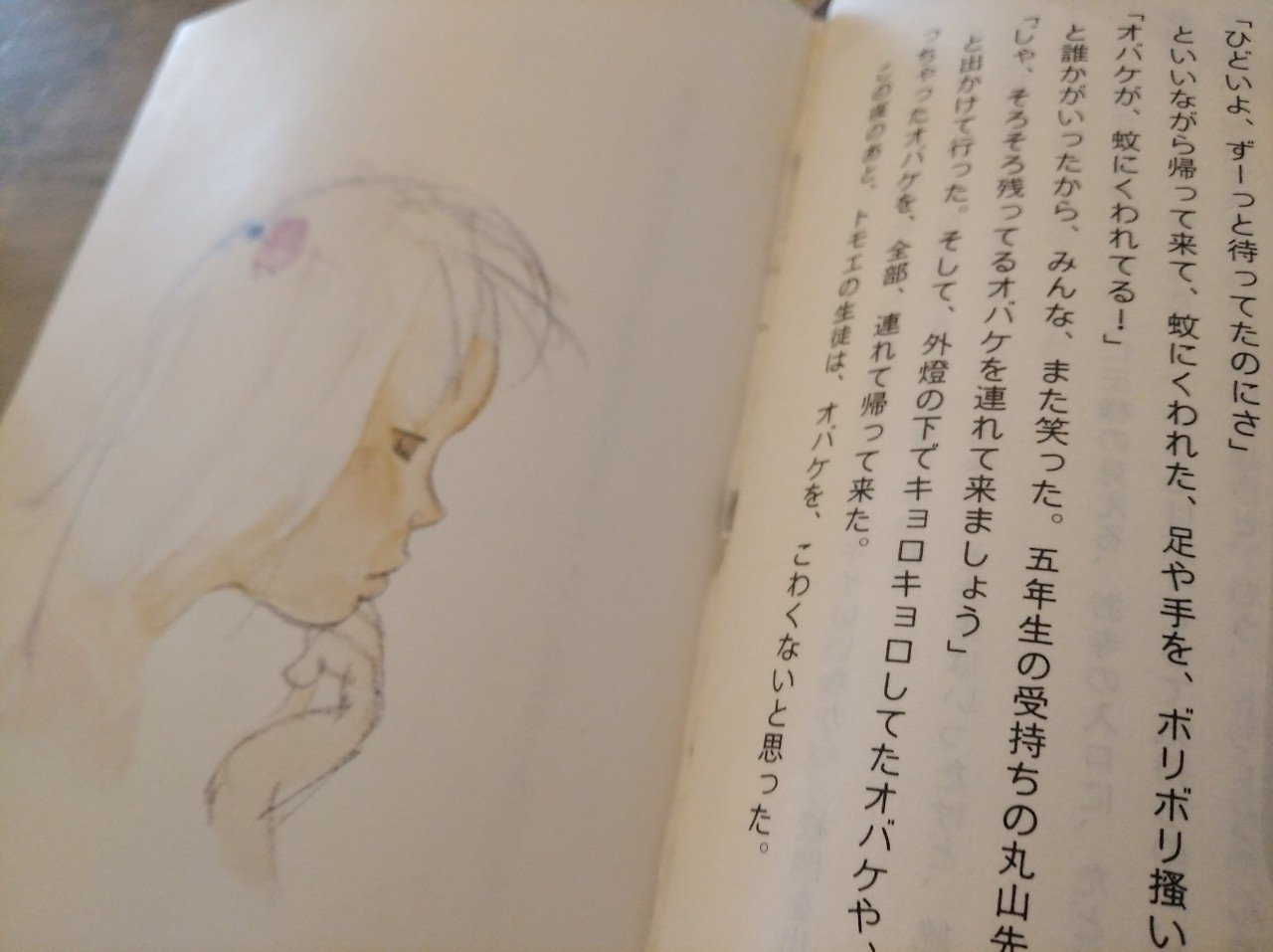
まだ、この本に本当に出会っていない人々へ。私は、あなたの今の境遇を知らないけれど、きっと何歳でも、どんな人々にとっても、学ぶことがある気がします。で、その学ぶことっていうのは、きっとすぐに「自分のもの」にはできないかもしれないけれど、人生を賭けて守りたいものや貫きたいものが、少しだけわかるような、そんな感覚です。
「こんな身近なところに、長い間、探していた事を知っている人がいた」
この言葉は、黒柳徹子さんの知り合いの方が、ずっと小林先生の子供たちへの向き合い方を研究されていて、それでも、黒柳徹子さんのトモエ学園の小林先生とは繋がらず、ようやく2人が同じ人のことをずっと話していたことが判明したときの言葉。でも、近くを注意深く見渡してみれば、きっと、そんな「運命」を感じられる瞬間はいくらでもあるのではないかな、とも思えた。
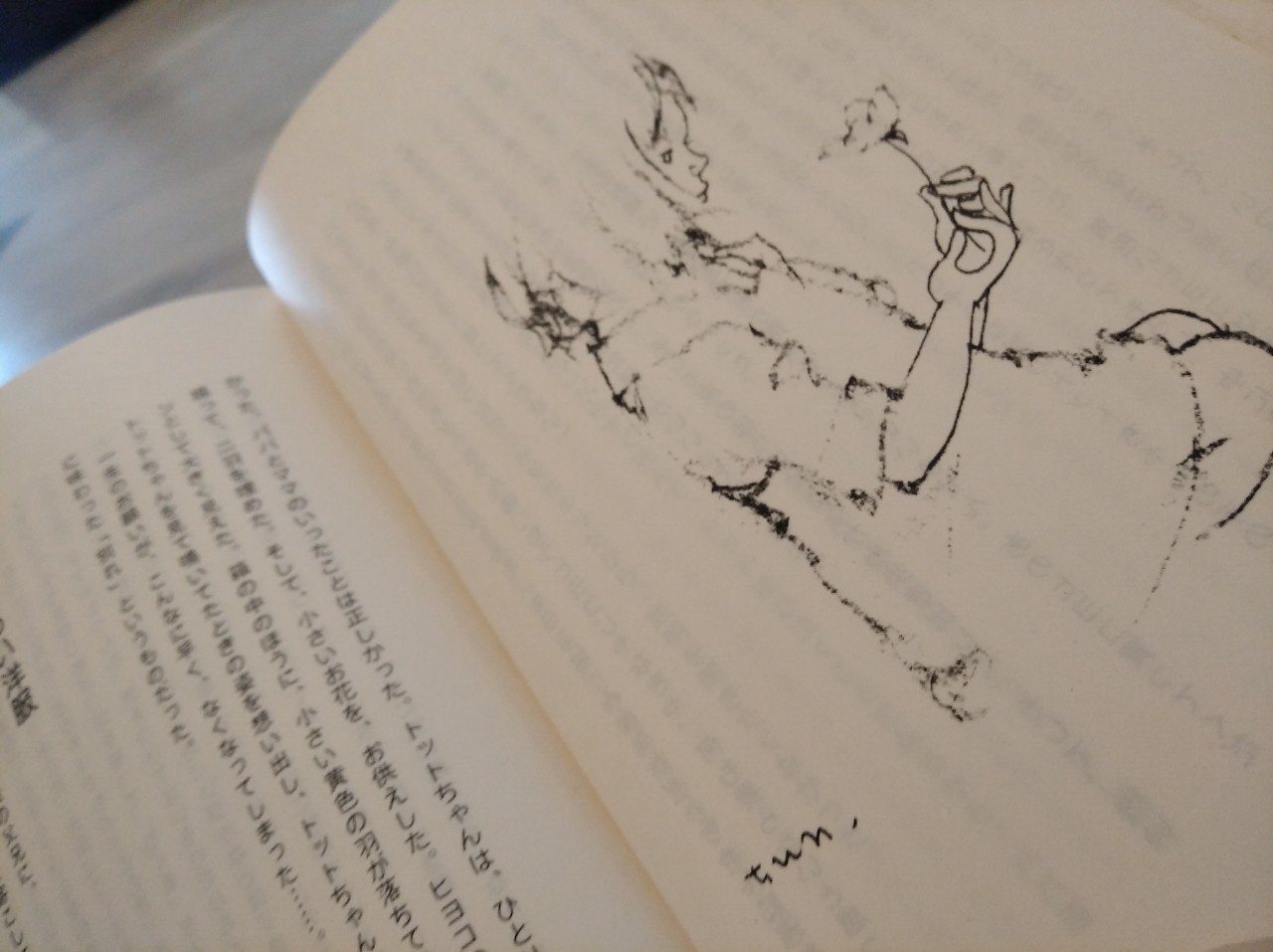
・トットちゃんは、なんだか、生まれて初めて、本当に好きな人に逢ったような気がした。だって、生まれてから今日まで、こんな長い時間、自分の話を聞いてくれた人は、いなかったんだもの。
・なんとなく、疎外感のような、他の子供と違って、ひとりだけ、ちょっと、冷たい目で見られているようなものを、おぼろげには感じていた。
・トットちゃんは、自分の全生命を、このとき、かけていた。
・トモエ学園のトモエは、白と黒から出来ている紋所の一種の二つ巴で子供たちの身心両面の発達と調和をねがう、校長先生の心のあらわれだった。
・「文字と言葉に頼り過ぎた現代の教育は、子供達に、自然を心で見、神の囁きを聞き、霊感に触れるというような、官能を衰退させたのではなかろうか? -世に恐るべきものは、目あれど美を知らず、耳あれども楽を聴かず、心あれども真を解せず、感激せざれば、燃えもせず・・・の類である」
・海のものと山のものを持ってくるお弁当。みんな食べる前に歌を歌う。そして、「いただきます」の前の誰かのお話。
・「これからの子供は、人の前に出て、自分の考えを、はっきりと自由に、恥ずかしがらずに表現できるようになることが、絶対に必要だ」
・運動会のごほうびは、野菜
・一等になった自信を、忘れないでほしい
・ふつうの小学校では、生徒に、なにかを教える人には「先生の資格」とか、いろいろ規則があるのだろうけど、子供たちに「本物」を見せる事が必要なのだし、それが、大切なことだ、と先生は考えていた。
・「君の本当の性格は悪くなくて、いいところがあって、校長先生には、それが、よくわかっているんだよ」
・トモエ学園では、年齢と関係なく、お互いの困難を、わかりあい、助け合うことが、いつのまにか、ふつうの事になっていた。
・作文を読む子供たちの知らないうちに、太平洋戦争は、もう、いつのまにか、始まっていたのだった
・さっきは「信じられない」という気持ちと、「なつかしい」という気持ちだったけど、今は、一度だけでいいから、生きている泰明ちゃんと逢いたい。逢って、話がしたい。
・明るい春の陽ざしが。始めて泰明ちゃんと、電車の教室で逢った日と同じ、春の陽ざしが、トットちゃんのまわりを、とりかこんでいた。でも、涙が、いまトットちゃんの頬を伝わっているのが、始めた逢った日と、違っていた。
・戦争の音。ご近所の、おじさんやお兄さんが、いなくなっていった。海のものと山のものも、実行が難しくなり、なにもかもが配給になっていった。
・「校長先生、私、この学校の先生になる」
・日本の空に、いつアメリカの飛行機が爆弾をつんで、姿を見せるか、それは、時間の問題、といわれているとき、この、電車が校庭に並んでいるトモエ学園の中では、校長先生と、生徒が、十年以上も先の、約束を、していた。
・「動物を、だましちゃ、いけないよ。君達を信じてる動物を、裏切るようなことをしちゃ、可哀そうだからね。」
・トモエが焼けた。
・小林先生の子供に対する愛情、教育に対する情熱。

以下、黒柳徹子さんのあとがき。
「君は本当はいい子なんだよ」と言い続けて下さった、この言葉が、どんなに、私の、これまでを支えてくれたか、計りしれません。
日本にも、沢山の、いい教育者のかたが、いらっしゃると思います。みなさん、理想も愛情も、夢も、お持ちと思いますが、それを実際のものとするのが、どんなに難しいか、私にも、よくわかります。
「自然の中のリズムを見つけよう」
小林先生は、宣伝嫌い、今でいうマスコミ嫌い、ということで、戦前でも、一度も、学校の写真を撮らせるとか、変わった学校ですよ、と宣伝することがありませんでした。そのおかげで、この小さい、全校生で50人足らず、という小学校が、誰の目にも触れることもなく、継続できたのではないでしょうか。
目先のことじゃなく、何十年もの先を考えて私達を育てて下さった小林先生。
こんな身近なところに、長い間、探していた事を知っている人がいた
どことなくあった疎外感と窓ぎわ
創造の場所であるカフェ代のサポートを頂けると嬉しいです! 旅先で出会った料理、カフェ、空間、建築、熱帯植物を紹介していきます。 感性=知識×経験 மிக்க நன்றி
