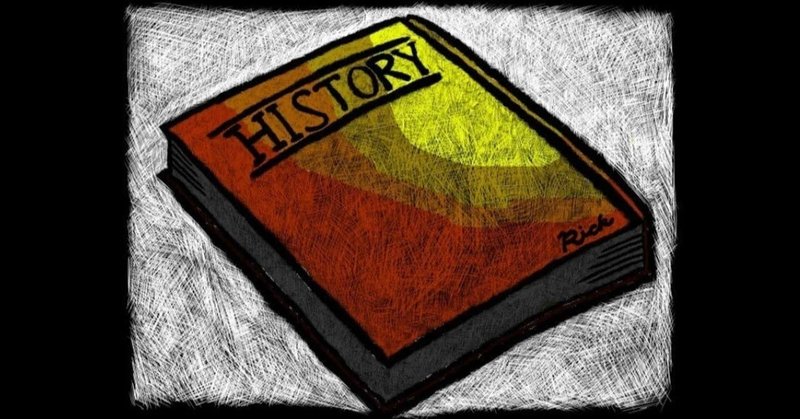
夢Ⅰ(36)
Λ V Λ Λ
森に入ってから、先を急ぐはずの旅の速度は明らかに遅くなっていた。
リックの歩幅に合わせたことも理由の一つではあったが、ヌエ達からも焦りや、背後から迫る者を警戒する様な緊張感は感じられず、要所々々でしっかりと休憩を取り、一日の終わりには長い休息を挟んだ。
休憩の折には、彼らは自慢の弓さばきで野鳥を獲り。澄んだ空が、ちらちらと映り込む渓流に差し掛かると、川魚を取ることで、日々の食卓を潤すこともした。
瑞々しい草葉を着込んだ、巨木から、老齢の古木まで、大小様々な木々。
ソリの中で《黄色》の話に幻想を膨らませて作り上げた湿り気を含んだリックの薄暗く影を落とす森とは、かけ離れて。
森は、種々の生命力で満ち溢れ、彩に富んでいた。
4人で囲む食卓には、歌や踊りが戻り、森を進む中で彼らは本来の姿を取り戻し。草原での食事に比べれば見劣りするものの、森から授かった恵みに感謝の祈りを捧げた。
彼らは、草原でしたように、櫓を囲んだ連日連夜の宴を執り行うことはしなかったが、リックが、「それがいつ始まっても、あの時のように、気を失うまで歌い踊ることが出来るだろうか。」と問いかけると。心の奥底。明るさを持った温かく人の形をした塊が、「出来るさ。」と答えてきて、リックは少し強く、優しい気持ちになった。
リックが腰丈の枝葉を払い、四苦八苦と草地を抜けると、小さな渓流が姿を現した。
久方ぶりの渓流は、木々の影に切り取られた空の輝きをキラキラと湛え。流れは、他の風景と同様に《茶色》からある程度離れると、まるで絵画のように、時を止められ、チラリとも姿を変えなくなる。
リックの、昨晩の寝不足を気遣い。一行は、その川岸で普段よりも早い休憩を取ることになった。
川を縁取る程よい小岩に荷物を下ろし、一息つく。足元では、下流へ向けて運ばれていく水が、躍動する力を少しずつ奪われながら、過去の光の中に折りたたまれるように吸い込まれていく。
リックが足元の流れを見るともなしに眺めていると、ハラハラと澄んだ川面に、羽織の鮮やかな赤が揺れた。
川面のまどろみから我に返る。視線を上げると明るく陽気な顔の《赤色》が隣に立っていた。誰よりも陽気で、おしゃべりな彼の纏う温かな雰囲気、それはヌエの大きな容姿をさらに大きく見せて、森の中、リックの少し前を歩く背中には、何度も励まされた。
隣の彼は、リックに合わせるように、じっくりとした間を置くと「この森の木で造ったんだ。」と小脇に抱えていた包みをそっと差し出し、微笑んだ。
包みは、手に取るととても軽く。結び目を解くと、黒く光沢を帯びた弓が姿を現した。それは、《赤色》が森の中で暇を見つけては削り、森の木から丹念に磨き出したリックのための弓で。ヒヤリとした肌触りがとても柔らかかった。
弓は、しなやかで、どれだけでも引き絞れて。
また、引いた力とは見合わない速さで、ビシリと元の姿に戻った。
下流で制止する水の流れに、閉じ込められた魚の背の光。
《茶色》から離れれば離れる程に歪にグニャリと数を増し、それらは決して減ることの無い過去の投影で。その中から、一匹の魚が光の呪縛から解き放たれ、飛び跳ねる自身の陽炎を下流に残したまま、リックたちと同じ光の流れに姿を現した。
降り注ぐ光の中で、川面から飛び跳ねる魚の姿。
ヌエ達は、「視覚」を使わずに狩りをする。
彼らにとって、相手が「意思の声」を持つ限り、「飛び跳ねる」ことを知ることは容易く。
過去の光に惑わされない彼らの、弓の技術は洗練されていて、魚の行き着く一点を正確に射貫いた。狩られるその一点を目掛けて。
その日から《赤色》は彼らのやり方で、弓の使い方を教えてくれた。言葉を使い、体の動かし方を伝え。リックも疑問があれば、自身の意思で口を使い、声にして《赤色》に問いかけた。
ヌエ達と違い、「心の声」が聞こえるわけでもないのに、彼らのやり方で弓を使い、獲物が取れるようになるはずがないと、以前のリックなら始めから取り合わず、彼らにどう答えようと、体が言うことを聞かなかっただろう。
あの部屋で《水色》に託された。《黄色》が繋ぎ《灰色》との別れを選び、森の中にいるリックは、彼らのために、「何か。」「どんなことでもいい。出来ることをしよう。」と思うようになっていた。この身体を使って。自身の声で。
《赤色》が話す言葉のすべてを、リックが理解することは出来なかった。
ヌエ達の「心の調和」を起点にした技術を、リックは「身体」で、彼らとは対極にある位置から、「弓」という、《赤色》の伝えようとしてくれている核となる中心を掴むために、繰り返し繰り返し練習した。
「言葉」では収まらない、まるで全貌の見えない巨大な球体の重心を探るようなその作業は、日に日に、少しずつ、少しずつと進んだ。
雪原越えで、中断されていた《青色》との短剣の型の練習も再開される中で、森での日々はするすると流れ。
一行は、「果て無き森」の中心へと、一歩一歩近づいていた。
Λ V V Λ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
