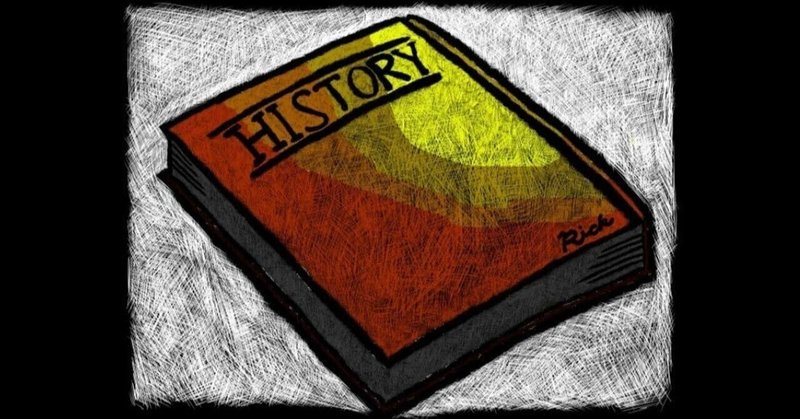
夢(37)
Λ V V Λ
川魚の表皮を火の穂が、パチパチパチと滑っていく。
木陰に腰を落ち着けて、四人が囲む即席の炉に並んだ6匹の魚の、小ぶりの1匹は、リックの記念すべき連日の弓の鍛錬の賜物である。
数十万回と繰り返し。
繰り返した動作は、次第に掌に、腕に、身体に馴染み、そして、筋となり体表に刷り込まれ、小ぶりではあるが1匹の魚を捉えたのだった。
《赤色》が練習を強制することはなく。
彼は本当に、純粋に弓を操る一つ一つを、大切しているようで、対話するように弓を絞る姿は、とても美しかった。
馴染みだした動きは心が落ち着き、とても心地よかったし。リックも《赤色》のようにありたいと思い。疲れを忘れるほどに、何度も何度も、弓を引いた。
また、《青色》との短剣の型の練習も、型の数が百を超えたところで、リック一人での練習へと様相を変え。相手の動きを想像し、受け止め、抑えて滑り込む。
それは、《青色》を相手に打ち込んだ練習よりも、はるかに難しかった。
相対する者の姿は、ときには《青色》よりも頭一つ大きくなり、または、リックよりも小柄だった。
ひたすらに。ただただ、ひたすら型どおりになぞり続けた日々の、慣れ親しんだ流れへと繋がる流線は、相手を失ってこその繊細さを得て。
以前に増してさらに洗練され、型に身を任せて無心になればなるほど。いないはずの、姿の無い相手の様子が鮮明に浮かび上がり。リックは《青色》から教わった型を通して、ときには、その流れに逆らいながら、短剣の支える力を感じ取ることが出来るようになっていった。
そして、並んで木剣を振るう《青色》の、一つ一つの身のこなしもまた、とても美しかった。
とてつもなく巨大な球体の体表は、ふやふやと、ゆっくりと大きく揺れ、重心を一点に留めることはなく、弓も短剣も、もしかすると、その他のあらゆるもの全てをその大きく揺れ動く重心に包括しているのかもしれなかった。
リックが、焼きあがった小ぶりの魚を噛みしめていると、隣の木立の先。茂みの奥で、カサカサと音がした。
動きを奪われた光は、茂みをピクリとも動かさない。
また、カサと音がする、小さな動物か、この森特有の何か動きを持った未だ見ぬ物体だろうか。ヌエ達は、落ち着いている、彼らと共に行動しているうちは、よほどのことがない限りは安全なのだろうが、得体のしれない物音が気になり、身構えてしまう。
せっかくの小魚の余韻を、味わう間もなく、すっかりと飲み込んでしまった。
この森に踏み込んだ頃は、《茶色》からある程度は離れる余裕のあったリックたちと同じ時間の流れを持つ光の円は、明らかに小さくなっていて。すぐ隣に立ち上がる木々の先で、動くことをやめた光の無限の連なりは、もう何一つ有益な情報を持ち合わせていなかった。日を追うごとに、目に見えて狭まる、動くもののない視界、もうほとんど役に立たない視覚。
焚火を囲み、川魚を頬張る。こうした、ヌエ達と過ごすことの出来る時間に、全く不満はないものの。小さく一塊で進む、木々の根の凸凹や、隆起する地形の登り降りに翻弄される路程に、最近は、息苦しさを感じるようになっている。
動きを止めた枝葉の合間から降り注ぐ日の光も、木漏れ日の新鮮さを感じることは出来ず、どこか色あせて感じられた。
視界を横断する、天を突き抜ける木肌は、眼前に迫ってはいるが、その圧倒的なスケールから距離感はあてにならず、月日を重ねても近づいてる実感を持つことが出来ない。
一行の最終目的地である、森の中心を目指す、この最後の行進に「本当に終わりはあるのだろうか」と、他人事のようにふと考えることが多くなった。
茂みのカサカサに重ねるように、最初は、《赤色》が抑揚を付けて、喉を震わした。
それは、リズムとは無縁の何の規則性もない闇雲に発せられる音でしかなかった。でも、スラスラと浮き上がり、ヒラヒラと下降する、まるで蝶が羽ばたくように大気と調和した音は、決して耳障りではなかった。
《青色》が後に続くことで、音は厚みを増し、色味を得た音階は次に繋がるべき道順を示し。
時に主階を《茶色》に譲り、拍の手の加わったそれは、スラスラと自由な音域を刻みながら、そして、リックにもわかっていた。どこから入り、どこで飛び出そうと、彼らの音楽は気負いなく、乱れさえも一つの道筋として次へと繋がることを。
心の。虚空から湧き上がる高揚感は、それは安心感だろうか。フツフツとリックの体を温めた。
震わせる喉を通して、それは誰に向けたものでもなかったが、優しさをのせて。なにかと、いつも忘れてしまうけれど確かにリックも、この得体のしれない森の中でさえ。「僕も。」足元から、周囲の草木から、立ち上るものに受け入れられて、一つに溶け合っていると。
どんな時でも。あのソリから降り立ち、自身の足で踏みしめた草原で感じたように。
夜の闇が青く照らし出されるあの光景を。
目を開いていても、石柱を照らす白銀の月を見つめることが出来ることを。
Д Ц Ц Д
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
