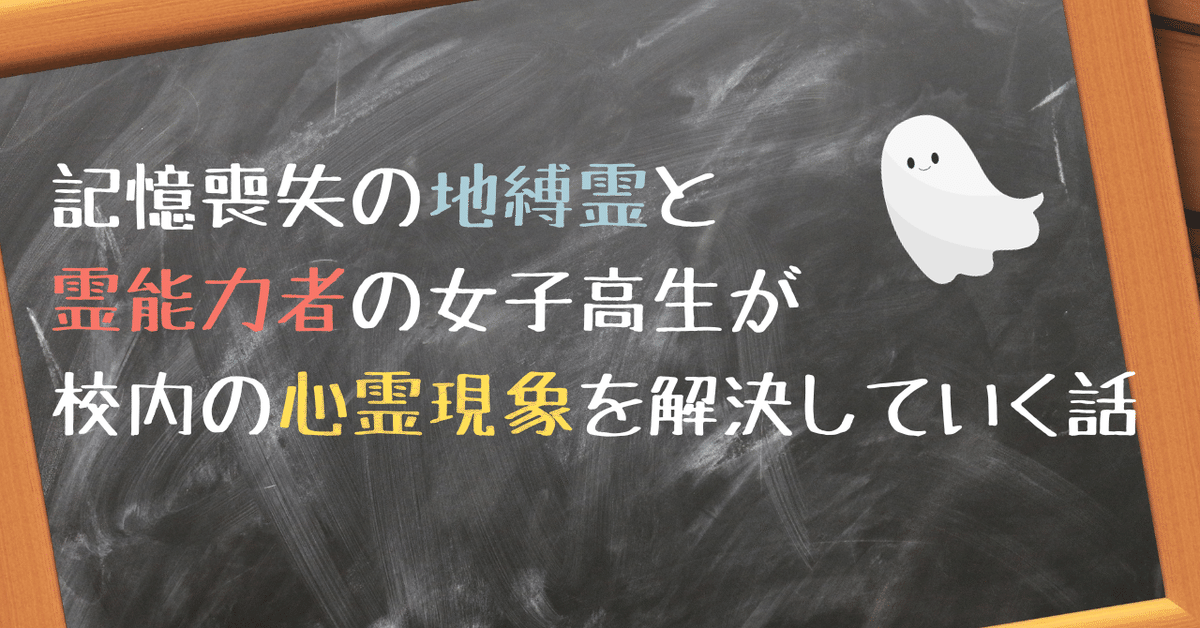
【長編小説】陽炎、稲妻、月の影 #15
第3話 死神の見識――(2)
校内の要所要所に護符を貼り、結界を補強する。
言葉にしてしまえばそれだけのことだが、作業量は尋常ではない。なにせ、先生が十数年がかりで張り巡らせた結界だ。一生徒であるアサカゲさんの学業に影響が出ないかどうか、という不安が俺にはあったのだけれど。
「先生のときは、結界を構築しながらだったから時間がかかったんだ。今回はそれを補強するだけだから、そんなに時間はかかんねえと思うぜ」
アサカゲさんは、俺の心配などどこ吹く風とばかりに、あっけらかんとしていた。
「俺は霊術に詳しくないんだけど、そういうものなの?」
「近くまで行けば、先生が昔に貼った護符の場所は、オレでも感知できる。その近くに、今回作った護符を貼っていくだけの、簡単なお仕事だ。あとは迷子にならなきゃ、なんてことはないだろ」
そんなやりとりをしつつ、最初に訪れたのは、第一教室棟である。
旧校舎の次に建てられたこの校舎は、築年数だけ見れば相当古いのだが、改築を重ねていった結果、全体的に真新しい印象に生まれ変わっている。トイレの照明は感知式だし、廊下も教室も、何十年も前に作られたとは思えないほど小綺麗だ。それ故、ここを使用しているのは三年生が主であり、一年生であるアサカゲさんは、普段ほとんど立ち入らない場所だ。
正面玄関を皮切りに、一階から順に回っていく。
アサカゲさんは小さな肩掛け鞄から護符を取り出すと、次々に貼っていった。感知できるという言葉に嘘偽りはなく、アサカゲさんの足取りには迷いがない。そうしてひとつの区画が終わる毎に、その場の空気が少しだけ、しかし確実に軽くなっていく。
「よし、終わり。ろむ、次の教室に行くぞ」
「はーい。それじゃ、こっち」
放課後というだけあって、昼間と比べれば生徒の数は少ない。が、全く居ないわけでもない。部活動や補習、その他にも様々な理由があって、各々学校に残っているのだろう。
そんな生徒の大半が、俺たちとすれ違う度、こちらに奇異の眼差しを向けていた。
俺は膝から下がない幽霊だから、そんな態度を取られても仕方がないと思える。
けれど、アサカゲさんにそれを向けてはいけないだろう。この学校の為、全校生徒の為にやっているのに、どうして彼女が疎まれなければならないんだ。
「……ろむ、お前、なんか余計なこと考えてんだろ」
「えっ、な、なんのことかな?!」
思考が顔に出ていたのだろうか。
俺は咄嗟に両手で顔を覆いながら誤魔化すように言ったが、アサカゲさんは軽く笑うと、
「そんなに他の奴らを睨んでると、悪霊と勘違いされちまうぜ」
と言った。
睨んでいるつもりはなかったが、彼ら彼女らに返す視線に負の感情が籠もっていたことは否めない。それは駄目だ、と、俺は自分の顔を両手で叩いた。
「ごめん、二度としない」
「は? あ、いや、別にオレ、そこまで強く言ったつもりはねえんだけど……」
アサカゲさんは、不意打ちを喰らったように目を大きく見開いていた。しかしすぐに平常心を取り戻し、言葉を紡ぐ。
「オレの周りの人間の大半は、物心がついたときから、ああいう奴らばっかりだった。だから別に、慣れっこだよ。いまさら噛みつく気力もわかねえだけだ」
移動先の教室で、アサカゲさんは護符を貼り始めながら、そう言った。
視えない人間になにを言ったところで、伝わることなどない。
そう物語るかのような、寂しげな表情をしていた。
だけど、慣れているからといって、傷つかないわけじゃないだろうに。
「……土地神様ってのが居たら、なにか違ったのかもしれないね」
現状為す術がない俺は、そんな他力本願な『もしも』を言うことしかできなかった。
なにせ、今のアサカゲさんの霊力の扱いは、ほとんど完璧である。能力が暴走することなど、万が一にもないだろう。だから、もしもここが普通の学校であれば、アサカゲさんは『視える人』として、ここまで悪目立ちしなかったかもしれないのだ。
「そしたら、オレとお前は会えてなかったじゃねえか」
護符を貼る手を止めず、アサカゲさんは言う。
「それにな、ろむ。弱くとも土地神の加護はまだあるんだから、最初から居ねえみたいに言うのは止せよ」
「だけど、人間がここまで手を入れないと場を保てないんなら、居ないも同然じゃない?」
本来は死者の魂の通り道であるというこの土地の空気を、清浄に保っていたという土地神。ハギノモリ先生もアサカゲさんも、まだその加護は消えていないと言うが、姿を現せないほど弱体化しているのなら、居ないも同義ではないだろうか。
己が守るべきものすら守れず、なにが神様だ。
「いや、確かにここには土地神は居る」
しかしアサカゲさんは、はっきりと言い切った。
「それは、まだ加護が残ってるから?」
それもあるけど、と言って、アサカゲさんは手を止めると、俺のほうに向き直る。
「オレ、ずっと昔にそれっぽいひとに会ったことがあるんだよ」
「えっ、なにそれ」
ここに長く勤めている先生でさえ、姿を見たことはないと言っていたはずだ。それなのに、この春入学したばかりのアサカゲさんが、何故会ったことがあるのか。
「この近くに越してきた頃に、いろいろあってな」
そうしてアサカゲさんは、当時の記憶を辿るように窓の外に視線を移す。
「当時のオレから見たら、ずうっと背が高く見えたから、もしかしたら今のオレよりも背が高ェかもしれない。長い黒髪を後ろでひとつに結んでて、秘色色の着物を着た、物腰の柔らかい、優しいひとだったよ」
「ひそくいろ?」
聞き慣れない色の名前だ。
「あのひとに着物の色の名前を訊いたら、そう言ってたんだ。浅い緑色っつうか、灰みがかった青色っつうか――」
アサカゲさんは言葉で説明してくれようとするが、いまいちぴんとくる表現が出てこないらしい。
「ねえ、もしかしてそれって、そういう色?」
言って俺が指差したのは、アサカゲさんが右手首につけているブレスレットだ。ずっと青みがかった薄い緑色だと思っていたけれど、彼女の言う色味に似ていないこともない。
「アサカゲさんのその髪型も、もしかして、土地神リスペクト的な……?」
「……」
「あ、あれ、違った?」
「……う」
「う?」
急に小声になってしまったアサカゲさんの声が聞き取れず、俺は聞こえた音を繰り返しながら近づくことにした。
「う、うるせえー!!」
途端、俺の推測を掻き消すように、アサカゲさんは、うるせえうるせえ、と大声で繰り返す。
「良いだろ別に! あのひとに会えたから今のオレがあるっつっても過言じゃねえんだからさっ! あのひとの格好を真似て、なにが悪ィんだよ!」
アサカゲさんは吠えるように吐き出し、唸るように俺を見る。
「ともかく! オレはガキの頃に、ここの土地神っぽいひとに会ったことがあんだよっ! 気配が独特だったから、ほぼ間違いねえ! 卒業するまでには絶対に見つけ出すつもりなんだから、邪魔すんじゃねえぞっ!」
「じゃ、邪魔なんてしないよお……」
かつてない勢いでまくし立てるアサカゲさんに、俺は怯えながらそう答えるしかなかった。
肩で息をするアサカゲさんを落ち着ける為に、俺はもう一度、邪魔はしないよ、と繰り返す。
「見つかると良いよね。それは俺も応援してる」
いつ消えて居なくなるともわからない幽霊に、こんなことを言われても仕方がないだろうけれど。アサカゲさんがそれだけ再会を熱望しているのなら、それが叶うようにと、俺も願いたい。
「……おう」
声を荒げることはなくなったが、今もなお険しい表情を浮かべるアサカゲさんは、徐ろに俺との距離を詰めてきたかと思うと、いつもより数段低い声で、それとだな、と言う。
「オレの髪は、いざというときの対価にする為に伸ばしてんだ。あのひとと同じ髪型になったのは、全くの偶然だ。そこんとこ勘違いすんじゃねえぞ」
「……」
いやいや、さっき『あのひとの髪型を真似てなにが悪い』って言ったじゃん。
喉まで出かけた突っ込みを、必死に堰き止める。それを言ったらどうなるのかは、火を見るよりも明らかだ。
「おい、わかったら返事しろよ、ああ?」
「イエス、マアム!」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
