
◆読書日記.《原田信男『日本人はなにを食べてきたか』》
<2023年3月10日>
いま読んでるのは国士舘大学教授で生活文化史学者の原田信男『日本人はなにを食べてきたか』である。
生活文化史学者による日本の食生活について古代から現代までの通史を作る試み。
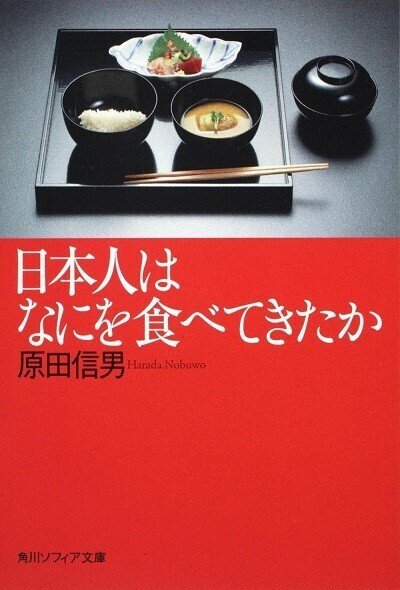
書名を見て軽い読み物だというイメージで読み始めたのだが、実際は著者の論文を250ページに圧縮した学術的な内容で情報量も濃い。が、これがバツグンに面白い。
やっぱり社会史というものは面白い。
しかし、この手の社会史が学校のカリキュラム化される事も一般に知られる事も少なく研究も活発でないのは、政治史や戦史、宗教史とは違ってしっかり体系的に記録されてきたわけではないので、残されている史料が少ないという事情がある。自然、この研究は学際的なものになるのである。
こういったジャンルを横断する学際的な思考が好きだからこそ、たぶんぼくはこの手の社会史が好きなんだなぁと思う。ぼくがカイヨワや澁澤龍彦なんかが好きなのも、学際的な傾向があるからだろう。
ただ、そのぶんこの手の研究は通常の歴史研究よりもより厳密性が問題になってくる、という事は否めないだろう。
考古学と人類学と歴史学では扱っている資料が違っているし、だからこそそういった資料や記録を恣意的に扱ってしまう危険性もある。著者によれば「超歴史的な解釈を施す傾向に陥りやすいことも否定できず」とも書いている。
研究者が少ない、研究コミュニティが小さい、という事も科学としてはマイナスに働いてしまう。
しかし、こういった研究も誰かが足場を作らねば永遠に手を付けられる事もなく様々な資料がどんどん失われて行ってしまうだけなので、意味のない試みとは思わない。
◆◆◆
日本の食生活の歴史に関する顕著な特徴を挙げるとするならば、「神聖なコメ」と「穢れた肉食」というのがあるだろう。これが本書の中でも一貫して重要なテーマとなっている。
日本はなぜ米を神聖視し、なぜ肉食を穢れとしたのか?というのは日本の食生活史にとっては重要な問題なのだ。
仏教思想が肉食を禁忌とした、という考えもあろうが話はそう単純ではない。著者は、重要なのは農耕との関係で見なければならない、と指摘している。肉食の禁忌は、国家政策としての水田耕作への注力とパラレルの関係にあるという。
例えば『日本書紀』に書かれた肉食禁止令は天皇から出されているそうだが、その条件は4~9月までの肉食禁止である事(おそらくその時期に農耕へ注力させる狙いがあったのだろう)、そして牛・馬・犬・猿・鶏の5つの動物に限って禁じているという制限であったという。
だから、それ以外は割と庶民も貴族も一般的に肉を食っていたらしい。
また、7世紀あたりからは国策として「農作の月」には酒と肉を謹んで、水田稲作に専念せよという法令が全国に出される。
どうもここから国家は農耕期間中に肉食や飲酒をすると稲が良く実らない、という迷信を持っていたらしい事が伺わせる。
魏志倭人伝にも、倭人は喪に服している時は肉食を控えると書かれているそうだから、古代国家から農耕期は肉食を控えねばならないという「穢れ」的な風習は存在していたらしい。
しかし、こういった肉食の禁令は逆に言えば稲作の推進のためのものでもあった。
何しろ国家を運営している人たちは畑仕事をしない。
農民から吸い上げた税で食っていっているわけだから、自分たちが安心して食事にありつけるようにするためには、食料の安定供給を国策として推進しなければならなかったわけだ。
農民は狩猟や採取生活でも食っていけるだろうが、貴族等はそうはいかないのだ。
安定的に食料が確保でき、長期保存が効き、栄養価の高い米の生産は自分たちの生活レベルを保つためにも必要だったのだろう。
それを貴族が食べる「聖なる食」として農民から献上させた。
しかし、農民としては米は厳しい税の取り立てでそのほとんどを国に献上せねばならないものだったから、相変わらず肉食で栄養を補っていたという部分はあったらしい。
と言う事で肉食への禁忌は律令国家を担った王侯貴族をメインに形成されていき、歴史を下るごとに徐々に社会の下層へ広まっていったようだ。
◆◆◆
国にとって「食」というのは無視できない要素だ。国家も食料の安定供給が出来、余剰生産物も出るようになってやっと成立する。
そういう社会基盤がしっかりとしていないと社会を動かしていく余力となる上級階層も生まれないし、他国と戦う軍事力を支える食料も確保できない。
食料事情というのは国力と無関係ではないのだ。
例えば、北海道に国家が成立しなかったのは、食料の安定供給が難しいという条件もあったようだ。
稲作に向く気候ではなく寒く厳しい気候条件があったために、蝦夷地はながらく狩猟や細々とした畑作などによって食料をまかなっていたので、まとまった国力を有する集団は発生しなかったようだ。
だから、蝦夷地は日本とは違った「異国」として、日本とは違って肉食を禁忌としない歴史を歩んだ。だからアイヌの貴重なたんぱく源として鹿、熊、鮭を捕って生活をしていたのだ。
ちなみに、日本はわりと古くから北海道との交流自体は持っていたらしい。
特に昆布なんかの自生地は寒冷でなければならないので、日本料理や沖縄料理で使われる昆布は古くからの北海道との交易がなければ成立しなかったという。
<2023年3月11日>
先日も説明した様に、日本の食生活の特徴の一つに「聖なるコメ」と「穢れた獣肉」というのがあった。
肉食は「食穢」の意味もあるが、コメの神聖視は現代も日本の祭祀のそこかしこに見られる。神棚には米・酒・塩などをお供えするし、神前に「おもち」や「お酒」を捧げる事が多いのも、どちらもコメを加工して作られたものだからという事もあるだろう。

逆に、獣肉は長いあいだ神前には「穢れ」として捧げられなかったらしい。
日本の「穢れ」感は三つあって「死穢」「産穢」そして「食肉穢」の三つだった。もちろん、このどれにも「血」が関わるから古代社会では忌み嫌われてきた。
人類学的にも古来から血を忌み物としてきた文化は世界各地に見られる。
そういう事情があるから、例えば農耕で使えなくなった牛馬を締める屠殺を生業としていた屠者は、日本でも卑しい身分の者とされた。
伝統的な被差別民の「穢多(えた)」の語源は「餌取(えとり)」で、牛馬を殺して肉を売る者を意味していたという。
古代社会でコメが重要視されたのは、宗教的な理由だけではなく国の食料政策として農民らに稲作を推進していたからでもあった。
古代の日本社会がコメを神聖視し、肉食を卑しいものだとしていたのは、稲作が当時の超先進国である中国から渡ってきた「優れた栄養価の食料を安定供給する技術」だったという事情もあっただろう。
稲作は古代社会にとって食糧事情を飛躍的に改善する優れた「技術」だったのだ。だから狩猟は「野蛮」とされたのだろう。
国をしょって立つ自分たち貴族らの食料を安定的に確保するにはどうすれば良いのか? 今よりも食糧事情が厳しかった古代社会で「飢えない」というのは重要な課題であった。
その「国策」として推進するには、狩猟-肉食体制では、肉は腐敗し易くて保存が効かず、安定的に獲物にありつけるとは限らないので不安定であったのだ。
だから、税を取り立てるべき農民には、栄養の安定供給が望めるコメを作るように「強制した」とも言えるだろう。
貴族の考えとしても、先進技術の稲作は文明的で優れている、それに引きかえ狩猟は野蛮だ……という風になっていきそうなのは想像できる。
だが、コメはもっぱら貴族のみが頂ける食材だった。
年貢として収穫したコメのほとんどを献上し、農民の手元にはわずかなコメしか残らない。だから農民にとってコメはハレの日などに食べる特別な食材になった。酒もコメから作られるし、正月にいただくお餅もコメから作られる。
普段は粟、稗、麦など雑穀や畑作で作った作物なんかを食べるのだが、それでも栄養価は足りず、そのためにしばらくは農民の間で「飢えないために」肉食は続けられていたのだ。
肉食をせずとも生きられる貴族らのみが、仏教思想に影響されてますます「肉食は穢れ/野蛮/悪」というイメージを強めていったらしい。
因みに、長和五年(1016年)『小右記』によれば、検非違使の妻に乱暴を働いた男に馬肉を食べさせるという「馬肉の刑」が課された事があったという。
中世には馬肉は毒だと信じていた人たちもいて、そのために馬肉食が刑罰としての意味を持ったのである。
◆◆◆
日本では常民にとって米は貴人のみが頂ける貴重な食材で、ハレの日くらいにしか食べず、また神前に捧げる神聖な食物であるという考え方もあった。
このように米を神聖視する見方は古の社会から長く伝えられていて、香川県三豊郡では「米は天照大神の御眼である」といい、新潟県西頚城郡では「一粒の米に三柱の神様がはいっている」などとも言われるように、常民にとっては長らく米は尊いものだと思われていた。
そのために逆に米を粗末にすると罰が当たるという言い伝えは全国各地に見られ、米にまつわる信仰や言い伝えは非常に多い。
(以上、参考文献:鈴木棠三『日本俗信辞典 植物編』)
それに関連してか、同じくコメに呪術的に神聖な力があるという信仰も生まれている。
塩をまいて穢れや凶事を祓う習俗があるように、コメにも塩と同じような魔除けの力があると考える習俗が日本各地に残っている。
例えば『源氏物語』には出産時に米を妊婦に撒くシーンがあるが、それもコメに清め、払い、魔除けの呪力が込められていると信じられていたからだという。
また、埼玉県入間市では「旗などを建てるための穴を掘る時は塩と米を少し撒いてから掘ると怪我なく行う事ができる」と、佐賀県東松浦郡鎮西町では「赤ちゃんのむつきを初めて洗う時は、川へ行って塩と米を撒き、川の水を汲んできて釜のなかでかき回すと良い」などとも言うそうだ。
(以上、参考文献:『Books Esoterica 30 呪術の本』(学習研究社))
<2023年3月13日>
「平らな土地が少ない」=「稲作面積が少ない」=「食料自給率が常に問題となる国」である日本は、古代から栄養価が高くて保存の効くコメ作を国策として推進し、その完成を見たのが近世社会だったと言えるだろう。
江戸幕府は米を国の経済基盤とし、全ての耕地の生産力を米で換算し、経済力が「石高」で示されるようになった。
こういった「コメ」を国の経済基盤に置くという石高制のシステムは世界でも類例を見ない特殊な社会システムだったようだ。
全ての税を「コメ」に還元して負担させるというコメ中心主義はこの近世社会によって完成した。
それまでの年貢というのは米だけでなく布や魚など様々なものが納められていたのだ。
ただ、こういった完全なコメ中心主義によって以前からあった肉食を「穢れ」と見る風習も、近世に至って遂に庶民一般にも定着し「常識」化される事となったのだという。
まぁ、幕末の庶民が外国人たちの肉食を驚いたのなんてのは、たかだか江戸社会200年ちょっとの短い常識だったわけである。
◆◆◆
食文化の発展というのは「贅沢」というものと不可分の関係なんだろうな、と思う。
社会の余剰生産物が庶民の間にまで行き渡っていなければ、食料による「贅沢」というのは享受できない。
食料自給率の厳しい日本で食文化が頂点に至ったのはやっと近世に至ってからで、他国も似たようなものだったのではないかと思う。
「食文化」と呼べるようなものがあったとしても、他国でも封建主義的な国家体制の中ではそれは王侯貴族らの間に限られるもので、大抵の庶民は重い税のために、年に数回の祭りの時以外は質素な食生活を強いられたという事情は変わらないのではないだろうか。
日本では近世に至るまで「食文化」とは支配者層が担うものだった。
中世までは貴族らが料理や食事作法を発展させたが、中世に至って武士が政権を担うようになると自前の「文化」的なものを持たなかった武士は、公家から積極的にそういった文化を取り入れるようになった。
武士は権力を持つまでは農民と同じく貧しい生活をしていたし、戦闘訓練の一環として狩猟にも興じた。
そのために武士には肉食の風習があったのだが、権力を握って食料の心配がなくなり、公家の文化を吸収し、更には水田の支配者としてコメを守る身分として、次第に肉食を否定するようになっていった。
そういった流れで、武家社会となっても古代律令国家から続くコメ中心主義的な食文化は受け継がれる事となったのだ。
◆◆◆
近世日本のコメ中心主義の完成と前後するように日本の食生活の重要なトピックとして挙がってくるのが「茶」であろう。
古代から一部で茶は飲まれていたようだが、本格的に茶が飲まれるようになったのは中世後期の事で、臨済宗の開祖・栄西が中国から茶種を持ち帰り禅僧寺院で飲まれるようになった。
こういった茶の由来が、後に茶道が禅思想と結びついていく契機ともなったのかもしれない。
当初茶は薬として用いられていたが、鎌倉時代末期から南北朝時代に至って都市や農村で庶民の間でも寄り合いなどで闘茶が盛んに行われるようになり、喫茶を楽しむ風習が広がって行ったのだそうだ。
日本の茶文化は懐石料理と共に発展していったという部分もある。
「懐石」というのも禅と関連のある言葉で、その由来は禅の修行僧が空腹をしのぐために、懐に温めた石を入れたという「温石」にある。懐石は茶会に出されるささやかな食事を意味した。
貴族の茶会にしても農民の寄り合いで茶を飲む事にしても、どちらも料理は出されていて、しばしば茶よりも酒宴のほうがメインになっていたりしたという。
そもそも寄り合いや茶会などは「供食」、皆で飲食を共にするという意味があり「懐石」も一座との共同性を持った「会席」を楽しむ事が目的の飲食であったのだ。
こうした会席の考え方の反動として、茶会は茶をメインに楽しむものだという考え方が先鋭化してくる事で後の「侘茶」が生まれてくる事となるのである。
<2023年3月14日>
江戸時代に至って長いあいだ肉食禁忌の習慣が一般庶民にまで定着していた日本だったが、一部では陰で食べられていたりもしたらしい。
それがいわゆるイノシシの肉を「牡丹肉」とか「山鯨」という隠語で食べられていたりという状況だった。
他にも馬肉は桜肉、鹿肉は紅葉肉と言っていて、それぞれの食材を使った紅葉鍋や牡丹鍋などもあった。

江戸末期には肉食への禁忌意識は当初よりも薄れていた部分があったそうで、特に西洋について学んでいた蘭学者やアウトローといった人たちはそういった獣肉も好んで食べていたのだそうだ。
その上で明治時代が始まって政府が西洋化政策を打ち出すと、徐々に庶民文化にも西洋料理が浸透してくるようになってくる。
特に西洋に詳しかった福沢諭吉は積極的に肉食を推奨していたそうだ。
一方でやはり獣肉の肉食には抵抗を示す向きも勿論あった。
例えば保守的な御岳信仰の行者などは具体的な行動に出たという記録もある。
天皇の御膳に肉食が出されるようになったと知った十名ほどの行者が明治五年2月に皇居に乱入し4名が射殺、1名が重傷を負い、残りも全員逮捕されるという事件も起こっている。
これらは決して小数ともいえず、中には徹底的に肉食を批判した者もいたという。
幕末から明治時代に活躍した戯作者である万亭応賀などは日本の西洋化を徹底批判し、肉食が横行した事によって社会がおかしくなった等と主張していた。
◆◆◆
帝国陸軍の軍医であった森鴎外は明治十八年に『日本兵食論大意』にて、その当時の国民全員が米食をした場合、およそ700万石のコメが不足すると計算しているという。
次第に米の消費量が増えてきていたのだが、その供給を政府はどこに頼ったかと言えば、日清・日露戦争にて領有した台湾と朝鮮であった。
つまりは、国内需要を解消するために、この2国に日本米の耕作を行うように押しつけたわけである。
台湾では日本米は巧く生産できなかったそうだが、朝鮮では水利事業の投資や土地改良などの努力が結実し、特に朝鮮南部は日本と気候が似ていたためもあって産米計画が推進されて行った。
朝鮮による稲作政策は実を結んで産米の増収できたが、ここで忘れてならないのは、このような日本の植民地化政策によって朝鮮では大地主に土地が集積していき、そのために逆に貧農が増える事となってしまった。
日本による朝鮮の米の増収は、逆に朝鮮の農村を荒廃させてしまったという側面があって、貧民に陥った朝鮮人がが満州や日本に渡って低賃金労働者になるという現代にも続く問題に繋がるのである。
◆◆◆
日本の食卓から箱膳が消えていき「ちゃぶ台」にとってかわられるようになるのは大正末期から昭和初期の頃であったという。

これは家族構成の変化も関わっているそうで、例えば大家族構成の食事であれば囲炉裏の間でとるのが普通であったが、小家族化が進むといちいち一人ずつに箱膳を用意するよりもちゃぶ台にまとめたほうが効率が良くなったのである。
その他にもオカズの数が増えて小さな箱膳には入りきらなくなったという事情や、食事の西洋化が進んで油が多く使われるようになったために食器をいちいち洗わなければならなくなった等と言う事もあって、けっきょく箱膳では手間が多くなってしまったという事もあるようだ。
<2023年3月15日>
先日からその内容を逐一ご紹介して来た原田信男『日本人はなにを食べてきたか』も遂に読了した。
食文化史を研究している著者初の「日本の食生活の通史」である。
本書のポイントでもある「なぜ日本はコメ中心主義を選んだのか?」という問題は、そのまま日本の食生活史を通貫するテーマともなっている。
そして、これがぼくにとっても今まで最大の謎だったからこそ、本書の内容は非常に興味深いと思ったのだ。
内容をざっとまとめるならば、最初に日本のコメ作の流れを作ったのは、国家政策として食糧事情の改善を目論んだ古代律令国家がコメを選んだためであった。
飢えないためには、日本の気候にマッチしていて毎年安定供給が望め、栄養価の高いコメを大量生産する事が最も効率が良いという考えがあったのだ(そして、稲作が大陸から渡ってきた「高度な新技術」であったという事情も関係しているだろう)。
日本は古代社会からずっと国家体制として稲作を推進してきて、やっとその完成を見たのが近世社会であった。
しかし、その間コメ食を享受してきたのはそれを作る農民ではなく、ほとんど貴族や武家など支配階級の者たちだった事は忘れてはならないだろう。
そういった事情が、根底で日本の食文化に大きく影響を与えているのである。
農民が長い事、ハレの日くらいにしかコメ食にありつける事はなかったために「コメの地位も上がった」という事もあるだろう。粟や稗といった穀物が「雑穀」と呼ばれる理由も分かる。
その反面、日本の食の作法や料理作法などはもっぱら貴族らが独自に発達させていき、それが中世で武士らに継承され、近世に至ってやっと庶民にも行き渡っていった。
「飽食する支配層と飢えた庶民」という偏った状況は、コメ食を庶民も享受できるようになった江戸時代に解消できたかと言えば必ずしもそうとも言えなくて、江戸で大食い選手権などが行われていた半面、地方の貧村では依然としてコメさえ食えぬ状況で飢えていた人たちもいたのである。
一部の人間が飽食を貪っているという状況にありながら、見えない所で飢えている人たちがいるという偏り、これは現代でもさほど変わりがない。状況がグローバルになっただけだ。
食糧問題について、日本国内では古代から近世にかけては支配層-被支配層という格差、都市-地方格差によってそういう偏りが出ていたが、現代では先進国と開発途上国との間での偏りというように国際化しているのである。
われわれも毎日テレビ番組でグルメ番組が定番のように放送されているので「飢え」という問題に鈍くなっている部分もあるだろう。
その陰で近年では国内でも貧困のために餓死する家庭も出てきているし、更に言えば開発途上国で未だ5億人以上の人々が食料不足に悩んでいる状況を忘れてはならない。
「飽食をするな」というのではない。問題なのは、食糧問題と言うのは現代に至っても撲滅するに至っていないにも関わらず、そういう状況を知る機会も少なく、われわれはそういう事情に半ば鈍くなってしまっているという事ではないだろうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
