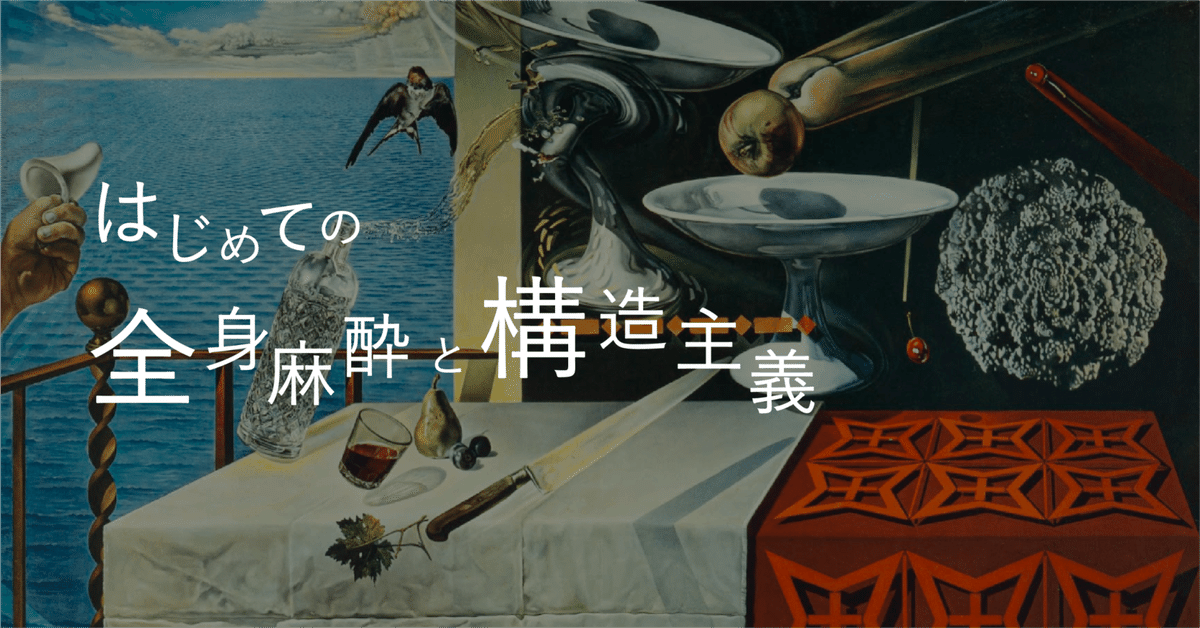
課程博士の生態図鑑 No.20 (2023年11月)
※ サムネイルの背景に使用しているのは、サルバドール・ダリによる「Nature Morte Vivente」という作品の一部を切り取ったもの。
人生初の全身麻酔
11月は、人生初の全身麻酔の手術を経験した。
といっても、重い病気に罹ったとか、そういうわけではない。
実は約2年ほど前から歯の矯正治療(厳密には顎変形症の治療)をしているのだが、手術はその一環である。
11月8日の朝9時に手術は行われた。8時間に及ぶ手術らしいのだが、命の危険に関わる類ではないので、術前の緊張は全く無く、全身麻酔が楽しみなこと以外に感情の起伏は特に無かったと思う。
いざ全身麻酔が始まると、少し体が熱くなり、次の瞬間には集中治療室にいた。本当に一瞬の出来事だった。ふと気付くと口の中(というより顔全体)はパンパンに腫れ上がった上に、開かないようゴムで固定され、さらに鼻は血が詰まっていたので、歯の隙間から呼吸するしかない状態になっていた。ちょっとでも気を緩めると呼吸が止まりそうな感じは本当に気分が悪い。定期的に看護師さんが鼻の中を吸引してくれて、少しは呼吸しやすくなったのだが、1分後にはまた同じ状態になった。鼻炎持ちのせいもあるかもしれない。
集中治療室はかなり異質な雰囲気で、常に看護師さんが慌ただしく何かをしている。そんな雰囲気も相まって、呼吸が止まることへの恐怖も増幅していく。多分6時間くらいたった頃だろうか。正確な時間は正直わからないのだが、流石に緊張している状態に疲れ、ふっと寝てしまった。だが、案の定呼吸が止まってすぐに飛び起きた。寝たら死ぬかもしれない、と本気で思った。
そんなこんなで、呼吸することだけに集中しながら翌朝まで集中治療室で過ごし、自分の病室に帰ってきた。呼吸の状態は特に変わらないので、安心して寝れるわけでもなく、かといって憔悴しきっていたので、スマホを触る気力もない。唯一変わったことといえば、下顎がひとりでに動き出すようになったことくらいだ。なぜかはわからない。術前の説明でもそんなことは聞かされていなかった。顔の形が少々変わったので、筋肉が適切な位置をひたすら探しているような感じがする。これがなかなか痛い。30針程度縫った傷口が閉じていないのにも関わらず、1〜2時間おきに10分間下顎が勝手に暴れ出すというサイクルに数時間悩まされることになった。
呼吸の苦しさと、顎が暴れ出す痛みに耐えながら数時間過ごしていると、看護師が車椅子を持って迎えにきた。どうやらCTを撮りに行かなければならないらしい。部屋を出れば何か変わるかもしれないと思い、すんなりと車椅子に乗った。(どのみち行かなければならないのだが)
検査室に入ると、歯科用のCTが部屋の奥に見えた。やったことある人ならわかると思うが、歯科用のCTは顎の高さくらいに設置してある台の上で頭を固定し、頭の周りをぐるぐると機械が回る仕組みになっている。今までも何回か経験したことがあるので、説明を受ける前に顎を台の上に乗せた。スキャンが始まると、いつも通り頭の周りを機械が回る。
すんなり撮影が終わったのだが、医師に撮り直しを命じられた。あまり気づいていなかったのだが、ちょっと下顎が動いてしまったらしい。また始まったか…と思い、下顎のことを意識した途端、さらに暴れ出した。2回目の撮影が始まっても顎の暴走は止まらないので、また撮り直しになると思い、なんとかして動きを止めようとしたが、全然ダメだった。自分の体すらもコントロールできない恐怖に怯えていると、自分の頭の周りを回る機械に対しても謎の恐怖を覚え、首から下も少しずつ震え出し、体勢が崩れてしまった。その様子を見ていた看護師が僕の背中をぐっと掴んで体勢を戻そうとしてくれたが、さらに体がガタガタ震え出し、最終的には過呼吸になって崩れ落ちてしまった。人生で初めてパニック状態に陥った。
気を失ったのか、あるいは記憶が飛んだのかはわからないが、気づいたら病室に戻されていた。口の固定がさらに強くなっていたが、そのおかげで勝手に下顎が動き出す恐怖からは解放され、鼻の通りも心なしかちょっとだけ良くなっていた。
安堵したのか、約30時間ぶりにまともな睡眠をとることができた。
さて、全身麻酔の手術についての体験談を書くのはこのへんで終わりにする。尿管を抜いた後のお小水の排出がクソ痛いだとか、食事が大変だったとか、書けることは色々あるが、基本的に手術翌日以降は特に問題もなく、1週間で退院することができたので、わざわざ書くこともない。といってもずっと暇だったので、ここからは入院期間中に読んだ本について紹介する。
実験的にいつもと違う文体で書いてみたが、ここからはいつもと同じ感じに戻す。
入院中に読んだ本たち
ダイアローグ
この本は、ヴァージル・アブローという黒人デザイナー(わざわざ黒人と書くのは、彼の意図を汲んだつもりである)が生前に残した対話をまとめたものである。ヴァージルはファッションブランドである Off-White の設立や、ルイ・ヴィトンのクリエイティブディレクターをやっていたことなどがあり、服や靴のデザインをしているイメージが強いが、実際には色んなものに携わっている。そもそも学生時代はエンジニアリングや建築について学んでいたらしいので、かなり異色な経歴と言える。
彼の最も特徴的なスタイルとしては、レディメイド(既製品)を使用することにある。ヴァージルが大学院を修了してから最初のプロジェクトは、PYREX VISION という、デッドストックのラルフ・ローレンを1着40ドルで買い付け、その上に文字などのプリントを施して550ドル以上の値段で販売するものだった。僕は全然知らなかったが、ストリートファッション好きの間ではカルト的な人気があったらしい。
彼にはゼロからモノをデザインしたいという欲が無いらしく、既存のものを別の場所(物理的にも、意味的にも)に移動することを志向している。どうやらデュシャンやモダニズムの影響を強く受けているみたいだ。
さらに、ヴァージルがデザインするものには以下のような特徴がある。
ヘルベチカはアブローが手がける大半のものに使用されており、それは彼が建築を学んでいた時分に魅了されたモダニズム・デザインの伝統を受け継いでいることを意味する。引用符もまたグラフィックを多用する彼の作品にはおなじみのものだ。インタビューの最中にも、雑誌に掲載される際にはかならず “ストリート・ウェア” と “マーチウェア” を引用符でくくってほしいと頼んできたほどである。
彼にとって、デザインの根底にあるのは目的と意図であって、問題解決だとか、問題創出だとかは関係ない。全く新しいものを作る必要もなく、あるものを別の場所に移動させるだけでもデザインなのだろう。本の中で、クリエイターにとって最も致命的なのは過去を認めないことだと言っている部分があった。
誰も作ったことがないものだけをデザインしようとするのはとても不自由なことであり、歴史との繋がりや関係性を捨象することになるので、世界が狭くなってしまう。彼が重視している “引用” という行為は、世界と繋がり(横にも縦にも)、視野を広くしてくれる手段なのだろう。
近代デザイン史
近代デザイン史について、プロダクト、建築、グラフィックなど、様々な分野から検討している本。結構前に斜め読みしたのだが、改めて熟読してみたら結構面白かった。
特に面白かったのは、第三章の「エディトリアルデザイン」のところだろうか。
エディトリアルデザインの歴史は古く、グーテンベルクより遥か昔である12世紀初頭の「しるしに関わる三つの大きな条件について」という文献の中に、書物の装飾の機能についての記述があるらしい。この文献では、これまで装飾として扱われていた図像を、書物をわかりやすくするための機能として扱っており、人と情報を繋ぐインターフェイスとしてのデザインが明確に意識されるようになったきっかけになったのだという。
また、エディトリアルデザインは、情報を人の記憶に定着させる役割を持っている。
神の言葉が書物化した聖書は、そこに語られる実体とは大きくかけ離れた象徴記号としての文字で記されており、それらをただ眺めるだけでは学修したことにはならない。学修するとは、文字という人間の持ち物によって書かれた神の言葉を記憶し、内面化し、それらをどんな時でも想起できるような状態にすること。それが神の言葉を読み、修めるということであるというのだ。そのような聖書の受容の仕方を提唱したフーゴはまた、自身の著作「しるしに関わる三つの大きな条件について」の中に《⋯私たちが書物を読むとき、記憶の表象を定着させるのにたいへん有効なのは表象力によって詩句や観念の数や順序のみならず、同時に文字の色や形、位置や並び具合、すなわちこれやあれやがどこに書かれていたか、どの部分、どの場(てっぺんか、真ん中か、一番下か)に置かれていたか、文字の線や、羊皮紙の表面の彩色が何色であったかを記憶に刻みつけるように努めることだ》と記す。
聖書は神の言葉を書の中に閉じ込めたものだが、それを人々が記憶し、いつでも引き出せる状態にしないと意味がない。神の言葉を記憶に刻み込むためには、文字を整理整頓し、情報の位置関係を平面的に表現する必要がある。
しかし、そこにはある種のジレンマが存在する。それは、オリジナルのテキストと印刷されたテキストは異なるということだ。ここでいうオリジナルのテキストとは、まだ視覚化されていない情報(聖書で言うところの神の意思そのものの内容)であり、シニフィエである。一方で印刷されたテキストとは、人間によって編集され、視覚化された情報であり、シニフィアンのことだろう。
エディトリアルデザインが情報と人との間のインターフェィスとしてあるならば、もちろんその一義的な役割はその情報をすみやかに伝達することであり、その伝達において情報が変わることは望まれない。が、しかしエディトリアルデザインの定義上、情報すなわちテキストが純粋な形で出てくることはありえない。つまりエディトリアルデザインはその作業を望まれつつ、敬遠されるという矛盾を抱えた技術であるといえよう。たとえば編集者の「デザインしないでデザインすること、そのままの原稿を大切にして」という言葉をそのまま受け取り、原稿のまま本にすると、そのデザイナーは怒られてしまう。
エディトリアルデザインは、不可視なオリジナルの情報を可視なものにする役割があるが、目に見えるものにした時点で編集作業が必ず発生してしまうので、情報を純粋な形で表現するのは不可能である。そこでモホリ=ナギは、エディトリアルデザインにおける写真の役割に注目し、単なる現実のコピーではなく、新しい現実を作り出す造形手段としての写真を探求した。元の現実をそのまま表現するのは無理だから、新たな現実を作ってしまえ、ということだろうか。そして、モホリ=ナギは図像や文字という峻別を超えた手法を「タイポフォト」と名付けた。
彼が取り組んだ活動の意味を完全には理解できないが、確かに現実は複雑で、言語だけで捉えようとするとむしろ現実から遠くなってしまう感覚はすごいわかる。言語を超えた、あらゆる感覚を統合するような情報伝達の先に現実は待っているのかもしれない。ただ、さっきも言ったようにエディトリアルデザインの定義上、現実にたどり着くことはできない。本来の現実の上に、現実っぽいものを重ねるように構築する以外に方法はないのだ。
この本は他にも面白い章がたくさんある。イギリスで産業革命やそれに伴うアーツ・アンド・クラフツ運動まで起きたにも関わらず、ドイツでデザインのメインストリームが形作られた理由や、コルビュジェとミースの違い、都市化や人間の移動スピードの向上に伴い出現したアール・デコなど、様々な出来事の背景が解説(というより解釈)されていた。気になる人はぜひ読んでみてほしい。
はじめての構造主義
ヨーロッパ中心史観に終わりを告げ、現代思想に新たなモノサシを提案した構造主義について解説している本。構造主義といえば、レヴィ=ストロースという人類学者を中心としたムーブメントである。以前「発酵文化人類学」という本を読んだ時にレヴィ=ストロースが紹介されており、その時から彼の本を読んでみたいなと思っていたのだが、まずは構造主義自体の概観だけでも触れておくか、という感じでこの本を手に取った。
とにかく難しい、というのが最初の感想だ。実際にレヴィ=ストロースの本を読んでみないことにはなんとも言えない。ただ、構造主義が登場した歴史的な流れには納得する部分があったので、ちょっとだけ紹介してみる。
そもそも構造主義が出現する以前、19世紀的な世界の見方は「社会とは、単純でどうしようもない状態から、徐々に複雑で機能的に、つまり近代的な文明に向かって進歩・発展していく」というものだった。そんな価値観に囲まれていたレヴィ=ストロースは、「一般的に未開人だとか野蛮人だとか言われている人々も、繊細で知的な文化を持っており、我々のやり方とは違うだけでかなり理性的な人々なのではないか」という主張をする。
話がちょっと前後するが、レヴィ=ストロースが構造主義に辿り着くちょっと前、機能主義人類学(マリノフスキーという人類学者に始まる学派)が、構造主義と似たような観点で19世紀的な世界の見方に反旗を翻していたことも紹介したい。
機能主義以前の人類学は、歴史主義、伝播主義とよばれている。社会は「未開」の段階からだんだん進歩していくもので、最終的には西欧近代にたどりつく。進化論の影響もあって、そう考えていた。原住民の社会は、どこか劣っていたり、欠けるものがあったりして、完全なものではない、と決めつける。(中略)それはおかしいではないか、と機能主義はいう。「未開」社会といっても、それなりにまとまりをもった社会のはずだ。ある習慣は、どこから伝播したかしらないが、そんなことより、その社会のなかでどんな役に立っているのか。それが大切である。いろいろな習慣や制度や宗教(ものの考え方)が、その社会のなかで密接に関連していることを、「機能」といおう。たとえば、トーテム信仰(いろいろな動物が、自分たちの氏族の祖先であると信じること)は、集団の結束を保ったり、親族関係をはっきり認識したりするのに役に立っているではないか。つまり、そういう機能をもっている、と考えればよい。
また、機能主義人類学は、二次資料だけに頼らず、現地に乗りこんで一緒に生活しながら現地住民の世界の見方を身体を通じて観察し(現在の人類学の原型と言ってもいいだろう)、詳しい調査報告を書き上げる手法を採用している。観察を通じて、調査対象の社会の「機能性」を突き止めようとしたのだ。
しかし、機能主義人類学には以下のような問題があった。
機能主義人類学は、ひとつの社会をまるごととりあげ、そこで見つかるいろいろな事柄のあいだにどういう関係があるか、考えようとする。全部をいちどにとりあげるわけだから、すべてがすべてに関連していることになり、何が何の役に立っているのだか、わからなくなってしまう。目的/手段の連鎖が、一列ではなく、ぐるっとひと回りしてしまうのだ。これではぐるぐる回りの循環論(説明しているようで、実は説明になっていない)になるじゃないか、と文句がでる。
AはBを実現したり達成したりするために行われ、BはCのために存在し、CはAのために存在する、そんなことが起きてしまうのだ。機能主義人類学はこれまでの歴史主義的な人類学のあり方に反旗を翻したという点で言えば構造主義と変わらないのだが、機能主義はその名の通りなんでも機能で説明しようとするあまり、非合理的で役に立たないものが説明できない。「やっぱり未開の人は非合理的だなぁ」という結論になってしまう。
よくよく考えてみると、社会のことを何でも機能で説明する前提の場合、すべての行為に主体的な目的が必要になる。レヴィ=ストロースは、そんな人間の主体性を否定し、「構造」という、ある種集合的な現象にアプローチを試みる。例えば人間はコミュニケーション(交換)をする生き物だが、すべてのコミュニケーションに目的があるわけではない。むしろ無目的なコミュニケーションが先行しているのだ。つまり、社会がまずあって、その中にコミュニケーションの仕組みができるわけではなく、そもそも社会とはコミュニケーションの仕組みそのものだという。主体的に目的を設定して行為を行なっているわけではなく、構造が先にあり、人間はそこに組み込まれているだけなのだ。あくまで交換のための交換が先にあり、それが変化していった場合にだけ、利害に基づいた目的性のある交換が現れるに過ぎないとレヴィ=ストロースは言う。ソシュールが「言語において、区別に先立つ実態はない」と言ったように、社会において交換に先立つものはない。交換こそが社会であり、人間なのだ。
彼は最初、親族の交換システム(女性の交換にまつわるインセスト・タブーなど)を解明することでこれを証明しようとしたが、のちに神話研究を始める。ものすごく簡単にいうと、各地に散らばっている神話をかき集め、それぞれをバラバラに解体し、出来上がった神話素のリストを貫く構造を抽出するというものだ。レヴィ=ストロースが画期的だったのは、テキストを文字通り読み解かなかったところにある。神話に現れるメッセージは表層にすぎず、本当の構造はその奥に隠れていると考えたのだ。
今でこそテキストの解体作業(テキストマイニングやコーディング)は一般に普及した手法だが、当時の西欧ではかなり衝撃的だったに違いない。なぜなら、テキストを解体するということは、それを書いた人の意志(聖書や神話の場合は神の意志)を解体するということだからだ。機能主義人類学は人間の意図や主体性が合理的に働いている証拠を炙り出すものなので、こういったことはできない。まさにレヴィ=ストロースらしいアプローチだろう。なので彼に言わせると、未開と言われる社会も、近代的と言われる社会も、皆同じ構造を持っているが、言語や土地などのプロトコルの違いが要因で、表象として立ち現れる文化や文明が違ってくるということだ。なので「未開→近代」の線形的なモデルにはならない。
ここまで、多くを端折りながらも何とか構造主義について説明してみたが、もっと説明すべきことはたくさんある(僕自身あまり理解していないという問題もあるが)ので、気になる人はぜひ本書を手に取ってみてほしい。ちなみに本書の最後では、ポスト構造主義についても軽く紹介されているのだが、どうやらポスト構造主義も構造主義の域を出ていないらしい。「レヴィ=ストロースの構造主義は完全な構造主義ではない」という、より構造主義的なものや、「構造主義だと、現象の通時的でダイナミックな部分が扱えない。人間の主体性が消えてしまった」という、構造主義以前に逆戻りするうような批判ばかりだという。ポストモダニムがモダニズムの域を出なかったように、ポスト構造主義も構造主義のくびきからは逃れられなかったようだ。確かに僕も、歴史や主体性をあまりにも捨象してしまった構造主義には若干の違和感が拭えないので、フーコーなどのポスト構造主義を中心に、もう少しだけ深掘りしてみたいと思う。
日本文化の核心
松岡正剛という思想家が、日本文化を様々なキーワードから考察している本。かなり面白かったのだが、構造主義の話でそこそこ文字数を稼いでしまい、僕にとっても読者にとっても疲れるので、できるだけ短くまとめる。ただ、めちゃめちゃ面白かったことだけは先に念押ししておく。
そもそも日本文化の魅力とは何なのだろうか?松岡曰く、日本の文化はかなりハイコンテキストであり、一見わかりにくいように見えるものにこそ真骨頂があるという。また、日本文化の正体は「変化するもの」にあり、一つのキーワードから分解できるものでもない。なので、「柱を立てる」という風習に注目して日本における神の捉え方を考察してみたり、「和すると荒ぶる」という相反するものが共存してきた歴史から、日本文化のデュアル性について論じたり、「まねびとまなび」の関係性から日本人がどのように文化を形成してきたのか解釈するなど、多角的な視点から日本を見つめ直している。
個人的には、デュアル性が肝なのではないかと思っている。神と仏の両方を信仰するという、海外から見たら訳のわからない現象も、漢字という中国から渡ってきたものを、音読みと訓読みを共存させる形で昇華させたのも、デュアルな文化たる所以だ。少しニュアンスが異なるが、日本近代科学史という本において、日本の文化を二重構造というキーワードから考察していたのが思い出される。
では、なぜ相反するものが共存している(共存しているように見える)文化が形成されたのだろうか。それは、日本が災害の多い国で、フラジャイルな島だったというのが要因の一つかもしれない。
日本という国を理解するためには、この国が地震や火山噴火に見舞われやすい列島であることを意識しておく必要があります。いつどんな自然災害に見舞われるかわからない。近代日本の最初のユニークな科学者となった寺田寅彦が真っ先に地震学にとりくんだのも、そのせいでした。日本はフラジャイル(壊れやすい)・アイランドなのです。しかも木と紙でできあがった日本の家屋は、火事になりやすい。燃えればあっというまに灰燼に帰します。すべては「仮の世」だという認識さえ生まれました。
これは、先ほど挙げた「まねび」ということにも繋がる。日本はフラジャイルな性質を持っていたからこそ、まねびにより外部から来たものを積極的に写しとり、それゆえに複雑で相反するものが共存するというデュアルな文化になってしまった。だからこそ変化も激しい。
また、松岡は日本文化の魅力の一つに「面影を編集する」ということも挙げていたのだが、これもフラジャイルでデュアルな性質から解釈できる。今まで日本文化は外圧により何度も上書きされ(完全にではないが)、変化を繰り返してきたからこそ、面影的に文化が継承されていく。その面影をまねび、復原し、さらにはそれを編集することが守破離なのだろう。日本文化における型とは面影なのだ。松岡が日本文化の核心を「変化」に見たのも、何となくわかる気がする。
日本人は記憶の中の面影を情報化し、そこに編集を加えていったのです。和歌も能も、俳諧も浮世絵もそのようにして生まれ、溝口健二や藤沢周平はそのような面影を映画や小説にし、美空ひばりや井上陽水はそうした面影を歌っていったのでした。ジョン・ダワーは「日本は Japan ではなく、Japans として見たほうがいい」と示唆したことがあります。ダワーの見方は日本を複合的に捉えるということですが、それは私にとっては日本の面影を編集的に捉えるということにあたっているのです。
その他の出来事
とある展示会のブースデザインをしました
ポートフォリオの更新。展示会のブースのデザインをしました。
— 岡本陸 (@okaokarikuriku) November 28, 2023
https://t.co/8nCxAvzG2g pic.twitter.com/uprgedlGC5
普段僕が働かせていただいている会社のお仕事で、とあるサービスを展示会に出展するためのブースデザインをした。
久々に3次元的なデザインをしたのだが、なかなか難しい。限られた予算の中で妥協点を見つけ、且つそれを方々に納得してもらえるようにプレゼンしなければならない。個人的には20点くらいの出来だ。ただ、来年の2月も別件で展示会のブースのデザインをする予定なので、今度はもう少し遊ぶ余裕を見せながらデザインをしたい。
次回のnoteは昨年同様、1年の総括的な内容にする予定。今年はどんな1年になったのだろうか。振り返るのが楽しみである。
ではまた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
