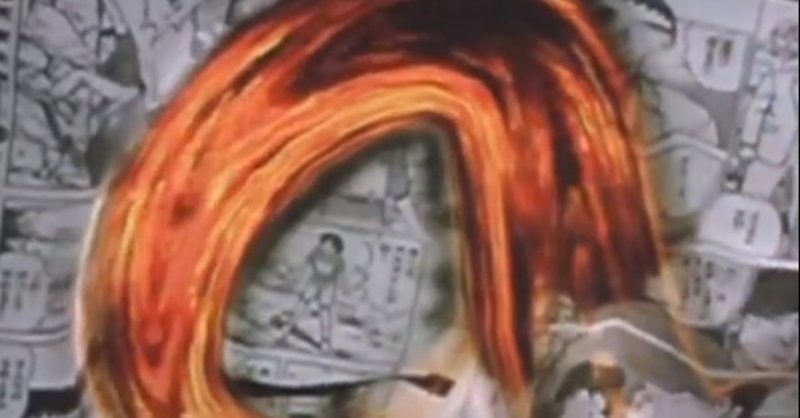
時に触れる
好きなSFを一冊だけ選んでほしいと問われたら・・・。
ダン・シモンズの「ハイペリオン」? フランク・ハーバートの「砂の惑星」? それともアイザック・アシモフの「われはロボット」? あげだしたらキリがない。
でも、タイムトラベルものに限定したら? 古典としてのウェールズの「タイムマシン」、エンターテイメントとしての「バック・トゥ・ザ・フューチャー」、いずれも捨てがたいし他にもよい作品は数えきれないほどあるけれど、私はやっぱりハインラインの「夏への扉」を選びたい。
SFではいくつかの法則が生まれている。有名なのはアシモフのロボット三原則だが、クラークの三法則もいいよね。
1. 高名で年配の科学者が可能であると言った場合、その主張はほぼ間違いない。また不可能であると言った場合には、その主張はまず間違っている。
2. 可能性の限界を測る唯一の方法は、不可能であるとされることまでやってみることである。
3. 十分に発達した科学技術は、魔法と見分けがつかない。
1と2と3のそれぞれで真実と皮肉の配合は違っている。けれども3の「十分に発達した科学技術は、魔法と見分けがつかない。」は有名なマーフィーの法則とともに工学分野では「かなりいいところをついている」と思っている人が多い。
タイムマシンの話に戻れば、タイムマシンは今のところできていないし、たぶんこれからもできない。1や2の皮肉の部分はそういうことで、アシモフも「SFとファンタージーの違いは、想像できるものがなんでも許されるわけではない。空飛ぶ絨毯は想像できるが実現しない。SFにおいても混ぜてもいい仮説は1つか2つまで」といっている。
「でも、昔の人は鳥のように空を飛びたいと願い、それは今、飛行機として実現している。だから、1や2も3と同様に成立するんだ。可能性がゼロではないということは《あり得る》ということではないか」ともよく言われる。
でも、それはやっぱり違うと思うんだ。
もちろん、それはそれでいいのだけれど、凧は昔から飛んでいたわけだし、原理や発想を転換すれば、できないこともできるっていう方が大切じゃないだろうか。もちろん、それは空飛ぶ絨毯ではないけどね。
タイムマシンの話に戻れば、人の記憶という装置を使えばタイムマシン的な効果を感じることはできる。写真という小道具によって「バック・トゥ・ザ・フューチャー」や「JIN−仁」はタイムパラドクスをエンターテイメントにしたわけだよね。
つまり、記憶と写真の組み合わせで、人はあたかも時間を止めたように感じられる。逆にいえば、時間は戻れないけれど、時間を固定し記憶を強化する装置としての写真は発明できたわけだ。
時間を止めたと感じることができるんだったら、時間を早く動かしたり、ゆっくり動かしたりしていると感じることもできるはずだ。
別にすごい技術はいらない。たとえば下記の"Khronos Projector: melting the "video cube"は10年以上前のアイディアだけど、まぁ、クールだよね。
理屈も含めたもう少し長いデモはこれ。
Khronos Projectorはとっても面白いコンセプトだったんだけど、まだ何に使えばいいか思いつけた人がいないから、知っている人は知っているという感じ。だけど、まぁ、技術というのはそういうものだし、今も実は世界のどこかでこの応用を考えている人がいるかもしれない。
そしてその技術が十分に発達するとき、きっと第一世代の僕らは「魔法みたいだ」と思い、その次の世代は「なんでかわからないけれど動く電子レンジ」みたいに感じるのだろう。
訪問していただきありがとうございます。これからもどうかよろしくお願い申し上げます。
