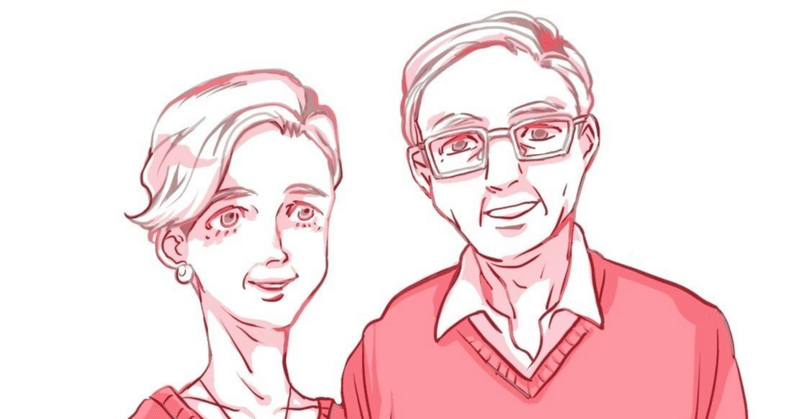
高年齢者雇用について
こんにちは。社会保険労務士の松本です。
70歳就業確保措置の努力義務って知ってますか?
今回は令和3年4月に施行されました改正高年齢者雇用安定法について、その概要をお話します。
長く安心して働ける制度を目指して今後進んでいく高年齢者雇用の概要がわかります。
今回の記事でわかることは、
・高年齢者雇用の概要
・70歳就業確保措置について
・高年齢者就業確保措置の注意事項
・学び直し、リスキリングの重要性
です。
元気があればなんでもできる。
高年齢者雇用に興味のあるかたは必見です!
1.高年齢者雇用の概況について
内閣府が発表した「令和4年版高齢社会白書」によると、65歳以上人口と15~64歳人口の比率を見ると、昭和25年には65歳以上の者1人に対して 現役世代12.1人がいたのに対して、令和2年には65歳以上の者1人に対し て現役世代2.1人になっています。
今後、高齢化率は上昇し、現役世代の割合は低下し、令和47年には、65歳以上の者1人に対して現役世代 1.3人が支えるという比率になることが予想され、社会の高齢化にまずます拍車がかかっていきます。
昨今では、老後2千万問題や国際情勢の影響による物価高など、年金だけでは生活がまかなうことが不安視されるようになってきました。
かつては「60歳になったら定年を迎えて65歳で年金をもらって余生を静かに過ごそう」と考える人も多かったのですが、実際には65歳以上になっても働く人が増えています
厚生労働省が発表した令和3年の高年齢高年齢者雇用状況当報告によりますと、65歳以上の常用労者数については平成21年が60万5千538人だったのに対し、令和3年では193万8千301人と、この10年あまりで3倍以上に増えています。
このような社会情勢の変化のなかで、改正高年齢者雇用安定法が施行され、70歳までの就業確保努力義務が始まりました。
2.高年齢者雇用安定法について
高年齢者雇用安定法では、現在65歳までの雇用確保を企業に義務づけております。
これは例えば60歳が定年の会社であれば、定年に達した労働者が希望した場合は65歳になるまで、継続雇用をする義務を課しているものです。
この65歳までの雇用の確保義務について、令和3年4月に高年齢者雇用安定法が改正され、70歳までの就業確保措置の努力義務が追加されたんですね。
ちなみに「高年齢者」というのは、高年齢者雇用安定法の定義では「55歳以上」の人のことを言います。
それでは、70歳までの就業確保措置とはどういったものなのでしょうか。

70歳までの就業確保努力義務の対象となる事業主は、
1点目は、定年を65歳以上から70歳未満に定めている事業主です。
65歳定年の場合、現在の法的義務である65歳までの雇用確保義務をはたしているわけですが、70歳までの就業は確保されていないので、定年を65歳と定めている企業も対象となってきます。
2点目が65歳までの継続雇用制度を導入している事業主です。
これは、70歳以上まで引き続き雇用する制度を導入している場合は除かれます。
これらの対象となる事業主が、次の5つのいずれかの措置、いわゆる高年齢者就業確保措置を講じるように努める必要があります。
その5つの高年齢者就業確保措置というのは
①70歳までの定年引上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度、・勤務延長制度)の導入
※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものも含む
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
です。
まず①と②はわかりやすいですね。
③の70歳までの継続雇用制度は、現在の65歳までの継続雇用制度が70歳まで延長になるものなので、これもイメージしやすいです。
ただし65歳までの継続雇用では、自社あるいはグループ会社での継続雇用ですが、65歳以上70歳の継続雇用の場合、他社での継続雇用も可能となります。
④と⑤については、独立した個人事業主やボランティアスタッフになるイメージです。
従業員ではなくなり社会保険や雇用保険の対象でもないので、過半数労働組合の同意あるいは従業員の過半数を代表する者の同意を得た上で、この就業確保措置を導入する必要があります。
③から⑤では、事業主が講じる措置について対象者を限定する基準を設けることができますが、その場合も、過半数労働組合等の同意を得ることが望ましいです。
また、高年齢者雇用安定法における社会貢献事業とは、不特定かつ多数の者の利益に資することを目的とした事業のことです。
社会貢献事業に該当するかどうかというのは、事業の性質や内容等を勘案して個別に判断されます。
次に高年齢者就業確保措置を講じるにあたっての注意事項について説明します。
まず、先ほどの5つの高年齢者就業確保措置のうち、どの措置を講じるかについては会社と労働者間で十分に話し合いを行い、高年齢者のニーズに応じた措置を講じることが望ましいです。
次に、複数の措置により70歳までの就業機会を確保することも可能ですが、それぞれの高年齢者にどの措置を適用するかについては、それぞれの高年齢者の希望を聞き取りし、労働者の意見を十分に尊重して決定する必要があります。
高年齢者就業確保措置は今のところ努力義務なので、対象者を限定する基準を設定することも可能ですが、その場合に過半数労働組合などの同意を得ることが望まれます。
そして高年齢者が定年前と違う仕事をすることになる場合には、必要に応じて新たな仕事に関する研修や教育訓練等を事前に実施することも望ましいとされています。
高年齢者就業確保措置の実施で基準を設けて対象者を限定する場合、対象者の基準の内容は原則として会社と労働者の話し合いによるものですが、会社と労働者間で十分に話合った上で定められたものであっても、事業主が恣意的に、つまり、会社の一方的な判断で高年齢者従業員を排除しようとするものなど、高年齢者雇用安定法の趣旨や他の労働関係法令に反するものや公序良俗つまり社会的ルールというか考え方に反するもの認められません。
厚生労働省がモデル就業規則で示している、65歳以降の継続雇用制度の対象者の基準の例としては、
(1)過去○年間の人事考課が○以上である者
(2)過去○年間の出勤率が○%以上である者
(3)過去○年間の定期健康診断結果を産業医が判断し、業務上、支障がないと認められた者
です。
おそらく多くの企業が、このモデル就業規則の基準を参考にすると思われるので、65歳以降になっても就業したいと考える場合は、会社の人事評価や出勤率、健康状態を意識して基準を満たすように努める必要があります。
また、定年後の高年齢社員を個人事業主として独立させ業務委託する場合、個人事業主なので万が一労災が発生した場合でも、基本的には労災が補償されません。
ウーバーやamazonの配達の方よく問題になっていましたね。
そのため、さきほどの④の業務委託の制度を導入する場合は、社会保険・労働保険が適用されないことを十分に説明することも重要です。
ただ、最近では多様な働き方が広く普及して推進され、フリーランスとして活躍する方も増えています。
フリーランスの立場であれば、他社の業務を請け負うことも可能となります。
継続雇用にせよ、業務委託にしても、高年齢社員の経験や知識は会社にとっては非常に戦略になるものです。
40代後半から自分のキャリアを見つめ直し、60歳以後にどのような専門性を持って仕事をしていくのか。
リカレント教育、リスキリングなど学び直しの機運も高まってきているなか、ご自身のキャリアを見つめ直して生き生きとした老後を過ごすことができるよう、今からでも準備していきたいですね。
まとめ

いかがでしたか。
今回は令和3年4月1日に改正されました改正高年齢者雇用安定法の70歳までの就業確保努力義務についてお話ししました。
今回のまとめとしては、
・近年の厚生労働省の統計等では70歳以上の方の就業率の割合が増えてきていること。
・高年齢者雇用安定法が改正され、5つの就業確保措置をとる努力義務ができたこと。
・70歳まで就業する対象者の基準を設ける場合は会社と労働者側で話合う必要があり、その基準は合理的なものであること
・フリー―ランス、個人事業主として独立して業務委託を受けたり社会貢献事業のスタッフとなる選択肢もできたこと。これには労働組合などの同意が必要で、基本的には労災の対象外となること
・70歳まで必要とされる人材となるよう早いうちからキャリアの棚卸や学び直しの機会を検討したほうが良い
でした。
60歳で定年して65歳から年金だけでの生活となってしまうのは、非常にもったいないことです。
皆さんがこれまで経験してきた知識や経験を今後の社会に役立てる素晴らしい機会となりますし、今後は皆さんの会社や社会的にもどんどん70歳就業の取り組みが進んでいきますので、この法律改正を機に今後は自分のキャリアを見つめ直して60歳以降はどのような働き方や社会への貢献ができるのか、生涯現役について考える機会が持てると良いですね
またかつては、老後の資産は元本を減らすなということで、高年齢になるとリスクのある投資はするべきではないという意見も多かったのですが、物価高や老後の長期化などにより資産増やさずにただ減らすだけでは、長生きのリスクに対応できなくなっています。
70歳まで元気に働きながら老後資金の確保のためリターンのある資産運用も考えていく必要もでてきていますので、資産運用の勉強も大切になってきます。
今回のnoteが良かったと思われた場合は、いいねボタンをしていただけるとうれしいです。
また今後このnoteでは、高年齢者の働き方に関する情報や年金、福祉、資産運用の情報についてもアップしていきたいと考えてますので、フォローもいただけますと幸いです。
本日の最後までご覧いただき、ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
