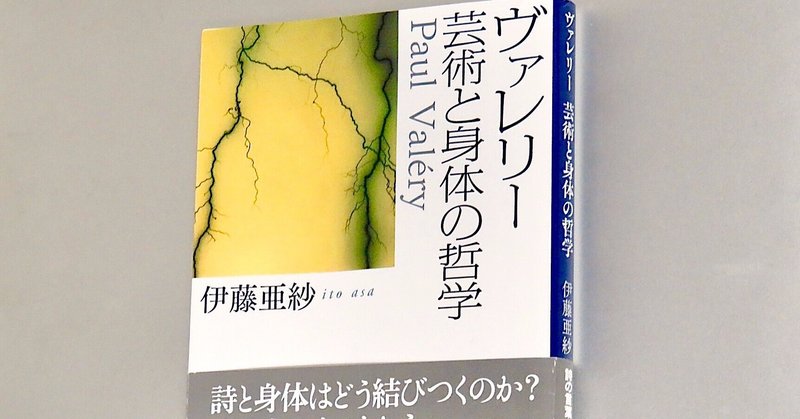
伊藤亜紗『ヴァレリー 芸術と身体の哲学』
☆mediopos-2262 2021.1.25
詩的言語とは何かという問いに
あけくれていたことがある
学生時代のことだ
ロシア・フォルマリズムや
ロマーン・ヤーコブソンの言語理論
シャルル・ボードレールの詩篇「猫たち」をめぐる
ミカエル・リファテールの分析などなど
詩的言語をめぐる問いをいろいろ彷徨っていたが
やがて「受容」という観点に収斂していった
詩とされる言語活動は
詩語の使用や音韻などさまざまなものによって
詩(らしきもの)として作られ読まれもするのだが
重要なのはそのテクストが
「詩」として作られ読まれるという社会的条件と
読み手がそれを「詩」として読むことが重なったとき
それが詩的機能を持つことになる
つまり同じテクスト(言葉)があっても
詩として読まれる場合もあれば
詩としては機能しない場合もある
たとえば谷川俊太郎に『定義』(1975年)という詩集があるが
その最初の「メートル原器に関する引用」という詩は
「平凡社・世界大百科事典による」言葉で作られている
百科事典の言葉も詩として詩集に収められると
それは詩として読まれ機能することになるのだ
問題はおそらくそのことにも関連しているであろう
ロシア・フォルマリズムの作家シクロフスキーや
ブレヒトが演劇における効果について考えていた
「異化」ということとも関係してくる
つまり詩的言語であるということは
通常の言語が「異化」されているということである
そこに「散文」ではない「詩」の世界が開示される
前置きが長くなったが
詩的言語や詩的機能への問いは
ヴァレリーの詩と散文をめぐって
本書で示唆されている観点と通じている
「散文」が「異化」されたところに
「詩」はあらわれるともいえるのだ
ここでヴァレリー/伊藤亜紗は
「詩」とは「私たちの行為の
散文的な運行がやぶれるような事態である」という
そして「それが機能を発見=所有させるのであれば、
文字どおりの詩、つまり言語によるそれでなくても
「詩」」であるという
わたしたちが日常的に使っている言葉や
それに準じた言葉を「散文」としてとらえれば
そうした言葉の「自然な流れ」が「断ち切られる」ことで
「私たちが持つ潜在的なものの総体としての
錯綜体へと接近」することが可能となったとき
そこに「詩」はあらわれてくる
そのことをあえて神秘学と関連づけるならば
「詩」(ポエジー)とは
言葉(だけではないが)を「意識魂」的に受容することで
私たちが潜在的に持ちえている認識への道を
ひらいていく営為だともいえるかもしれない
ここで「意識魂」的な受容というのは
言葉をベタな「散文」としてとらえるのではなく
「異化」された「詩」として
言葉を働かせるということだ
つまり「そういうものだ」という機械的な受容ではなく
「それはいったいなにか」という
問いそのものでもあるプロセスとしての受容である
ゆえにそれはまた「自由」への道ともつながっていく
■伊藤亜紗『ヴァレリー 芸術と身体の哲学』(講談社学術文庫 2021.1)
「われわれの問いは、ヴァレリーの創造後の創造、すなわち作者の手を離れ、読者のもとにとどけられた作品の働きの諸相を解明することであった。伝達の媒体とは異なる、「装置」としての詩とはどのようなものか。ヴァレリーにとって詩とが、私たちの行為の散文的な運行がやぶれるような事態である。「散文的な」とは、「正常」で「健康的」な、ひとことでいえば「うまくいっている」状態である。それは外界の刺激に対して私たちが遅れなくついていっている円滑な状態だが、反面、身体は習慣的で自動的な働きしかしておらず、道具化している。他方、詩が関わるのはむしろ「うまくいかない」という不成功の状態である。身体は応答をただちに組み立てることができず、拘束される。詩のもつ修辞、たとえば倒置や脚韻などは、ヴァレリーにとって、読者の身体を拘束する不成功とその解消が連続する持続を作り出すことを目的とした、さまざまな「仕掛け」に他ならない。このような仕掛けが多層的に組み合わされることによって、詩はひとつの装置として働きだす。こうして詩人は、詩を通じて読者を拘束的な状態に置くのである。ただし、この拘束は、「真の行為」を促すような拘束である。自動的な応答ができない状態において、読者は道具化していた自身の諸機能を新たに組み立てなおす。真の行為とは逆説的にも行為の失敗のうちにあるのであり、この機能の組み立て直しの過程で、読者はみずからのうちにありながら知らなかった機能に出会う。ここに、ヴァレリーがしを通して果たそうとする「大きな目的」がある。ヴァレリーにとって詩とは、読者にみずからの諸機能の「開拓」と「所有」を促す装置なのである。
諸機能についての知に関わるということが、詩と生理学を結びつける。たしかに、詩がその可能性をひらくヴァレリー流の生理学は、実験と観察にもとづく既存の学問体系としての生理学とは異なる、しかし詩がもたらす機能についての知が、言語的な表象を介さない直接的な「所有」であるという点で、むしろヴァレリー流の生理学こそ、実践=実験と不可分な生理学であるといえよう。それは一種の「解剖」である。伝達の媒体であるかぎり、文学は作者の個人的で恣意的な体験にしか関わることができない。しかしヴァレリーの生理学としての詩は、主観的でありながら人間の機能に根ざすがゆえに、普遍的な実践=実験に関わるのである。視覚の役割が肥大化し、人々がみずからの身体を忘れつつある時代にあって、ヴァレリーの芸術哲学が作品に見出した役割は、人々がみずからの信頼を「解剖」し、そうすることによって身体をふたたび「所有」できるようにすることだったのである。
そして、この実践=実験としての側面が強まるとき、(・・・)詩ないし詩的な体験は、必ずしも言語的構築物としての狭義の詩である必要がなくなる。ヴァレリーは音楽や建築といった他の芸術ジャンルにも「詩」を見出すし、「マッチの火がつかない」ような日常的な経験もまたひとつの詩になると言う。もちろん、そう主張することでヴァレリーは詩という概念を単純に拡張しようとしたわけではない。詩は、言語という日常的な素材を使用するがゆえにその装置としての性質が際立つのであるし、その複雑さや持続の長さをかんがみても、一群の詩的なもののなかで詩はあくまで中心的で本来的な位置を占めている。重要なのは、詩を散文から区別するという局所的な問題にこだわることが、芸術のジャンル論を超え出る可能性につながっているというヴァレリーの議論の構造である。ヴァレリーは、詩と散文の区別を形式主義的に押し進めはしなかった。区別じたいはたしかに形式主義的だが、それぞれのジャンルの本質をつきつめると、ジャンル論どころか芸術論を超え出る可能性にむかってひらけてしまうのである。ヴァレリーの詩論の可能性は、まさにそれが詩論を超え出るところにある。もちろん、身体や時間についてのヴァレリーの思考は、すでに研究がなされている。しかしこの超え出た部分をたんなる哲学的な思考の集成としてではなく、詩論の可能性として分析すること、それがこの芸術哲学の目論見であったといえるだろう。」
「ヴァレリーは、それが機能を発見=所有させるのであれば、文字どおりの詩、つまり言語によるそれでなくても「詩」と呼んだ。たとえば「マッチを擦って火がつく」のは詩ではないが、「マッチを擦って火がつかない」のはひとつの詩になる、とヴァレリーは言う。「それはひとつの−−−−詩になる・不-成功は強く感じられるものになる。だが成功したもの、予想され−−−−実現したものは、存在しないものになっていただろう」。一般に、「生の機能作用の大部分が成功し、沈黙している」。もちろん、「正常と健康は、道具的な特性」であって、この成功による沈黙が身体の道具化であることは言うまでもない。言語によるそれにせよ、それ以外のものにせと、詩があらわれるのは、「事物の自然な流れ」が断ち切られるところである。そしてこの断ち切りによってのみ、「私たちが持つ潜在的なものの総体」としての錯綜体への接近は可能になる。「成功していたら行為のなかで存在しないままにされていたであろうさまざまな錯綜体を燃え上がらせる」のは「抵抗」「失敗」「我慢できなさ」といったものなのである。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
