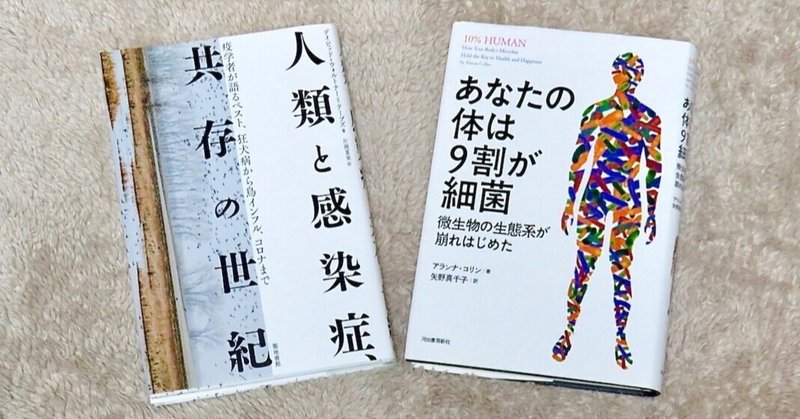
デイビッド・ウォルトナー=テーブズ『人類と感染症、共存の世紀』
☆mediopos-2256 2021.1.19
人は微生物とともに進化してきた
人から微生物を除くと
そのからだの10%ほどしか残らないほどだ
動物たちや虫たち
そして植物たちもまた
微生物と共生することで生きている
宿主たちが減り絶滅すれば
微生物たちもまたその生息環境を失い
存在ができなくなるか
新たな生息環境をさがし
その場所に適した姿で生きていくことになる
環境破壊が動植物に及ぼす影響は議論されても
微生物に及ぼす影響とその対策についは
考慮されることは少ないようだ
わたしたちのからだの90%を占める微生物
その生態系もまた崩れ始めている
その存在にもっと目を向け
共生共存者としての環境づくりを行うことなく
わたしたちは生き延びていくことはできなくなる
感染症との関係も同様である
感染症と戦うという発想(物語)を
変えていく必要があるようだ
その戦いはじぶんとの戦いになるからだ
その戦いに勝つことは
じぶんを敗者にしてしまう矛盾を抱えることになる
共生共存するための
調和できる関係づくりが重要であり
ほんらいそこに勝者も敗者もないのだ
わたしたちはからだの10%では生きられない
90%を占める細菌のほんの一部が
病気の原因となってしまうとき
その一部を取り除く対処療法的な戦いをすることも
時には必要なこともあるのだろうが
必要なのはなぜそうなってしまったのかを
生体全体さらにいえばその置かれた環境も含め
その生態系全体について見ていかなけばらない
そうした観点はからだや自然についてだけではなく
心的なものについても必要だと思われる
さまざまな心的な病もまた
対処療法的にとらえることでは
まさにじぶんとの戦いになってしまう
からだ10%で細菌90%と戦うように
心の10%で無意識のじぶんの90%に
無謀にも戦いを挑むようなものだから
じぶんと戦って勝ち目はなく
結局のところ共倒れとなることになる
重要なのはじぶんの心的生態系を
いかに調和させ順応していくかということなのだ
■デイビッド・ウォルトナー=テーブズ(片岡夏実 訳)
『人類と感染症、共存の世紀/疫学者が語るペスト、狂犬病から鳥インフル、コロナまで』
(築地書館 2021.1)
■アランナ・コリン(矢野真千子 訳)
『あなたの体は9割が細菌/微生物の生態系が崩れはじめた』
(河出書房新社 2016.8)
(アランナ・コリン『あなたの体は9割が細菌』より)
「私たちは微生物たちに頼るように進化してきた。人体から微生物がいなくなったら、真にヒトの部分はわずかしか残らない。ヒトの部分は一〇%でしかない。」
「ヒトゲノムは、過大に期待されていたにもかかわらず、生命の設計図や暮らしの哲学になるほどの存在ではどうやらなかったようだ。私たちは人間全般の特性や個人の性癖を語るとき、「だって、そういうDNAなんだから」とよく言うが、実際にはヒトのDNAが私たちの日常生活を左右することなどほとんどない。しかし、人体にはほかに一〇〇兆個の細胞ちょ四四〇万個の遺伝子をもつ微生物がいる。彼らと共に進化してきた私たちは、彼らなしには生きていけない。この残りの九〇%が加わってやっと、ダーウィンの進化論は私たちの人生に意味あるものとなる。
数百万年ものあいだ私たちと共に旅してきた微生物の存在に敬意を払うこと。これこそが、私たちの真の姿を理解し、ひいては一〇〇%のヒトになるための第一歩だ。」
(デイビッド・ウォルトナー=テーブズ『人類と感染症、共存の世紀』より)
「私たちの大部分は二〇世紀の特徴である荒れ果てた風景、失われた生息地、消えゆく大型動物に気づいている。私たちは鳥やサイの絶滅を心配している。ある節足動物、ミツバチやチョウのようなものを守ろうとしながら、同時に別のものを殺そうとしている。それでも、消えゆく動物たちをすみかとする何兆というウイルス、酵母、菌類、細菌について、また、私たちがその生息地を壊して鉱山や牧場や都市にしてしまったら、こうした微生物相がどこを新しいすみかとすればいいか。もっとも環境保護意識が高い者でさえ考えることはめったにない。本書で述べる病気は、ある意味で、そうした失われた生息地と消えゆく種からの顕微鏡サイズの難民が関わっているのだ。
地球上のすべての生き物は、機能不全を起こしている一つの大家族だといえる。その中ではほとんどの細菌、ウイルス、寄生生物が有益で不可欠であり、病気には本質的に有益な役割があり、私たち自身が微生物から進化し、微生物で構成されている。私たち−−−−厄介ですばらしい。矛盾した人類を含めたこの大家族−−−−は、ある種の真剣な物語療法の力を借りて、問題を解決することができる。戦争は、動員、技術兵器、国家の威信、市民的自由の停止、外国人嫌悪、副次的被害を伴うため、いかに感染症と闘うかの比喩としてよく使われる。だがそれはあまりに貧困で偏狭なイメージだ。たぶん政治、いわゆる可能性の技術のほうが比喩としてふさわしい。戦争は最後の手段だ。
数千年にわたって病原菌と闘い、最悪のもののいくつかを撲滅したわれわれは、病原体と交渉し、互いに必要とするものを融通しあい、形式的なちょっとした小競り合いをし、双方にそこそこ許容範囲の犠牲者を出して終わるという道さえも見いだせるかもしれない。二一世紀には、われわれには共通の未来があることが、あるいはそもそも未来なんかないことがわかりつつある。だが、そうした未来のためには、今までと違う生態学をより意識した形で、私たちはみずから学ぶ必要がある。数多い過大の一つが、その学びを新しい常識、われわれが共有するこの驚くべき惑星への思いやりに満ちた、他の人々や他の生物種との連携のようなものに変換することだ。
「二〇二〇年のCOVIDパンデミックの教訓の一つが、自然の「支配者にして所有者」になりたがるより、私たちはサーファーになって。コントロールできない力の波に乗り、順応しようとするほうがいいということだ。だが、どうやって?
『千夜一夜物語』でシャフリヤール王は、最初の妻に裏切られたと感じ、すべての女性に復讐しようとする。王は宰相に命じて毎夜新しい花嫁を連れてこさせ、翌朝には首をはねさせる。宰相の美しい娘、シェヘラザードは、すべての女性のためにみずからのイノチを賭ける決意をする。シェヘラザードは、美しいとは言えない妹のディナルザードをこの非暴力的な策略に誘う。毎日、夜明けの直前、ディナルザードはシェヘラザードを起こし、物語をせがむ。王は、もちろん聞いており、夜明けにはもっと聞きたいという気になっている。王は毎日、シェヘラザードを生かしておくことにする。やがて王は、まずシェヘラザードの物語を、やがてシェヘラザードを愛するようになり、残忍で横暴な妄執を捨てる。シェヘラザードは長く有意義な人生を送り、世界中の若者と平和活動家に称賛される。
シェヘラザードの物語は、つまるところ、私たちすべての物語だ。地球は、シャフリヤール王のように、私たちの目の前で多くの種の首をはねてきた。地球の歴史は突然の、あるいは緩慢な大量絶滅に満ちている。地球は文字通りわれわれの祖先の骨と分解された分子からできている。われわれ人生も宿主と、われわれを支えている細菌を裏切ってきた。すぐにグリプトドンや翼竜と同じ道を歩みたいのでなければ、世界人類は十分な精神療法を受ける必要がある−−−−ただの精神療法ではなく、私たちがみずからの物語を、生存、公正、生態学的なくつろぎ、居心地のよさの物語として、作り直し、語り直してきた物語療法を。この物語を見つけるには、これまでに試みたことのない調査研究の取り組みが求められる。シェヘラザードのように、私たちの命がそこにかかっているのだ。」
「人獣共通感染症の自然史は、私たちの感染症への取り組みは戦争ではないことを教えてくれる−−−−あるいは、もし戦争だとしても、それはわれわれの自身との戦争なのだ。微生物は私たちのまわりじゅうに、私たちの中に、地球上の動物の仲間たちの、至るところにいる。私たちの取り組みは、究極的には地球全体の連帯と、鋭く注意深い生態系意識だ。以前私は、人口過剰と成長の限界を心配する人から、おまえは疫学者として人の命を助けることで、問題の一端を担っているのだと告げられたことがある。結局のところ、われわれは自分の心配を、あるいはわれわれが住む惑星と、それを共有する他の生き物たちの心配をすべきであると論理的、科学的に証明する研究はない。私たちの心配は、道徳的立場なのだ。」
「いいニュースもある。地域社会一つひとつから始まった世界中に、この怖ろしいパンデミックのさなか、新しい世界的なビジョンが生まれ、予想だにしなかった複雑さと謎と美に満ち溢れた惑星、理論的にも実践的にも手段がないために探求されなかった世界が明らかにされているのだ。この新しいビジョンから生まれるのが、物語に、それもわれわれの大いなる妄想の陰に隠れた興味深くすばらしい物語に満ちた、世界という小説だ。生物圏はまだ私たちを生かしておいてくれるだろう。あるいは、もし物語が私たちを救わないとしても、それは少なくとも、われわれの今際の際、人類最後のときに、こんな台詞をわれわれに言わせることだろう。「われわれは立派にやったじゃないか? 全世界に語るに値するみずからの物語を残したのだから」」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
