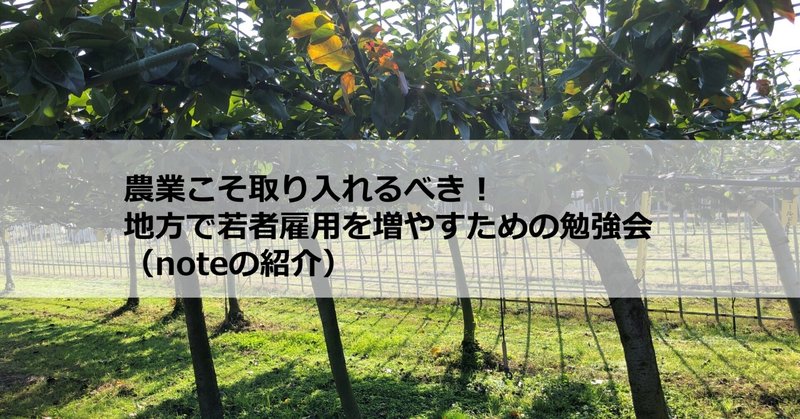
農業こそ取り入れるべき!地方で若者雇用を増やすための勉強会(noteの紹介)
この度、株式会社イマクリエのnoteで記事を書かせてもらいました。
内容としては昨年度に行った三重県明和町での「起業勉強会」について。
この勉強会では自分は運営の1人として参加しました。
運営しながら「新しい新卒採用、若者雇用」として勉強会を活用できるのではないかと思う様に。
ちょうどその頃に、農業大学校に入学したこともあり「この手法であれば、農業大学校の学生と一緒に実習を受けることで、いつかウチで働いてもらえる可能性があるんではないか?」と思えたきっかけです。
ある意味では僕の人生を変えた事業であり、今もどうしたらよくなるのか必死で考えています。
よろしければまず、書かせてもらった記事を読んでからこのnoteを見て頂くとありがたいです。
学生という立ち位置が社会人を本気にさせる!
読んでいただけましたか?
最初から学生と一緒に勉強会をすと決まっていたのではなく、色々な考えが合わさって「企業+学生」になったのです。
明和町を訪れて皇學館大学の教授と話をしたのが、2023年7月末。
この頃には、農業大学校に入学することが決まっていたので「学生の可能性」について真剣に考えることができました。
「学生が前に出てきてくれさえすれば、必ず意味のある勉強会になる。」
そう思えていたのは、僕自身が住んでいる自治体のまちづくり協議会に参加していた時の体験があったからです。
協議会には自治体内の大人だけでなく当時高校生だった女性も参加。
話し合いでは、今後の自治体の方針が正しいかを判断するのですが大人同士だと、暗黙の了解という感じで会は停滞気味になってしまいます。
そこで高校生が意見を言うと、実現のために大人が真剣に議論をする光景をみていたから。
そんなことを帰りの高速バスの中で思い出しながら「この勉強会が上手くいけば、農業大学校でも、採用候補の学生をみつけられるかも」と思う様になりました。
この考えは後に正解だったと分かり、農業大学校でも活かせる様になりました。
学生と企業の勉強で地方からの若者流出を阻止!
そしてこの勉強会を通じた雇用の形は地方自治体こそ行うべき。
その地域の大学や短大、専門学校に来た若者が「自分のやりたいことが出来る会社が無い」と首都圏に行くことが地方からの若者流出の原因でもあります。
自分が今、住んでいる地域でもやりたい事が出来ると思わせる様に、学生の頃から「自分の頭で考えた」ビジネスプランを実践。
そうすることで「この企業なら自分のやりたい事をやらせてもらえる」と考え就職先として考えてくれると思います。
また、首都圏の企業に行きたいというのであれべ、その企業と勉強会をオンラインで開催しテレワーク主体で就職するという形も。
働き方のスタイルが変化している今、就職活動の形も変化してくべきではないでしょうか。
農業こそ農家と学生の勉強会を開くべき!
学生と企業の勉強会を開催するにあたって感じたのは「学生は学ぶことが主であり、企業は実践することが主である」ということ。
学生は勉強するということに慣れているので、アドバイスの吸収力が凄いです。
一方で考えが片寄りがちなので、そこを企業がフォローすればビジネスにも活かせると実感。
農業においても、学生の作業スピードや効率は教え方ひとつで決まると考えます。
さらに学校では農業の研究を1人1人がテーマをもって1年間行う「プロジェクト」というものがあり、そこに農家の参加が効果あるのではないかと想像。
農家のリアルな課題に対して学生が研究を行うという形はどうでしょうか。
農家自身が課題に向き合うのは日々の作業の中では、難しいです。
そこで学生がプロジェクトの中で農家の課題解決ビジネスプランを作り上げていくというもの。
共同作業の中で、農家は学生のスキルを知ることができるので雇用を考えることもできます。
また、農家は個人経営なので雇用が難しいのですがプロジェクトの内容によっては新規ビジネスとして発展できるので、新しい収入源も確保できるかも。
そうすれば雇用のハードルも下がるのではないかと考えます。
この様に農業においても勉強会といのは有効。
そう思えたのも、企業と学生の勉強会を運営した結果からだと思います。
その後(三重出張後の話)
ちなみになのですが、この三重出張の後に体調を悪化させます。
1週間ほど激しい腹痛に見舞われ、検査を重ねた結果「胆のう炎」。
その後、胆のうを摘出する手術を受けるなど大変な夏となりました。
復帰して実際に勉強会を開催した後のエピソードは、次回のnote更新の際に綴ります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
