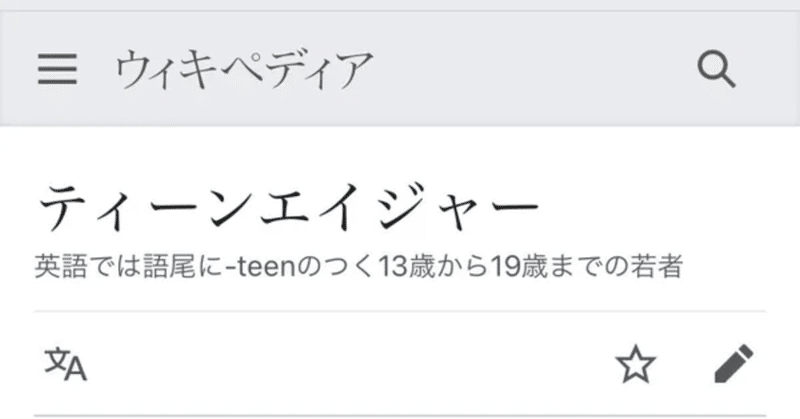
短編小説 『ティーンエイジャーの憂鬱』(二)
※前回
二
「進路希望の紙、出した?」
クラス委員の女子からそう言われたのは帰りのホームルームが終わってからだ。
提出期限までにクラス全員に出すよう知らせて回るのがクラス委員の仕事なのだと云う。うちのクラスは優秀で未提出者は片手で数えられるくらいしかいないらしい。
ああ、と返事にとれるか怪しい反応しかできなかったが彼女はそれで納得してくれたみたいだった。
自分とは正反対のにこやかな笑顔で「第一回目だから、結構みんな適当みたいだよ」
フォローをそこそこに彼女は踵を返して教室の入り口で待っていた友人の元へ駆けていった。
目線を鞄の中に詰め込んでいた紙に戻す。折れとシワでよれているそれは俺のどうしようもない未来への鬱憤を形にした様だった。どうせゴミならと乱雑に教科書で押し込もうとしたが委員長の顔がよぎり、勘弁してやることにした。
すると頭の中で「ほうら」と"ティーンエイジャ―"自分の声が気持ち悪く反芻してまた落ち込んだ。
いつもの公園にはいつもの風景しかなかった。ベンチに座っているとなんだか高尚なことを考えているような気がして、自分の思考を麻痺させてくれる。向かいのベンチに座る陰鬱な顔をした背広を着た男と一瞬視線が合わさったが嫌な敵意を感じてすぐさま逸らした。
どちらが散歩しているのかわからなくなりそうな大きなゴールデン・レトリバーと身長の低い女性のペア、水分補給に立ち寄ったランニングマン、砂場で遊ぶ子どもとそれを見守る母親たち。
時間は動いているのに、いつも止まって見えて、しかもそれが自分にしか知覚できていないんじゃないかと疑うことがあった。でもそれはやっぱり誰もが感じる凡庸なものであって、あそこの砂のトンネルを開通させた子どもも汗を拭くランニングマンも小便をしている犬でさえも時間が流れていて、俺を置いて進んでいくのだろう。
──何を考えてんだ、俺は。
大分、酔っている。頭を振って意識を"今"に持ってくる。
これこそ"ティーンエイジャー"であり"厨二病"じゃないか。
頭を抱えた。こんな恥ずかしいことがあるか。否定を繰り返して、それで達観した気になって、結局自分が"ティーンエイジャー"だということを証明しただけじゃないか!
顔が高揚していくのがわかる。無情なまでの自覚は知らなくていい事だったのだ。さっさと公園を出ようと鞄を担いだ。
「やあ。進路調査の思案中?」
笑いかける声がベンチ後ろから舞い込んだ。目の前ににょっきと出た顔はクラス委員の彼女だった。
驚いて浮いた腰が再びベンチに落ちる。なんて返したらいいのかわからなかった。
「と、友達は?」
吐き出た言葉はなんとも前後性が無い、数時間前の会話の続きを思い出したものだった。やはり自分だけが時間の中に置き去りにされている気がした。錯覚なのかもしれないがそう感じた。
「あーね、雪子は塾だから駅前で別れたよ」
「はは、そうなんだ……」
苗字も思い出せないクラスメイトの名前はバツが悪く、せっかくの空気を淀ませてしまった気になる。指先がベンチを指す彼女は何となしに隣に座った。
「偉いよねー。毎週毎週さ。ちゃんとしてるっていうか」
自分から見れば君もしっかりしていると思う、なんて返すことはできない。
「へえ」とひきつった笑顔を晒した。どんな顔で今彼女と対峙しているのだろうか。やけに脈が速く、心臓が熱い。自分のことばかり気になった。
「み、皆、ちゃんとしてると思うけどな。早く出すよ、紙。悪い」
「いやいやいやいや!!」胸の前で大きく手を振った。彼女は悪く言ったつもりはないと、慌ててそういう意味ではなかったとフォローした。
「紙さ、ちょーっと覗いたんだよね、クラスの」
意外だ。そういうことするようには見えない。
彼女は「ではは」と頭を触った。
「そうするとさあ、なーんか色々考えちゃって。『ホントに皆もう決めてんの?! 嘘でしょ!』って。流されて決めてんじゃないのかなーなんて意地悪い事考えながらクラスの子と話してても、なんか芯があるっていうか……。勿論、そういう軽い感じの子もいるけど」
なんかなあー、と首をかしげる彼女はやけに幼く見え、かといってそれが愚かではなく、等身大に見えて、良いなと思った。
「委員長もそういうこと考えるんだな」
声が軽い。先ほどの緊張はもう無かった。
「そりゃそうだよ。だからまだ紙出してない人とかいると、安心する。あー同じなんだな、って」
あれ?っという顔をする俺の前に彼女は鞄から紙を取り出した。自分の鞄の中にあるものと同じ、空欄の目立つソレを。
「一緒じゃん」
「そだよ、同じ同じ」
気づけば声を出して二人とも笑っていた。ペットの散歩をする人は増え、砂場で遊んでいた子どもたちは17時のチャイムで友達と別れ、ランニングマンは歩きながら帰路についている。夕暮れの中、笑う自分たちを誰が気にするか。誰もしない。それでいいのかもしれない。
胸に沸いた"何か"は明日も残るだろうか。変わってもいい。変えて、変わって。
また明日彼女と話したいと思った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
