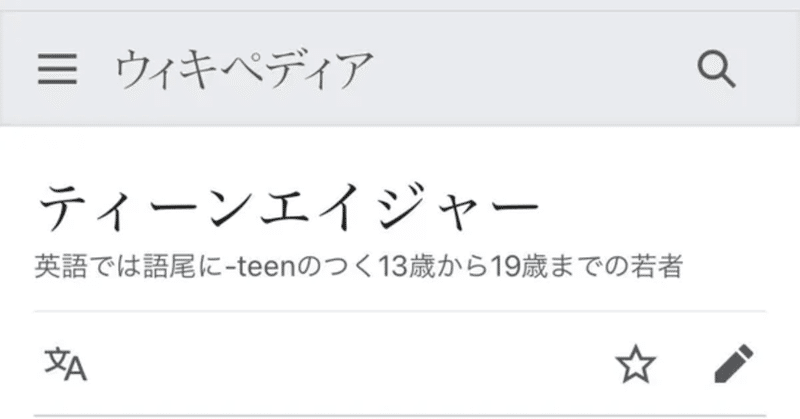
短編小説 『ティーンエイジャーの憂鬱』(四)
※前回
四
「少し歩いたほうがいいかもしれませんね」
男が追ってくる気配はない。ようやく少し気分が落ち着いた。いまさらになって心臓の音が早まっているのを自覚する。ああ、少しは"らしいこと"ができたのかもしれないとよくわからない充足感が全身を巡った。
横目で彼女を見るとコクコクと頷いた。彼女の緊張もまだ解けていないらしい。
駅が近づくにつれ、歩くスピードもゆっくりになってきた。私がそうしているわけではなく彼女に合わせた結果がそうさせた。肩の力が抜けたのかもしれない。私の心臓もすっかりいつも通りのリズムを刻んでいる。
小雨が完全に止んだことを確認したタイミングで彼女の視線が私の顔を捉えた。
「あの! すいません本当に、なんか。変なことになってしまって」
「いえいえ。逆に大丈夫でしたか。出過ぎたマネだったら、こちらこそ申し訳な……」
「全っ然ッ!」食い気味に体を近づけた。ハッとすると先ほど喫茶店で見たように体を折りたたみ「すいません……」と小さく謝った。
「保険の営業で。私押しに弱いから……良いカモだったのかなーなんて」
自嘲し、頭を掻く仕草はなんだか悲しく見え、途端に自分の『らしい行動』を恥じたくなった。彼女が生きている今日という日を、自分と同じようなルーティン化されたものと決めつけていたのかもしれない。体を巡った充足感の正体は『俺の非日常的な行動が彼女の一日を変えたんだ』などという私のエゴでしかなかったのだ。
「そんなことないと思いますよ」
彼女と自分を正当化する言葉が咄嗟に出た。
「営業っていうのはお客さんの問題を解決することが仕事なんです。困っているのならそれこそ問題だ。あいつは"あなたの問題"を解決するために引くべきだったんですよ」
いつか上司に聞いたお小言がペラペラ出て、日ごろから叱られておくべきだなと初めて感謝した。
「……ありがとうございます」と御礼を云う彼女の背筋はピンとしていた。
気づくと駅のロータリーに着いていた。雨が止んだことでタクシー乗り場にできていた列が散り散りに解散している。
「じゃあ、僕は地下鉄なんで」
「あ、そうなんですね」
――。
一瞬の間。その空白の時間に私は公園で見たカップルの相合傘の風景を脳裏に浮かべた。
しかし男子学生の影が私と重なることはないのだろう。彼女に軽く会釈をし、帰路に就くサラリーマンの一団に自分を溶け込ませるように歩いた。
歩こうとした。
が、ピンと張った糸の様なモノが私をその場に縫い付けるのを感じた。
振り返ると別れたはずの彼女の左手が私のジャケットの裾を控えめにつまんでいたのだ。彼女の指先に私と地面を縫い付けるだけの力は無いように思えたが、私がはその場から動けないでいた。
サラリーマンの一団はそのグループを変え替え、また新しい一団となって視界の端から消えたようだった。
彼女はつまんでいた左手を離すと、今度は右手を腹に突き出してきた。ワン・ツーだと錯覚したのも無理からぬ話だ。一瞬体を振るわせてしまった。
「こ、今度、今日のお礼をしたいので連絡先交換しませんか?」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
