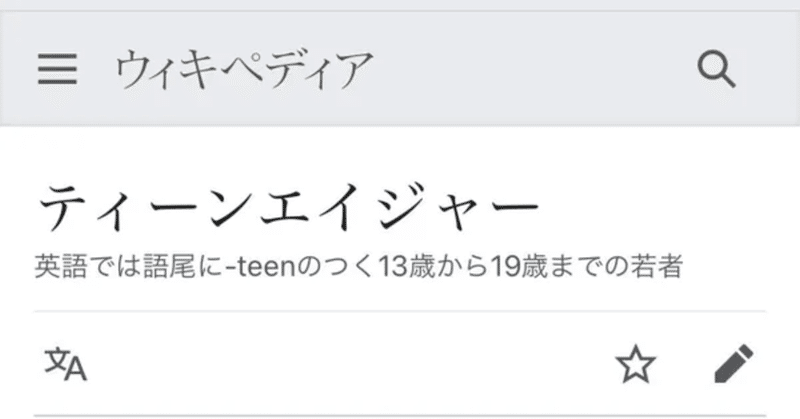
短編小説 『ティーンエイジャーの憂鬱』(三)
※前回
三
鬱陶しい。
目の前のイチャイチャしている学生を見て思った。
ベンチに体を全部預けるくらいには疲労が溜まっている。学生らのやり取りはギリギリのストレス値をまだいけるまだいけるといった具合に押し上げてくる不快さがあった。これは彼ら彼女らの青春を羨ましがっているわけでは決してない。そう思いたい。
やけにイライラするのは何も今日に始まったことではなかった。
社会人になってからずっとそうだ。
毎朝決まった時間に起き、満員電車に揺られながら出社し、決まったデスクに座り、その日の業務をこなす。入社した当初に感じていたやりがいや熱意はルーティン化された毎日に埋もれていった。
『何かを変えたい』と願いながら休日は身体を休めることに消耗し、ケータイを弄る時間はあるくせに『時間が足りない』なんて生意気を云う。繰り返される平凡な毎日に嫌気が差してはいるが、変わることは嫌だ、大変だ、と平凡に胡坐をかき続ける。
そんな自分がどうしようもなく嫌いで、イライラする。
つうっと首筋に汗が伝った。イライラの結晶かと思うと余計に気になった。オフィスカジュアルなんて聞こえはいいが一昔前のネクタイを締めたスーツスタイルと大差ない。
首にあてた指先は想像よりもさらっとしていた。すると
――ポタ。
今度は手の甲に冷たいものが当たる。どうやら汗ではないらしい。梅雨入りはまだ報告されていなかったと思ったが、気づけば公園には件の学生らと私しかいなくなっていた。彼らも腰を上げだしている。
ポタタタタと地面の打つリズムが早くなる。こうなると避難しかない。
駅前までのダッシュを決め込み、鞄を頭の上に載せる。走り際に横眼が相合傘を捉えた気がしたが、決して羨ましくなんかない!
鞄のおかげか、それとも自分のダッシュ力がまだまだ現役だったのか、はたまた憐れんだ神が天気を調整してくれたのか、ずぶ濡れとはいかないまでに駅前のコーヒー店に滑り込むことができた。
店内は自分と似たような連中でいささか混んでいる。アルバイトの子が差し出すメニューには目もくれずにいつも通りのアイスコーヒーを頼んだ。
いつも余っている窓際の席も、チェーン店の変わらぬ味も、変わらない。変わり映えはない。焦点が定まらないまま、虚空を眺めた。
つまらん。
一息ついた途端これだ。急な雨に非日常を求めるのはいささか荷が重たいのはわかるが、それでももう少し"ナニカ"を期待したかった。能動的な変化を面倒くさがるが、退屈は嫌いな私にはもはや雨のようなありふれた事象にも日常の破壊を求めた。我儘だ。どうしようもなく。
何もなかった虚空に紫煙が溶けた。銘柄の判らないタバコの臭いが鼻から肺に流れ込む。残留するコーヒーの余韻と合わさり、少しうっとりした気分になった。
紫煙の先を追うと予想していた人間よりも幾分も若い、なんなら性別も違う、女性が座っていた。私と同年代くらいだろうか。チャコールグレイのパンツスタイルを律儀に着こなし、余裕のある椅子の中で窮屈そうに体を縮こまらせている。
ああ、と私はすぐに自分の予想が正しかったことを知る。目線をほんの少し横にずらすと中年の少しカサッとした雰囲気の男がタバコを灰皿に押し付けていたのだ。女性とは対照的な嫌に自信に満ちたオーラが別席からもわかった。視線が向くと耳も傾くのは人間の性というものだろう。決して野次馬根性が発揮したわけではない。
「――はあ……、あ、いえ。それはちょっと」
「いやいや! そんなんじゃないですからウチの銘柄は。絶対若いうちから入っていた方がいいと思いますよ、はい!」
「でも、話だけのつもりだったんで……」
保険か何かの営業をしているみたいだ。やり取りをしているうちに会話にも熱が入ってきたのだろう、声量が大きくなっている。男の声量と反比例して女性の方はますます体を内向きに折った気がした。
少しいたたまれなくなり視線をサッと手元に戻す。途中、離れの席の女性と目が合う。営業男と同じような嫌な笑顔をされたのですぐに伏し目にした。ワタシヲタベテモオイシクナイデスヨ。
視線を上げるのは止め、耳だけを再び営業男と女性の会話に傾けた。
「――さん。確かに保険に入って、絶対に良くなるかはわかりません。でも、これだけは、これだけは絶対言えます! 今ここで保険に入らなかったら良くなる可能性は100%、0です」
男の必殺トークなのか、それを機に男の営業トークも女性の反論も止んだ。店内に流れるクラシックがやけによく響いた。
これはマズいなと直感した時には既に事は終わっていた。
「なんだ、ここにいたのか。ニアミス」
「は?」
「え?」
営業男と女性の間に割り込んでいた。
何とか気づいてほしい。営業男に見えないよう、テーブル下で左手で小さな○を作ってみる。しばらくキョトン顔した彼女はようやく視線を落としてくれた。目には"YES"と書かれている気がした。いや、そうであってくれなきゃ恥ずかしすぎる。
「全然メッセージの既読が付かないからさ。なんかしてるのかなと思って」
「う、ううん。ぜ、全然! ちょっと話が長くなってただけだから」
「そう? じゃ行こうか」
半ば強引に彼女の腕を掴んで立ち上がらせる。彼女も慌てて床に直置きした傘を拾い上げた。すると営業男は彼女の腕を掴む私の腕を掴んでみせた。
「え、あ、お友達? じゃあ、一緒に聞いていってよ。ね。今いいところでさ」
柔らかな口調とは真逆の腹黒い力が腕に食い込む。痛いんだよ、馬鹿野郎。
男の営業顔に合わせてこちらもニコっと気持ちの悪い笑顔を見せた。
「いえ、彼女も話聞くだけって聞いてましたから。すいません店を予約してるもので。話はまた今度でも」
なあ、と話をふると彼女は首をブンブンと縦に振った。その様子に気後れしたのか掴まれていた腕の力が弱まる。すかさず腕を振り切る。「では」
足早に歩く私の後ろをカッカッとヒールの音が追ってくる。入れ替わるようにカランと店の退店ベルが鳴った。
雨はやや小雨になったというところだろう。
雨の出番はもう終わったんだけどな。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
