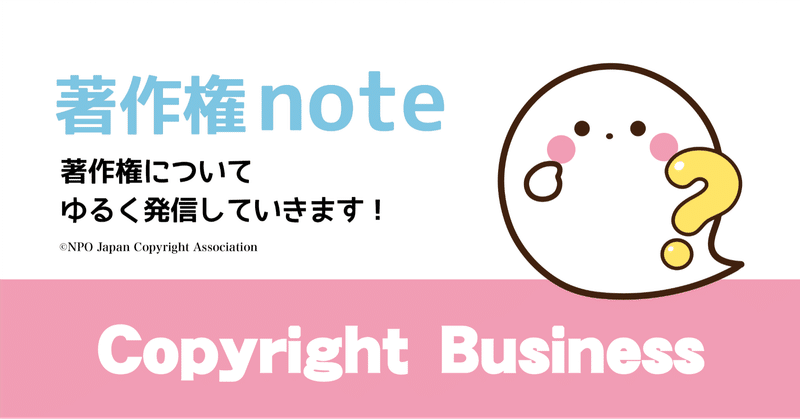
33.note記事は、著作権の証明や登録は必要ないといいます、それではどうやって「著作者の証明」をすればよいのでしょう。
質問㉚・「無方式主義」とはどのようなことですか?日本は無方式主義だから、著作権の証明や登録は必要ないといいます。それではどうやって「著作者の証明」をすればよいのでしょう。
「無方式主義」は、1908年におけるベルヌ条約のベルリン改正条約以来の原則といわれ、無方式主義に基づいて著作権・著作隣接権を取得した場合には、それぞれの条約加盟国において同時に保護が受けられることとなります。
つまり、特許権などの出願方式ではなく、〈著作権は創作した時点で自動的に取得できる権利〉のため、著作権の場合は、何ら登録する必要はない、ということです。
これを「無方式主義」と呼んでいます。
文化庁では、「著作権、著作隣接権は無方式主義で取得できるために、権利の取得は極めて簡単だが、他方、特許権のような公的機関による登録という公証的な役割を果たす仕組がないため、著作権の取得を主張するためには、結局、著作者が自ら創作したという事実を立証しなければならない」としています。
このように、著作権の権利は著作者が自らの責任を負い、自らが創作したという事実を立証しなければなりません。
著作権の証明は、自分に合った方法を取り入れてかまいません。自分で証明する方法をつくってもかまわないし、第三者に証明してもらうのも自由。文化庁や民間著作権登録団体や、その他の団体で証明する、公証人役場で証明する、郵便局の内容証明郵便で証明することも自由です。
なぜならば、著作物はさまざまな形をし、表現されているものです。したがってどんな方法を選ぶかは自分の都合によって決められるのです。
著作者自身が自らの手で著作物の事実証明を考え、独自の方法を開発すればよいのです。
質問㉛・「複製権」という言葉を耳にしますが、どのような権利のことをいうのでしょうか?この権利はどのような場合に働き、著作権に及ぶのでしょうか。
今の世の中、特に商品製造、販売の分野では、すべてのモノが複製され大量生産されています。それらを複製物といいます。
著作権の中の「複製権」とは、著作権の「支分権」の中で最も基本的な権利といわれ、ほとんどの著作権トラブル(侵害行為)がこの複製権によるものです。
「支分権とは著作権が複製・上演などのように利用形態別に権利が分かれていることで、公表権・氏名表示権・同一性保持権などは著作者人格権の〈支分権〉と呼びます」
著作権法は、すべての種類の著作物について、著作者に複製権を与えているものです。複製権は、「印刷、写真、複写、録音、録画、その他の方法により、有形的に再製すること」と定義しています。
この定義は印刷などという例示をしていますが、これに限定されるわけではなく、新しい手段で出願すれば、自動的に複製の範囲も拡大するという意味です。
FD(フロッピー・ディスク)やCD・ROMに著作物を保存し、コンピューター内のハードディスクに著作物を蓄積することも、複製となります。
また、SNSやフェイスブックなどのネット媒体において、他人の撮影した写真や、映像、イラストや絵、文章などをコピーすることも複製(複写)となります。このように、他人のモノを複製(複写)する場合に働く権利の事をいいます。

※特非)著作権協会おすすめ電子書籍~あなたの著作権の証明方法を教えます~「著作権創作事実証明」前編・後編の二部作。好評発売中!「富樫康明・アマゾン」で検索してください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
