
まだ使える廃止公共施設のその後をどう考えるか
増え続ける周防大島町の空き家。全国トップクラス
国土交通省の調査によると、周防大島町は、空き家率が全国でも指折りで高く、36%。4410件。なんと3軒に1件が空き家だとか(全国平均は13.6% 、山口県平均は17.6%。平成30年住宅・土地統計調査)。
昨年度初めて町が実施した独自の空き家調査では、11813件中2371件、20%が空き家との結果が示されました(人口14000人に対して家屋が12000件あることも衝撃)。
でも、不動産流通に乗っている物件は少なく、空き家を求めている人は多いのに、見つからないというジレンマ。
高齢化が進んでいる集落によっては、現役世代が数件入れば地域が存続できる(逆にいうと新たに入らなければ存続が難しい)というところもあると感じています。家は個人の持ち物だから簡単ではないけれど、移住者を戦略的に入れていくことも、集落として考え動く地域とそうでない地域で、これから進む道が違ってきそうな気がします。
これって、公共施設についても言えることだと感じています。公共施設は人口減少によって余剰になってきています。
特に周防大島町は、一人あたりの公共施設床面積は、全国平均のかなり上を行っていて、近年毎年、廃止になる公共施設について議会に上程されています。
当初の役割を終えた公共施設に、次の役割を担ってもらい、地域のどんな拠点にしていくか。全国の自治体が地域や民間と連携して、その地域らしい活用を、意志を持って試みています。
建物を次の人に託す想い:民間の酒蔵の場合
そんな中、知人のSNSを通じ、とある民間物件の、活用の後継者を募集する情報が流れてきました。
実際に、4代目の石津さんともお会いしてお話を伺いました。うまくマッチングできたら・・・エリアにとっても重要な拠点になると感じています。
にしても、本当に広い敷地。これまで維持管理してこられたことにも脱帽です。
この記事をみても、持っていた資産をなんとか次の人につなぎ、生かしてほしいという思いが伝わってきます。
物件を持っている自分たちが使えたら一番だけど、それが難しい。
建物の魅力を発揮して今の世に生きる建物であってほしい。
そのためにはどういう人に使ってもらうのがいいか。
どうやったらそういう人と出会えるか。
それを考えて、こういう形で募集をされているんだと思います。
空き校舎の活用を町の課題を解決につなげる:紫波町の場合
岩手県紫波町では、統合により7つの小学校が廃校となりました。
廃校活用にあたり、「学校跡地活用基本方針」が策定されています(徹底して”廃校”と表現していないところにも、行政の愛と意志を感じます)。
方針を定めるにあたって、地域の現状と課題が、対象エリアにフォーカスして整理されているところから始まっています。
次に、「地域の意向調査」が行われています。紫波町の「市⺠参加条例」に基づき、市⺠と行政が協働でまちづくりを行うため、さまざまな施策において市民の意見を聞く機会が設けられることになっています。
さらには、「民間の意向調査」。活用のコンセプト 決定の参考とするため、⺠間市場調査が実施されています。
つまり、活用のコンセプトを示した上で、活用を具体的に決めようという考えかたにより、この方針は策定されています。

また、コンセプトは町の目指す将来像を実現するためのものなので、民間事業者を決めたら「あとはお任せ!」ではなく、
⺠間事業者等による利活用を促進するため、企業版ふるさと納税制度や構造改革特区制度の活用、ガバメントクラウドファンディングなどを活用した公的支援の検討も適宜行います。
とあるように、自治体の財政負担を最小限に抑えながら、⺠間との連携により事業を進める覚悟と行政ができる伴走型の支援の検討の用意があることが明記されています。
周防大島町の廃止公共施設の行方は
公共施設は、関係する担当部署がそれぞれ管理しています(学校であれば教育委員会、観光施設であれば観光担当課)。ただし、廃止された公共施設、特に役割を変えて後利用を図る場合は、通常(何を通常というのかは難しい所ではありますが)、管財課のようなところがまとめて管理されることが多いようです。
しかし本町の場合は、それまで所管していた部署が、そのまま後利用を企画して続きをするという流れが続いています。
それでは、町全体のまちづくりに関わる後利用に関して、不慣れな部署、たまたま廃止直前に担当していた部署が、それまでの文脈やその後の展望を踏まえて民間活用の企画をしていくことになります。
それって、なかなかハードなことだと思います。
現在、2つの学校跡地について民間の利活用者が公募されています。
示されている利用条件のうち、コンセプトらしい部分は、
学校が地域の中核的な公共施設であったことを踏まえ、地域の活性化や振興発展に貢献できるよう、地域の活性化や雇用促進につながる活用であること
ということです。
活用方法を具体的に議論することもなく、即応募となっており、どんな可能性があるか市場調査も予定されていません。住民の意向を反映させる余地も、ありません(一部住民利用は配慮、避難所としての活用は町と協議することは条件に付されています)。
また、事業決定後の町の関与(維持管理費等)について、
現状での貸付となり、他の費用が発生した場合は原則、利活用者の負担となります。
とされていますが、一昨年貸付を決定した別の空き校舎については、当初民間が自ら行うとしていた施設整備の一部に、国費も含めて町から補助金が充てられることになりました。
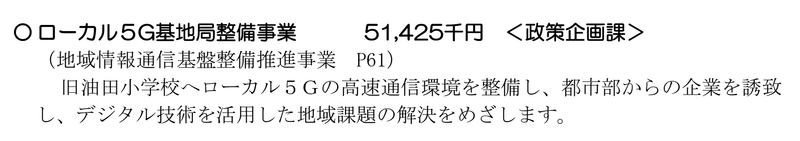
そのような可能性があるならば、紫波町のように募集段階から示しておく方が、応募者に「採択案件の実施については町も積極的に支援します」というメッセージが伝わるのではないかな?と思います。また、選定から漏れた応募者も「応募者が自ら行うと言っていたのに、そんなのズルい!」というモヤモヤを抱えなくて済むと思います。
これからも、周防大島町の公共施設は老朽化や余剰によって、廃止統合されるものが年々出てくると予想されます。
空き家と同様、有効活用されないとどんどん廃墟化してしまうし、もったいない。
物件を持っている自分たちが使えたら一番だけど、それが難しい。
建物の魅力を発揮して今の世に生きる建物であってほしい。
そのためにはどういう人に使ってもらうのがいいか。
どうやったらそういう人と出会えるか。
「前回このやり方で問題がなかったから、次もこのやり方で行こう!」と、前例踏襲するのではなく、より良い方法にブラッシュアップして、視野を広く将来を見据えた民間活用を実現していくことが大切だと思います。
私は議員として行政に提案することと、住民の方やパブリックマインドを持つ民間事業者の方々と行政をつないでいくことが役割だと考えています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
