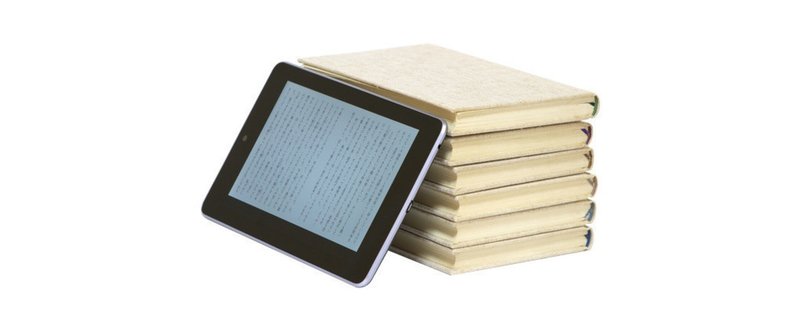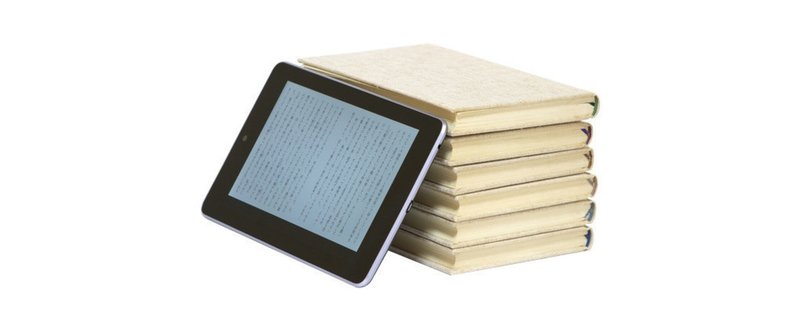- 運営しているクリエイター
2014年9月の記事一覧
〈戦後〉というものはいかにあやういイメージのもとに創られてきたものだったのか!──五十嵐惠邦『敗戦と戦後のあいだで』
この本はまず4本の日本映画(『野良犬』(黒澤明監督)、『黄色いからす』(五所平之助監督)、『私は貝になりたい』(橋本忍構成のテレビドラマ。翌年橋本忍監督で映画化)、『馬鹿が戦車でやってくる』(山田洋次監督))の分析から始まります。この序章ともいうべき箇所で五十嵐さんは戦後日本から見た帰還者(外地、収容所からの帰還者)たちのイメージがどのように変容していったか、その素描を記しています。
そして
共生を喪失した私たちに植えつけられた〈個性という牢獄〉──養老孟司『「自分」の壁』
「私がずっと繰り返し主張している「参勤交代」は、ビッグピクチャー(大きな構図のこと)の一つです。都市に住む人に、年間数か月は田舎に住むことを義務付ける。まずは官僚から実践させる。そうすれば日本は確実に変わります」
政治(社会)的な実践方法のひとつとして養老さんが提唱しているものです。どこかである批評家が次のようなことをいっていたのを思い出しました。それは、退官(退職)した大学教授を少年少女(
どのような大義があろうとも戦争自体が犯罪であり、そのような戦争を行う国家こそが犯罪者なのだ──ハンス・ヘルムート・キルスト『将軍たちの夜』
1942年ワルシャワで起きた猟奇殺人事件、目撃者は犯人らしき人物がドイツの将軍ではないかと証言します。その証言にもとづいてある男(グラウ少佐)が犯人の捜索に当たります。しかし、その途中で少佐は昇進と引き替えにパリへと追いやられてしまいます。
しかしそのパリで1944年に同様な手口で殺人事件が起きました。グラウ中佐はパリ警察のプレヴェールとともにその情報を集めますが、そこに浮かび上がったのは
キースの声そのものが音楽だ。思い出につつまれた魔法の瞬間を綴り上げた絵本!──キース・リチャーズ『ガス・アンド・ミー ガスじいさんとはじめてのギターの物語』
ローリング・ストーンズのギタリスト、キース・リチャーズが娘のセオドラ・デュプリー・リチャーズと一緒に作った絵本です。キースのおじいちゃんのセオドラ・オーガスタス・リチャーズ(愛称ガス)との思い出、そしてギターとの出会いを綴った絵本です。
パン職人のガスは大の音楽好き、ピアノ、バイオリン、サックスそれにギターを弾きこなす腕前を持っていました。小さなバンドのリーダーもしていたようです。
湿っぽさなど少しもない語り口、それが豪の者であり、無頼というものなのではないでしょうか──団鬼六『死んでたまるか』
「大体、エッセイというものは人生とか、真理を追究するものではないと思っている。また、文学でも大衆文学でもない。読者の人生に対する好奇心をくすぐるのが目的だけの単なる娯楽感想文だと思っている」
という団鬼六さんの文章で結ばれている本ですが、こちらの好奇心をくすぐるだけなんてものではまったくありませんでした。
軍需工場での勤労動員に狩り出された団少年は、将棋をきっかけにアメリカ軍の捕虜と親し
〈空気〉という壁が私たちの前をふさいでくる、時に常識という仮面を付けて──佐藤直樹『世間の目』
1998年から活動している日本世間学会の呼びかけ人のひとり、佐藤直樹さんの世間学概論というものだと思います。世間などというとなにか古い世界のように思う人もいるかもしれません。でも昨年来、問題視されているLINEいじめに代表されるSNSいじめも残念(!)なことにこの世間というものがもたらしたものかもしれません。
かつて山本七平さんは『空気の研究』を著し、日本人の縛る、ある種の絶対的権威のよ
いまどこに政治家と呼べる人たちがいるのだろうか──御厨貴・芹川洋一『日本政治 ひざ打ち問答』
テレビの「時事放談」でおなじみの御厨貴さんですが、この本は政治のニュースの裏側にあるもの、政治家という人間の生身の姿を語り尽くしているものです。「政権論」「政党論」「メディア論」等に分かれて語り合っていますが、根底にあるのは政治(権力)というものが徹底的に人間のドラマだということなのだと思います。
安倍首相を論じて御厨貴さんは
「で彼の最大の弱点は (略)これまで一回も、いわゆる普通の各
現実は時に人間から言葉を失わせてしまう。だからこそ語り継ぐことが大切なのだ──佐野眞一『津波と原発』
「誤解を恐れずに言えば、大津波は人の気持ちを高揚させ、饒舌にさせる。これに対して、放射能は人の気持ちを萎えさせ、無口にさせる。それが福島の被害者が三陸の被災者のような物語をもてない理由のようにも思われた。放射能被曝の本当の恐ろしさとは、内面まで汚染して、人をまったく別人のように変えてしまうものなのかもしれない」
この佐野さんの言葉を裏づけるように、この本は、無口な放射能を追った部分が全体の3
力業ともいえる言葉の分析から浮かび上がった怪物の姿!──高田博行『ヒトラー演説』
ヒトラーの演説というと、おおぶりなジェスチャー、絶叫している甲高い声、おおげさな舞台等が撮されたドキュメントフィルムでのヒトラーの姿がまずは浮かんできます。でも、それは私たちがヒトラーに〈大衆煽動者〉というレッテルを貼ることで、その中身を充分に検討することなく遠ざけさせていたのかもしれません。これは、それを気づかせる本でした。
高田さんは、まずはそのような先入観を排除し、ヒトラーの演説に
私たちの死はどのように変貌していくのだろうか。それへの向き合い方はあるのだろうか──結城康博『孤独死のリアル』
現在の日本では年間3万人以上になるという〈孤独死〉、この本は結城さんのケアマネジャーとしての実体験に裏打ちされた考究で、孤独死に直面している当事者(高齢者自身や民生委員等)の視点からこの孤独死問題に対して多面的にアプローチしたものです。
生命体の終焉はもちろん個別に訪れます。けれどその生命体の終焉がそのまま〈死〉ということにはならないのではないでしょうか。人間(もしくは社会性を持つ動物た
危機は私たちが気づかないうちに忍び寄ってくる、そして不意打ちするものなのだ──内田樹『街場の憂国会議』
日本の〈今ここにある危機〉を内田樹さんをはじめとする8人の論客が論じた一冊です。〈今ここにある危機〉といっても単なる時勢論ではありません。民主主義の危機(変貌)と国民国家の崩壊という〈今始まっている危機〉であり、私たちの未来に関わることを論じています。
「政治家の権力もまた期限があるということを、政治家自身が知っておくべきです。憲法のような、政治家よりもはるかに長い永続性を持った規範を、期
吉田調書を読むにはこの本のことを知ってからです!──門田隆将『死の淵を見た男 吉田昌郎と福島第一原発の五〇〇日』
「待っている作業員の前で、“なんで俺がここに来たとおもってるんだ!”って怒鳴ったんです」
という現場での、そしてテレビ会議での菅直人元首相の声、
「「撤退したら、東電は百パーセントつぶれる、逃げてみたって逃げきれないぞ!」(略)この菅の言葉から、福島第一原発の緊対室の空気が変わった。(なに言ってんだ、こいつ)これまで生と死をかけてプラントと格闘してきた人間は、言うまでもなく吉田と共に最後まで
時間は人を癒やすことが本当にできるのだろうか……──門田隆将『記者たちは海に向かった』
東日本大震災とそれに続く原発事故に直面した福島、その福島で発行されている新聞、福島民友新聞の記者たちの姿を主軸としたノンフィクションです。あの災害と事故の中で自分たちの使命を果たそうとした人々の姿とあの日を丁寧に重層的に描き出しています。
門田さんは
「哀しみは「時」が癒やすというが、本当にそうだろうか。東日本大震災で亡くなった一万八千人を超える人々と、それを見送った人々の哀しみが癒える
靖国、それは日本固有の不可思議さと矛盾を明らかにしている──原武史『知の訓練』
『可視化された帝国──近代日本の行幸啓』『皇居前広場』『〈出雲〉という思想──近代日本の抹殺された神々』などの著書でもうかがえるように原さんはいつもユニークな視点で現在の日本がどのような構造(歴史をふくめて)の中にあるのかを私たちに教えてくれます。なにより、この本は原さんの研究をコンパクトにまとめた総集編のように思いました。しかも、学生への講義録をもとにしているためもあり、わかりやすく(学生と