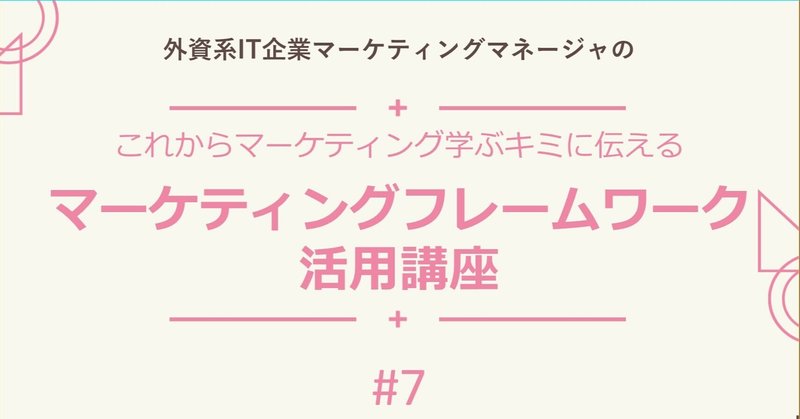
7.ポーター教授が示す「良い戦略」とは?
まず事務連絡からです。『骨太不動産マーケティング』と題して本連載シリーズを開始していましたが、どう考えても不動産にしばらく辿り着きそうにありません。
当初目的の「(不動産投資家を含めた)初心者の方へマーケティングフレームワークをお伝えしたい」とい思いを強調するために、連載タイトルを変更したいと思います。
連載シリーズタイトルは、
『初めてマーケティングを学ぶキミに伝える
マーケティングフレームワーク活用講座』
としたいと思います。
過去掲載のバーナー等も順次変更していきますので、続きものとして読んでいただいている方は、よろしくご理解下さい。
優れた戦略とは
これはそのままマイケル・ポーターの競争戦略/ジョアン・マグレッタ著のまとめです。僕の独自性というのはほとんどありません。それをなぜ書こうと思ったかだけ説明いたします。
マーケティングを学ぶ目的は人それぞれだと思います。
しかし、最終的には自分で戦略策定をすることが最終ゴールなのかな、と思います。
その際、「フレームワークに従って戦略立案をすればいいよ」とボクは言っているわけですが、フレームワークではカバーできない、「姿勢」とか「ルール」みたいなポイントがあります。ポーター教授は「条件」と言われています。
フレームワークに則って戦略を立てればそれなりの戦略にはなるはずです。
しかし、いくらフレームワークに沿ってマーケティング戦略を策定しても、そのフレームワークが全体として機能しない場合があるのです。
チグハグな戦略、中身のない戦略、表面だけカッコいい戦略
まー機能不全を起こしている戦略ですね。そうならないために、抑えておかないといけない条件、ポイントが書かれています。それを、コトラー教授の本からピックアップしたいと思いました。
実際には、マイケルポーターの競争戦略P133にでてます。P133からP247までの第Ⅱ部が、まさにこの内容が詳細に書かれています。
優れた戦略が満たすべき条件・特徴ある価値提案
・特別に調整されたバリューチエーン
・ライバル企業とは異なるトレードオフ
・バリューチェーン全体の適合性(フィッ卜)
・長期にわたる継続性
ひとつづつ、ちょっとだけ見ていきたいと思います。
「特徴ある価値提案」
この条件はさらに次のポイントを考慮する必要があると述べられています。
・どの顧客を対象にするか
・どのニーズを満たすか
・しかるべき価値を提供しつつ、しかるべき収益を実現するか
3CのCustomerに通じる部分ですね。と同時に、3つ目のポイントは、「競争優位を実現させていないといけない」という、ポーター教授がいつも主張されている点でもあります。
「特別に調整されたバリューチェーン」
・集中、差別化、コストリーダーシップのいずれか、複数を選択
・選択した顧客ニーズに対応する特定のバリューチェーンを構築
”バリューチェーン”、また出てきました。ポーター教授の書籍では頻繁に登場するフレームワークの1つです。このnoteシリーズでは、このバリューチェーンにも当然触れる予定です。ただし、ポーター教授の本をそのまま説明したのでは、ボクの独自性がでません。
「マーケティング初心者の時にはなかなか使いこなせなかったこの有益なフレームを、どうやって使いこなせるようになったか」
を詳細に説明する予定です。ボクのPowerPointでは70ページ中の4ページがバチューチェーンを占めています!

多くの方が使いこなせない理由は、
・この有名なバリューチェーンの主要素をそのまま使おうとするからです。そうすると、カバー範囲が大きすぎてしますのです。
・また、自社ビジネスにそぐわない要素をそのまま使おうとするからです。範囲を小さくし、自社ビジネスに合う要素に変更、Competitor分析とともに自社Company分析で使用すると有効なフレームワークになります。
ちなみに、
どの本にも出てません。競合と戦う日々の業務で「なぜ競合に勝てないか」を突き詰めて考え抜いて、経験から見い出せたバリューチェーンの活用法です。
この詳細はおいおい詳しく説明します。ご期待下さい!
ボクの独自性部分だと思います。
「ライバル企業とは異なるトレードオフ」
・何をやらないか選択する
・万人に提供しようとしない
これは前回のnoteで取り上げたテーマです。
「トレードオフとは、何をやり、何をならないか、そして、何を得て、何を犠牲にするか」です。
サウスウェスト航空の例が非常に良い手だと思います。コストリーダーシップ戦略を優先するために、顧客を選定し、その戦略で確実に収益をあげるために低コスト経営を仕組みとして徹底的に行っています。
トレードオフを突き詰めた経営です。大いに見習いたいと思うところです。
「バリューチェーン全体の適合性(フィット)」
・相互依存的な選択を行うことによって成り立つ
・ある活動の価値やコストが他の影響活動に影響与えることを認識する
・システム全体が戦略とも切り離せない状態をいう
・模範者を締め出し、独自のコアコンピタンスとなり得る
ポーター教授は、全体の統一、相互依存状態を、「適合性」という言葉で表しています。僕はこの状態を、「首尾一貫性」とした方が理解しやすいのかなと思っています。
いずれにしても、使用するフレームワーク間の結合、その方向性やベクトルが同じ方向を目指していなくてはならず、その根拠や導きだした戦略が論理的でなければならない、ということを言っています。
当たり前と思われるかもしれませんが、「豊富な機能性を志向した製品なのに、セクシーな女性を使った広告展開を実施」なんてことが往々にしてあります。
お恥ずかしながら、自分が経験したことです。まだ転職したばかりで、社内的に発言権もなく、部門のセクショナリズムもあり、プロダクトマネージャーのボクの方向性を全く理解しないまま、「目を引くから」という理由で広報が勝手にこの内容で広告展開しました。
社長の逆鱗に触れ、この広告展開は中止されましたが、マーケティングや戦略を理解していないと、こうなります。反面教師の例です。
「長期にわたる継続性」
・上記の帰結
・核となる価値提案が安定していればやり方はいくらでも考察できるし、すべき
・ニーズの変化、イノベーション、技術経営でのブレイクスルーが起きたときは再考する
4つの「優れた戦略」条件に合致した戦略策定を行ったとしても、それは時代とともに競争優位を発揮しなくなる可能性があります。そのために適宜戦略を見直しアップデートをかけなければなりません。
あるいは、ニーズの変化等で全く使い物にならなくなってしまう可能性もあります。その際には、競争優位を継続するために、過去の競争優位のフレームワークに固執せず、積極的に見直さないといけない、という戒めです。
次回は、『誤った戦略』について考察してみたいと思います。
そして、その次からいよいよ実際のマーケティング戦略立案に入っていきます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
