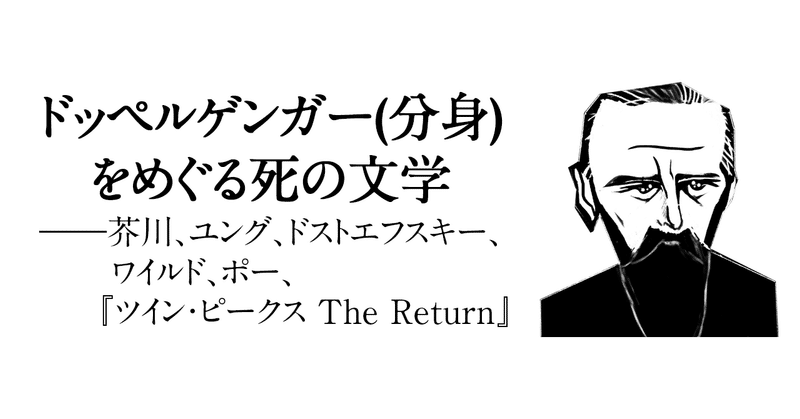
ドッペルゲンガー(分身)をめぐる死の文学――芥川、ユング、ドストエフスキー、ワイルド、ポー、『ツイン・ピークスThe Return』
「死」の文学入門~『「死」の哲学入門』スピンアウト編 第5回
内藤理恵子(哲学者、宗教学者)
『誰も教えてくれなかった「死」の哲学入門』著者、内藤理恵子氏の寄稿によるスピンアウト企画「『死』の文学入門」。
第5回のテーマは「ドッペルゲンガー」です。
第1回 K的な不安とSNS―夏目漱石『こころ』
第2回 芥川龍之介は厭世観を解消するために筋トレをすべきだった?
第3回 “夢オチ”死生観とマドレーヌの味―池田晶子、荘子、プルースト
第4回 「死の文学」としての村上春樹の短編小説
※関連記事『誰も教えてくれなかった「死」の哲学入門』幻のあとがき
私のドッペルゲンガー体験
7年前のことです。当時、非常勤講師を掛け持ちしていた私は、目の回るような忙しさに疲れ果てていました。そこで私が思いついたのが、睡眠をコマ切れにする方式でした。午前0時に少し眠って起き、午前2時頃から明け方まで原稿に向かい、それからまた少し眠る。そんな生活が続いたある日の朝、心身ともに消耗し尽くし、ついに明け方に気絶してしまいました。何とか回復した数時間後に仕事先に向かったのですが、勤務先の大学に着くと、二人の学生が「先生(内藤)にまるでそっくりな人を電車の中で見た、何度見ても本人か? と思ったが様子が変だった」と騒いでいました。何かの見間違えだろうと信じていなかったのですが、目撃したという場所には思い当たる節がありました。それは前職(似顔絵師)の自分が乗っていた路線の電車なのでした。にわかには信じがたいことですが、それが学生たちの錯覚ではないと仮定すれば、ドッペルゲンガー(ある人物とウリふたつの人物・ドイツ語)の出現、ということになるでしょう。
「分身=ドッペルゲンガー」に相当する言葉は世界各国にあり、その定義もまちまち。辞書的な意味を持ち出すならば「自己像幻視」が当てはまりますが、過去の事例の中には、まったく違うパターンも混在しています。私の体験も第三者による目撃のため、自己像(分身)幻視には該当しません。私の場合、生活パターンを変えることで、日常に戻りましたが、分身が出現した頃の、日常とは違う次元に片足を突っこんだかのような奇妙な感覚が今でも忘れられません。
こうした分身の出現は、文学の世界ではどう描かれているのでしょうか。
神経衰弱による幻覚――芥川龍之介のドッペルゲンガー
本連載2回目で取り挙げた芥川龍之介(1892〜1927)は、神経衰弱の末にドッペルゲンガーを見て、それを小説(タイトルは「二つの手紙」)にしています。この短編小説(初出は1917年)は芥川晩年のリアルなドッペルゲンガー体験(自分の分身を2回目撃する。ただし小説では3回)をベースにしています。主人公は倫理学と英語の教師(哲学科卒・35歳)の佐々木という名前の男性ですが、晩年の作品は私小説に近いため、芥川本人と重ね合わせて読んでもよいと思います。作中で、主人公の佐々木は分身をこのように目撃します。
「第二の私は、第一の私と同じ羽織を着て居りました。第一の私と同じ袴を穿いて居りました。そうしてまた、第一の私と、同じ姿勢を装って居りました。もしそれがこちらを向いたとしたならば、恐らくその顔もまた、私と同じだった事でございましょう。私はその時の私の心もちを、何と形容していいかわかりません」
(芥川龍之介「二つの手紙」 青空文庫)
この場合のドッペルゲンガーは、「第二の私は丁度硝子に亀裂の入るような早さで、見る間に私の眼界から消え去ってしまいました」との鮮烈な描写があることからも、主人公の見た幻覚のように思われます。主人公はその後も分身を目撃しており、2回目は「妻の分身と私の分身が仲睦しく街中に立っている」、3回目は「家の中で妻と私の分身が、私の日記を読んでいた」というものです。最後には「妻のようにヒステリカルな素質のある女には、殊にこう云う奇怪な現象が起り易い」「夢遊病患者の意志によって、ドッペルゲンゲルが現れる」という主人公なりの結論を出すのですが、自身の狂気を妻に責任転嫁しているようにも感じられ、どこからどこまでが事実なのかモヤに包まれるような気分になります。読み手によっては、すべてが事実とも、「私」の妄想だとも読めますし、あるいは事実と妄想が入り混じったものとも読めるのです。読み手によって顔が異なるロールシャッハテストのような作品ともいえるでしょう。
ユングで読み解くと…
このドッペルゲンガーを理論的に考えるとすれば、どのような手がかりがあるのでしょうか。まず心理学者ユング(1875〜1961、『死の哲学入門』p137〜139)に登場を願いましょう。
ドッペルゲンガーは科学では説明不可能な摩訶不思議な現象ではありますが、仮説として有効と思えるのは、無意識や神秘、オカルトをも研究対象とする心理学者ユングの「シャドウ」とその「投影」の理論です。まず、シャドウの概念を理解するには「元型の概念」を、さらにそれを包括する「集合的無意識」も理解する必要があり、遠回りになりますが、焦らずに確認していきましょう。
ユングのいう集合的無意識とは、普遍的かつ超個人的な無意識のことを指します。人間であれば誰もが等しく備えているであろうとユングが考えるものです。物質主義的な現代人にとって、「個人を超えた無意識が存在する、それが意識までコントロールする力がある」なんてことは科学的ではない、と敬遠したくなるかもしれませんが、ひとまずそこを起点にしましょう。集合的無意識には、「元型」という概念がいくつも存在するとされています。ユングにおける「元型」とはイメージの源泉であり、人の集合的無意識の中に先在している普遍的な型を指します。
シャドウの他の元型の事例としては、「アニマ」「アニムス」などが挙げられます。アニマというのは男性の無意識の中にある女性的な面、アニムスというのは女性の無意識の中にある男性的な面のことを指します。「老賢者」など、特定のイメージを持つ場合もあります。その型が個人の枠組みを超えた集合的無意識から個人の意識上に上がってくる時に、特別な強い意味を持つとされるのです。それをふまえた上で考えるとすれば、シャドウはこの「元型」の中の一種類です。他にも元型はいろいろありますが、手っ取り早く私たちが意識的に察知できる元型がシャドウです。このユングの説を、もう少しわかりやすく説明しましょう。
突然ですが、あなたは嫌いな同性がいますか? すぐに思い浮かべることができるとすれば、それがシャドウを探る手がかりになります。例えば、「自分は社交的で友人が多く、誰からも愛される好人物(俗にいう「リア充」)」と自認している人物Aがいたとしましょう。人物Aは、「孤独なくせに妙に充足感を得ているような人物B」を毛嫌いしているとします。その場合、人物Aは無意識の中に、人物Bに似た性質をシャドウとして持っているのです。つまり人物Aが認めたくない自身の「ある側面=シャドウ(無意識)」を、実在の人物Bに重ね合わせる(投影といいます)ことで、人物Bを嫌う(意識的に嫌う)、という流れになります。誰しも、「無意識の中の嫌いな自分」を眼前に持ってこられたら避けたくもなるでしょう。相手は自分の無意識を投影しているわけですから、避けようとすればするほどそれは追ってくる、というわけです。
<ユングのシャドウ>

イラスト:内藤理恵子(以下同)
そのような「シャドウ」を取り扱ったゲームが『ペルソナ5』(アトラス、2016年)です。このゲームは個人の無意識を宮殿(パレス)として描き、その中に潜むシャドウを倒し、時には懐柔して主人公(プレイヤー)の力とします。パレスの中では、キャラクターに「ウリふたつの姿」でシャドウが描かれることもありますが、基本的には、神話や民話の中に出てくる「悪魔の姿」として出現します。人類に共通するシャドウを「悪魔」として描くことで、集合的無意識の中に普遍的なシャドウの形があることを示しているのです。シャドウをコントロールすると自身(プレイヤー)のパワーアップにつながるというルールが、ユング心理学に通じるのです。「あいつはなんとなく嫌いだな」という状態から一歩進めて「なぜ嫌いなのだろう」と疑問を投げかけ、最終的にはシャドウの存在を認める(無意識から意識に上げる)ことで、精神的な成長が望めるということなのです。
ここで、前述の人物Aが人物B(影)を嫌い続けると仮定してみましょう。すると、無意識の影響力は思ったよりも甚大で、シャドウは一生つきまとうことになります。それは悪夢として繰り返し現れたり、強迫的な衝動につながったり、あるいは分身が出現します。自身の内側(シャドウ)に原因があるのに、延々とそれを他者に投影し、分身に見立てたシャドウと攻防戦を繰り広げることになる、それがドッペルゲンガーという現象の正体であると思います。
ドストエフスキーの『分身』
ユングの理論をふまえた上で、ロシアの小説家・ドストエフスキー(1821〜1881)がドッペルゲンガーというテーマに挑んだ小説『分身(二重人格)』を読んでみると、それが文学的なだけではなく、心理学的にも実によく練られた作品であることがわかります。
『分身』では、主人公ゴリャートキン(下級の役人)が恩人の娘に失恋をしたことにより、彼は深い失意に陥り、分身(シャドウ)を見るようになります。シャドウは同姓同名で顔もそっくりな人物(新ゴリャートキン)として登場し、主人公の立場をおびやかします。そして、「そんなにもそっくりな人物が実際に主人公の前に偶然出現したのか?」と、いったんは読者に思わせます。が、この小説が面白いのは、主人公が自分の「そっくりさん」だと思っていた人物が、(小説上)実際にはそうではなく、似ても似つかぬ人物だったという点にあります。つまり主人公ゴリャートキンの「投影」により、新ゴリャートキンという人間が、あたかも彼にそっくりな人物として実在しているかのように描写されている……というのが作品のキモです。
例の人物ですらいまではどうやらゴリャートキン氏にとってはまったく有害邪悪な人間ではなく、また双生児(ふたご)の片割れでさえもなく、まったくなんの関係もない局外者で、実はきわめて愛想のよい人間のように思われた――
(ドストエフスキー『二重人格』小沼文彦・訳 岩波文庫、p307)
※筆者注:他の翻訳だと『分身』というタイトル表記だが、岩波文庫では『二重人格』。原題は『ドッペルゲンガー』である。
“自分”とは何なのか、それがまったく見えていなかったからこそ、ゴリャートキンは自分とはまったく似ていない人物を自分の双子のような存在に見立てていたわけですが、そこには社会的な背景が隠されています。子が親の価値観(階級的、民族的、宗教的)を継承していた時代には、職業選択など個人としての自由は制限されていましたが、アイデンティティを確立することは比較的容易なことでした。対して、近代以降はそれが難しくなっています。歯車の一つにされてしまうような社会や組織の中で、取り替え可能なパーツとして働かねばならず、同時に人間的魅力を持ち、周囲に愛されることが求められる。あまりにも難易度の高い「人生ゲーム」に参加させられたがゆえに、自分に割り振られた能力値を見失った上に、まったく関係のない「他のキャラクター」を「自分のコピー」だと誤認してしまう。現代人は誰しもゴリャートキンを笑えません。少なからず彼のような自己誤認を抱えたまま社会を生きざるをえないからです。
この小説は、刊行当時はあまり評価されませんでしたが、複雑な社会背景とそれに伴う個人の精神病理を軽妙な物語に昇華させたドストエフスキーには、先見の明があったと思われます。
<ドストエフスキー (1821〜1881)>

イギリス映画『嗤う分身』
ドストエフスキーの小説『分身』は、映画『嗤(わら)う分身』(イギリス・2013年 監督リチャード・アイオアディ)として映画化されています。この映画は、ドストエフスキーを下地にしながらも、独自のドッペルゲンガー観を打ち出しています。
映画の舞台となる「過去か未来かわからないSF的な世界」は、前回当連載で取り上げた「ヴェイパーウェイブの世界と似た空気感」とも重なりますが、ドスフトエフスキーが描いたロシアの貧しい役人の世界を、レトロフューチャーに翻案したものとも解釈できます。また、そんな世界を舞台に、ドッペルゲンガーと主人公との関係が親密になったり、裏切られたりして、主人公の感情が揺れ動くシーンには、日本の昭和歌謡が流れるのがこの映画の大きな特徴になっています。この音楽体験は全身を揺さぶられるようなまったく新しいものだと思います。というのも、イギリス映画に日本の昭和歌謡が使用されるのは珍しいことであり、欧米の若者にとっては「知らない音楽なのに懐かしい気分になる」日本の昭和歌謡は、異化作用と擬似的なデジャブを引き起こすのかもしれません。それは、よく知っている自分の顔なのに、内面は馴染みのない人物が出現するというドッペルゲンガーの現象を表現するのに、膝を打つほどにぴったりとハマるのです。というのも、自分の分身が出現した奇妙な感覚とは、音楽などを通じて初めてそれを擬似的に追体験できるような特別なものだからです。
さらに映画版では、原作のラストを大幅に改変しています。ドストエフスキーの小説『分身』では、主人公(私)は分身に敗北して社会から追放されますが、映画では、主人公が分身の裏をかいて出し抜きます。また、映画版の主人公は自身の身体と分身の身体が奇妙に連動している(主人公が負傷すると分身も同じ箇所を負傷し、その逆もしかり)のに気づき、分身を欺くプランを思いつきます。主人公は、分身を身動きできないように仕向けて、自分は助かるような形で飛び降り自殺をします(自分だけが救急救命にあずかり、分身はそのまま落命するように仕向ける)。劇中、最終的に主人公の試みが成功したかどうかは描かれていませんが、主人公である「私」は少なくとも、無残な敗北だけは逃れています。
とはいえ、この映画のアイデアには、なんとなく既視感も覚えます。私は、そこにアイルランドの作家オスカー・ワイルド(1854〜1900)の『ドリアン・グレイの肖像』のラストが援用されている可能性を見出しました。つまり、映画『嗤う分身』は、ドストエフスキーの『分身』を原作にしながらも、最終的にはワイルドのドッペルゲンガーに関するアイデアを借用することによって、主人公が分身に打ち克つという新しい物語を編み出した、といえるのではないでしょうか。
<オスカー・ワイルド(1854〜1900)>

ワイルド VS ポー
『ドリアン・グレイの肖像』の主人公、美青年のドリアン・グレイは年上の悪い男に「官能主義的に生きること」をそそのかされ、堕落した人生を送ることになります。しかし、グレイはそこで奇妙な現象に見舞われます。彼の堕落した生活の影響は外見には現れず、本人は驚くべき若さと美しさを保ち続け、まるでその代償のように肖像画だけが醜く変貌するのです。物語が進行するにつれ、肖像画を描いた画家は奇妙なこの現象に驚き、グレイを執拗に問い詰め、ついにグレイは画家を殺してしまいます。しかし、それだけに留まりません。グレイは自身の魂が実は絵に移っており、グレイの方こそが、絵画作品の影の存在になっていた(反転)ということに気がつき、肖像画を“殺す”ことで自身の過去の罪をすべて消してしまおうとします。
ナイフはきらりと輝いていた。画家を殺したときと同じように、その画家が描いた絵を、その絵が持つすべての意味と共に殺すのだ。過去を殺してしまえ。過去が死ねば彼は自由だ。このいまわしい魂が死ねば、おそろしい警告がなくなれば、彼は平和を取り戻せる。彼はナイフをつかむと、肖像画に突き刺した。悲鳴が聞こえ、続いて何かがぶつかる音がした。
(オスカー・ワイルド『ドリアン・グレイの肖像』仁木めぐみ・訳、光文社古典新訳文庫Kindle版、2013年)
しかし、シャドウになっていたグレイが、「本体」に転化した肖像画を傷つけたら、グレイ自身が死にいたることは避けられません。実際に、肖像画をナイフで傷つけたグレイが落命するという再反転が起こったところで、この物語は完結します。
<『ドリアン・グレイの肖像』における反転と再反転>

19世紀のアメリカ作家エドガー・アラン・ポーの短篇小説「ウィリアム・ウィルスン」(創元推理文庫など)も、仮面舞踏会に参加し、そこで仮面を被ったもう一人の自分を殺してしまう分身小説です。原作はここで終わりますが、映画化されたオムニバス映画『世にも怪奇な物語』の中の「影を殺した男」(ルイ・マル監督、1967年)では、明らかに『ドリアン・グレイの肖像』のラストと思われる「再反転」が、まるで取って付けたように加えられています。分身をシャドウだと思っていたら、実は自分こそが分身のシャドウに過ぎず、分身を殺すことは自分を殺すことになる、というオチは、どこかドッペルゲンガーという現象の本質をついています。
<エドガー・アラン・ポー(1809〜1849)>

壮大なドッペルゲンガー物語『ツイン・ピークス The Return』
次に、ドッペルゲンガーをテーマに、壮大な多次元のドラマを描き出した映像作品を紹介します。2017年のアメリカのテレビドラマ『ツイン・ピークス The Return』(製作総指揮 デイヴィッド・リンチ、マーク・フロスト)です。このドラマの劇中には、主人公の分身が3体いて、総計4タイプの“主人公”が登場します。本作は、1990年から1991年にかけて放映された旧シリーズ『ツイン・ピークス』の主人公が、異次元(赤い部屋)に閉じ込められているうちに、彼のドッペルゲンガーが悪の限りを尽くしていたという設定が前段階としてあり、主人公はその分身を倒すために多次元を往来するという壮大かつ奇妙なドラマです。このドラマは舞台設定も構成も複雑なため、メインテーマが見えにくいのですが、旧作・新作いずれにおいても、「ドッペルゲンガー」というキーワードがセリフの中で殊更に強調されていることが、ヒントになっていると思います。物語全体を通じて、『ツイン・ピークス』は切実なまでの「生の1回性」を伝えます。
本作がニーチェの永遠回帰を基盤にしていることは、拙著『死の哲学入門』でも指摘しましたが(P50〜P52、P234)、永遠回帰にドッペルゲンガーを絡ませることによって、まったく新しい哲学を生み出した作品だと思います。ニーチェは「この同じ人生が何度繰り返すとしても、それを愛する(運命愛)」とした哲学者ですが、新作『ツイン・ピークスThe Return』では、ドッペルゲンガーを使うことで「永遠回帰があったとしても、2度と同じ物語は生まれることがない」というメッセージを発したのではないでしょうか。なぜなら、主人公は分身に一旦、勝利しますが、勝利をおさめたかのように思われた主人公の人格自体も無常のものだった、という悲しいラストシーンが鑑賞者を容赦なく突き放すからです。誰しもが愛しく好ましいと思えるような旧作の主人公の魂が、新作では二転三転し、分身との決着をつけて元に戻ったかと思いきや、また違った種類のシャドウが彼をコントロールしているように見受けられます。光と影の相克は永遠に続くのだ、と示唆するグレーな結末は「勝つか、負けるか」からの脱却を示しているといえるでしょう。
こんにゃくから考えるドッペルゲンガー
ここまで来て「ちゃぶ台」をひっくり返すようで申し訳ないのですが、ドッペルゲンガーには、ユングの「シャドウ」と「投影」の理論では説明しきれない逸脱があります。自己像幻視のケース以外、たとえば冒頭に挙げた私の「自分の分身が遠隔地で目撃される」パターン(世界各地に似たような逸話があります)に関しては、ユングの理論は当てはまりません(自分が自己の分身=自己像を見るのではないから)。『ドリアン・グレイの肖像』においても、第三者の目にも「肖像画の変化」があったことから、心理学的な自己像幻視だけでは片付けられない多様なドッペルゲンガー概念の性質を、そこに見立てることが可能です。ユングの理論で片付けることのできる範囲と、そうでない範囲とを分けて考える必要があるでしょう。
さて、ここからは私の仮説になりますが、ユングやワイルドよりもずっと前に、ドッペルゲンガーに関する何らかの秘密をつかんでいたと思える人物に思い当たります。
2017年、ある取材で京都の八坂庚申堂(大黒山金剛寺八坂庚申堂)を訪れた際、「こんにゃく祈祷」という奇妙な儀礼に出会いました。その寺のお坊さんに話を聞いてみると、それは浄蔵貴所(じょうぞう・きしょ、891〜946)という平安中期の僧侶・山伏が突如始めたとされる、異形の祈祷方法でした。こんにゃくの上に名前を書いた人形を貼りつけ、そこに悩みや苦しみを持つ人の苦を背負わせることによって祈祷を受ける人を守る、という珍しいものです。
この話を聞いて真っ先に思い出したのは『ドリアン・グレイの肖像』です。すでに触れたこの小説の場合、主人公の魂を絵に移行させたマジカルな力は、肖像画を描いた画家の、主人公に対する同性愛的な愛慕の念と設定されていました。そうした「念」のようなものを僧侶の祈祷の力に置き換えるなら、こんにゃくを人の肉体に見立て、こんにゃくの側に苦を背負わせることで(グレイの肖像画の役割)、祈祷を受けた人はまるでグレイのようにノーダメージで過ごせるはずです。
それにしても、浄蔵はなぜこの方法を思いついたのでしょう。彼は山での修行中に、何かの拍子で己にひそむ「影」のようなものの存在や、「意識と肉体のズレ」に気づいたのではないでしょうか。登山中にドッペルゲンガーに遭遇するケースは、世界中でよく耳にするエピソードでもあり、浄蔵が山伏であったという点が示唆的です。こんにゃく祈祷は、これまで観てきた文学、映像作品、心理学の知識を総動員すれば、その仕組みの一端を察することができそうではありますが、それだけでは不十分です。
そこで、「ドッペルゲンガーは心理学的な投影だけではなく、宇宙のバグのようなものではないか?」 と、違う方向から考えてみましょう。『死の哲学入門』(P262〜P276)では、イタリアの修道士ジョルダーノ・ブルーノの多元宇宙論的な死生観を取り挙げましたが、それを思い出してみてください。彼の思想は、多元的な宇宙の中には「私たちと同じ宇宙が存在する」という、途方もない「無限=神」のイメージをベースにしています。そして、そのイメージは、現代の科学の力をもってしても「笑い話」とは否定しきれない類のものなのでした。
とすれば、私たちと同じような面子が、そこ(別の宇宙、別の次元)にも存在する、ということすら「あり得ること」になります。もしブルーノのいうような「無限の宇宙」があったとして、そこに「もう一人の私」がいるとしたら? 「この私」と「もう一人の私」の差はどこにあるのでしょう。私と彼女(?)を分ける“実体”などは、どこにも存在しないのです。ちょっとした決心、ちょっとした偶然の重なりが、「今の私であること」をたまたま決めているだけなのです。近代化以前は、社会に職業選択の余地すらあまりなかったので、人の歩むべき道はまっすぐでシンプルなものでした。それに比べ、現代に生きる私たちは誰しも可能性の海の中で溺れ死ぬような日々を送っています。
冒頭の話に戻るとすれば、私が前職のままでいる可能性は高く、ちょっとした出来事が私の心を変え、その結果として今の自分がいるだけなのです。
複雑になった私たちの道は多重交差のように重なり、それに伴って世界もますます複雑化していきます。それは、精神世界(ユング風にいうとすれば集合的無意識)も、より複雑にします。そこにもし、何かのバグが起これば、表層としての物質的な世界にも、ダミーのような「分身」が形作られることだって、あり得なくはないわけです。そう考えれば、「第三者の目に見える形としての分身」も一応の説明はつきます。
そして、そのバグを逆手に取ってみたらどうでしょう。つまりバグの分身を人為的に先んじて作り、そこに厄災を押し付けて死を避ける、というトリッキーな手法です。それが「こんにゃく祈祷」の種明かしではないか、と私は思います。千年以上、この祈祷は人々から求められ、脈々と寺院に継承されています。それは欧米とはまったく違う角度からドッペルゲンガーの秘密に達した人物の知恵の結晶といえます。
著者プロフィール
内藤理恵子
1979年愛知県生まれ。
南山大学文学部哲学科卒業(文学部は現在は人文学部に統合)。
南山大学大学院人間文化研究科宗教思想専攻(博士課程)修了、博士(宗教思想)。
現在、南山大学宗教文化研究所非常勤研究員。
日本実業出版社のnoteです。まだ世に出ていない本の試し読みから日夜闘う編集者の「告白」まで、熱のこもったコンテンツをお届けします。
