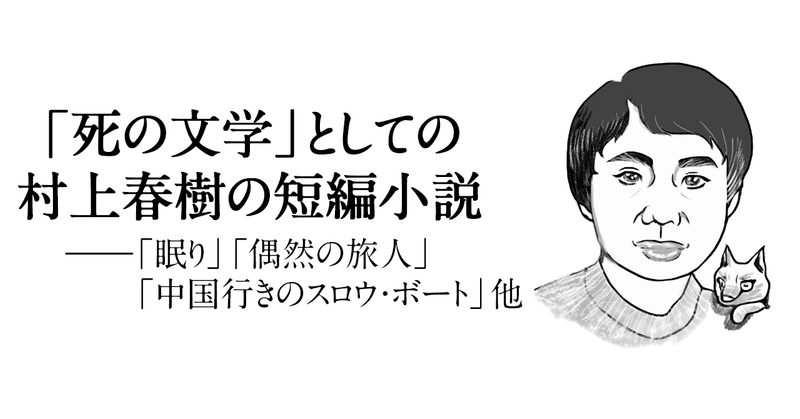
「死の文学」としての村上春樹の短編小説
「死」の文学入門~『「死」の哲学入門』スピンアウト編 第4回
内藤理恵子(哲学者、宗教学者)
『誰も教えてくれなかった「死」の哲学入門』著者、内藤理恵子氏の寄稿によるスピンアウト企画「『死』の文学入門」。
第4回は、「村上文学の死と生」について論じます。
第1回 K的な不安とSNS―夏目漱石『こころ』
第2回 芥川龍之介は厭世観を解消するために筋トレをすべきだった?
第3回 “夢オチ”死生観とマドレーヌの味―池田晶子、荘子、プルースト
※関連記事『誰も教えてくれなかった「死」の哲学入門』幻のあとがき
ヴェイパーウェイブと村上春樹
もう一度、村上春樹を読み直そう。そう思ったのには、きっかけがありました。2010年頃から広がりを見せている音楽と映像のムーブメント「ヴェイパーウェイブ」に属する音楽を聴いていたら、村上春樹の世界がありありと蘇ってきたからです。
ヴェイパーウェイブとは、80年代頃の映像(アニメやCMなどを切り貼りし、つなげたものだが、オリジナルもある)と、それにシンクロした音楽で構成される音楽のジャンルです。カセットテープなどのオールドメディアで音源だけが販売されることもありますが、動画サイトや短い動画をシェアできるブログサービスなどで拡散されることが多く、エンターティンメントなのか、はたまたアートなのか、いまだに判別しかねる謎の多さも魅力です。
専門ガイドには「1980年代のポップスや店内BGMなどの音源の音質やスピードを落とし、延々とループさせる音楽のジャンル」(佐藤秀彦『新蒸気波要点ガイド ヴェイパーウェイヴ・アーカイブス 2009―2019』2019年、DUBOOKS)とあり、定義を読めば、懐古主義のようにも思えますが、若者にとってはレトロな素材のリミックスで新鮮に映るでしょう。
一方、70年代後半生まれの私には、それらが「バブルを謳歌した死者が、あの世で“この世の春”を思い出しながら聞く異次元の音楽」のように聞こえるのです。「バブル」「異世界」という2つのイメージから、私は村上文学を初めて読んだときの感触を思い出しました。村上の初期の短編集は、「死の匂い」をシティ・ポップの感性で装飾したようなものが多く、ヴェイパーウェイブの空気に重なるからです。
死の文学の名作「眠り」
ヴェイパーウェイブの映像&音楽は、クリエイターが異なっても、使用される素材には定番があります。ギリシャ彫刻、サイバースペース、80年代のテレビCM、イルカ、レトロなドライブ系のゲーム画面などですが、なかでもドライブ系のゲーム画面に、スローでメランコリックなメロディを重ねた作品が村上の短編小説「眠り」(『TVピープル』文藝春秋、1990年)を想起させました。
「眠り」のあらすじは、不眠症に悩む女性(歯科医の妻)が夜のドライブに繰り出す、というもの。彼女は、もともと表面的には何一つ不自由のない生活を送っていたはずでした。ところが強烈な不眠によって、誰にも気づかれず日常から逸脱します。奇妙なまでにリアルで、読者は死者の日記を読み返している感覚に陥ります。
女性は、夜中にそっと家を抜け出し、自家用車で横浜の港へと向かいます。ラジオから聴こえる歯の浮くようなベタベタとしたJ・ポップのラブ・ソングを聴きながらのドライブ。到着した港の駐車場で彼女は恐怖体験をします。この恐怖体験が「事件」なのか、はたまた彼女が正気を失っているだけなのかはわかりません。直接的に彼女の死が描かれているわけではなく、それとなくわかる描写でこの小説は突然終わります。
この小説の初出は1989年。80年代をフィーチャーしたヴェイパーウェイブと重なるところがあるのは当然かもしれませんが、バブル経済の狂乱を目前にしつつ、その後のカタストロフィーへの予感が同時に息づいていた当時の空気を、一人の女性の精神崩壊に投影した作品とも読めます。彼女が眠れない夜に読み継いでいたトルストイの小説『アンナ・カレーニナ』(ヒロインのアンナは破滅的だが自分の気持ちに正直に生きた)にも注目すべきです。主人公は同書を再読することで、自我を取り戻してくのですが、そこに生まれた葛藤も彼女を逸脱へと駆り立てることになります。その後の彼女の心身の変化をグラデーションのように描いた「眠り」は、死の文学として優れたものだといえるでしょう。
怨霊か? ユングか? サルトルか?
村上のイメージソースは何なのでしょう。作品のタッチなどからアメリカ文学と誤解されがちですが、村上は心理学者河合隼雄との対談集『村上春樹、河合隼雄に会いにいく』(新潮社、1996年)において、自身の作風に関連して、源氏物語に登場する超自然的な力、たとえば怨霊などについて語っています。
ぼく自身の感じからいくと、装置(筆者注:怨霊などの超自然的な存在を物語の装置とすること)としてはじめても、ある時点で装置を越えてしまう部分がある。
(『村上春樹、河合隼雄に会いにいく』新潮社、1996年)
彼の小説のベースには日本的な霊魂観があるということでしょうか。実際、村上文学の、特に「眠り」など短編小説の読後感は、アメリカ文学よりも、上田秋成の『雨月物語』のテイストに近いようにも思います。
しかし、村上が超自然的なことに関して特に情熱を持っているかというと、それはちょっとニュアンスが違います。『東京奇譚集』(新潮社、2005年)に収録された「偶然の旅人」では、作者自身が登場し、「輪廻にも、霊魂にも、虫の知らせにも、世界の終末にも正直言って興味はない。まったく信じないというのではない。その手のことがあったってべつにかまわないとさえ思っている。ただ単に個人的な興味が持てないというだけだ。しかしそれにもかかわらず、少なからざる数の不可思議な現象が、僕のささやかな人生のところどころに彩りを添えることになる」と語っていることから、奇妙な出来事に作者自身が巻き込まれるタイプであることがわかります。
奇妙なシンクロニシティ(日常の「偶然」に意味を見出すこと)の体験も綴られていることからしても、カール・グスタフ・ユング(1875〜1961)からの影響は感じます。これらをまとめるとすれば、日本の怪奇小説、作者の体験、ユング心理学などが独自の作風を生んでいる、といったところでしょうか(ユングのシンクロニシティについては『「死」の哲学入門』P137〜P139)。
「偶然」をキーワードにして、もう少し考えを深めてみましょう。たとえば、哲学者ジャン=ポール・サルトル(1905〜1980)は、「突然やってくる死」の性質に着目しました(同P171〜P187)。短編小説「壁」は、単なる偶然が、処刑されるはずだったある男の生命を救うというストーリー。人間同士の小さな駆け引きとは別の次元に人の寿命がある、ということをテーマにしています。もしかすると、ユングよりも、皮肉な偶然が人間の生死を決定するというサルトルの思想の方が、村上文学と相性がいいのかもしれません。
村上の短編「ニューヨーク炭鉱の悲劇」(初出1981年、『中国行きのスロウ・ボート』中央公論社、1983年)と、サルトルの「壁」は、多くの仲間の無残な死、主人公の身代わりのような人物が死んで主人公が生き延びる点など、物語の舞台は違うけれども死生観は共通していると思います。
しかし、サルトルの小説よりも、やはり村上文学の方が題材も身近なものが多く、親しみを感じます。一方、サルトルの小説は、彼の哲学を踏まえないとなかなか主題が見えにくいともいえます。そこで、今回、取りあげた「眠り」の以下の箇所を、本稿「死の文学入門」における重要な問いかけとして、引用したいと思います。
私はそれまで、眠りというものを死の一種の原型として捉えていた。つまり私は眠りの延長線上にあるものとして、死を想定していたのだ。死とは要するに、普通の眠りよりはずっと深く意識のない眠り──永遠の休息、ブラックアウトなのだ。私はそう思っていた。でもあるいはそうじゃないかもしれない、と私はふと思った。死とは、眠りなんかとはまったく違った種類の状況なのではないのだろうか──それはあるいは私が今見ているような果てしなく深い覚醒した暗闇であるかもしれないのだ。死とはそういう暗黒の中で永遠に覚醒しつづけていることであるかもしれないのだ。でもそれじゃあまりにもひどすぎる、と私は思う。もし死という状況が休息でないとしたら、我々のこの疲弊に満ちた不完全な生にいったいどんな救いがあるというのか? でも結局のところ、死がどういうものかなんて誰にもわかりはしないのだ。
(村上春樹「眠り」『TVピープル』)
この問いは、前回の「夢オチ死生観とマドレーヌの味」にも通じるところがあります。人生は夢のようなもの、リアルな現実と思っていたものは単なる夢かもしれないという「夢オチ死生観」を村上は前段階として想定しつつ、同時に疑問を投げかけています。「夢から覚めるようなものが死」だと仮定もできるが、それよりもずっと厳しい状態(死が「夢から覚めて別次元の夢に移行する」わけではなく、「暗黒の中で永遠に覚醒しつづけていること」である可能性)を想定しうるのではないか、ということです。
村上作品は「死」の文学だった?
デビュー翌年に発表された短編小説「中国行きのスロウ・ボート」(初出1980年)を探ってみると、作者は一貫して「死」の一点を注視し、そこから湧き上がるイマジネーションで物語を編んでいることがわかります。この短編では、野球の試合中に、バスケットボールのゴール・ポストに激突し、脳震盪を起こした主人公がうなされて「大丈夫、埃さえ払えばまだ食べられる」という、譫言(うわごと)のようなものを呟きます。
「大丈夫、埃さえ払えばまだ食べられる」
そしてそのことばを頭にとどめながら、僕は僕という一人の人間の存在と、僕という一人の人間が辿らねばならぬ道について考えてみる。そしてそのような思考が当然到達するはずの一点――死、について考えてみる。死について考えることは、少なくとも僕にとっては、ひどく漠然とした作業だ。
(村上春樹「中国行きのスロウ・ボート」)
この小説では、死後の世界を異国のイメージに重ね、日常から死後の世界への航海を中国行きのスロウ・ボート(船足の遅い船)にたとえていますが、国際化した現在の日本において、この作品のメタファーは古めかしいものになってしまいました。一方、先にあげた「眠り」は不眠(不穏な予感)、高速道路(死の世界に向かう橋のイメージ)、港(海=死の世界に向かうための停留)、という普遍性の高いメタファーを使っているため、いま読んでもライブ感に満ちた作品だといえます。高速道路が異界との越境の比喩になっていますが、これは『1Q84』(新潮社、2009年)でも同様です。
村上の描く死生観には、セルフパロディ的な側面があります。つまり、現世とは違う世界に「死」を設定し、日常(料理や体を鍛えることなどが多い)と対比させるのです。死の世界と日常の間に、非日常的な体験(不眠、旅、失踪、身体的な変化)や「次元のズレが現れたような場所」を置いて、それらの間の往来の経緯を仔細に描くことで、彼の文学の多くは成立します。それが村上作品の常套手段ですが、そこから外れた、いわば定番以外の死生観にハッとさせられることがたびたびあります。思わぬところから死の本質を射抜く、スナイパーのような本領が発揮されているのです。特に、明らかに異彩を放っているのが、以下に紹介する短編小説「7番目の男」(初出1996年、『レキシントンの幽霊』文藝春秋、1996年)だと思います。
夏目漱石の死生観を上書きする村上文学
「7番目の男」が際立っているのは、その骨子が、夏目漱石『こころ』へのオマージュであり、同時に明らかな反論でもあるということです。なお村上は漱石の『こころ』について、「あの登場人物がみんな何を考えているのか、さっぱりわけが分からなくて、感動できませんでした」と述べています(「村上春樹 期間限定公式サイト 村上さんのところ」2015年1月〜2015年5月)。それを前提として、「7番目の男」と『こころ』を比較すると、両作品の共通点が見つかります。
第一に登場人物が、「主人公」と「Kという名前の友人」という点。語り手としての第三者がいる点も同じです。主人公とKの力関係を見ると、「7番目の男」では、学校内の評価においても経済的にも主人公が優位にあるようですが、主人公はKの顔立ちの美しさや絵の才能に秘かに嫉妬しているようです。この憐みと嫉みが混ざり合う微妙なバランスも『こころ』と似ています。過去の出来事を回想する形で物語が進行するという手法も同じです。
「7番目の男」の主人公が長年抱えていた「トラウマ的な出来事」は以下のようなものでした。10歳の頃、海岸沿いに住んでいた主人公は、台風の目の中の「静けさ」を珍しく思い、海岸に散歩に出かけます。その途中で友人のKに遭遇し、二人で浜辺に降ります。しかし、静かに見えた海は、台風の影響で変則的な波を作り出し、あっという間にKだけを巨大な波の中に引き込んでしまいます。
実は、Kが波に飲み込まれる直前、主人公は「Kを助けられなくもない微妙な場所」に立っていたのです。しかし、主人公は恐怖心のゆえに、自分だけが防波堤に走って逃げ、Kに大声で波の存在を知らせたときには、もうKの背後には高波が迫っていて助けられなかったのです。ここまでならば、反「走れメロス」のシンプルな寓話としても読むことができます。
ところが、ここから話は奇妙に変質します。なんと、主人公は第二波の高波の先端に、先ほど波にさらわれたばかりのKの姿を見た、というのです。
ほんの一瞬のことですが、波は崩れかけたままの格好で、そこにぴたりと停止したのです。そして私はその先端の波がしらの中に、その透明で残忍な舌の中に、Kの姿をはっきりと認めたのです。あるいはみなさんには、私の申し上げることを信じていただけないかもしれません。それはたぶん仕方のないことでしょう。どうしてそんなことが起こったのか、正直に申し上げまして、私自身にさえ今でもうまく納得できないのです。もちろん説明もできません。しかしそれは幻でも錯覚でもありません。噓偽りなく実際にそのとき起こったことなのです。その波の先端の部分に、まるで透明なカプセルに閉じこめられたように、Kの体がぽっかりと横向けに浮かんでいたのです。それだけではありません。Kは私に向かってそこから笑いかけていたのです。(村上春樹「7番目の男」)
Kの口は文字どおり耳まで裂けるくらい、大きくにやりと開かれていました。そして冷たく凍った一対のまなざしが、じっと私に向けられていました。彼はその右手を私の方に差し出していました。まるで私の手を摑んでそちらの世界にひきずりこもうとするかのように。しかしほんの僅かに、彼の手は私を捉えることができませんでした。それからもう一度、Kはもっと大きく口を開いて笑いました。
(同)
ここでの「波」は、死と、その恐怖のわかりやすいメタファーでもありますが、同時に夏目漱石の『こころ』へのオマージュでもあると私は思います。『こころ』には、「先生」とその友人のKが海岸の岩の上で遊んでいるうちに、Kが「先生」に自分の命を託すというような会話のエピソードが出てきます。『こころ』は失恋物語と読まれがちですが、海岸の岩のシーンにおける心の機微こそが作品の本質です。
“美学”なんていらない、グズグズ生きろ!
むしろ、『こころ』の「先生」の長い語りに隠されてなかなか見えてこない実存的な問題を、村上が短編として明らかにしたといえるように思います。『こころ』の「先生」に自殺ではなく生きることを選ばせ、心身ともに癒しに導くという世界をつくり出す――そのような文学的ウルトラCをやってのけたのが、「7番目の男」なのです。
その後、7番目の男(主人公)は故郷を離れ、死んだように生きながらも、自殺をせずに長い年月を経ます(物語の時点で55歳)。やがて、彼はKが描いた風景画を通じてKと心の中で邂逅を果たし、自身とも和解します。ここに確かに、漱石の『こころ』を超えた領域があるように思います。生き残った者がグレーのまま生き延びることで、生と死に隔たれた友情すらも優しく溶け合う世界、それが村上の出した答でした。片や自殺を選択した『こころ』の先生の方は、思春期に読めば何だかロマンティックなヒーローのように映りますが、やはりそれは、旧時代の遺物と見るべきではないしょうか。生者から見れば、死は美しく見えるものです。私の乏しい人生経験を振り返っても、そのように感じるのですから。
それに反し、村上文学は「グズグズした生」を肯定します。そこに一種の冗漫さを感じるとすれば、彼が、自決の美学を否定し、つまらなくても「保留した生」を選び続けることに重きを置いているからです。彼の小説の主人公に通底する「グダグダな生き方」こそが、実は多くの読者の死生観を知らぬ間に上書きし、読者を救っているのです。
<村上春樹 小説家(1949〜)>
上・デビュー当時の村上 下・近年の村上


イラスト:内藤理恵子
著者プロフィール
内藤理恵子
1979年愛知県生まれ。
南山大学文学部哲学科卒業(文学部は現在は人文学部に統合)。
南山大学大学院人間文化研究科宗教思想専攻(博士課程)修了、博士(宗教思想)。
現在、南山大学宗教文化研究所非常勤研究員。
日本実業出版社のnoteです。まだ世に出ていない本の試し読みから日夜闘う編集者の「告白」まで、熱のこもったコンテンツをお届けします。
