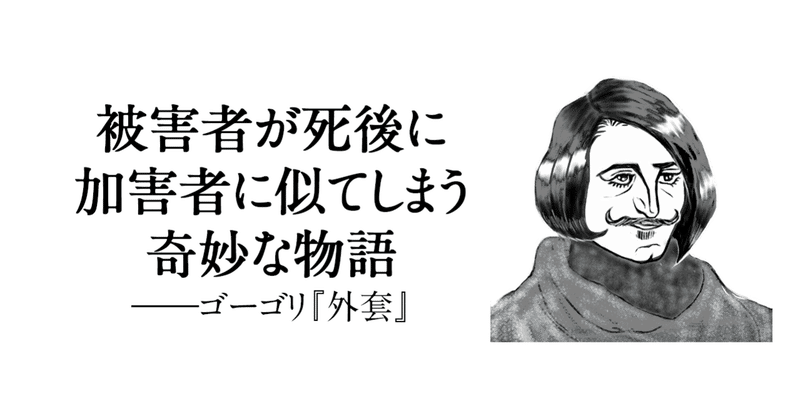
被害者が死後に加害者に似てしまう奇妙な物語──ゴーゴリ『外套』
「死」の文学入門~『「死」の哲学入門』スピンアウト編 第6回
内藤理恵子(哲学者、宗教学者)
『誰も教えてくれなかった「死」の哲学入門』著者、内藤理恵子氏の寄稿によるスピンアウト企画「『死』の文学入門」。第6回はゴーゴリの怪作『外套』を取り上げます。
マガジン「内藤理恵子『死』の文学入門」はこちら
ゴーゴリ、どこから入門するか
これまで「分身小説」を多面的に取り上げてきたことで、ニコライ・ゴーゴリ(ウクライナ生まれのロシアの小説家・1809~1852)の『外套』が改めて気になってきました。『外套』には、私たちの死生に関する思い込みを、勢いよく蹴飛ばすような鋭さと思わぬ諧謔(かいぎゃく)があります。はたして生が幸福で、死が不幸なのか? そのようなことを問題提起する力のある怪作『外套』には、生きている人間の愚かさや滑稽さを、死者の側から見て笑っているような奇妙なテイストがあるのです。
<ゴーゴリ(1809〜1852)>

イラスト:内藤理恵子(以下同)
ゴーゴリは、ドストエフスキーに比べると現代の日本では知名度が低いのかもしれません。が、かつては芥川龍之介や、現代では後藤明生といった奇才に愛された作家です。ロシアでは現在も、彼の特異な才能は、世代を超えて支持されています。
一例として、2017年にはロシア映画『魔界探偵ゴーゴリ 暗黒の騎士と生け贄の美女たち』が公開されました。この映画は三部作のシリーズもので、三作ともDVDやネット配信を通じて日本でも鑑賞することができます。これらは、ゴーゴリのキャラクターとしてのユニークさを手取り早く知るには格好の作品です。ただし「魔界探偵」という冠からしてもわかりますが、映画の中でのゴーゴリのキャラクターは、彼の実際のプロフィール(ウクライナ生まれ、プーキシンに影響を受けた、本を焼いてしまう癖、公務員としての職歴など)と、フィクション(闇の世界と交信できる等)の混交物なのです。
とはいえ、映画の中のキャラクターとしてのゴーゴリは、実在の作家ゴーゴリの個性を絶妙に表現しています。映画でのゴーゴリは、生まれた時から闇の世界の住人の力によって生かされているという設定になっています。一方で、映画のストーリーの中でゴーゴリと恋に落ちるヒロインは、ゴーゴリのことを「神が語るための道具としての作家」と、セリフの中で評するのです。闇の世界に通じた存在でありながら神の代弁者……この矛盾を含む映画での表現は、そのままリアルなゴーゴリ像に通じているところがあります。
また、映画『魔界探偵ゴーゴリ』(シリーズ三部作)は、『外套』を理解する上での助けにもなります。当時のロシアの人々の服装や所作などを知るには、映画は有効な手段です。たとえば『外套』の最重要アイテムとなる外套(=俗に言うコート)について、単に寒冷の国ロシアにおける実用的な意味合いだけではなく、当時の人々にとってはコートというものが権威や男性性の象徴になっていることも、映画の中から自然に感じとることができます。その感覚を前提にしておかなければ、『外套』が何を伝えようとしているのかつかみにくい側面があります。
ゴーゴリ『外套』あらすじ
『外套』のストーリーは以下のようなものです。主人公アカーキー・アカーキエヴィチは役所勤めの筆耕係(公文書を清書をする係)。気弱で常に周囲の人々にからかわれて生きています。彼は真面目に職務をまっとうしている(清書に至上の悦びを見出しているようにも見える)のですが、生活はパッとせず、身なりもよいとはいえず、コートまでがボロボロです。ある日、コートを修繕に出そうとしたアカーキーですが、あまりに傷みがひどいので新調するしかなくなります。
素寒貧ともいえるアカーキーでしたが、コートの新調に関しては、とんとん拍子に運び、予想外の収入もあって、思った以上に上質で贅沢なコートを手にします。彼は周囲に乗せられて、コートのお披露目会に招かれます。しかしフタを開けてみると、それはただの仲間からの冷やかしだったのです。
問題は、その帰り道の出来事でした。アカーキーは新調したばかりのコートを、口髭を生やし大きな拳を誇示する二人の男にひっぺがされ、盗られてしまうのです。アカーキーはショックのあまり体調を崩し、そのまま亡くなってしまいます。
凡庸な小説であればここで終わってしまうのですが、ゴーゴリの作品は、ここからが面白くなります。アカーキーはどういうわけか幽霊になって街頭に立ち、自分の盗まれたコートに似たコートを着た人間を見かけると、ひっぺがしにかかります。
とうとう自分の理想に近いコート(高官が着ていたもの)を手に入れた幽霊のアカーキーは、あら不思議、奇妙なことに「身長が高く、立派な口髭を生やしている姿」に大変貌し、攻撃的に大きな拳を振り上げるような男の幽霊になるのでした。それはまるでアカーキーのコートを盗んだ男たちのようで、生前のアカーキーのコンプレックスの人格化そのもののようでもありました。

<被害者が加害者に酷似するという関係性を描いた『外套』は、分身小説と言えるでしょう。被害者が死後に加害者に同一化してしまうところに独特のユーモアがあります>
アカーキーのシャドウとは
コートを盗まれた被害者の幽霊が、加害者の特徴を真似る(「なぞらえる」といったほうがよいかもしれません)――この奇妙な設定はまったくユニークです。具体的には、何がどのようにユニークなのでしょう。
まず、分身小説としてのユニークさ。当連載第5回には数々の分身小説の事例を挙げましたが、そのどれもが「実在の他人に自身のシャドウを投影する」形でストーリーが進行していきました。それらとは違って、ゴーゴリはシャドウを実在の人間に見立てずに「象徴」にまで昇華しています。
主人公アカーキーは「生まれた時に、なし崩しに父親と同じ名前をつけられた」という点からも、生まれてすぐに、将来個人として立つことを拒まれている人間です。そのような事情が、ある種の呪いとして機能したと解釈することも可能です。ですから、アカーキーのシャドウも、個性を持った人型ではなく、「立派な外套」「ヒゲ」「大きな拳」(それぞれ社会性、権威、暴力・男らしさなどの象徴)の断片として出現したわけです。
なお私は、アカーキーからコートを奪った人物は、アカーキーの無意識が形をとった霊的存在(シャドウの断片を切り貼りしたような人物像)である可能性が高いと思っています。その場合、コートを奪った人物と、ラストシーン(変身後のアカーキーの幽霊)がイコールになり、そうすると物語全体がグニャリと歪んで丸くつながってしまうのです。そこがこの物語のトリッキーなところだと思います。
幽霊小説としての『外套』
いずれにしても、コートを奪われ、そのショックから追い剥ぎのような幽霊となった主人公アカーキーは、死後に、「コート」「ヒゲ」「大きな拳」という三点セットを自分のものにしたわけで、それはコンプレックスからの解放と見ることもできます。
ゴーゴリは幽霊を、どのように考えていたのでしょうか。アカーキーの第一段階の幽霊は、現世(もしくはコート)への未練ゆえに、限りなく生身の人間に近い存在として描かれています。
これは意外なことに日本の怪談によく似たものがあります。三遊亭円朝『怪談牡丹灯籠』の幽霊(生前好きだった男性への未練から、あたかも肉体があるかのように振る舞い、思いを遂げようとする女性の幽霊)とよく似ているのです。
加えて、アカーキーの幽霊が第二段階に変化する様(つまり生前の肉体の制約から解放され、純化した「霊」に近い状態になっていく変化)は、中世の日本の説話と共通するものがあります。特に「信州某所の地頭に財産をだまし取られて悶死した山寺法師が、死後にカエルの姿で出現し、恐ろしくなった地頭が財産を返還し、法師のために祠(ほこら)が建てられた話」(池上良正『死者の救済史 供養と憑依の宗教学』角川書店、2003年)と、『外套』は非常によく似た構造になっています。
つまり、「タタリ」として出現した幽霊が、問題を解決したとたん、その性質を転換する(怨みのある死者から、祠に祀られる神になる)という説話は、日本の中世によくあるパターンであり、そのような日本の説話とゴーゴリの幽霊のイメージが偶然の一致を見せているということは、それが何かの真理を突いている可能性があります。
ナボコフのゴーゴリ評
どこか日本的なゴーゴリの幽霊は、ロシア人の目には神秘的なものに映ったようでした。ゴーゴリの幽霊のオリジナリティについて、非常に鋭い考察をしていたのがロシアの作家ウラジミール・ナボコフ(1899〜1977)です。彼はアカーキーの幽霊について次のように述べています。
アカーキー・アカーキーエヴィチが我を忘れて深入りしてゆく外套着用の過程、つまり外套の仕立とこれに腕をとおしてゆく過程は、実のところ彼が服を脱いでゆく過程、自らの幽霊の完き裸身へと漸次回帰してゆく過程にほかならない。
……素朴な読者の眼にはありふれた幽霊話と映りかねないこのくだりは、結末近く、今わたしが適切な形容詞を見出しかねるなにものかへと変貌をとげる。それは神化であると同時にdégringolade(堕落)でもある。(ウラジミール・ナボコフ『ニコライ・ゴーゴリ』青山太郎訳、平凡社、1996年、p219〜p 220)
「神化であると同時に堕落」、これはどういう意味なのでしょう。
アカーキーは生前、自分の小さな仕事を神からの恩寵だと考える信仰の篤い人間でした。ですから、キリスト教の価値観からすると、彼が自分の欲望(コートへの執着心)を死後にあらわにし、暴力的に変貌したのは、堕落に他ならないと思います。しかし、他方でアカーキーは、生前の自分に欠けた性質を補完していくという道をたどってもいるのです。
<ウラジミール・ナボコフ(1899〜1977)>

アカーキーは「個性化」した
アカーキーのたどった道、つまり自分(自我)に欠けた性質を補完していくという道は、ユングのいう個性化過程そのものであると私は思います。
ユングの個性化(すなわち自己実現)とは、一般的に使われる「個性的なその人の独自性を揺るぎなきものにすること」や、それによって「社会的に成功する」ということではありません。ユングのいう個性化とは、他人の自己すらも取り込んでいくようなものです。最初は少しの水たまりのようだった自我が、大きな沼のように拡張し、他人まで呑み込んでしまうような成熟のしかたを指します。
ですから、『外套』のアカーキーのように、自分に害を与えた他者すら自らの中に取り込んでいくことも自己実現の過程ということになります。
ループするユングの死生観
とはいえ、ユングの「個性化」とは、一般的な自己実現イメージとはかけ離れているため、なかなか先入観をぬぐえないと思います。そこで、ここではミュージックビデオでわかりやすく説明をしたいと思います。
アメリカのロックバンド「Cage The Elephant (ケイジ・ジ・エレファント)」の「Come A Little Closer」アニメーション版のミュージックビデオは、たった4分弱でユングの個性化過程がわかる画期的なものです。
最初のシーン。ケージ・ジ・エレファントのメンバーは、どこかの惑星の上で演奏しています。そこに火の玉が出現して、メンバーを旅へと誘います。旅の開始と同時に、シャドウの群れに追いかけられるメンバーたちは、シャドウから逃げるためにボートに乗って必死に漕ぎ出します。
すると、ヴォーカルの男性だけが鯨に襲われて、舞台が鯨の腹の中へと変わります。鯨の中にはなぜかバスタブがあって、そこに女性の影とヴォーカルの男性が1対1で対峙することになります。女性の影はあっという間に怪物のようなものに変身して、ヴォーカルの男性は怪物を燃やし、そのエネルギーを利用して鯨の腹から脱出します。
すると、彼は、今度は巨大な鳥に捕まって、鳥たちと闘うことになります。彼はスキを見てパラシュートで脱出し、惑星の間を軽やかに逃げまわります。しかし、今度はまた火の塊が彼を捕らえ、死の惑星へと誘います。惑星の中のベルトコンベアーに乗せられて、処刑(死)の瞬間を待つしかない状態になったとき、ヴォーカルの姿が突如、曼荼羅へと姿を変えます。この旅路は心象風景であり、最終的にまた最初のシーンに戻るというループ構造になってビデオは終わります。
これはそのまま「人の一生における個性化の旅路を早送り再生したようなもの」だと解釈すればわかりやすいです。
まずは、自分のシャドウとの対峙(自分の意識が認めたくない無意識の「ある側面」を、同性の他者に重ね合わせること。詳しくは当連載第5回)、そして自分自身のアニマ(男性の無意識の中の女性性)を、実在する異性に投影しては恋などをして、自分の中のアニマを育てていきます。そうして中年期にさしかかり精神的に成熟していくにつれ、今度は死という目標へと向けた旅路へと切り替わります。かつて未熟だった自我も、全体的な存在へと変容していくかのように見えます。しかし、結局のところ、人間は、また「振り出しの地点」に戻ってしまうのです。
ミュージックビデオのラストがループ構造になっている点がとても重要です。これは、ユングが「人間が生きている間の自己実現」については、地球が太陽の周りを周回するような状態にまでしかたどり着かない……と想定していることに通じています。つまり、生きている状態でゴールまでたどり着くことは考えず、むしろ道半ばで死を迎えることを前提としているのがユングの個性化過程、ということになります。
生に限界を見出していたユングは、死によってこそ全体性を獲得できると考えていたようです。これには一理あって、生きている人間が「私は神だ」と言い始めたら、周囲は「正気の沙汰ではない」と思うでしょうし、神と合一した生きた人間が、そうしばしば現世に出現されても世の中は混乱するばかりです。ですから、無限なるものの周りをグルグルと徒労感に苛まれながらも周回している状態を、生きている人間のゴールとするユングは、その神秘的なイメージとは裏腹に、意外と現実的な着地点を想定していることになります。
『外套』はハッピーエンドか?
死によってこそ全体性を獲得できると考えていたユングですが、死によって人間がただちに「無限の存在」(超越的な存在)となる、と考えたわけでもないようです。
ユングは、魂のタイプによっては、超越的な存在になるよりは三次元(現世のどこかに幽霊として留まること)のほうが幸福なのではないか? と考えていたようです。それを『外套』にあてはめて考えるならば、現世の人生が明らかに不完全燃焼であったアカーキーの魂は、死後にセカンドチャンスを得て、ラッキーだった……いうことになります。アカーキーは死後も「個性化過程」の只中にある、というハッピーエンドの話にすら思えてくるのです。アカーキーは生と死を超えて、「全体としての彼自身」になっていく道をたどっていくわけですから。
振り返ってみると、生前のアカーキーは、心身ともに弱く、社会的にもごく限られた領域で活動する能力しか持ちませんでした。それは生きている限りにおいては、克服することのできない壁でした。ですから、アカーキーの死後の変容は、彼にとっては解放と自己実現の過程に他なりません。アカーキーの死を不幸とみなすことは生者の傲慢であるのかもしれないのです。
霊的存在? マヤカシ? ユング VS カント
それにしても、心理学者であるはずのユングがなぜここまで「幽霊の視点」で論を繰り広げることが可能なのか? という疑問も出てくると思います。
ユングは自身の幽霊との遭遇体験(イギリス、バッキンガムシャーの古い農家での出来事)から発想を得ています(ユング『オカルトの心理学 生と死の謎』島津彬郎他訳、サイマル出版会、1989年)。
こうした考察を、よくあるオカルト話から派生した意味のないものだとか、催眠麻痺(金縛り)に伴う錯覚だと一蹴してしまうことも可能ですが、この論は、霊的存在(幽霊)の実在を否定する哲学者イマヌエル・カント(1724〜1804)の主張を明らかに意識しつつ、それを越えようとするものです。幽霊の出現を、空想によるマヤカシの像とするカントの主張(カント『視霊者の夢』金森誠也訳、講談社、2017年、Kindle版)を考慮しつつ、自分の幽霊体験からカントの主張するような可能性を慎重に差し引いて、理性的に考察を重ねるユングの姿勢は、神秘と心理学に橋をかけようとする知性そのもののように私には感じられました。
<カント(1724〜1804。カント『視霊者の夢』は、もともと神秘思想家であるスウェーデンボルグへの批判のために書かれたものです)>

アカーキーの「ゴール」を想像すると……
『外套』の主人公アカーキーは死後に、「自己実現の道」を選んだわけです。彼が、このままユングのいうところの個性化を達して、完全体のアカーキーになった……と、彼の「ゴール」を想像してみましょう。善も悪も、自己も他者も呑み込んで完全になったアカーキーは、果たしてどのような存在になるのでしょうか。
想像してみると、アカーキーは、多神教の神の一人のような存在になると思うのです。たとえば、日本の平安時代、右大臣だった菅原道真が左遷され、失意のあまりに死後に怨霊となり、都に天災をもたらしたと伝えられています。それを恐れた人々が、道真を「天神さま(神)」として祀るようになったわけです。いまも道真は「学問をつかさどる神」として受験生の合格祈願の対象となっています。
アカーキーも、このまま突き進めば、道真のような「人々から恐れられつつ、崇められるような性質」を持つ、強い魂になるでしょう。『外套』のラストには、以下のように、すでにその片鱗が見えています。
……いきなり幽霊が振り向いて立ち止まり、「なんぞ用かい?」そう言うと、人間のものとは思えないでっかい拳固をぐいと突き出した。「いや別に」と言うと、巡査はその場で回れ右をする始末。いや、なんでもその幽霊は背丈もずっと高く、おまけに立派な口髭を生やしていたそうで、オブーホフ橋とおぼしき方角に歩を進めると、夜陰にまぎれてぷつりと行方をくらましたと申します。
(ゴーゴリ「外套」『鼻/外套/査察官』浦雅春訳、光文社古典新訳文庫、2013年、Kindle版)
これは、かつて虐げられていた者による逆襲にも見えます。アカーキーが生前の弱さを克服して、恨みを晴らし、強さを求める――それは、まるで日本の怨霊のようでもあり、それをキリスト教の側から見れば、一神教の神からはかけ離れた、多神教の神の誕生……すなわち異教の神の誕生のようにも読めるのです。
ゴーゴリの死を考える
ゴーゴリ自身はキリスト教の信者でしたから、彼の物語上に誕生した神的な存在と、彼自身の信仰との分裂によって、葛藤が生まれるに違いないのです。私は、この宗教上の葛藤こそが、作家ゴーゴリの死とどこかでつながっているように思えます。
というのも、ゴーゴリ自身は、『外套』のアカーキーよりも不可解な死を遂げていて、そこには未完の遺作『死せる魂』が関係しています。『死せる魂』は、賛否両論を巻き起こし、それに恐れをなしたゴーゴリは、その反動で強い信仰に目覚めたのです。さらには狂信的な神父がゴーゴリの恐怖をあおり、文学を棄てるように、と仕向けます。その結果、ゴーゴリは『死せる魂』の第二部の原稿を焼却し、断食の末に瀉血(しゃけつ)と荒治療を施され、死亡したのです(光文社古典新訳文庫版『鼻/外套/査察官』に収録された浦雅春による解説を参照)。
作家や芸術家が自分の創作物の世界に呑み込まれることはよくあります。当連載第二回で取り上げた芥川も不可解な自死を遂げています。芥川はゴーゴリから強い影響を受けた作家ですから、ゴーゴリの死を考えることは、同時に後進たちの不可解な死の謎を解くヒントにもなると思います。
芥川の場合は、日本の宗教観から離脱しようともがき、キリスト教の信仰への渇望の末に自死しました。芥川の自死の理由は一つではなく、複数の要因が組み合わさったものと考えるべきですが、彼がキリスト教へ一縷の望みを賭けたことは確かなことです。なぜなら、芥川の遺作「西方の人」の内容は、明らかに異教の地からのキリスト教へのラブコールでした。以下は「西方の人」の冒頭の部分です。
わたしはかれこれ十年ばかり前に芸術的にクリスト教を──殊にカトリック教を愛していた。長崎の「日本の聖母の寺」はいまだに私の記憶に残っている。こういうわたしは北原白秋氏や木下杢太郎氏の播いた種をせっせと拾っていた鴉に過ぎない。それからまた何年か前にはクリスト教のために殉じたクリスト教徒たちにある興味を感じていた。殉教者の心理はわたしにはあらゆる狂信者の心理のように病的な興味を与えたのである。わたしはやっとこの頃になって四人の伝記作者のわたしたちに伝えたクリストという人を愛し出した。(芥川龍之介「西方の人」『或阿呆の一生・侏儒の言葉 』角川文庫、2018年、Kindle版)
日本の土着的な信仰からキリスト教の神を希求した芥川と、キリスト教の世界で多神教のような……しかも、なぜか中世の日本の説話のような物語を紡いだゴーゴリは、一見すると逆を向いているように見えますが、宗教的な葛藤の末に亡くなったという点においては同じです。
『外套』は軽妙な喜劇にも見えますが、その死生観は明らかな反一神教です。ゴーゴリの作品と、ゴーゴリ自身の信仰との板挟みの葛藤が、彼を日常生活から逸脱させていったのではないでしょうか。そして、その葛藤は、彼の作品自体が呪術的ともいえるような強烈なパワーを持っていたことにより、なおいっそう強くなったのではないでしょうか。
著者プロフィール
内藤理恵子
1979年愛知県生まれ。
南山大学文学部哲学科卒業(文学部は現在は人文学部に統合)。
南山大学大学院人間文化研究科宗教思想専攻(博士課程)修了、博士(宗教思想)。
現在、南山大学宗教文化研究所非常勤研究員。
日本実業出版社のnoteです。まだ世に出ていない本の試し読みから日夜闘う編集者の「告白」まで、熱のこもったコンテンツをお届けします。
