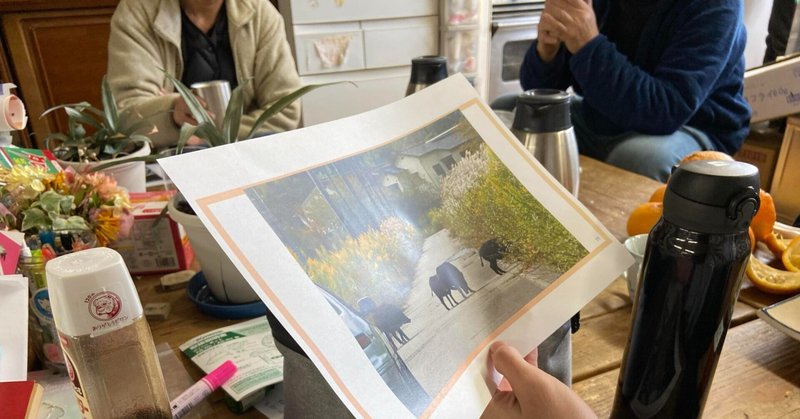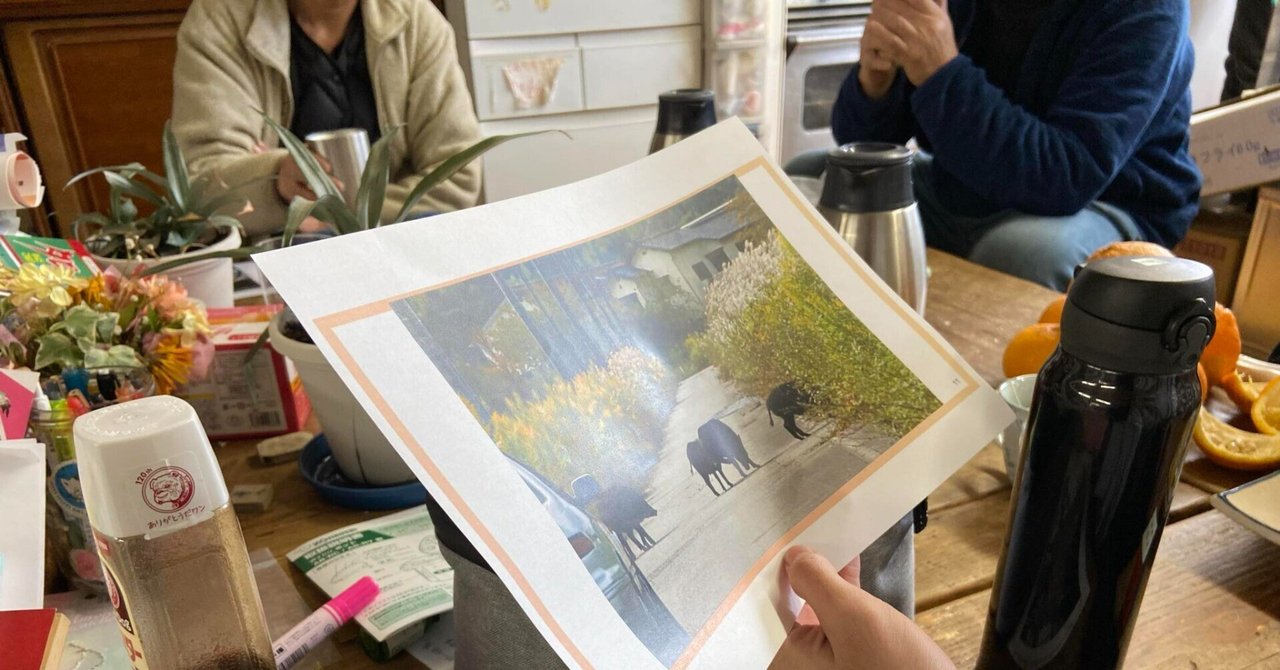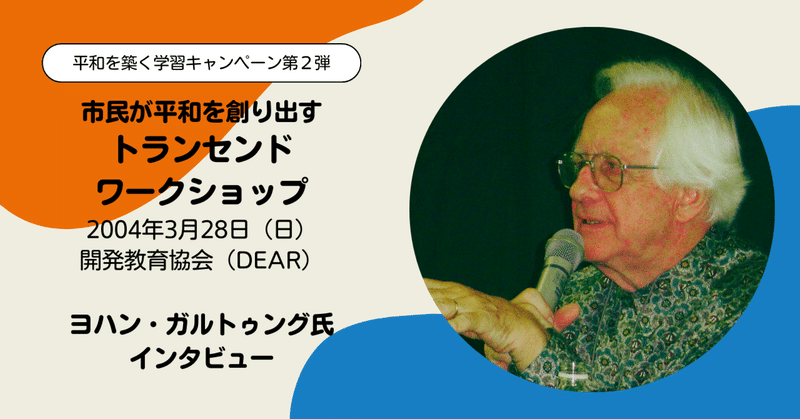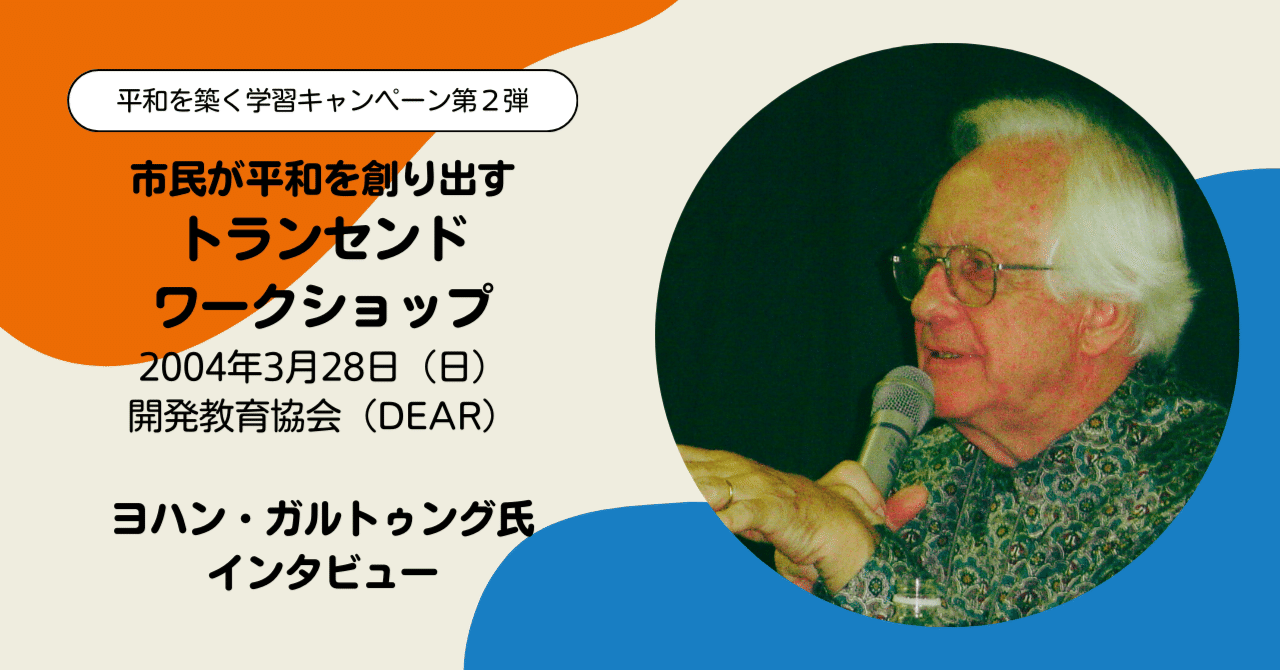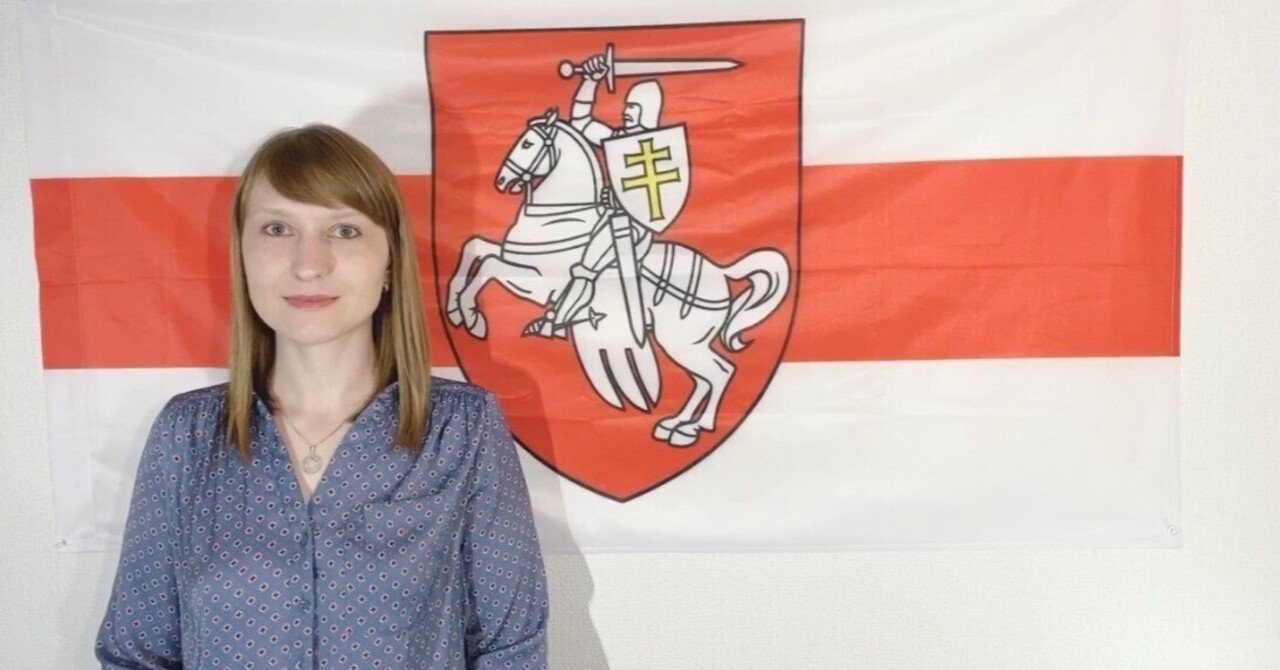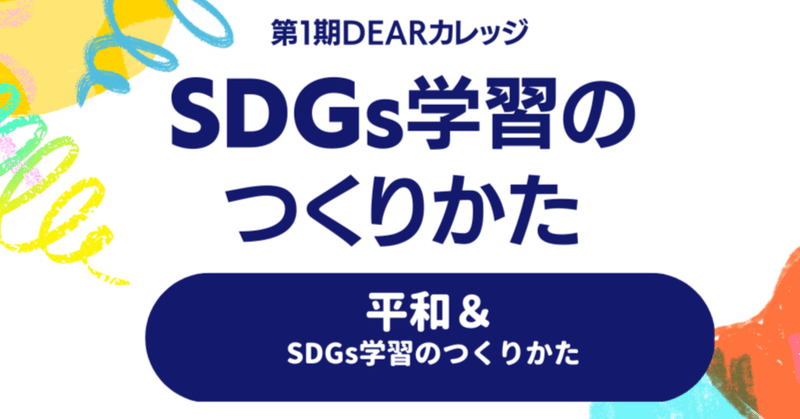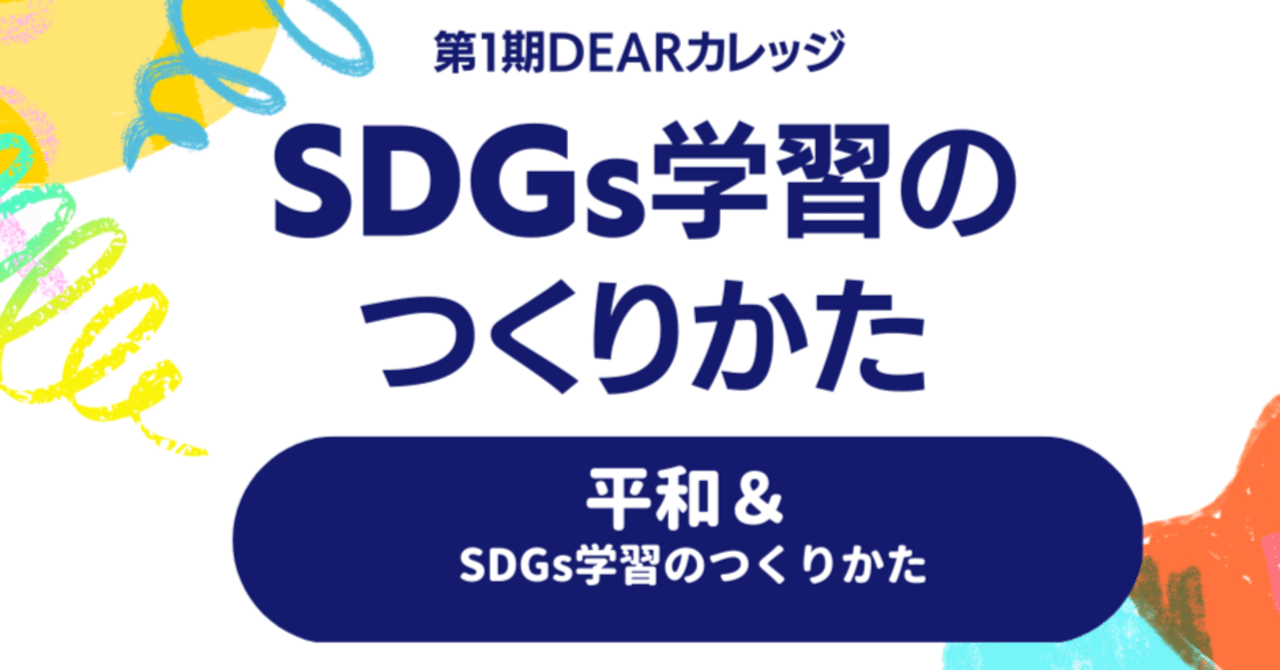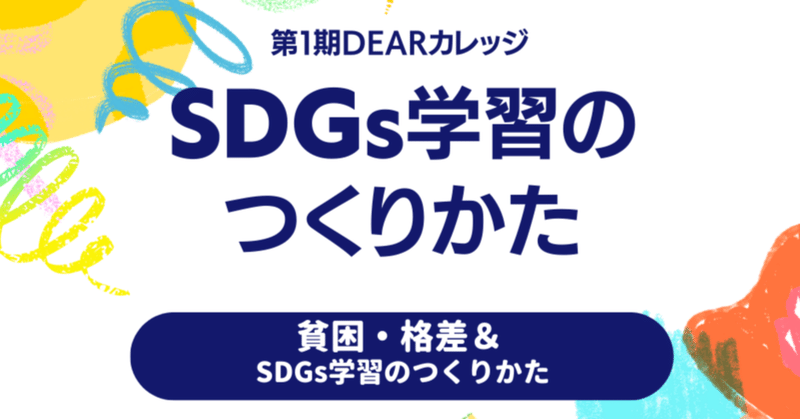最近の記事

開発教育ファシリテーション講座2024 セッション2「感情や枠組みに気づき、ありのままの相手を聴いてみよう」セッション3「開発問題に合意形成は欠かせない!」 セッション4「交流を通して、つながりを深めよう」2024.5.18(土) @国際青少年センターYMCA東山荘
こんにちは!インターンのぱるです。ついに迎えた2日間の合宿。今回は、1日目の内容に焦点を当てて紹介していきます。 合宿は、静岡県の御殿場にあるYMCAさんの東山荘をお借りして開催されました。会場到着まで、ご近所さん同士で協力しながら、バスの遅れなどあったものの、無事参加者全員で合流することが出来ました!5月半ばではあるものの、夏の訪れを感じながらの2日間になりました。そして何より、富士山がとても綺麗に見えて、私含めみんなで見入ってしまうほどでした…! セッションについて

開発教育ファシリテーション講座2024 セッション1「私と開発教育とファシリテーション」 2024.5.10(金) 19:30~21:30@zoom
こんにちは!インターンのぱるです。 今回から、本格的なファシリテーション講座の内容に入っていきます。 記念すべきセッション1のテーマは、「私と開発教育とファシリテーション」。オンライン形式で、ファシリテーション講座運営メンバーのユーコンさんとナンシーさんが中心になって進めてくださりました。 セッション1は、以下の流れで進んでいきました。 1.はじめに(参加にあたって) ファシリテーション講座の本格的な内容に入っていく前に、まずは参加者の皆さんにDEARからお願い