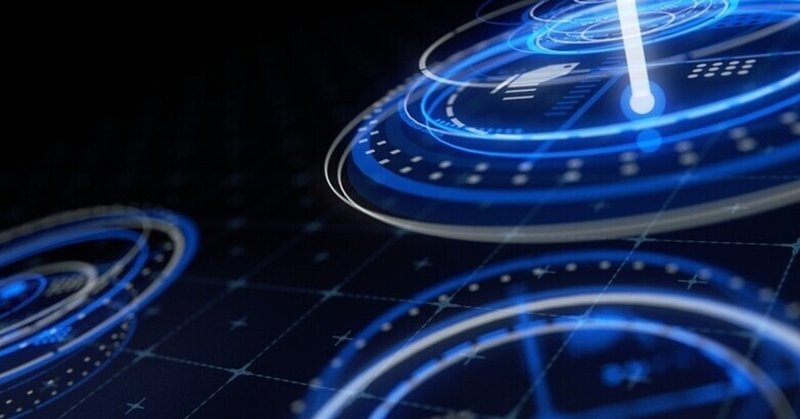
ダフネのオルゴール第13話
クロエの様子を気にしながら、早足で車椅子を押していく。廊下には医療機器や患者さんの私物と思われるものが散らばっているだけで、人が居る気配はない。ついさっきまでの騒がしさが嘘のように静まり返っている。
早く安全な場所へ。早く。足に力を入れて、またスピードを上げた瞬間、車椅子が小さな障害物に乗り上げてしまった。バランスを失って右に大きく傾き始めた車椅子の右側に回り込み、身体全体で支える。左足首に激痛が走った。
「うわっ!……クレス、ありがとう。……足、どうかした?」
「……大丈夫」
「絶対大丈夫じゃないでしょ。挫いちゃった?右?左?」
右足だけで飛び歩きながら、左足の靴下を下げる。足首が赤く腫れあがっている。重い車椅子を支えようと踏ん張った時に、変な方向に捻ってしまったようだ。素早く靴下で足首を隠し、床に座り込んだ。
「そんなに酷くないみたい」
「クレス嘘つかないで。どういう状態か教えて」
「……左足首が腫れあがってる。たぶん捻挫。歩くことはできても、たぶん走れない」
「そうか……うん、じゃあゆっくり行こう。確か20階下のフロアに脱出用シューターがあったはず。とりあえずその階までエレベーターで辿り着ければ大丈夫だから。クレス、歩ける?」
「うん。行こう」
「無理そうだったら言ってよ。どうにかなるから。隠そうとしないで」
「うん」
覚悟して一気に立ち上がった。シンバルの音のような激痛に冷や汗が出てくる。右足で体重のほとんどを支えながら、車椅子を押していく。早く動けない自分に苛立ちながらも、なんとかエレベーターに着いた。
何度も音声認識用マイクに呼び掛けてみるが、反応がない。非常用の手動式ボタンを試してみても、動く気配もしない。エレベーターの扉を強く叩き、助けを呼んでみる。無反応。病室で聞いた恐ろしい爆発音が耳の奥で鳴り始める。パニックになりかける自分を必死に抑えた。プールからあふれた水は戻らない。どうやって広げていくか、考えるしかない。クロエの言葉が、溺れている私を陸に引き上げた。
「……そうだ!非常用階段があるよ!」
閃いたと同時に走り出そうとするが、左足が出ずに崩れ落ちた。
「慌てないでクレス。走っちゃ駄目だよ。非常用階段なら私が見てくるから。もし問題なさそうであれば、クレスだけ先に下りて脱出して。私には階段は無理だから」
「ちょっと待って。私が背負っていくよ。クロエだけここに残すわけにいかない。いつ別の爆弾が爆発するか分からないんだよ?」
「その足じゃ無理でしょ。階段から落ちたらどうするの。私はどうなってもいい。クレスが無事であればいい」
「自分だけ助かったって、クロエに何かあったら私は無事じゃない!」
怒鳴った直後にふらつき、壁に手をついた。自分自身への苛立ちをクロエにぶつけてしまった後悔で、口の中が苦い。
「……そうだね。ごめんクレス。じゃあこのフロアのコントロールエリアに行ってみよう。カンザキさんから聞いたんだけどね、エレベーターの電力の供給元を独立させてから不具合が多いから、念のためにエレベーター用の小型発電機がコントロールエリアに置かれてるんだって。通信機もあるかも」
「じゃあ行こう」「行こう」
今来た道を戻っていく。壁に貼られたフロアマップを確認しつつ、コントロールエリアを目指した。左足がじくじく痛む。額の汗を乱暴にぬぐいながら、1歩ずつ進んだ。
ついに目指す場所のゲートが見えてきた。痛みを無視して早足で近づき、認証パネルに右手首をかざす。青白い光が手首を撫でると、ゲートが左右にスライドして開いた。2人でガッツポーズしてから入る。
「ここは職員しか出入りできないエリアだからクレスがいてくれて助かったよ。職員の手具に埋め込まれてるチップがなければ入れないし、忍び込めても機材は使えないだろうし」
「そっか。職員専用エリアだとセキュリティが厳しいんだよね」
「そう。エリア内の職員のチップは常にスキャンされてて、職員がいなくなると全ての機器が強制ロックされる。ゲートも開かなくなるらしいね。ホルスホスピスに来たばっかりの頃は、もし患者の私が独りでここに迷い込んじゃったらって想像して身震いしてたもんだよ」
「はは、完全に閉じ込められちゃうもんね」
クロエの車椅子を安全な場所に停め、小型発電機と通信機を探す。エリア内は雑然としていて、ほとんどの機器がロックされていて動かせそうにない。まだ使えそうな機器を探していると、いくつかの院内監視用モニターが目についた。起動している。
「……すみません!誰か応答してください!誰か!」
マイクに向かって叫んでみるが、通じている手応えはない。スピーカーに耳を澄ませるが無音。カメラの音声通信機能は駄目そうだ。
「通信機あった?」
「動いてる監視用モニターがあったんだけど、スピーカーとマイクは壊れてるみたい」
「そう。ああ、マイクは極力使わないほうがいいかも。本当に爆弾テロだとしたら、犯人たちにも聞こえるかもしれない」
はっとした。爆弾テロリストたちの存在を忘れていた。
「そう、だよね。ごめん」
「大丈夫だとは思うけど、念のためにね。ここは超高層の建物だから、私たち2人を探すためだけにフロアを1階ずつ見て回るなんて手間と時間がかかること、きっとやらないよ」
犯人たちがこのエリアに入ってきたら。恐ろしい想像を振り切りながら、モニターの周囲を探す。モニターの横に小型通信機があったが、何らかの衝撃で電気回路が剥き出しになってしまっている。使えないだろう。脇にどけて無機質な森のようなコントロールエリアの奥へと進んだ。
非常用ロックがかけられていなそうな機器を見つけては適当にボタンを押してみるが、起動するものはない。そもそも動くかも分からない年代物の機械ばかり。普段使われていないからロックをかけられなかったのだろう。
焦りが募ってきた時、暗がりの中に冷蔵庫のような大きさの黒い箱型の機械を見つけた。特に傷はついていない。側面に稲妻のマークが付いている。見覚えがあった。エレベーターの扉の上部に貼られているステッカーだ。すぐにクロエのもとに戻った。
「クロエ!見つけたかも!」「さすがクレス」
機械の近くまで車椅子を慎重に押していくと、クロエはしっかりと頷いた。
「たぶんビンゴ」「やった!」
「でもたぶん、起動させるには手間がかかるタイプだね。倉庫で働いてた時こういう発電機を見たことある。一緒にいた同僚がこういう機器のマニアでさ、毎回いかに複雑な機械かって自慢げに話してきたの。無駄話も無駄じゃなかったね」
「え……そんなに大変なものなの?」
「操作手順をまとめた分厚い手順書があって、それに書いてある通りに起動しないと強制ロックがかかるとか」
「強制ロック……またややこしい。次は手順書か……」
「左の奥じゃない?書類が入ってる棚があるよ」「あ、本当だ」
「じゃあクレスが探してる間、私は監視モニター見ておく。何かあったらすぐ知らせるよ」「うん、お願い」
自ら車椅子を押していくクロエを見送り、機械と機械の間を進んだ。左にあったガラス張りのブースに入ってすぐ、棚にぎっしりと収まっているファイルやノート類を引き出しては、表紙を確認して床に落としていく。なかなか見つからない。もう残り数冊という所で、稲妻のマークが付いたファイルが出てきた。
「リンシャ!リンシャ!聞こえる?!」
見つけた、と高らかに宣言しようとした口を閉じ、急いで監視モニターのところに戻ると、クロエがマイクに向かって必死に声を張り上げていた。モニターには、狭い倉庫のような場所でうずくまっているリンシャちゃんが映っていた。やはりマイクは動いていないようで、リンシャちゃんは無反応だ。呼びかけを諦めて、深呼吸し始めたクロエの背をさする。
「……なんでこんな所にリンシャちゃんが」
「前に大きな音が怖いって言ってた。患者の叫び声を聞いてパニックになって、丸一日行方不明になったこともある。この警報音と爆発音で、きっとまた……」
「そうだ!モニターが生きてるなら扉の開閉を遠隔操作できるんじゃないかな。ちょっと待って……」
倉庫の扉を開けようとしてみるが、どうやっても開かない。カメラを切り替えて倉庫の外側を確認してみると、扉に付いている認証パネルはめちゃくちゃに破壊され、火花を散らしていた。画面の端に、倒れている人工知能体も映っている。パニックになった職員や患者さんたちの集団に押され、認証パネルにぶつかってしまったのかもしれない。これでは実際に倉庫まで行っても、すぐには救助できないだろう。唇を強く噛んだ。
「どこから入ったんだろう。倉庫の扉も職員しか開けられないはず」
「窓……は倉庫には無いんだよね」
「そう……扉以外の……ダクトだ。ダクトの入り口も普段はロックされてるけど、昨日は一斉点検で開いてた。作業員がロックし忘れてたら」
クロエの指摘に突き動かされるように、モニターの横に浮かんでいるフロアマップのホログラム画面を食い入るように見る。倉庫内に繋がっていると思われるダクトの入り口は、このコントロールエリアから約50m先にあった。思わず安堵のため息が出た。
「近くてよかった。じゃあすぐに連れてくるよ」
「待って、私が行ったほうがいい」
聞こえた言葉がよく理解できず、呆然としている私の前でクロエは続けた。
「クレスがここにいないと、監視用モニターも発電機も動かなくなっちゃうんだよ。扉も強制ロックされるから、もし奇跡的に助けの知らせがきても、私はクレスたちにすぐには伝えられない。それに捻挫が思ったより酷そうだし。あんまり歩かないほうがいい。ここで発電機を起動させながら、モニターでリンシャの様子を見ていて」
「駄目だよ。ダクトの中を這っていくんだよ?体力を消耗しすぎたらクロエの身体が……。私が行く」
「捻挫、私をかばったせいでしょ?それに私も活躍したいんだ。一瞬でもヒーローになってみたい」
「止めて!」
なんでもないことのように笑いながら話すクロエに、また大声を出してしまった。生まれてしまう沈黙をそのままにする。クロエに生きたいと思わせることもできず、泣きそうになっている自分に腹が立った。
「ここで待っててくれるなら、絶対にリンシャを連れて戻ってくるよ。意地でも死なない。3人で生き残ろう」
クロエが私の両手首を強く握ってきた。温かい。
「カンザキさんが」
「え?」
「また新しい果物が生ったから、プラントエリアにまたクロエとおいでって。一緒に行くって、もう決めたから」
クロエの目を睨みつけるようにして一方的に言い放つ。クロエは目を細めて大きくゆっくり頷いた。
●ダフネのオルゴール第14話
●ダフネのオルゴール第12話
●ダフネのオルゴール第1話
お気に入りいただけましたら、よろしくお願いいたします。作品で還元できるように精進いたします。

