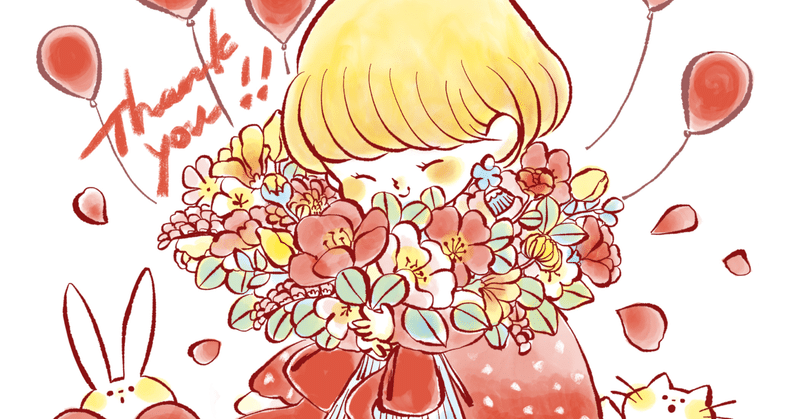
【詩人の読書記録日記】栞の代わりに 2月13日~2月19日
はじめに
こんにちは。寒い日が続きますね。長尾早苗です。実は今週末、誕生日を迎えます! 新たな29歳の旅立ちとして、この記録を応援していただけるとさいわいです。
2月13日
ちょっと昨日の夜体調が悪くなって、しんどくなっていました。
お医者さんによるとストレスの一過性のものなので、プレッシャーのかかることが終わったら治りますと断言されました。
どうかリラックスして今週も過ごせますように。
人とのうまい距離って、家族でも難しい時ってあるんですね。
相方さんが電話してくれました。
文学フリマで発売される3誌に寄稿します。楽しみです。
2月14日
詩集を出版したからこの季節の移り変わりで不安定になってしまっているけれど、詩集を出すってこういうことなんだと実感しつつ原稿を進めました。新作1編。今日は家で原稿をがんばりました。一週間ぶりにYouTubeの動画を作るなど。
こちらで朗読しています。
以前伺った検診場所が再開したとのこと! よかった、安心しました。

もう足元にひなあられ!
今日は作り置きお休みの日。
誰かの優しさを素直に受け止めようと、素直に抱きしめることがわたしの課題ですね。もう少し肩のちからを抜こう、とコーヒーを飲んでチョコを食べました。
・竹田信弥『めんどくさい本屋』本の種出版
お仕事やイベントでご一緒させていただいたのがご縁の、赤坂の双子のライオン堂という書店の店主、竹田信弥さん。
彼の本屋さんの魅力は「行ってみてください」としかいいようがないです。
とにかく、本が魅力的。そして、カオスに近く天井まで本が並んでいる。
本に携わる人々とご縁が深い。
よく話を聞いてくれて、おしゃべりが面白い。(毎週金曜朝9時からの渋谷のラジオ「渋谷で読書会」のパーソナリティでもあります)
そんな彼の「書店」を続けていくにあたっての覚悟と「100年」というスパンで考えた「これからの書店」。
わたし自身が学校やクラスに馴染めなかった頃、助けてくれたのが本だった、図書室だったという経緯が同じで、きっと竹田さんの近くには本屋さんがたくさんあって、わたしの周りには図書館がたくさんあった。
わたしが図書館員だった頃と、竹田さんが複数の仕事を掛け持ちながら書店店長を続けていくのに、何か近いものを感じます。
また、合評リアルイベントを開かせてくださいね。
そして、こういう生き方もあるんだよという道しるべにこの本がなりますように。
・渡辺信二『詩集 不覚あとさき 記憶のかけら』シメール出版企画
渡辺先生には学生時代、本当にお世話になりました。
ご恵送、ありがとうございます。
他のメンバーがいる立教大学での厳しい合評会のあとから、わたしたち学生を呼んで中華料理屋さんでごはんを共にした記憶、今でも忘れられません。
先生の英文科教授としての生き方、詩人としての生き方。
いつも、研究のことばと詩のことばが先生の中で戦っていたのではと思います。
先生はわたしたちの詩や今までの詩人(アメリカ・イギリス詩人が多かったです)には熱く語ってくださっていましたが、ご自身のことについてはあまり多くを語っていただけなかったので、この詩集やエッセイを読んで、先生の詩に対する向き合い方が変わっていくように思います。
息子さん、お父さまと、渡辺先生を結ぶ大切なご縁が次々と喪失の時期を迎えていきます。
それでも、生きてきた先生。
詩のことばがあったからこそ、生きられた先生。
まだまだ、長尾も元・立彩のメンバーとして活動を続けさせていただきます。
今回はご恵送、ありがとうございました。
・瀬尾まいこ『春、戻る』集英社
これから結婚しようとしているさくら。
彼女の前に、突然一回りしたの「お兄さん」と名乗る男の子が現れて……。
結婚をする・しないの選択肢の中で仕事を続けていくことって、実は結構厳しいんです。
結婚準備って色々忙しいので、そんな中での自分や周りの不可解な出来事に立ち向かおうとするさくら。
30代から40代にかけての淡い、けれどしっかりと地に足をつけて生きている女性の姿、もがく姿に心を打たれます。
・若林正恭『完全版 社会人大学人見知り学部卒業見込』角川文庫
わたしもオードリーがM1に出ていたころを知っていました。懐かしいなあ。
今ではあまりテレビを見ることが少なくなったのですが、わたしは割と10代後半からラジオのヘビーリスナーのため、一時期深夜ラジオばかり聞いていたことがあって、「オードリーのオールナイトニッポン」を聞いていたころもありました。
高校生だった頃は若林さんがこんな苦労も抱えていたのも知らず、友人にも「若様」ファンは多くいました。トゥース! は流行していました。
やっぱり、有名になることと仕事が増えることは同時期にやってきて、でもその中でその波にちゃんと乗れていた若林さん、偉いと思います。
声が特徴的な方なので、文体との違いに少し驚きながら読みました。
2月15日
わたしの数少ないライフイベント、移動図書館と配達の日がやってきました!
火曜日はやることが多いけれど楽しいのです。
作り置きも5種類、がんばるぞ! と思っています。
サン=テグジュペリ/〔著〕堀口大學/訳『人間の土地』新潮文庫予約。新作一編。
移動図書館通いももう一年。さすがに本棚の本に既視感が出てきたので、今住んでいる市内の図書館通いをはじめようと思います。(移動図書館の本棚を読みつくしてしまって……)
バスや電車は使ってしまうけど、わたしにとって読書は食事。
必須のことなので楽しみにしています。

相方さんの朝食を作らなくていいので、
本当に自己流。
卵かけご飯ですが、ご飯自体は
半合解凍しています。
オリーブオイルか胡麻油とマヨネーズ、
しょうゆとコショウをかけるのが最近の鉄板です。


ハムと卵の中華スープ。



・鳳晶子『みだれ髪』大空社
与謝野晶子に改名したのはこの後なんですね。
時間があると自分の本棚から探しに行ってしまいます。
一度じっくり読んでみたい本として積読していました。
なんだろう、恋というものにおいて、彼女自身が「おんな」を生きていたことによって、外に飛び出していく若々しさと、自分のことがよくわからない狭間で詠んでいたのかなと思います。
よくでてくる単語は「神」です。時に恋する人を崇める対象だったり、何かよくわからないものに対する畏怖の気持ちが「神」という強いことばに集約されていると思っています。
だからこそ、彼女はきっと家の外に何度も飛び出したかったんじゃないかと思います。歌人は吟行で得て書くひとが多いように思います。
瑞々しい歌集でした。
・サンテグジュペリ 池澤夏樹訳『星の王子さま』集英社
箱根に「星の王子さまミュージアム」があって、実家で暮らしていたころは一年に一度は行っていました。
小学六年生くらいのときのおみやげにこの愛蔵版を買ったんですよね。
わたしにとっては原点であり、その後自分が「王子」として舞台で朗読するなど思っていませんでした。
わたしの声はメゾアルトなので、少年の声に近いと思います。
いい意味でも悪い意味でも純粋無垢ということ、それでも生きていることから、きっと読ませていただいたんだと思います。
わたし自身はサンテグジュペリを詩人だと思っていて、「大人になってしまう感覚」がある種怖かったように思うんですよね。
いつまでも「子どもの感覚」「子どもの言語感覚」で生きていけないことが非常に嫌だったし、だからこそ「大人」に対する怒りとしてわたしは詩を書き続けているのかもしれません。
・北爪満喜『奇妙な祝福』思潮社
人を喪失するという経験を詩にするということ。
先日わたしたちが開催したオンライン合評会でも議論になりましたが、やっぱりリアルとして個人的な体験ののち、かけることのように思います。
それじゃないと読者に伝わりづらくなってくると思うんです。
北爪さんのこの詩集を読んだのはもう7年前になります。
吉祥寺の「クラワンカ・カフェ」で北爪さん・野村喜和夫さんたちの朗読会・講演会があって、うちうちだったのでチケットを何とかとって行ったんですよね。懐かしいなあ。
母という存在や、自分がかつては少女であったこと。
みんな誰しも娘であること。
喪失するという事実と共存する、ということをおっしゃってくれた方も合評会でいましたが、その通りだと思います。
もしかしたら自分がその人をうしなう手助けをしていたのかもしれない。
でもそんな苦悩の中でなにかできることといったら、思い出になるまで自分の中で時間をかけるしかないのですね。
そして、新たな一歩を踏み出していく過程が大事なんだと思います。
・東直子『とりつくしま』ちくま文庫
以前、朗読してみたいと思って読んできましたが、やっと読める年齢になってきたのかなと思います。
ある恩師に、『とりつくしま』は恋をしてから読みなさいと言われてきました。女性で、活発な方でした。
わたし自身は人生経験も少なく、誰かの「喪失」と共に生きること、それでもその記憶と共存しながら人を愛し、恋をしてある種の「異文化」に触れることで、変わっていった点が多くあります。
この世に未練を残して亡くなった人々が「モノ」にとりつく。
今だったらわたしは「日記」の妻の気持ちも、「白檀」の先生を一生慕う気持ちもわかる気がします。
時に美しく、しかし残酷でとても肉感的な。
誰かに恋をするということはある種の狂気ですが、その中でよい恋愛をくり返していると、大きく自分が変わっていく。
きれいになっていく。
それは男性女性問わずあるように思います。
齢を重ねたからこそ自分のうちに秘めていた思いが開かれていく感じ。
大人におすすめしたいです。
・谷川俊太郎『谷川俊太郎詩選集 1』集英社文庫
小さなころは神さまがいて
というのはよく聴くユーミンの曲の出だしですが、そういうふうに軽やかに「神さま」と対峙できたのは「小さなころ」だったんだよな
と思い返します。
そういう時を思い返す時、ふと谷川さんの詩を読みたくなります。
彼がまだまだ若くって、それでも今も書き続けていらっしゃる真実。
どれだけこの世界と、そして「ぼく」と「あなた」と対峙していたのか。
そして「ことば」とも。
その姿勢が軽やかに描かれているのはきっと、毎日書いている習慣のようなものでしょう。
改めてお話ししてみたい方だと思います。
2月16日



今日は仕事を深夜から早朝で切り上げて、仮眠をとってマイナンバーカードの更新に行きました。新作2編。とっても自由な気分になれた! 相方さん、ジャンさん、ありがとう。

アメリカ流でコーヒー・ポテトおかわり自由。
かぶりつきました。
なんと、ツイッターに投稿された140字詩が現代詩手帖に掲載されるらしいです!
【拡散希望/情報解禁‼️】
— 平川綾真智| 詩集『h-moll』(思潮社)| 「#礫の楽音」@スペース‼️ (@197979ahirakawa) February 15, 2022
「#礫の楽音」×「#現代詩手帖」
[#礫の朗読]
開催
朗読のための作品を「#礫の朗読」を付して頂き、ジャンルを問わず募集致します。
・募集期間:3/1(火)〜3/20(日)
【企画】
和合亮一
平川綾真智
ikoma
『現代詩手帖』(思潮社)#礫 #MIDNIGHTPOETS pic.twitter.com/IDeM18CEXK
2月17日
満月。昨日はそこまでつらくもなく、今日は作業がとても捗りました。
スノームーンというのですね。
昨日は身体的に困っていたことが解決することがわかり、一安心でした。
今日、少し症状がひどかったので診ていただいたのでした。
市内の建物の図書館に初めて行ってきましたよ!


・石原八束『川端茅舎』桜楓社
写生って、画家にしかないものだと思っていましたが、スケッチするように句を詠むもの、花鳥諷詠というものがあるのですね。そして、印象的だったのが咳という季語を使った句でした。晩年の茅舎はそれによってなくなっていたからです。無論、季語や目についたものに自分の感情を託して詠む句作は素晴らしいのですが、その中でも仏教観、空想の余地を持たせる句が素晴らしいと思いました。
随筆もなかなか上手な方で、一気に惹かれました。
・有川浩『阪急電車』幻冬舎文庫
女性の物語だなぁと思います。淡い恋のはじまり、彼氏とのDV関係、そして彼氏をマリッジブルーの中取られた女性。グループの中に馴染もうとして馴染めなかった女性。そんな彼女たちが、行きずりの誰かに救われていく。
おばあちゃんであったり、成長した高校生だったり。
でも、その人々も大人になれたからこそわかる道理を持っていて、痛み苦しみがわかるのです。
いつか阪急電車に乗って、こんな痛快な旅ができたらいいのにと願いはやみません。
・吉田修一『さよなら渓谷』新潮文庫
吉田修一さんは初読かもしれません……。
不勉強をお詫びします。
この本では、集団強姦をした側、そしてされた側、そして彼ら彼女たちのその後を書いています。
ある日起こった殺人事件。
そこに関与していたかもしれない容疑者の集団強姦の過去。
ずっとその人を追い続けている記者。
そんな人々を描きながら、究極の愛とはという本質に迫る物語です。
2月18日

ちょっと昨日、嫌な気持ちになったのですが、歩き疲れていただけで用事も済ませました。ラジオをアーカイブで聞き、読書や明日本を買うためのリストを作りました。お取り置きの電話をしたりなど。週末があるからがんばれる。一人旅、結構好きです。しかもタイミングがかぶって誕生日に……! うれしい~がんばるぞ!
・町田康『浄土』講談社
痛快に笑えたり、シュールに笑えたり。
時にはブラックユーモアだったり。
とにかく「笑い」というものの言語感覚に置いて、ことごとく研究しつくされた一冊になっています。
人はなぜ笑うのか。面白いということはどこから来るのか。
その一つの解答として、「本音街」があるように思います。
真実を人がつくと、それは「普段の状況から少しずれる」ことになるんですね。真実こそがことばにすると面白いんです。
今、笑いというものが厳しい時代にあります。人の容姿など、笑ってはいけないとされている項目がいくつもある時代。
不自由ですが、この小説を読んで痛快に笑ってもらえればと思います。
・まさきとしか『きわこのこと』幻冬舎
貴和子、という謎の女をめぐるびっくりするニュースの数々から浮かび上がる人間模様。
人と人がむつみあうこと、そして生きていくということ、生活していくということ。
どれも平凡なように思われますが、それをやってのけるのは至難の業だったりします。
時折事件が発生してしまう時、わたしたちはその中に人の生活があることを忘れてしまうように思います。
そんなことを思いました。
・大江健三郎『二百年の子供』中公文庫
十年以上ぶりに読みましたね。
大江さんのお子さんがモデルになって作られている「児童文学」のような作品です。
三人の兄妹が木のうろに入ると、それがタイムマシンになってしまう。
三人の兄妹はそれぞれ性格もバラバラで、特に真木は障碍を持っていて、でも真実をついたことを度々言ってくる。
あかりという女の子と朔という男の子と真木がこの小説の主人公ですが、作者が子どもたちに託したかったことが大江作品のなかでもわかりやすく説明されているように思います。
未来は子どもたちが作る。
子どもたちが大人になり、いつか子どもをもって、次の世代へ、次の世代へと受け継がれていく。その移ろいは決してやむことがない。
よい小説でした。読めてよかった。
・村上春樹 佐々木マキ『羊男のクリスマス』講談社文庫
気になってたんですよねえ……
読んでみたら村上春樹さんのなかでもたぶん一番好きなナンセンス小説かもしれません。
羊男の存在こそ謎ですが、その謎の男の周りに多くの謎の人物(人物じゃないものもいますが)が現れ、羊男の呪いを消すために奔走します。
やっぱりクリスマスはみんなで喜ぶものなんですね。
またパーティーができる世の中になってほしいなあ。
これを読むとドーナツを非常に食べたくなります、気をつけてくださいね!
2月19日



うれしい〜
29歳の誕生日を迎えました!
本当に、七月堂で出した詩集で始まって今日が七月堂さんのリニューアルオープン日だとは……食材の買い出し用のように(仕事として)書店巡りをしてきます。
今まで支えてくれたみなさん、ありがとうございます!
久納美輝『アイスバーン』七月堂、松井ひろか『十六歳、未明の接岸』七月堂、アニー・ディラード 柳沢由実子訳『本を書く』田畑書店を巡って購入。


詩集を買ったらガーベラをいただいてしまった……!




・ヴィカス・スワラップ 子安亜弥訳『ぼくと1ルピーの神様』ランダムハウス講談社
クイズ王になってしまった青年。
昔ありましたよね。賞金をかけたクイズ番組。
しかし、この舞台のインドで、青年は学校に通ったことがありませんでした。それでも、青年が生きていくうえで知識を身に着けていき、結果最高賞金を手に入れてしまいます。
番組側スタッフと警察は慌てに慌てますが……
インドの中で起こるすさまじい事件と、人情と人の業が織り交ざって、
「運は自分で作るもの」
と教えてくれた物語でした。
帰ってきてから、中原中也賞が國松絵梨さんの『たましいの移動』(七月堂)に決まったということ。同じインカレ叢書から出した詩人としてとてもうれしいです!
國松絵梨さんの作品はほかでも読んでいましたが、とても中也賞向きだなあと思っていました。これからもお互いがんばっていきましょう!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
