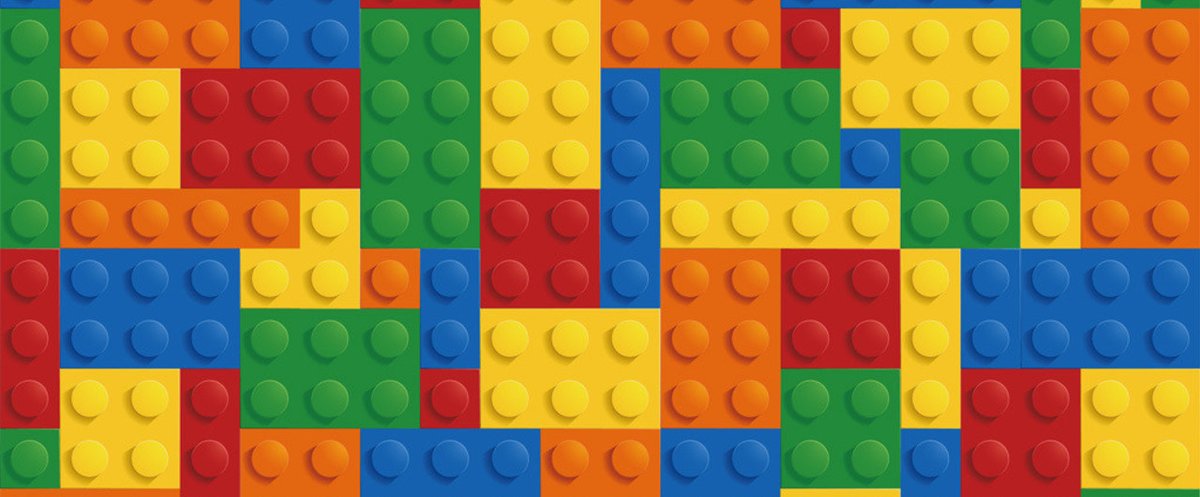
7-2.発達の最近接領域
ねぎぽんです。ワークショップのデザイナーとファシリテーターをしています。
このテキストの全体像は「目次」をご用意しましたのでご覧ください。
熟達者の「わざ」の秘密が身体に宿るスタイルにあることを見てきました。身体的なスタイルである以上、公的なマニュアルと違って、誰にでもアクセスすることはできません。それはマイケル・ポランニーの「暗黙知」の領域にあるものです。
そうであるならば、初心者はどのようにして「わざ」を学んでいくのでしょうか。それを考えるために旧ソ連の心理学者レフ・ヴィゴツキーの業績を参照します。
ヴィゴツキーは人の発達と成長を分析した心理学者ですが、彼は発達のエッセンスを言語に見ています。ヴィゴツキーによれば言語には二つの側面が存在します。
ひとつは公的でアクセスフリーな「外言」であり、もうひとつが私的でその人だけの「内言」です。人が話をしてコミュニケーションに用いる言葉が「外言」で独り言や頭のなかでかわす内的会話の言葉が「内言」です。
子どもは大人の使う外言を取りこんで試しに使ってみます。子どもの内言は「自己中心的な言葉」といわれ、大人が使う意味合いとは少し違った使われ方をするものです。「海」という言葉を覚えれば、川面プールも水たまりも「海」と言ってしまうように。そのとき大人は優しく諭します。そうして内言を外言によって修正することを学び、外言の操り方を覚えるのです。
内言と外言の往還は大人になっても続きます。新たな知識を身に着ける際、大人もはじめは画一的なマニュアルを参照しますが、次第に自分の文脈や周囲の環境に落とし込んでマニュアルを少しずつ変えて運用することを始めます。普遍的な外言はそのままでは偶有的な状況に馴染みにくく、内言としてはじめて使用可能となります。
畢竟、画一的でお堅い理論を現場に即して和らげるショーンの「わざ」は外言を内言として発露するプロセスに一致します。ヴィゴツキーの指摘した外言と内言の往還による学習の仕方を参考にすることで「わざ」の学び方も見えてくるのではないでしょうか。
以下11700字です。
7-2. 発達の最近接領域
7-2-1. 発達のプロセス
熟達した専門家の「わざ」は即座には意識の領野に浮かんでこないものであり、言葉にされることさえも拒む「暗黙知」でもある。無意識的なきわめて身体的な知である。『暗黙知の次元』においてマイケル・ポランニーは、人間の身体に根づく暗黙の知について顔の認証や盲人の杖の事例を引き合いにして説明している。
人の顔を見て誰かを認めることは誰にもできることだ。けれど、そのとき髪形、輪郭、目の形、鼻の高さ、口の形をいちいち思い出しているわけではない。ぼんやりとした総体で認めている。どうして顔が分かったのか、どのようにして見分けているのかをあらためて言葉で説明するように求められても困ってしまう。このように暗黙知はそのプロセスを明確に言語化できるものではない。
あるいは目の不自由な人が杖を頼りに歩く場合、はじめは用心深く杖で探り探り歩いていく。そのとき杖はあくまで道具として自分とは異質なものとして感じられている。しかし、次第に杖が体に馴染んでくるとあたかも自身の腕の延長であるように扱えるようになってくる。杖の先端が自身の指であるように物に触れることもできるようになる。暗黙知は異質なものを身体的に取りこんでいくことのできるものだ。違和感のあったものがいつの間にか自己に統合されたものへと変容しているのである。
暗黙知には以上のような特徴がある。無意識的に発露してくるものであり、言語による反省は難しいものの、それがあるからこそ人間の行動を統一したものにすることのできる身体的な知恵である。
ショーンの視点によればプロフェッショナルは抽象的な理論と具体的な状況を自身の身体に宿る「わざ」において結びつけて調和と統一を生みだしている。プロフェッショナルの「わざ」は明確に言語化することの難しい無意識的な知であるとともに、外的な形式知を内化かつ同化して自分のものとして自在に操る身体的な地でもある。このようなプロフェッショナルの「わざ」はポランニーの暗黙知としても理解できる。
自身の身体に根づいた「わざ」を発露しているときプロフェッショナルがいちいち自分を振り返ることはない。外部にある仕事の対象に集中かつ専心している。そのとき統合された感覚を無意識的に覚えている状態であり、「いまここ」の一回きりの状況とも調和のとれた関係を取ることができている。これは細分化と統合化がともに達成された複雑化の状態、フローの状態だ。そして「わざ」はその人の身体に根づいた唯一無二の「スタイル」の発露でもあった。だから、そこには唯一性と自己原因性の感覚も生まれてくる。
ポランニーの暗黙知はメルロ=ポンティの哲学にとても近しい。プロフェッショナルの「わざ」はポランニーの暗黙知としての側面とメルロ=ポンティのスタイルとしての側面を有している。
熟達したインプロバイザーもそれぞれに「わざ」をもっている。「わざ」を顕わにしているときこそプレイヤーがグッドネイチャーな状態でいられるときであるとぼくは考えてきた。インプロバイザーの「わざ」も身体に根づいた入れ替え不能で唯一なスタイルにほかならない。
しかし「わざ」も始めから身についていたものではない。実験や試行錯誤の末にやっと自身のものとすることのできる熟達の証である。では「わざ」を身に着けるためにインプロバイザーはひとりで試行錯誤の経験を重ねていかねばならないのだろうか。そうではない。
インプロの「わざ」、インプロの知恵は共有不能な独自性を備えるがゆえに逆説的に独力で習得することが困難なものなのだ。というのも、客観的に判定するマニュアル、公的なテストがないためにジャッジを独力で済ますこともまた不可能だからである。だから、インプロの熟練した「わざ」を後進が習得するためには熟達したインプロの先輩の間近でそれを伝授してもらうほかはないのである。
***
インプロのマニュアルがあるとしたら脚本がないこと、イエス・アンドをすること、後はゲームのルール指南、それくらいしか書くことがない。イエス・アンドにしても「まず共演者のオファーをイエスして、それから自分のアイディアをアンドしましょう」というだけのことでしかない。優れたインプロバイザーにどのようにしたら近づけるのかは書きようがないのである。とにかくインプロは独学自習が難しい。
「イエス・アンドができた」と思う瞬間なら初心者にもよくある。しかし、本人はできたと感じても熟達者の目にはまだまだイエス・アンドが足らないと見えることは少なくない。そのとき「イエスしきれてないよね」「イエス・アンドの角度を変えてみれば」「イエス・アンドの質を深めたいよね」などと熟達者がフィードバックをすることがある。そこではじめて初心者は自分のインプロに何が足らなかったのかを振り返るのだ。インプロには成功も失敗もない。明確な基準がないだけ他者からの示唆がなければ振り返るポイントも不明瞭なままに留まってしまう。
とはいっても、初心者が即座にその言葉の意味を理解して自分のインプロを変えられるわけでもない。なぜならば、熟達したインプロバイザーの言葉は「わざ」の言葉がそうであるように共有不能な独自性をもったものだからだ。そのためプレイヤーが違えばまったく違ったフィードバックをすることになる。
初心者インプロバイザーは誰の言葉を信じてみたものか悩んでしまうかもしれない。結局は次のイエス・アンドをすこし変えてみる工夫をしてみるほかはない。そうして何が変化したのか、再度先輩にフィードバックを仰いでみる。その反復だけが初心者に自分自身の独自の「わざ」を見いださせていく。
内言と外言
「わざ」は唯一無二である。身体に深く根付いたスタイルは代替不能だからだ。しかし、伝承されていくものでもある。「わざ」はこの矛盾のなかで生成する。クイストとペトラのやり取りをクイストの培ってきた「わざ」がいままさにペトラに変化を与えていく伝承のプロセスとして見ることもできるだろう。
職人仕事や芸事の「わざ」の伝達は古今東西を問わず師から弟子へと受け継がれる形でなされてきた。ぼくもまた師匠からインプロの「わざ」を伝えられたと思っている。この「わざ」の伝承を巡るプロセスについて語るために旧ソ連の心理学者レフ・ヴィゴツキーに言及したい。
ヴィゴツキーは人間の学習プロセスを分析したことで知られており、彼の独特の概念はいまなお学習理論においては注目されている。フランスの心理学者ジャン・ピアジェの発達心理学に着想を得たヴィゴツキーはピアジェの分析した幼児の「自己中心的な言葉」に独自の注目をする。
幼児が手作業をしている様子を目で追っているとなにやらブツブツとつぶやきながら手を動かしているのに気づくだろう。お絵かきをしながら「これはまる」「さんかく」「おはなはきいろ」などとつぶやいているはずだ。ピアジェによればこれが幼児の「自己中心的な言葉」である。
周囲の大人たちから円形の形が「まる」という名だと教えられたのかもしれない。花びらを緑色で塗っていたら花の色は緑ではないことを教えられたのかもしれない。そのように大人たちの使用する言葉という外面的な意味のシステムを幼児が自分の内面へと取り込んでいく過程で生じるのが自己中心的な言葉だ。
しかし、ピアジェは幼児の自己中心的な言葉に対して否定的な評価を与えていた。幼児の言葉は幼児の自己中心性を露見させるものでしかなく、いずれ大人たちの使う一般的なことばに取って代わられるにすぎないものと考えていた。これはピアジェが発達を脱中心的で脱文脈的なものとして理解していたからである。
***
幼児の言葉はそれを話す子どもを中心とした個別的な文脈の世界に閉ざされている。そのため周囲の大人たちにはいまいちその意味が呑みこめない。その文脈=世界の外へと意味は届くことがないのである。しかし、大人の使う言葉は一般的で普遍的だ。誰が使っても同じように意味が通用する言葉、脱中心的で脱文脈的な言葉でなければならない。
だから、自己中心に閉ざされた世界から他者とともに存在する世界へと開かれていくことこそ発達であるとピアジェは考えた。それゆえに幼児の言葉は不完全で乗り越えられるべき言葉としてしか評価しえなかったのだ。
それに対してヴィゴツキーは自己中心的な言葉の地位を高く評価している。たしかに、人間が発達する過程で幼児の自己中心的な言葉は消失する。だからといって、その機能までなくなってしまったわけではない。そうヴィゴツキーは考えた。
困難な状況に直面したとき自分が何をすべきか頭のなかで自問自答しない人はないだろう。さらには「どうする」「どうする」などとブツブツ口に出す人もいる。これをヴィゴツキーは大人になっても存続している「自己中心的な言葉」の名残だと考えた。それを「内言」と名づけている。
内言の特質としては幼児の言葉と同様に文脈依存的なことが挙げられる。もし成人の内言を一言一句正確にテキスト化することができたとしても主語や述語が抜けていたり、論理的に飛躍があったり、圧縮や略語や比喩ばかり並んでいたりして、そのとき彼の置かれていた状況の情報を捨象してしまえば、なにがなんだかさっぱりわからないに違いない。そもそも内言は自分のためだけに語られる言葉だからだ。
成人の使う言葉は日常的なコミュニケーションに使われる社会的な道具である。ぼくの使う言葉と相手の言葉が違えばコミュニケーションにはならない。だから、言葉は普遍的で一般的な道具でなければならない。このような言葉を内言に対して「外言」と呼ぶ。
しかし、内言は客観的なコミュニケーションのためにあるわけではない。話者が目の前の状況に直面しながら主観的な思案や確認のために頭のなかや独り言で反芻するための言葉である。外的な状況を内的な理解へと接続するための転換機が内言なのだ。だから、内言の結果を人に伝えるためには再度、内言を外言へと転換しなければならない。
***
子どもは大人たちの使う社会のなかに生まれてくる。社会にはすでに大人たちの使う言葉が外言として存在している。子どもはそれを拒めない。したがって、子どもはまず外言を受容する。大人たちが話しかけてくる言葉を徐々に自分のものにしていく。そのプロセスで生まれるのが自己中心的な言葉だった。「パパ、ママ」「わんわん」「ぶーぶ」と自分の周囲の環境、自分の文脈に、言葉を落としこんで確認しながら、理解を進めていくのである。
はじめは声に出して意味を確認するので、周囲の大人たちにも知覚できる幼児的な振る舞いとして認知されるわけだけど、次第に声に出さなくてもできるようになっていく。だからといって、消えてしまったわけではない。いわゆる「頭のなか」で声に出すという内言のプロセスへと変容したのである。日本でも江戸時代や明治時代の初期までは本や新聞を声に出して読む音読が主流だったそうだから、黙読には高度な概念的思考ができる素地が必要なのだろう。
内言は成人しても失われることはなく、むしろ人間の学習に必要不可欠なものとなる。人間が新しい知識を学習する場合、知識ははじめ外的かつ公的なものとして、すなわち一般に共有されたフォーマルモデルとして、学ぶ主体に出会われる。フォーマルモデルとしての知識は万人に妥当する標準化=規格化された知識だ。誰にとってもアクセス可能で、それゆえに匿名のものである。このような誰の知識でもあり誰の知識でもない知識が「外言」としての知識である。
しかし、人間は無色透明な外言をそのまま内面化することはできない。学ぶ主体はそれぞれに固有の文脈すなわち記憶や経験を有するために自分の文脈に応用してはじめて知識を自身へと落とし込むことができる。人は自分の視点からしか知識を理解することはできないのだ。こうして無色透明な外言に次第に精妙な綾がつけられていく。
外言は個人の文脈によって綾づけられたものとして内面へと取りこまれることになる。公的で画一的な知識や技能が個人特有の理解と使用へと偏差をつけられていくプロセスは、ショーンの指摘したプロフェッショナルの「わざ」を習得するプロセスにほかならない。プロフェッショナルの「わざ」は身体のスタイルに根ざした固有かつ唯一のもので、その「わざ」の持ち主にしか理解できないものでもあったが、それは内言の性質ときれいに符合する。
外面的で公的な意味を自分の内面へと取りこんでいくプロセスは幼児の言葉の習得に始まって成人してからも続くけれど、そこにはかならず外言と内言の往復運動が存在する。抽象的な知識としての外言は個別具体的な人の内言となってはじめて有効に利用できるものとなるのだ。
医学や法務や建築デザインといった高度に専門的な技能についても話は同じである。専門知もまたそれが適用される状況とそれを適用しようとする個別具体的な文脈があってはじめて現実的な力を発揮する。医師、弁護士、建築デザイナーはそれぞれに外言的な専門知を内言として操ることで一流へと成長していくのである。
一流のプロフェッショナルはそれぞれのスタイルで「わざ」を編みだしている。畢竟、プロフェッショナルの「わざ」とは内言そのものだ。文脈を同じくしない人には理解がしがたいという点でも内言と「わざ」は一致する。「わざ」も内言も身体的なスタイルの発露という点で同一の事象だと考えられる。
7-2-2. 発達の最近接領域
ヴィゴツキーには「発達の最近接領域」(Zone of Proximal Development)という有名な概念がある。それもまた外言と内言の関係で理解することができる。彼が最近接発達領域という言葉を使うのは主著『思考と言語』のなかでも終盤、子どもに対する科学教育の方法論について考察する第6章においてである。
ヴィゴツキーははじめに子どもの思考が具体的な文脈に密着していることを指摘する。「2+3」について思考するときはじめ子どもは指を折って数えるだろう。指という身体的な文脈を数の計算から切り離すことができないのである。
しかし、科学には抽象的で普遍的な概念的思考が必要不可欠だ。このままでは「100+215」のような計算は難しい。個別具体的な文脈から普遍的かつ抽象的な科学的概念へと子どもの知を脱文脈化するためには子どもひとりの独力では難しく、大人の手助けが必要だとヴィゴツキーは考えた。
そもそも子どもの思考は科学的な概念とは似て非なる「擬概念」によって構成されている。擬概念とははじめ犬のことを指さしていて「わんわん」と言っていた子どもが、そのうち信号機にも「わんわん」と言うようになり、車にも「わんわん」と言うようになり、最後には友だちにも「わんわん」と言うような事態に確認できる「わんわん」のことである。彼にとって「わんわん」は「音を出す」という共通点のあるものであって、だから犬も信号機も同じ「わんわん」なのだ。だが、外から見ている大人にはさっぱり理解できない。
このように子どもは世界の文節の仕方、そのカテゴライズの仕方を外言的な概念とは似て非なる擬概念でしている。だから、多くの場合、擬概念に接した大人たちは「それはわんわんではないよ」と優しく諭して言葉の正しい用法を教えていく。そうして「わんわん」は「音を出す」ものではないことを知るのである。
子どもの擬概念は周囲の大人の指摘によって正しい概念へと補正され導かれていく。子どもの文脈と分かちがたく結びついていた自己中心的な内言が成人の使う脱文脈的で脱中心的な外言へと置き換えられたのである。指を折りながら数えていた計算が頭のなかだけで暗算できるようになるプロセスをこのようなものとしてヴィゴツキーは考えている。
***
子どもの「擬概念」は大人たちが使う言葉を彼らなりに操ってみた試行錯誤の結果である。非科学的だからといってその価値を否定すべきではない。むしろ、大人の外言を子どもが内面化していく過程として評価すべきものであろう。擬概念を徐々に正しい概念へと導いていくように大人の助けが子どもの成長を促していく。そのとき子どもに変化を生じさせる能力の代(しろ)が「発達の最近接領域」なのだ。
したがって、発達の最近接領域において大人が子どもに対して行う働きがけは子どもの内言を外言へと繰り広げていくことにほかならない。ただし、その手助けはすべての子どもに画一的なやり方ですることはできない。それぞれの子どもに適した水準で行われる必要がある。擬概念を諭すときもその子にわかる言葉遣いで接しなければ伝わるものも伝わらない。子どもによって発達の幅が違うことをヴィゴツキーは発達の最近接領域の差異として語っている。
『アフォーダンスの心理学』においてリードは幼児が言葉を習得していくプロセスのなかで「指し示し」を見せるようになると述べている。一歳前後になると幼児は人や物を指で指し示すようになる。「これは何?」「これが欲しい」「これが好き」と多様な意味で使われる指さし言葉は幼児がいま興味関心をもっていることにフォーカスをあてる行為であり、周囲の大人たちの関心をそのフォーカスに向けさせる行為である。このとき幼児は周囲の世界に影響を与え意のままに動かすことのできているという自己原因性の感覚を感じている。だから、この時期の幼児は急速に世界との関わりを増やし多くのことを学んでいく。
しかし、人間の社会はすべてがすべて思い通りになる環境ではない。排泄はトイレで済ませなければならないし、キッチンは子どもが遊ぶには危ない場所で、食事は決められた時間に決められた場所でしなければならない。幼児が自由に自分の行動ができる「自由行為場」とトイレやキッチンやテーブルなど特定の行為をするように決められ促される「促進行為場」の別が存在することをリードは指摘している。そのことに幼児は次第に気づいていく。
幼児が社会性を学んでいくプロセスは自由行為場と促進行為場の往還なのだ。幼児は自由行為場において自己原因感覚そのままに思い通りに指し示しをすることができる。しかし、その自由な行為は促進行為場において制限される。周囲の大人たちによって「してよいこと」と「してはいけないこと」を明示される。そうして行為の調整を覚えていく。次第に促進行為場において制限された行動を弁えながら自己原因的に振る舞う仕方も覚えていくだろう。精神分析的に言えば「快感原則」(一次過程)が「現実原則」(二次過程)へと推移していくプロセスである。
自由行為場と促進行為場の往還は外言と内言を往還する発達の最近接領域の理論と一致するプロセスである。現在自在にできる自由行為と相応しさを求められる促進行為の間のギャップが最近接発達領域だと考えられる。そうすることで、自分がしたいと望んでいる行為を現実の世界のなかでどのように実現していったらよいのかを学ぶことができる。
促進行為場において幼児は周囲の大人からもっとよく見るべきアフォーダンスがあることを教えられる。したがって、発達の最近接領域を学習者がキャッチできるアフォーダンスの幅が広がろうとする可能性の場として考えることができる。
インプロの初学者はまず自由にインプロを楽しんでみる。周囲の熟達者は喜んでイエス・アンドをしてくれるだろう。自己原因性を思う存分発揮すればよいのである。そのうち先輩たちが「こうすればもっとよくなる」と促進すべき行為を伝えてくれるようになるから、そのときはそれを「イエス・アンド」してみればよいのである。次第に何が良質なイエス・アンドで、何が自分と他者とで違うのか、おぼろげながらに見えてくるはずだ。
インプロの熟達
インプロの初心者は「イエス・アンドをしていきましょう」「ブロッキングはしないで」「考えないで」などとインストラクターや先輩から声をかけられる。言葉の字義通りの意味は理解できたとしても、実践するとなれば話はまた別である。言われてすぐできるものでもない。結局「ためしにやってみる」ことをしてみてそれがどのような結果になるのか自分の身で確かめてみるほかはない。やってみれば、周囲の熟達者からフィードバックを得ることもできるだろう。それを手掛かりに次の行動の変化の可能性を振り返ってみるのである。
熟達者から与えられたフィードバックは初心者にとっては外言でしかない。外言だけを受け取っても自分の身体で理解できるわけではない。だから、自分の思ったように体を動かして表現してみるほかはないのだ。それは一面において外言を内言に落とし込んでみる行為であり、他面において落とし込んだ内言を周囲に見えるように外言へと広げてく行為でもある。周囲の熟達者はその表現を見て改めてフィードバックをする。そうして初心者の学びは深まっていく。インプロの学びは外言を内言に落とし込み、そして内言を外言へと表現しなおす、その反復の営みである。
共有不能の「わざ」を他者から学ぶという不可能な逆説をインプロのワークショップでは生々しく体験できる。後輩には先輩の「わざ」の秘密がわからないし、反対に先輩にも後輩の「わざ」の理解の程度がわからない。だから、相互にブラックボックスの関係にあって、伝えながら、確かめながら、少しずつ共有できる範囲を広げていく必要がある。この場こそ相互作用によって生まれてくる最近接発達領域そのものだ。
もっとも、互いに理解しあえない以上、発達の課題には自分で気づかなければならない部分も存在する。先輩のフィードバックは受け取る初心者にとっては外言でも、発する先輩にとっては自身の「わざ」から生まれてきた内言的な性質の色濃いものである。指摘が適切なのか、表現する言葉の選択が適切なものか、果たして明瞭ではないだろう。
だから、練習をひとつ終えるごとに省察を欠かすことはできない。この「省察的実践」がひとりでできなければインプロの熟達は難しい。とはいえ、熟達の速度の程度に違いはあっても、先輩との相互作用を続けていればどのプレイヤーも自然と「省察」(リフレクション)ができるようになる。これもインプロで得られるスキルである。
***
インプロの学びとヴィゴツキーの理論には相違する部分もある。ヴィゴツキーは旧ソ連スターリン政権下の研究者だ。共産主義的イデオロギーと無縁ではいられまい。そのために彼の理論は「発達」の可能性を無条件の前提としているようにも思われる。発達の初期段階にある子どもが発達の階段を一段ずつ踏むように上昇して大人へと成長していく、その枠組みが疑われる気配はない。発達のプロセスが目指すべき科学的な概念の習得は公的で普遍的なものであり万人に共有されるべき性質のものとされる。ヴィゴツキーにとって発達のゴールは明瞭で到達可能なものなのだ。
ところが、インプロの「わざ」はそもそも内言的な性質の色濃い身体的な知恵である。科学的な外言のように客観的で普遍的なものではありえない。もちろん熟達者は初心者個々人の程度にあわせて、いまいちばん必要だと推察されるポイントをコメントしようとするだろう。だからといってそのコメントが一般性な性格をもつかといえば、どうしても内言から生まれてくるという性質のため難しい。
インプロの初心者はしばしば上級者から「もっと無責任になってもいいよ」とフィードバックをもらうことがある。初心者はひとりで何でも決めなければと抱えこんでしまいがちなので、もっと周りを頼った方が自分も周りも楽になるという意味の助言である。とはいえ「無責任」という言葉は人によって感じられる意味に大きな幅のある言葉に違いない。どのように理解されるかは完全には予想できない。
だから、インプロの熟達者には自身のしたフィードバックが相手にどうイエス・アンドされるか、それさえもイエスできる了見がいる。自分のフィードバックした意図とまったく違った理解をされてもそれを受容できる度量が求められるのだ。
ここにまたインプロの学習の特色がある。ヴィゴツキー型の学習であれば教師はあくまで子どもに対して優位に居続ける。教師が「L」であれば子どもは「R」に留まりつづける。それに対してインプロの教授では、熟達者が自身の経験について初心者に語るとき、自身の内言を外言へと繰り広げるための工夫が求められる。その教授が適切なものであったかどうかはその後の初心者が見せる「イエス・アンド」の質によって左右される。その反応を見て熟達者も自身を振り返らずにはいられない。
熟達者にも初心者と同様な変容が不可避的に生じてしまうのがインプロという学びの場の特質だ。劇的な変化を初心者が見せることもあるし、ときにひどく混乱させてしまうこともある。教えることが最大の学びであるとは、その通りのことだが、初心者の反応を受け止めて熟達者もまた自身の経験を変容させていくことになる。インプロは教授においても「L」と「R」がつねに反転するのである。
インプロの学びにおける熟達者からのフィードバックと、プレイヤーがシーンでするオファーは本質的に同一のものである。初心者は熟達者のフィードバックをまずは「イエス」する。ただし、フィードバックの外言的な部分は理解できてもその真意ともいえる部分はまだ分からない。分からないからこそフィードバックが初心者の内言を触発する。
すなわち、熟達者のフィードバックは初心者の内言において差異化=微分化されていくのである。そして、あるところで初心者の新たな表現として異化=分化した姿で現れでてくる。これがフィードバックの「アンド」に相当する。そうして現れてきた表現は後輩が先輩のフィードバックをイエス・アンドしたオファーにほかならない。だから、今度は先輩の内言を触発するのである。
インプロの教授はシーン中のオファーのように差異による生成変化を連鎖的に誘爆させていく。しかし、それはインプロだけに特別なものではないのかもしれない。プロフェッショナルの「わざ」が息づく世界における「わざ」の伝達には普遍的に見られるものなのだろう。クイストとペトラのやり取りは師の目には見える世界の法則を、なんとか弟子の目にも垣間見ようという相互作用だったはずだ。省察的実践が「わざ」をつねに更新していこうとする実践なのもそこにかならず他者が介在する実践だからであって、教授という場面においてはそれがなおさら強調されるのである。
結局、熟達者と初心者の相互行為によって生成するインプロの発達は段階的でも直線的でもありえない。ヴィゴツキーの考える科学的教育は万人に共通のゴールに到達することを目的とできたけれど、インプロの熟達には明確なゴールがそもそも存在しない。
つまるところ、インプロの教育のゴールは、それぞれのプレイヤーが自身のグッドネイチャーを輝かせることのほかにはない。ただし、グッドネイチャーは一律の尺度で測れるものでもないので、何をもって熟達したかの基準はきわめて曖昧である。強いて言うならばプレイヤーがそれぞれに自身のスタイルを肯定して、そこから独自の「わざ」を編み出したと感じることができるかどうかではないだろうか。
***
「わざ」は自身の試行錯誤からしか生成しないものだ。だから、熟達者の教えをただ待っているだけではいつまでたっても熟達できない。初心者が自身のインプロを振り返って「もっと熟達するには何が必要なのか」「人に無くて自分にあるものは何か」と強く意識する必要がある。そこで気づいたポイントが次に挑戦すべき発達の代となるのである。
つまるところ、インプロの学びに、学習者自身が自身の発達の最近接領域を設定して、そこを意識的に刺激していく必要がある。そこから内発的かつ自己目的的に自身の発達の最近接領域を広げていく努力を楽しめるようになれば熟達は加速度的に進んでいく。だから、インプロバイザーは、熟達の過程でいわば「学ぶことを学ぶ」チャンスを得ていることになる。
インプロの学びにゴールはない。しかし、ないとはいえ、方向も分からないまま学びつづけていくことも人間にはできない。目指したいと思える目標は必要だ。では、その発達の目標をどこに定めるのか。といえば、多くのインプロバイザーにとって目標は憧れとする先輩や熟達者の姿である。インプロには誰もが目指すゴールが存在しないからこそ「ああいう人になりたい」「あんなことができるなんてすごい」という、個々のプレイヤーの純粋に個人的な思い以外に次の一歩を踏み出させるものはない。こうしてインプロの学びは模倣と欲望いうテーマに繋がっていく。
【了】
著作者:webdesignhot
画像は著作権フリーのものを使用しています
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
