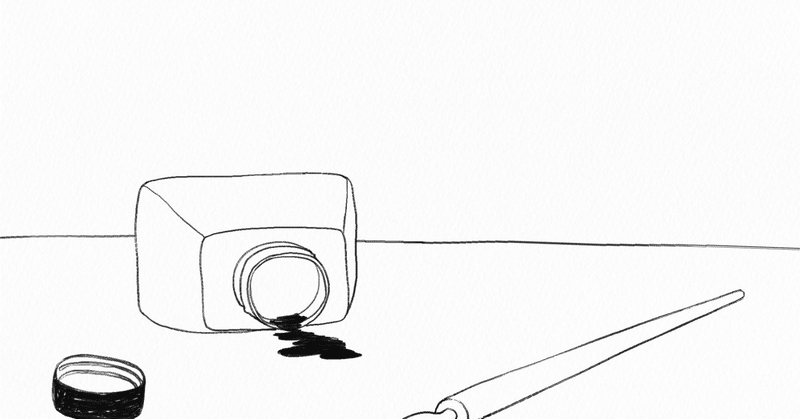
2024年上半期の活動をnoteと一緒に振り返る
2024年も半年が経とうとしている。世間ではここまでを上半期というらしい。そこで僕の上半期活動(発信)を毎月noteを一本ずつ取り上げて振り返っていく。
1.書評連載はじまる
1月:【連載第1回】『宇都宮徹壱WM』で書評の連載をはじめます【お知らせ】
ウェブマガジン『宇都宮徹壱WM』での書評連載がついに始まった。この連載のお誘いが「書評家」と名乗るきっかけになった一つでもある。声をかけてくれた宇都宮徹壱さんには本当に感謝しかない。外部メディアに連載を持つことで「書評家をしている」ことの説得力が増す。これは現実だ。僕も書評家として自己紹介するときに「ただ自称してるだけじゃなくて、連載も持ってまして」と言いやすいのは事実である。今後も外部への寄稿は目指していきたい。書評書けます。他の記事も書けます。よろしくお願いします。
◎マガジン『つじーの書評集|ふまじめな読書室』
2.トルコフィーバー起こる
2月:トルコに縁もゆかりもない僕がどうしてトルコのサッカークラブの「最初の日本人サポーター」と呼ばれることになったか
トルコのアダナ・デミルスポルの「最初の日本人サポーター」と現地のトルコ人に認知され、トルコ人がXのフォロワーの約5%(100人程度)を占める異常事態が起きた月だ。翌月にその顛末をまとめた2万字超のnoteは、僕の記事で最も読まれている。このときのフィーバーほどではないがトルコ人との縁は今も続いており、その交流で気がついたことを不定期で書くつもりだ。また、2万字以上書き切ったことで文章を書く体力への自信がついた。書くことを以前よりも面倒に思わなくなった。ありがとうトルコ。美味しいぞトルコ料理。
◎マガジン『部屋から出ないで国際交流』
3.Xを利用して文章を書く
3月:2024シーズン初めのコンサドーレを見て感じた3つのポイント
試しにやってみた書き方が思いのほか上手くいって定着した。僕は応援している北海道コンサドーレ札幌に関して、特に試合がある日はXにまとまった投稿をしがちだ。そのXの投稿をそのままnoteにはりつけ、多少編集をすれば記事になるのでは。そう思い始めてみたのだが、まず記事作成が楽で時間がかからない。自分の思考をまとまって残せるし、何よりウケがいい。今や毎月コンサドーレの振り返り記事をXの投稿を利用して作るのが定番になっている。
◎マガジン『コンサドーレを考える部屋』
4.東郷平八郎で自分の原点を思い出す
4月:「東郷平八郎がイギリスのニューカッスルでサッカー観戦を楽しんだ」説を検証してみた
自分の中で一番わくわくする記事を書くことができた。Wikipediaの東郷平八郎の記事で偶然見かけた記述から、彼が本当にサッカーと縁があるのかあれこれ調査したのだ。結論にたどりついたときは本当に興奮した。自分しか関心のない話だと思っていたので、このわくわくをnoteに乗せて多くの人に伝えることができたのも本当に良かった。この件を機に歴史好きの自分とサッカー好きの自分をもっと近づけられないかと改めて考えだした。己の好きなジャンル同士を結び付ける楽しさ、それが僕の原点だからだ。今後も学校の習う歴史の出来事や人物とサッカーとの関わりを紹介していきたい。
◎マガジン『歴史の中のサッカー』
5.「いいね読み」で新しい景色へ
5月:いいねしてくれた人たちのnoteを読み続けて分かったこと【いいね読み振り返り】
この月は「自分の投稿にいいねを押してくれた人のnoteなど文章を読んで感想を書く」という企画にチャレンジしたことが本当に大きかった。これきっかけに普段のタイムラインでは絶対に遭遇しなかったアカウントが自分の目の前に現れるようになり、交流する機会にも恵まれた。書くのでなく読む。それなのに「書きたい」という思いに一段と火がつく。僕が本店と支店(サッカー)にXのアカウントを分ける決断をしたきっかけの一つでもある。いいね読みは今後も不定期でやっていきたい。
◎マガジン『何にもくくれない雑文集』
6.ぼくは歴史が書きたい
6月:クラブ誕生前夜―なぜ古きコンササポは北電のSNSに感慨深くなったのか【ぼくのコンサ史・1章】
勝手にnote連載企画『ぼくのコンサ史』が本格始動した。北海道コンサドーレ札幌の歴史をあくまでも僕なりの史観で書く。誰に頼まれたわけでもないが毎月必ず連載することにした。僕は小説家にも歴史学者にもずっと憧れていたのかもしれない。でもなれないし今からなるつもりもない。でも在野の立場で歴史を書いていきたい。そういう個人的な思いと、クラブの歴史を後世に残さねばという危機感が重なって今回書くに至った。完結はまだ遠く先だがコツコツ進めていきたい。
◎マガジン『ぼくのコンサ史』
7.思わぬ新機軸が見えた上半期
まだまだ紹介していないトピックは多い。ポッドキャストを2本始めたのも、毎週noteを書くことが継続できてることも、サポーターの話を書いたら意外と共感されたのも、エッセイにあこがれる自分に気がついたのも、全部この上半期だ。
そもそも僕は2024年を「毎週書評を書いて『自分は書き続けられる』という自信をつけよう。そして来年から本格的に打って出よう」ぐらいに捉えていた。それが予想外の方向に転がり、書評以外の「思わぬ新機軸」をいくつも手に入れることになる。おかげで毎週書評は毎週投稿に変わっていった。
正直、書評家と名乗っているわりには書評の活動が今は一番地味だ。自分は本当に書評家なのかと思うことも少なくはない。でも他の肩書きは思いつかないし、しっくりもこない。書評家は現状一番しっくりくるし、活動を続けられそうな冠だ。僕にとって書評は基礎練習である。本を読み、自分で考えて意見を持つ。そのプロセスを繰り返すことで鍛えた思考力を他の文章で発揮する。そういう感覚でいる。だから書評は僕の思考の原点だ。これからも続けていく。
下半期の活動はどんなことになるだろうか。願わくば新たに連絡や依頼がくるような身分になれるよう、今後も試行錯誤していきたい。上半期はあっりがとうございました。下半期もよろしくお願いします。
※この記事は、矢野けいかさんのnoteに"インスパイア"されたものだ。読み比べると似ても似つかないことに気がつくだろう。あくまでも"インスパイア"。
本の購入費に使わせていただきます。読書で得た知識や気づきをまたnoteに還元していきます!サポートよろしくお願いいたします。
