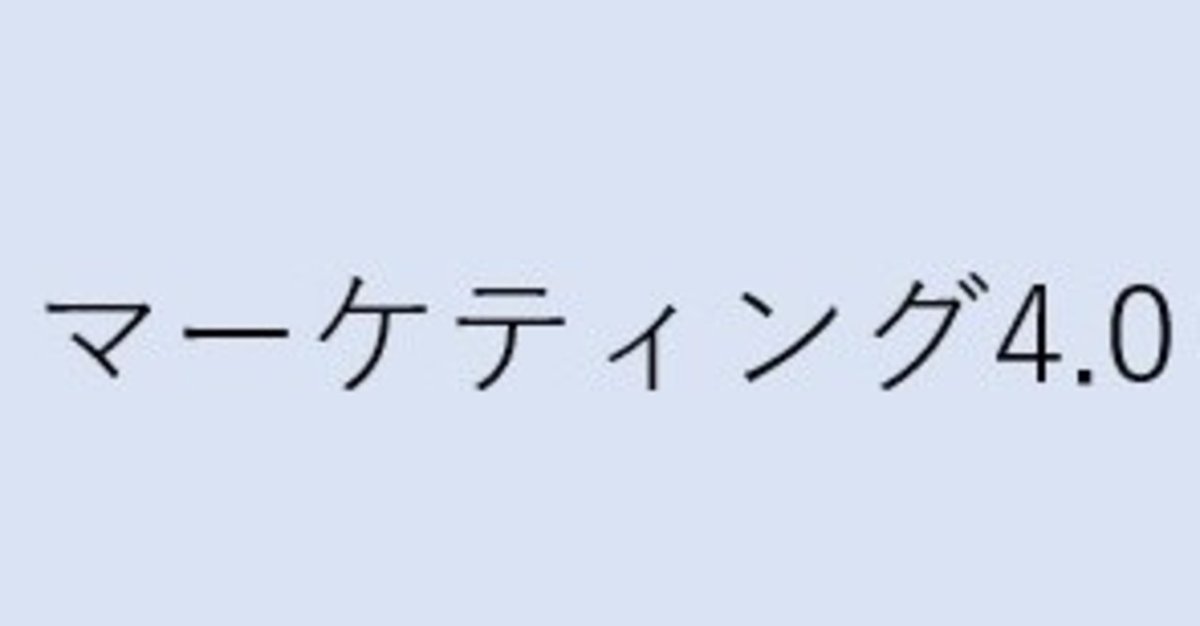
マーケティング4.0とマーケティングの未来
近代マーケティングの父でおなじみのフィリップコトラー。数々のマーケティング理論を唱えてきたが今回はこちらを紹介します。
まず、マーケティング理論について。
マーケティング1.0→「生産中心のマーケティング」
マーケティングの基本となる4P

キホンとなる考え方。マーケティングを学ぶときに1番初めに学ぶフレームワークの1つですね。
マーケティング1.0の考え方は「生産中心のマーケティング」です。需要が供給よりも多かった1900年代は、「安くすれば売れる」という概念が浸透していました。
マーケティング1.0時代において、企業の活動で利益を最大化するためには、製品の価格を下げることで購入する顧客を増やすことでした。つまり、価格弾力性のしくみで需要を増やすことがマーケティング1.0の中心的な考え方です。製品と価格で需要をコントロールできたマーケティング1.0の当時は、企業が顧客に対して優位に立てる環境であったといえます。
マーケティング2.0→「顧客中心のマーケティング」
ここで提唱されたのがSTPモデル

マーケティング2.0では、マーケティングそのものが、買い手志向にシフトしました。企業が製品を安く売ることではなく、買い手にとって何が必要であるか、つまり「ニーズ」を知ることが重要になりました。ここら辺から顧客主導のマーケティングが生まれてきたと思いますね。
マーケティング2.0の概念である「顧客の中心マーケティング」は、買い手を特性ごとにまとめてセグメンテーションし、攻略すべき市場を特定して、自社に見合った製品を提供する流れが必要になりました。これが、STPモデルと呼ばれるマーケティングのフレームワークとして知られるようになりました。
マーケティング3.0→「人間中心のマーケティング」
「3i」というフレームワーク

マーケティング3.0では「ポジショニング」「差別化」「ブランド」という3つのフレームワークの下で企業を評価するようになりました。
この時代からインターネットの普及で、今まで得ることができなかった情報を獲得できるようになりました。企業はインターネットを使ったマーケティング活動を積極的に手がけるようになりました。(1990~)
一方で、企業の社会的責任(CSR)にも注目が集まり始めました。企業は、自社の利益を追求するだけでなく、倫理的観点から事業活動を通じて、社会に貢献する責任を果たすべきであるという考えが広まりました。
企業は経済だけでなく、社会にとっても優秀な団体であること、これがマーケティング3.0の概念です。
マーケティング4.0→「自己実現のマーケティング」
自己実現はマズローの5段階欲求説の最後の段階である自己実現欲求に基づいてます。

マーケティング4.0の概念は「消費者を満たすこと」。
企業は環境への配慮のような社会的要因だけでなく、自己実現のような精神的価値を満たす製品が求められるようになることを意識するようになります。
最近では、自分で買った商品をソーシャルメディアやブログを通じて情報発信できるようになりました。これをUGCと言い、企業は自社で製品をPRするだけでなく、消費者同士が製品を推奨し合うような製品を作っていく必要があります。
そのため、企業のマーケティング活動は製品購入までのプロセスだけでなく、買い手の購入後のプロセスまで考える必要が出てきました。
マーケティング4.0の究極の目標は、ただ製品を認知してもらうだけでなく、製品のファンになってもらい、顧客自ら製品の推奨をしてもらうことが重要です。
さて、ここからはコトラーのマーケティング4.0を引用しながら自分の思考を交えて展開します。
まず、本書で僕が付箋を入れた箇所はたくさんありますが、その中でも3箇所を引用して紹介。(これらは一連の流れにはなっておりません。)
1,マーケターの課題
マーケターが前進するための課題は二つある。第一に、マーケターは顧客の関心を勝ち取る必要がある。(中略)第二に、マーケターは結果をあまり制御できなくても顧客コミュニティの中でブランドに関するカンバセーション(会話)を生み出さなければならない。
前者はマーケティング4.0の5Aの認知(Aware)以前の課題ですね。関心がない→認知されないのでまずはここをどう施策するか。後者は、UGCに近いかもしれません。ブランドを支持してくれる人をどのように作るか。決して自分でなくても他者が作ってくれれば良いと思います。
2,伝統的マーケティングとデジタルマーケティングの統合

コトラーも伝統的マーケティングとデジタルマーケティングは関わるべきではないと言っていますが、ここは僕も賛成です。マーケティングは1.0から4.0へと時代を超えて進化してきましたが、過去の考え方が消えるということはありません。過去の考え方から進化し現代のマーケティング理論が確立されたのでこれらは分けて考えるべきだと思います。
3,段階的なコンテンツマーケティング

コンテンツ・マーケティングに踏み出す前に、まずは1の目標設定です。コンテンツの評価の物差しになるような具体的な数値目標の設定が必要だと思います。特にKPIは数値で、KGIはさらに具現化された言葉で表されるべき。
次にオーディエンスマッピング。これはいわゆるペルソナ設計のことですね。どんな顧客を想定しているかを具体的にしていく作業です。
3番目にコンテンツの中身やどのように価値提供をするかという構想をプランニングします。
そのあとは、いよいよコンテンツの制作です。2番で設定したターゲットに3番で設定したコンテンツを提供していく作業になります。ここで重要なのはとにかく実直に継続していくことだと思います。
さて、いよいよ作ったコンテンツを配信するタイミングです。チャネルとしては
・オウンドメディア(自社チャネル)
・アーンドメディア(獲得チャネル)
・ペイドメディア(有料チャネル)
アーンドメディアは単独では効果を発揮しないと思います。もしコンテンツ単体で配信するならオウンドメディアやペイドメディアが良いと思います。
ただ、オウンドメディアはコンテンツが資産として積みあがりますが、ペイドメディアは一時だけです。
次はコンテンツの拡散です。ここはアーンドメディアをいかにうまく使うかです。TwitterやInstagramなどで今では多くのインフルエンサーが存在しますが、彼らを使わない手はありません。なぜなら配信するコンテンツで自社で獲得したいファンをすでに持っているからです。コンテンツの拡散には適切なチャネルと効果的な手法を使うことが重要です。
そして評価に移ります。PDCAのCの部分ですが、苦手な人は多いと思います。ここでは、確かな指標である数値で判断すべきです。効果測定で得られた数字を活かして、データドリブンなマーケティングをすべきです。
最後に、改善。1~7の施策をどのように改善に移すかです。伝統的なマーケティング(4P,STP)は測定しやすいことが利点にあり、ABテストしながら確度の高い施策に近づけることを容易に試せます。ずっと成功していてもその成功がいつまで続くか分からない。評価と改善を繰り返しながら、手法を変更したり思考していくことが重要だと思います。
まとめ
全体を通して、コトラーの言葉は分かりやすく理解がしやすいので、マーケティング初心者でも簡単に理解できると思います。マーケティング4.0から勉強しても、マーケティング1.0などの考え方は後から学んでも問題なく理解できます。伝統的なマーケティングからデジタルマーケティングに移行するのではなく、融合するという考え方が僕の中で腑に落ちたところ。
おそらく、今後もマーケティング理論がアップデートされると思います。現在の究極のマーケティング理論は4.0ですが5.0、6.0のように時代によって異なるニーズや社会の変化に対応するために変わるだろうし変わっていくべきだと思います。
Twitterでも日常生活での体験から感じたマインドを書いてます。ぜひこちらもフォローをお願いします!
前回のnote
この記事が参加している募集
いただいたサポートは、今後のインプットのために書籍やnoteの購入代金にさせていただきます。
