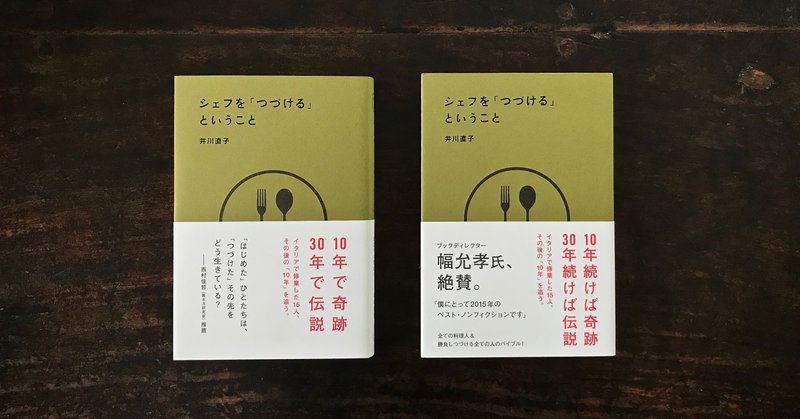
『シェフを「つづける」ということ』のこと
「まだ何者でもなかった」コックたちの10年後
前回お伝えした最初の本『イタリアに行ってコックになる』では、まだ何者でもなかった料理人とサービスマンたち24人のことを書きました。
あの「うじゃうじゃ」いた若者たちのうち、一体何人がシェフになれたのか。そのうち何人が店を持ち、さらに何人がつづけられるのか。
2002年の取材当時はまったく想像もできませんでした。
その、彼らの10年後を辿ったのが『シェフを「つづける」ということ』。2015年にミシマ社より出版しています。
個人的には、料理をやめてボクサーになる人がいたっていいじゃない?と思いながら足跡を追うと、ほぼ全員がなんらかの形で「食」と関わっていた。そのなかで「シェフ」になり、「つづけている」15人の、10年の軌跡を書いたノンフィクションです。
なんて堂々と言えるようになったのは出版した後からのことで、初めから「10年後を書こう」などとは1ミリも思っていなかったんです。
『イタリアに行ってコックになる』の原稿を持ち込んだとき、出版社のほとんどが「有名シェフの話でなければ売れない」と言いました。けれど私は「じゃないんだよなぁ」なんて思っていた。成功した人の回顧録より、道の途中でもやもやしている人のリアルな言葉を訊きたいんだ、と。
しかし結果として、出版してくれた会社に重版という恩返しはできませんでした。やっぱり有名じゃなければ、とはいまだに思っていませんが(笑)、ただ、初版しか売れなかった本の続編的なものを出してくれる出版社もないだろう、とは想像できました。
大きな宿題
なのにどうしてか、またしても、すべてが未定のままつい書いてしまった。
いちばんの理由は、一人の言葉がずっと心に引っかかっていたからです。
「あの時イタリアにいた人たち、どうしてるんですかね。お店持った人もきっと多いよね。10年後、書かないの? 僕、車椅子でピースサインするよ」
(第6章「車いすシェフという自由」より)
彼は現在、車いすシェフとして活動している伊藤健さん。イタリア、スペインで修業して帰国後、スペインバルのシェフとしてがんばっていたある日、突然倒れて2カ月意識不明に。目が覚めたら半身が麻痺していました。
事故から1年を迎えようという頃。お見舞いに言った私に、生死に関わる体験を終始ひょうひょうと語っていた伊藤さんが、最後に真顔で伝えた言葉です。
私は、何か大きな宿題をもらったような気がしていました。
10年を見てきた責任
もう一つは、私自身が10年以上、取材したコックたちを見つめてきたという事実です。
仕事を抜きにして、単に「気になる」というだけの理由なので、去る者追わず、来るもの拒まずのスタンスですが、成長する彼らと伴走することができました。
だとしたら、彼らの10年を書けるのは、技量うんぬんでなく「知っている」という意味において自分しかいないということです。
私が書かなければ知られることがない。これもまた、知ってしまった責任のようなものがあると、勝手に感じてしまった。
で、この「書いちゃった」原稿を世に送り出してくれたのがミシマ社さん。
「有名無名でなく、料理の世界だけでもなく、あらゆる仕事を「つづける」人に読んで欲しい」
そう言ってくださって、タイトルは『シェフを「つづける」ということ』になりました。
2015年2月27日発行、おかげさまで3刷。

上のコラージュと前回のそれと、位置は同じ。それぞれの10年後です。
ちなみに「思い描いていた未来」の通りになっていた人は、「ほぼ」を含めて24人中たった2人。みんな10年の間には何かしら想定外のできごとがあり、方向修正をしながら、それでも料理や食の道を歩いてきたということです。
本書に登場するシェフたち ※店名、所在地は取材時のものです
福本伸也『Cá Sento Shinya Fukumoto』(兵庫県・神戸市)
泊 義人『Kitchen Igosso』(中華人民共和国・北京)
堀江純一郎『i-lunga』(奈良県・奈良市)
高田昌弘『Ristorante Takada』(シンガポール)
佐藤雄也『Colz』(北海道・函館市)
伊藤 健 車いすシェフ(愛知県・丹羽郡)
下江潤一『el Bau Decoration』(大阪府・豊中市)
宮根正人『Ostu』(東京都・渋谷区)
中川英樹『Villa Tiboldi』(イタリア・ピエモンテ州カナーレ)
白井正幸『GITA』(愛知県・豊川市)
永田匡人『Ristorante dei Cacciatori』(京都府・京都市)
武本成悦『il cuore』(大阪府・八尾市)
小曽根幸夫『リストランテ鎌倉felice』(神奈川県・鎌倉市)
青木善行『Ristorante Ravieu』(沖縄県・那覇市)
磯尾直寿『ISOO』(東京都・渋谷区)
第1章「カ・セント シンヤ・フクモト」福本伸也さん 試し読み(抜粋)
「おかん」からの国際電話
二〇〇六年には父のセントが引退、同時に店を改装した。二つ星を獲りにいくのだろう、これから『カ・セント』をつくり直していくというラウールは、福本に「共同経営者にならないか」と声をかけた。一緒に店を育て、上を狙っていくパートナーとして。答えは「もちろん」だ。
この時、福本の目には新生『カ・セント』での未来しか見えていなかった。日本でなくスペインで、料理人としてどこまで行けるか。大海に漕(こ)ぎ出すような期待感しかなかった。
「おかん」から国際電話がきたのは、そんな気持ちが膨らんでいた矢先のことだ。様子がちょっと変だった。
「会話しても、何言うてるかわからへんのです」
どうも口が回らないらしい。夏休みに帰国して大きな病院へ連れて行くと、おそらくはストレスだろうという診断が出た。おかんも彼も深刻な病気じゃなさそうだということにほっとして、福本はスペインへ戻った。
けれどその一カ月後、再び病院から国際電話がくる。
ALS(筋萎縮性側索硬化症)という難病だった。筋肉を動かす神経が障がいを受けるため、手足、喉、舌といった全身の筋肉が痩せていく病気である。話しづらい、食べ物が飲み込みにくいという症状から始まり、次第に呼吸や歩行が困難になり、やがて水を飲むことさえできなくなる。そしてその進行を、止めることができない。
「三カ月後にはこうなる、一年後にはこうなると。その説明を電話で訊きながら、もう日本へ戻ろうと決めていました」
母子家庭で育った彼には、父がいない。ただひとりの兄は知的障がいを持っている。兄の面倒を見て、一家を支えてきたのはおかんだ。今、おかんはどんどん変わっていく自分の姿に希望を失って、「死にたい」とまで漏らしている。
「もう僕しかおれへん。お世話になったスペインの店もこれからという時だったけど、日本に帰らない道を選んでもよかったんだろうけど、でも人間として大事なのはどっちや? って」
そもそも福本が料理人になったのは、おかんのためだ。苦労をかけたおかん、「がんばんねんよ」と海外へ送り出してくれたおかんを、料理人になって喜ばせたい。二〇〇二年の取材当時から、彼はそれを繰り返し語っていた。だから福本にしてみれば、「あたりまえのことを、あたりまえに選んだだけ」。しかしその瞬間、ずっと続いていくはずだったスペインでの日々は、コンセントを抜いたように突然切れた。
サポートありがとうございます!取材、執筆のために使わせていただきます。

