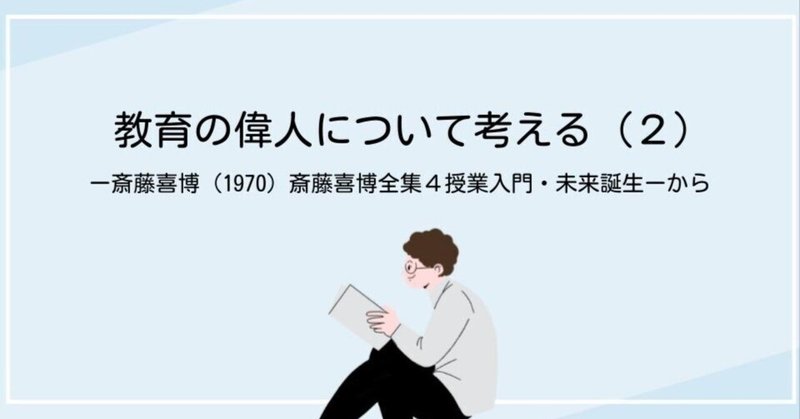
教育の偉人について考える(2)ー斎藤喜博(1970)斎藤喜博全集4授業入門・未来誕生ーから
この前の続きの記事になります。全集となると前編・中編・後編くらいの規模になってきます。
しばらく,同じ本になってしまいますが,お付き合いいただけますと幸いです。
斎藤喜博全集は全部で18冊です。これだけでも,何個も記事が書けそうです。(必死)
なぜ,1からじゃないのかと言われそうですが,興味もあるため許していただければと思います。
早速,内容に関して触れていきたいと思います。
授業のうまい人はそうではない。説明もうまいし、教えこむこともうまいし、子どものことばを早くとらえ、そのなかのどれを取り上げ、どう使えば学級全体の学習が高いものになるかということを知っている。子どもたちの学習が停滞したとき、どういう投げ方をすればそれを破り、また生き生きと子どもの学習が発展するかということを知っている。
「知っている」という表現が自分には刺さりました。
まるで教師が授業全体,学級全体を把握しているようにも感じます。
斎藤喜博先生の時代とは違いますが,クラウドでのモニタリングや机間指導中のモニタリングの様子を見ているとその様子を感じ取っている気がします。児童の個性を理解した上での声かけ,また学級全体の特性を理解した上での声かけがあると,学習全体が盛り上がっていく印象です。
この話は,一斉指導の教師のスキルということも,個別指導の教師のスキルということも含まれていると私は考えています。
教師の感覚のよさということも、よい授業をするための大切な条件になっている。学級全体の子どもの学習が行きづまっているかどうかを見ることもそうである。いまが集中しきったときであり、考えきった時であるから、いま「つっこみ」をやることが必要であると見ぬくこともそうである。(中略)
そういう感覚のよさが教師にあったとき、子どもたちは、どんな子どもでも完全に生かされ、自分に満足して生き生きと学習していくということになる。
子どもたちが主体的に学んでいるとするのであれば,その活動を裏で支えているのは教師であると捉えています。
この感覚は授業をした際に得ることができるのでしょうか,それとも授業を参観している時にも得ることができるのでしょうか,きっと両方からも感じることができるんではないかと思っています。
どんな子どもでも生かされるということは,学級全体が共同体となって学んでいる姿です。個別化・個性化教育でも同じように進んでいくと考えましたが,斎藤喜博先生が行っている授業のスタイルはそれに近いものだと思っています。
教師の感覚の良さだと勘に近いものになってしまうので,研究で数値として表されたりしていることもあると思います。
自分が知っている中で斎藤喜博先生の授業について,井上光洋先生が研究で伝えているところもあるのでいつかはピックアップして書いてみたいと自分に期待を込めながら,今回の記事は終わりにしようと思います。
よろしければサポートお願いします! いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!
