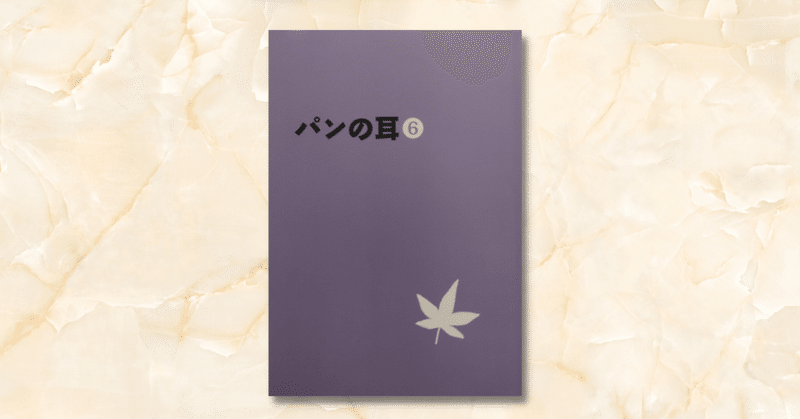
【一首評】短歌同人誌「パンの耳」6号(前半)
「パンの耳」は松村正直さんを中心とするフレンテ歌会の皆さんが
年に1回発行している同人誌。
発行後には「パンの耳を読む会」という場を設け、
連作を作った後、それをしっかり読み直したり批評し合ったりという場も大切にされている。
今回は「パンの耳」6号から各同人の皆さんの連作一首評の前半部分を。
話すほど遠ざかる午後テーブルにアップルティーは明るく澄んで
弓立悦「三日月の匂い」
下句の伸びやかな明るさに惹かれる一首。
アップルティーという言葉の響きが跳ねるようで、甘酸っぱい味もイメージされる。
でも、上句は「話すほど遠ざかる午後」。話せば話すほど上手く伝わらずもどかしい感じだろうか。
それとも過去の思い出話をしていて、話すほど過ぎ去ってしまったという思いが強くなるのだろうか。
もやもやした上句と、透明感のある下句の取り合わせが効いている。
考えて選んだはずの言葉だった 屈曲の月が窓から覗く
鍬農清枝「パワースポット探して」
こちらも口に出した言葉に悩んでいるような一首だ。
考えて考えて選んだはずの言葉なのに、口に出すと、ああ、うまく気持ちを伝えられなかったと思う。
私にもとてもよく思い当たる感情だ。
後になって、そのことに思いを巡らせている主体を覗くように、窓に月が差しかかる。
その月の形容が「屈曲」というのが美しい。折れ曲がっているのだ。
緩やかにカーブを描くはずの月が、折れ曲がって見えるような気持ちなのだろう。
残圧は10MPa 面体の中は自分の呼気がうるさい
雨虎俊寛「メーデーコール」
未知の世界を知ることができるので、私は職業詠を読むのが好きである。
この主体は消防士であり、日々、人命と直接関わるハードな仕事をしている。
「面体」は、調べると顔面を覆うマスクで、背中のボンベから空気を吸えるようになっているもののようだ。
それを被って現場に入っているので、自分の息をする音が耳につくのだろう。
残圧が少なくなる、ということは、急がないと空気がなくなるということだと思われるので
ここを読むだけでこちらも息苦しいような気持ちになる。
実際に経験した人にしか描けない、壮絶な世界だと思う。
タイトルの「メーデーコール」は緊急信号。
火災現場での消防士の活動を描いた緊迫感のある一連だ。
田を渡る風は涼やか 祖母の背に天花粉はたき粉にむせけり
長谷部和子「銀色のトランク」
田を渡る風を感じて昔のことを思い出している歌ととった。
昔、私の家にも「天花粉」があり、母が「てんかふ」と言っていた。
お風呂あがりなどに、汗をかかないよう、さらさらの粉をはたかれたような記憶がある。
主体は小さい頃、天花粉を祖母の背中にはたいて、粉にむせた。
その記憶がふわりと蘇ってきたのだろう。
やわらかな球体として眠らせたフクロウ冬の陽のなかへ置く
紀水章生「風のリンカク」
この一連には動物がたくさん出てくる、その冒頭の歌である。
不思議な歌だ。このフクロウは本物か、人形か何かか。
「やわらかな球体」と表されているので、ふわふわした毛並みが思われ、私は本物のフクロウととった。
「眠らせた」フクロウを冬の陽のなかへ「置く」主体。
眠らせることも置くことも、本当は主体にできることではないのかもしれない。
でもこうして歌になると、紛れもなく眠らせられ置かれたフクロウがいて、弱い冬の陽射しを浴びているのだった。
ゆずるのもゆるすのも難しい夜オリーブの葉は銀色に照る
添田尚子「銀色のオリーブ」
見たくない、ぐぐっと痛いところを詠っていると思う。
「いい人」は、何かを人に譲ることも、誰かを許すことも、できるはずだ。
でも自分は「いい人」だろうか。本当はどちらもしたくないのではないだろうか。
そういうことを自問自答しているように思って読んだ。
具体的なことは書かれていないけれど、私自身はどうだろう、と深く考えさせられる一首だ。
「ゆずる」と「ゆるす」をひらがなにすることで、字面が似ていることに気づかされる。
2句と3句の句またがりにも屈折した心を感じる。
下句のオリーブの描写も、夜に浮かび上がるようで美しい。
もう無理とシーツの波に溺れてく笑顔はとうに期限切れして
甲斐直子「青い魚」
闘病生活をされている状況を詠んだ一連。
「シーツの波に溺れてく」の描写がとても辛く、この言葉だけで、苦しい状況が胸に迫ってくる。
「溺れてく」と縮めた言葉は、音数を合わせたというより、切羽詰まった様子が出ているようで、はっとした。
笑顔になりたくても、もうなれない、という下句もまた辛い。
乗ることを泣いて拒んだ公園の忘れられない木馬の目付き
佐々木佳容子「いもうとの息」
よく見ると、公園の遊具のあれこれは、かわいくない。
木馬の顔も、大人が見ても怖かったりする。
木馬の目が怖くて、乗りたくない!と拒んだ子供時代を、主体は思い出している。
一連に「いもうと」が出てくるので、ここで泣いているのももしかしたら「いもうと」かもしれない。
いずれにせよ、他の記憶は曖昧でも、あの木馬の目付きだけは忘れられないのだ。
※後半に続く
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
