
リモートワークで見えてきたデザイナーの本来の価値、そしてnailmarksにとっての「デザイン」
nailmarksは、共にデザイナーとして活動する飯島と加嶋がリモートで1on1をしはじめたことがきっかけで2020年に生まれました。コロナ禍により、世界中でコミュニケーションのあり方が変化するなか、デザインのプロセスにも大きな影響を与えます。コロナ禍がはじまってから、そしてnailmarksが生まれて3年が経過した今、あらためてリモートワーク以降のデザイナーの働き方について、そしてデザインの本質について、2人が語り合いました。
取材・執筆 長瀬光弘(ライター)
リモートワークをしながら変化していく2人の関係

ー2020年にnailmarksが生まれ、3年が経過しました。発端は、加嶋さんが発案したオンラインでの1on1だと聞いています。
加嶋:そうですね。noteにも書きましたが、コロナ禍によってリモートワークに切り替わっていったのが、2020年の春頃です。フリーでの活動に慣れ、これからもっと多くの人と出会えると思っていた矢先に、人と対面で会う機会がほとんどなくなってしまいました。最初こそは物珍しさや移動しなくていい利便性もあって、オンラインでの仕事は平気でしたが、少しずつ不安を抱くようになっていたんです。
ーどのような不安でしょうか?
加嶋:一緒に仕事をする人と関係性をしっかり築く機会がなかったり、新しい人と出会う機会が減ることで仕事も減るのではないか…とかいろいろな不安が混ざっていたように思います。さらに、オンラインだとコミュニケーションが仕事だけの話というか、何か目的ありきの会話ばかりになるというのも感じていて…。
雑談というか、無目的に人と話す時間がほしいなと思って、飯島さんに「1on1をしませんか?」と声を掛けたんです。すぐに快諾してくれました。
ー1on1は組織のマネジメント手法としてここ数年で広がったものですね。一般的な会社に当てはめると、上長とメンバーが1対1で対話をしながら、成長を支援したり、相談に乗ったりする取り組みのことを言います。飯島さんは1on1の話を聞いてどう思いましたか?
飯島:普通は会社というか、組織で行うものですが、フリーランスがお互いに行うのは面白いな、と思ったんです。私自身、メンターと言いますか、人の話を聞いて、サポートをすることに昔から興味がありましたし、加嶋さんとは以前から仕事をするなかで、よくコミュニケーションも取っていました。確かに、このリモートワークの中で、意識的に1on1のような時間を取るのも大事だな、とすぐにやりましょうと返答したことを覚えています。
加嶋:1on1を誰にしてもらおうかと考えたときに、すぐに飯島さんが思い浮かびました。以前からよく雑談のようなこともしていましたし、自分にとっては自然な選択でした。
飯島:自分では絶対に思いつきませんから。ただ、仕事以外で、デザインについてや、なんてことない日常の話を加嶋さんとするのは自然なことでした。加嶋さんから言われて、そういえばそういう時間って最近ないなと自分自身でも気づいたんです。自分は、そういうところにはやや無頓着なのかもしれませんね。
ーそして、その1on1での対話を通じて生まれたのが、nailmarksですね。
加嶋:そうです。これは、飯島さんからの提案です。2人で取り組む案件はずっと続いていて、ワークスも溜まっていました。そして、1on1を通じて、新しい関係性も生まれてきている。そんななか、飯島さんから「この一連の活動に名前を付けてみませんか?」と言われたことをきっかけに、nailmarksは生まれました。
飯島:他者から見ても、この2人が組んで仕事をしている、という見え方をしたほうが、わかりやすいですし、魅力的に映るかなという考えがありました。
加嶋:こうして、会社でもないし、コミュニティでもない、チームというときもありますが、なんか少しまだしっくりこない感覚もある。そんな、何ともいえないnailmarksが生まれました。今は、少しずつ人数が増えて、十数人のメンバーがいます。

ーリモートワークがはじまって、2人の間での仕事はスムーズにできましたか?デザインワークをリモートで行うのは、イメージの共有など難しい点もあるのかなと想像しますが。
飯島:今はツールが発達していますから、特に難しいことはありませんでした。具体的には、FigmaやMiroなどのツールを使って、仕事を進めることが多いです。
こうしたツールを使いはじめた頃から、私と加嶋さんの仕事の仕方も少し変わってきたんですよね。
加嶋:はい、そんな気がします。
ーどのように変わったのですか?
飯島:以前は、私がコンセプトやワイヤーを考え、それを渡して加嶋さんがデザインするという流れがほとんどでした。
加嶋:デザインの仕事では、ディレクターがコンセプトを考えて、デザイナーが“目に見える形にする”という意味でのデザインをします。私は、独立以前からデザイナーとしての仕事が多く、飯島さんはディレクターとしての仕事が多かった。こうした関係性はデザインの仕事では、スタンダードかなと思います。
飯島:それが、リモートワークになることで、コンセプトやワイヤーについても加嶋さんがアイデアを出したりするようになりましたよね。これは、ツールによる影響が大きいと思います。私がMiroを使ってコンセプトの土台を共有して、それに加嶋さんがコメントする。これまでにないコミュニケーションが、リモートワークによって生まれました。
過程のデザインを見せることが増えてきた
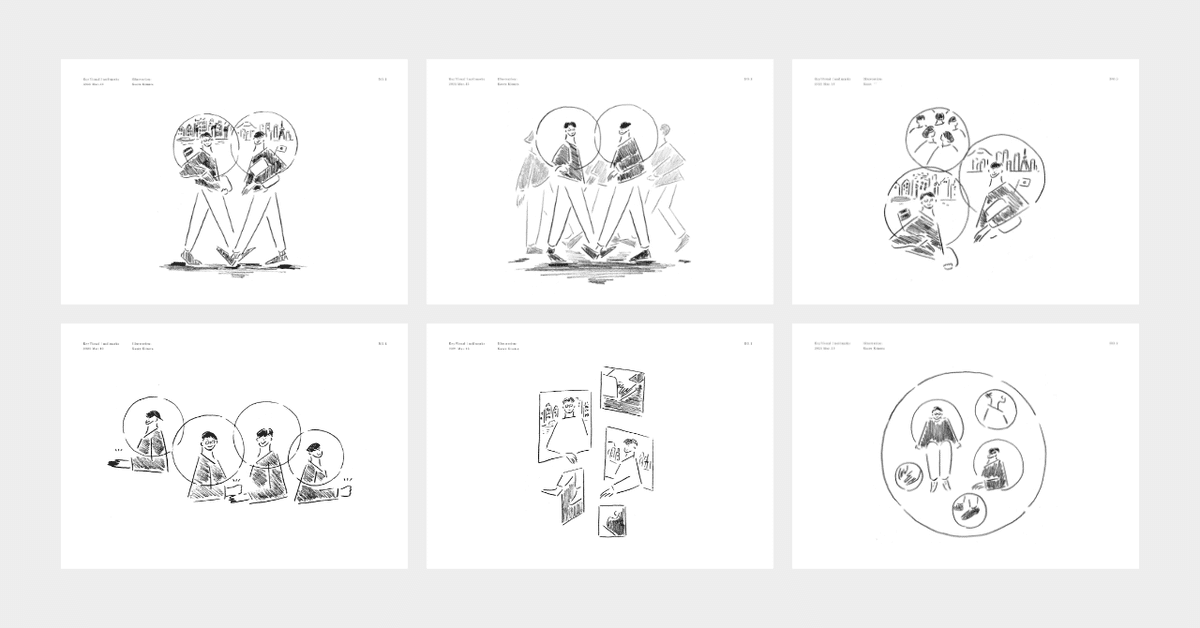
ー確かに。私も仕事で、MiroやFigmaを用いることが多いです。ワイヤーなり、デザインをまだ叩きの段階から共有して、コメントし合う。そういうプロセスがいつの間にか当たり前になっていましたが、振り返ってみるとリモートワークの普及と連動していたというのは面白い捉え方です。
飯島:私はそう考えています。そういう意味では、リモートワークがはじまったことにより、私と加嶋さんの間で、ディレクターとデザイナーといった役割の線引きが、少しずつ溶けていったようにも思います。ただ、私も一応UXデザイナーを名乗ってはいるので、デザイナーではあるんです。
こうなってくると、じゃあデザイナーとはどういう役割なのか、という話になってくる。
加嶋:飯島さんとの関係性が変わってきたのは、僕も感じています。同時に、デザイナーとしても考える範囲が広がったというか、今までと違う役割も担うようになってきた気がします。
ー加嶋さんからの視点で見れば、リモートワークによって、デザイナーとしての役割が変わってきたとも言えるのでしょうか。
加嶋:個人的には変化はしています。ただ、飯島さんは以前からそうした役割を担っていましたから…。
飯島:そうですね。ですので、「変わった」というよりは、デザイナー本来の価値や役割が「見えるようになった」というのが本質的な気がします。ただ、グラフィックやUIを作り込むだけがデザイナーではないというか。
加嶋:過程のデザインを共有することが増えたんですよね。これまでは、例えば2週間後にクライアントにデザイン案の提出があったとして、打ち合わせの数日前に一度ディレクター、つまり飯島さんに見せてフィードバックをもらって、最後の調整をする。最後にもう一度見てもらって、ディレクターがOKだったらクライアントのもとに持っていく、というのがよくある流れでした。
それが、Figmaなどを使っていると、作業をするボードに飯島さんも僕もいつでもアクセスできます。なので、作っている途中のものがいつでも見られる状態になるんですよね。これまでの、AdobeのIllustratorなどであったら、ある程度できあがったアウトプットを見せるしかありませんでした。それが、リモートワークにより使うツールが変わり、プロセスにも大きな変化が起きたのは間違いないです。
飯島:これまでデザイナーが、作りかけのものを見せることってほとんどなかったですからね。デザイン案と言いつつも、ある程度は1人で作り込んで、打ち合わせなり、メールなどで共有していた。
今は同期、非同期関わらず、共通のツールの上で作業をするので、加嶋さんも言うように、過程のデザインを見ることができる。そうした過程のデザインについてやり取りをすると、自然とコンセプトの話にもなっていくんですよね。コンセプトを探るために、デザインのプロトタイプを見ながら考えている、と言ってもいいかもしれません。
加嶋:そうすると、自然と僕もコンセプトについて考え、意見を言うようになっていたんです。途中段階のアウトプットがコンセプトにも影響を与えるというか、そもそもの考え方をより強固にしたり、あるいは違う方向性がいいのではと考えたりすることってあると思うんです。そうしたコンセプトとアウトプットの反復のようなものが、飯島さんとの間で増えた気がしますね。
ーなるほど。これまではリレーのように、コンセプトを考える人、デザインをする人と役割が別れていたのが、ツールの変化によって一緒に走りながら作っていく形になっていたんですね。
飯島:さらに、そういうプロセスにクライアントも参加するようになってきているように思います。作りかけといいますか、「コンセプトを考えるための途中段階のデザイン」をクライアントと共に見ながら、先方の目的は何か、どういう課題感があるのかといった話を一緒に紐解いていくんです。
加嶋:確かに、クライアントとの関係性も変化があったかもしれませんね。これまでは、クライアントが固めた要件があって、それに沿ってコンセプトを考えるなり、デザインをすることがほとんどでしたから。
「決めてもらう」ことがディレクターの役割か?
ー確かに。2週間後にクライアントにデザイン案を持っていくとして、その間の過程ってクライアントには共有しませんもんね。打ち合わせの前日にメールで送るか、あるいは当日にデザイン案を持っていってモニターなり、プリントアウトしたもので見てもらうのが常でした。
加嶋:そういうコミュニケーションってオフラインだから成り立っていたんですよね。
飯島:そうですね。そうやって対面で話す価値も当然ありますが、仕事のほとんどがオンライン化したことで、クライアント含めて同じ場所、つまり同じボードで仕事をするようになりました。この変化も大きいかもしれません。
加嶋:そういう意味ではクライアントとの関係性であったり、仕事の取り組み方はある種フラットになってきているように思います。
ー「変化の時代」とか「正解のない時代」といった言葉をよく聞きます。クライアントからしても、先が見えないから要件を固めようにも固められない時代なのかなとも思います。
飯島:確かにそうですね。昔は、ディレクターといえば、クライアントの要件にしっかり答えて、納得いく形でデザイン案を決めてもらうことが一番の役割だったように思います。3つのデザイン案があったとして、その中からしっかりとクライアントに決めてもらう。「他にも見たい」「いい案がない」といった反応をもらうのは、ダメなディレクターといった風潮もあったように思います。
そうなると、ディレクターは決めてもらうことばかりに力を注ぐようになるんです。そのために、案件のスタート時点でのヒヤリング能力が求められる、なんてことも言われていました。いかに上手に、クライアントの要件を聞き出せるかがディレクターの一つのスキルだったんです。
ーよくわかります。企画案であったり、キャッチコピー案であったりをしっかり決めてもらわないといけない。そのために相手が「うん」という勘所をしっかりと探って、それに合わせた提案をしていく。デザインであれ、コピーライティングであれ、その構造は一緒ですね。
飯島:極端な例ですが、ディレクターの中には、最初に「赤が好きですか?黄色が好きですか?」といった質問をする人もいました。正直、私はそういう質問は本質的ではないのでは、と違和感を抱いていたんです。
加嶋:決めてもらうためのデザイン制作というのはすごくわかります。でも、当時はそういうやり方しかないと思っていました。
飯島:うん、わかります。私はもともと決めてもらうことだけを目的とした仕事の仕方は、少し違うなと考えていました。クライアントの要望を聞いて、それに合わせたデザイン案を出していくのは、デザイナーの半分ぐらいの役割でしかない。
クライアントの話を聞いて、いきなり「これが正解です」といって出すのではなく、仮説を立て、一緒に検証するなかで納得のいくコンセプトやデザインを見つけていく。ただ、これまではクライアントの要望に合わせてアウトプットを作っていくしか選択肢がない、といった状況も多かったですね。
コンセプトだけ、デザインを形にすることだけではない存在
ー仮説からコンセプトを導いていくこともデザイナーの役割としては大切だという考えが、nailmarksの根底にありそうですね。
飯島:そうした考えはありますね。ただ、大切なのは、「コンセプトを考えるだけ」で終わらないことです。コンセプトを考えるために仮説を立て、そして仮説を検証するためにアウトプットを作っていく。この一連のプロセスを進めていくことが大切だと思いますね。
加嶋:nailmarksの場合だと、仮説を立てて、それを週単位などでアウトプットにして、クライアントと一緒に考えていくというプロセスが多いですよね。Webプロダクトの場合だと、それがずっと続くという感覚です。その一連のプロセスを、クライアントともフラットになって進めていく。
仮説だけをクライアントと話しても、理屈っぽくなってしまいます。ロジックだけで話を進めるのではなく、アウトプットも見せながら話を進めていく。これは、デザイナーだからこそできることなのかな、と。アウトプットを見せていくと、いろいろな反応がクライアントからあります。「こっちのほうがかっこいいですね」といった反応に対して、「ただ、今回の課題に対してはもう1つの案の方が合っていると思います」といった形で具体的な話ができる。そうやって、両者が納得行く落とし所を探っていくんです。
飯島:ずっとコンセプトについて議論していても疲れてしまいますからね。
ー先程の話にもありましたが、週単位で細かくアウトプットを共有する進め方は、リモートワーク以前にはあまり考えられなかったように思います。
飯島:そうかもしれませんね。ただ、私自身はそうしたプロセスに合致する特性も持っているし、相反する特性も持っているんです。
加嶋:どういうことですか?
飯島:前にストレングスファインダーを受けたときに、自分の特性として「適応性」と「最上志向」というのがあったんです。適応性はまさに今日話しているように、変化に応じて仕事の仕方などを変えていくことで、そういうことは得意なのかな、と。一方で、常に最上のクオリティを求めようとする特性も持っています。
週単位でアウトプットを出すためには、納得いくまでクオリティを追求する時間がありません。途中段階のものを見せながら、ブラッシュアップしていくプロセスを優先するからです。ただ、やっぱり心のどこかでは「もう少し質を上げたい」という思いがどこかにはあって…。
加嶋:なるほど。確かに、デザイナーからすると途中のものを見せるのに、躊躇する感覚はありますよね。私も、少し違う角度かもしれませんが、自分が作業しているところを他の人に見られるのは、過去には抵抗があったように思います。
飯島:最上志向と細かくアウトプットを出していくプロセスのバランスは、なかなか結論が出ないですね。ただ、クライアントには喜んでいただけているので、そういう意味では今のやり方が間違っているわけではないのかな、と。
加嶋:なんというか、もったいぶらずにデザインを見せられるようにはなりましたよね。
飯島:うん、その感覚はすごくわかります。
nailmarksにとってのデザインとは?

ーなるほど。クライアントとの関係性が変わり、デザインのプロセスも変わってきたということですね。
加嶋:飯島さんは専門用語を使うのもあまり好きじゃないですよね?
飯島:うん。というのも、クライアントと変に線引きができてしまうんですよね。提案するときや打ち合わせで、専門用語を使うと、関係性が「クライアントとデザイナー」とハッキリと決まってしまう。そうすると、デザインの話にフレームが定まってしまうんですよね。議論のレンジがそれ以上広がらないというか…。
加嶋:クライアントから「デザイナーとはデザインの話しかしない」と思われてしまうと、それ以上の議論ができないですもんね。
飯島:そうそう。特に案件の初期の頃はもっと引いて、広いレンジで話をしたいんです。それには、フラットな言葉で、専門用語を使わないで話さないといけないんです。専門用語を使えば、デザイナーっぽくふるまえるかもしれませんが、それによって話のレンジも狭くなってしまう。クライアントにとってももったいないと思うんですよね。
ー面白いですね。飯島さん、加嶋さんの関係性が変わり、クライアントともフラットな関係にどんどんシフトしている。そうしたなかで、冒頭に飯島さんは「デザイナーの本来の価値が見えるようになった」と話していました。改めて、デザイナーの本来の価値とは何なのでしょうか?
飯島:デザインを形にするという役割は変わりません。専門的な知識で美しいUIを作り込むといった仕事は、デザイナーが発揮する価値としては、変わらずあると思います。
一方で、これまではそうした作り込むプロセスをある種ブラックボックス化してきた、というのが正直なところあったと思うんです。クライアントからすると、提案されるまでどういう考えで、どう作っているかが見えない。
さっきも言ったように、アウトプットだけを見せて、そこでの判断がスムーズにいくようになんとかするのがディレクターの主な役割とされていました。そうしたときのディレクションが、やや相手を煙に巻くというか、何かまやかしのようなものがあった気がするんです。
でも、今日話していたように、リモートワークになった今、プロセスが全部オープンになり、関係性もどんどんフラットになっています。ブラックボックスだった部分が、開かれている。
そうしたオープンになったプロセスの部分で、クライアントとコミュニケーションしながら、最適解を見つけていく。こうした役割を、デザイナーが担うようになっている。ただ、それはもともと「デザインする」という言葉の意味に含まれていたはずなんですよ。
加嶋:デザイナーとして、どこに専門性を持つか、という意味では無駄なものが削ぎ落とされたような感覚がありますね。今日の話にもあった「決めてもらうためのデザイン」に時間をかける必要がなくなったり、クライアントとのコミュニケーションが密になったおかげでわからないことを聞きやすくなったり…。
そのうえで、プロセスがオープンになり、いかに抽象的な思考と、具体的なアウトプットの思考を振り子のように反復できるか。具体と抽象の振り子については、『takram design engineering|デザイン・イノベーションの振り子』に書かれていて、私たちもよくする話です。いかにこの振り子を何度振れるかを、デザイナーは問われているように思います。
飯島:クライアントと我々の間で線引きがなくなってきたとはいえ、クライアントがデザインをできるわけではありません。それに、クライアントのビジネスサイドの話を我々が全部踏み込んで考えるというわけでもない。そういう意味では、もちろん役割の違いはあるんですよね。
ただ、お互いがそれぞれの領域のことを全く知らなくていいかというと、そうでもない。フラットに物事を考えていくからには、相手の領域の理解も必要にはなってきます。クライアントからしても、ビジネスサイドの話でこちらをまやかしていた部分って少なからずあると思うんですよね。そういうのも、全部オープンになっていく。
加嶋:そのバランスってすごく難しいですよね。ビジネスとデザインの話、抽象と具体の話、それぞれのラリーというか、コミュニケーションの密度が上がっているのは間違いないです。そのなかで、仮説とアウトプットをもとに、案件を進めていくのが、nailmarksの仕事のベースにあるように思いますし、このプロセスの精度であったり質を高めるのがデザイナーの本来の価値なのかなとも思います。
飯島:そうですね。nailmarksが考えるデザインにおいては、そう言えるかもしれません。これからも、もっと考えていきたいテーマではありますね。
ーデザイナーのみならず、さまざまなクリエイターが共感や気づきが得られる対話だったかと思います。また、次回のインタビューも楽しみにしています。
文中に出てくるロゴやイラストは、nailmarksのクリエイターとのコラボレーションから生まれたアウトプットです。次回記事では、組織をまたいだコラボレーションなどについて話しています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
