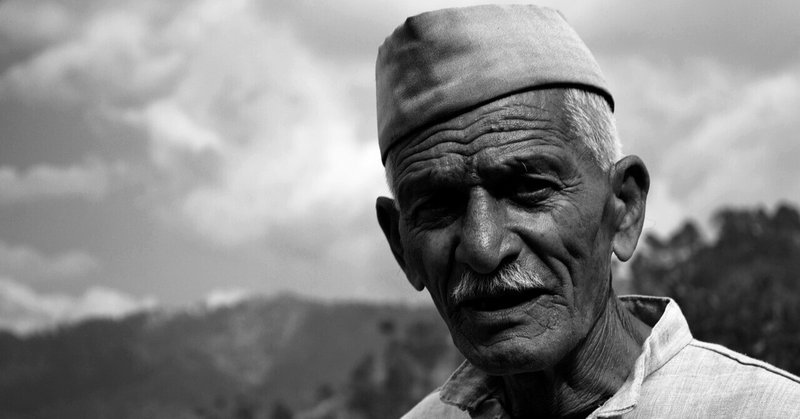
17 ミッションの船出・野口復堂の凱旋帰国まで|第Ⅱ部 オルコット大菩薩の日本ツアー|大アジア思想活劇
分断されたインド社会
約一カ月のインド滞在中、講演や名所めぐりにと多忙な日々を送った復堂センセイ。日本人初のスペシャル・デレゲートは、同じアジア人としての同情もあってか、比較的偏見のない眼差しで植民地インドのありさまを観察していた。しかし当時のインド人の間で頑固に守られていた迷信じみた奇習や、宗教やカーストの違いに捉われた頑なな排他主義・閉鎖性に対しては噺家らしいユーモアも交えつつ、これを非難している。ヒンドゥー教修行者サドゥーやマハラジャたちの奇行を描いた伝聞交じりの与太話も、べらぼうに面白いが今回は割愛するとして、ここでは彼がマドラス総督の主催する迎賓館でのパーティーに、オルコットとともに招かれた夜のエピソードを御紹介したい。
十二月二十四日のクリスマスイヴ。つい三日前にもやはり総督主催でマドラス在住の白人を集めた舞踏会に招待され、夜を徹した乱痴気騒ぎに怖気をなして逃げ帰ったばかりの復堂だったが……。
……今度はインド人ばかり、饗応は庭をはい回る花火を見せるだけでそれが済めばホールの舞踏場に来客残らず円陣を作らしめ総督夫妻が握手して廻るだけで、それが終われば湯茶一ツも与えず帰らしむるのである。単にこれだけ聞けば総督は英国人には厚くもてなし、異邦人には残酷に扱う様に見えるが、決してそうではない。現に復堂は英国人に非ざるも英国人以上の歓迎を受けて居る。これ何が故か。復堂は宗教上の偏見迷執を持たぬからである。
インド人はこれに反し牛肉は食わぬ。何時より何時迄の間は湯茶一ツ飲まぬ。他人とは会食せぬ。何々宗の者とは同卓に座らぬ。この祈祷の出来ぬ席では物食わぬとか、実に馬鹿げた迷執を固守する故、総督も饗応の仕様がない。これインド人自ら求めてこの淋しき席を作るのである。しかしこの淋しき席も総督あればこそ一堂にこれだけ異宗の者を集め得たのである。政治を英国にして貰うのも当然であると言いたい。
特に最後の一節など、少々一方的な見方のような気もしないではないが、時はまだ明治二十一年である。口当たりのよい文化相対主義など一顧だにされない厳しい世相であった。しかも野口青年がまのあたりにしたインドの根強い宗教対立、加えて陰湿なカースト差別による人心の分断は現在もなおインド社会の宿痾であり続けている。四民平等を掲げ、若い国民国家として自前の憲法(大日本帝国憲法)まで制定せんとしていた日本の代表選手としては、インドの体たらくにあきれ返ったとしても無理はなかろう。
百六歳の老翁との対話
迎賓館でのパーティーからの帰路、復堂は暗闇で彼を待ち受けていたあるインド人老翁に声をかけられた。当年百六歳(復堂談)という老翁は、復堂に遠い極東の独立国のさまを詳しく問うた後、はるかあなたに桃色の服を着た一インド人を指さして、こう嘆いた。

時が時世が世なればあの方が、今夜総督や君が占めし上壇に座して、我々を見る印度の王様の末である。印度の土が産した糸や絹をマンチェスターへ送り、紡いで織ってもらって高い代償を払って形だけは印度風に仕立てて、王様も我々も着ているので、我々は結構な印度語もあるにも拘わらず之は家族だけの言葉となって公には英語を使わねばならぬのである。国は小さく人は少なくても、君の国は国として立派なものだ。俺の国は大きく人数は君の国の幾倍もあるが、どうしてイギリス(英吉利)の厄介にならねばならぬのであろうか。
復堂はこの老翁に応えて、
日本は仏教をこの国から貰いしも、国家の為になるよう東方仏教となし、錫蘭セイロン島のような戒律に束縛されて動きの取れないような死仏教とは違う。またこの印度の如く、折角の仏教を亡ぼして、迷執深い宗教に因って、飲食物の端にまで争いを生じているような事では、とても一国民の資格は備えられない、やむをえず政治はイギリスの厄介とならねばならぬのである。
予がチューチコリンとマドラズ間の汽車旅行中の所見に、車上の車掌とフォームの駅長が別れの挨拶をなすに、各自宗教が違う故、駅長は指を曲げて鼻の上に当てて胸を左右に振ると、車掌は右手で左の胸を打つと同時に左手を左方へ開く。これでも喧嘩なしに同じ鉄道の仕事に従事しているから宜しい。
しかるに今夜のこの客を御覧なさい。同挨拶の者ばかり一団となって、他団を敵視している。遠くこの鉄道従事員に劣っている。位置低き鉄道員の方が国家の組織に近付きいるにも拘わらず、総督に招かるる程の有力者が互いに敵視して、国家組織に遠ざかりつつあるは実に貴国の為に惜しむ処なり。
復堂の諄々と説く言葉に、インド人の老翁は深く溜息を吐き、「御忠告骨身に徹せり」と復堂の手を固く握って涙をしつつ、
過日の新聞に、Mr.Noguchi, special representing Japanese Buddhism in the 13th Anniversary of the Theosophical Society, Madras and the guest of our Governor-General is making a circle of eminent friends in India. His wit and humour, his genial temper and the mystery playing in his eyes and lips, in fact Mr.Noguchi as he is, is sunshine to all. One feels in his presence the flow and radiation of Love and Light through his simple words and short episode of his own life and the way-side experiences.(マドラスの神智学協会十三周年大会における日本仏教の特別使節であり、我らが総督の客でもあるミスター野口は、インドに於いて傑出した友人の輪を作っています。彼の機知とユーモア、穏やかな気質と彼の瞳と唇がかもしだす神秘、まさしく彼自身が、皆の太陽なのです。人は彼の簡潔な言葉と、自身の人生と、路傍の出来事を語る短いエピソードを通じて、彼の中から溢れ出す愛と光を感じるのです。)の書き出しで、長々とあなたの御経歴を読み、是非今夜はお目にかゝりたしと思って居ったが、幸いお目にかゝる事が出来てこんなに嬉しい事はない。如何にもあなたは新聞の記事通りのお方で、此の老人にも大に得る処があった。お別に臨んで一言する、印度と同じ亜細亜の中にも、あなたの如き人を生ずる日本国のあることを知ったのは、死し行く百六翁の冥土へのよい土産である、何分とも今後の印度を頼む。
老翁は復堂と固い握手を交わして、また闇のなかへ去っていったとか。さて、ホントかね。あまりにもできすぎたエピソードではあるにせよ、当時「国家の体をなさぬ」まで零落していたインドの知識人にとって、アジアで唯一近代化と独立維持に成功しつつあった日本人による率直な批判は、しごく身に滲みるものだったに違いない。ともかく、極東の独立国からはるばるインドまでやってきた復堂、行動は大胆不敵ながらも、その思想と眼差しはほどよい身びいきに貫かれながら中庸にして常識の線を外れない、質実剛健な明治日本の侠(おとこ)であった。
パッチャパス・ホールでの大演説
アディヤール(アダヤール)で開かれた神智学協会大会でも、野口は特別待遇であり、百六歳の老爺が読んだ如く、現地の新聞にも大きく取り上げられた。「彼は素晴らしい男だった。記念式典における彼の感動的なスピーチは、ノグチを協会本部や一般のヒンドゥー・コミュニティーの人気者にした。」オルコットは、その回想録で野口復堂のことを一貫して好意的に記している。*6 野口の講演活動は、インド人の極東の未知の国日本に対する関心を大いに盛り上げた。
さて(神智学協会大会の)会期中マドラス市内で時々公開演説会を開催した。その広告ポスタァに麗々と姓名を大きく印刷されてあるのは会長オルコットと復堂の二人で、他は世界各国よりの諸デレゲートとあるだけである。復堂たるもの大に喋らざるべからずで……
なかでもマドラスのパッチャイアッパズ・ホール(Pachaiyappa's Hall 復堂の手記では”パッチャパス・ホール”と記されている *note注)で行われた講演は反響が大きかったようだ。オルコットは回想録にその演説の大部分を紹介している。野口はこのとき日本語で演説し、次いで英語の翻訳が読み上げられた。

https://www.madrasmusings.com/vol-29-no-13/the-mahatma-in-madras/
神智学徒の同志諸君、そしてヒンドゥーの友人達よ、私は最初のインド滞在の機に、日本人と他のすべての仏教徒が心から親愛をよせる神聖な国、我々の宗教の創始者が生まれ、彼の尊い教えが雄弁な声で発せられた国の皆さんに演説できることに、たいへんな幸福と名誉を感じます。
私は「日出づる処の国」から、最速の汽船で二十日間太平洋を航海しここにやってきました。しかし私たちに共通する兄弟愛が、まさに我々を黄金の鎖で束ねている事実を悟るとき、我々の間は一ヨージャナ(インドの距離単位 一ヨージャナは約七キロメートル)ほども、否このホールの幅ほども、隔たっているとは思えないのです。私たちを結びつけるものは、宗教復興へ向けた偉大なムーブメントにおける共通の関心事、すなわち我々の父祖たちによって教え説かれ、彼ら自身の生き方によって厳格に示されてきたモラリティの復興なのであります。
彼はインドと日本との精神的な絆の太さを説き、聴衆の心をがっちりと捉えた。そのうえで復堂は、日本の仏教が置かれた現状について、オルコット来訪以前のインド・セイロンの状況と重ね合わせながら熱弁を振るう。そしてインド人聴衆にこう哀願したのである。
私たち日本人仏教徒は、あなた方にかの社会的な奇蹟の働き手、宗教の守護者、寛容精神の教師を、少しの時間お貸し願いたいのです。彼は、自らと彼の同僚とがインドの宗教のために成し遂げた仕事を我々の国の宗教のためにも成してくれるでしょう。我々はオルコット大佐が我々を助けるために来てくださることを祈っております。どうか来て、我々の老人の希望をよみがえらせてください。我々のカレッジや大学の卒業生たち、また教育のために米欧に留学した人々に、欧米の科学は宗教の自然の姉妹であるにせよ、それは絶対確実でも、宗教の代用品でもないことを分からせてくださいと。
ついで復堂センセイは日本の仏教僧侶の堕落ぶりについてもコテンパンにこき下ろし(さすがにその部分はオルコットも引用していない……)、日本の宗教復興のためにはもはや外部からの清新な風を吹き込むしかないこと、日本の仏教徒がオルコットを『十九世紀の菩薩』と崇め、その来訪を心待ちにしていることまで付け加えた(こりゃリップサービスが過ぎる気もする。)たとえそこにどんな誇張やはったりが混ざり込んでいたにせよ、多くのインド人にとって、二十三歳の野口善四郎の言葉こそが有史以来初めて耳にする日本人の公式メッセージであった。
ミスター野口のまじめな話しぶりは、インド人の琴線を打ったように見えた。そして彼はホールに集まった人々の祝福をひとり占めにした。一五八四年の歴史的イベント以来、日本が外国に宗教的な助力を求めるアピールを発したのはこれが初めてであった……
会場にいたオルコット大佐の回想だ。野口復堂のインド訪問を、戦国時代にはるばるローマを訪うた天正少年使節団になぞらえているわけで、これは恐れ入る。オルコットはさしずめローマ法王の役回りであるが、オルコットと日本仏教の関係の推移を見てゆくと、このたとえもあながち的外れではないような気もする。
野口復堂は日印交流の先駆け
ところで、復堂の回想によれば、彼はこのパッチャパス・ホールの講演で日本国の商業や工業・農業についても言及したという。その講演を聞き、新たな商機を悟ったインドの綿業業者は日本の農商務省に生綿の見本を続々と送り込む。その結果として、翌明治二十二年七月の日本政府による印度綿業視察団派遣、インドへの本格的なアプローチが実現したというのが復堂本人の主張である*10。
……その結果は日本郵船会社が始めての海外航路をインド「ボンベイ」へ開き、又同地に日本政府がインドに領事館の置き始めをなし、インド生綿の輸入よりして、紡績会社の勃興は此時から始まる。*11
……従来英のマンチェスタァより外にゆかざりし印度綿が、同じ亜細亜の特に佛教関係のある日本へ来て、綿そのものも大喜び、茲に鐘ヶ淵紡績会社の如き今日日本が世界に誇り得る大紡績会社が出来たのである。*12
……いささか誇るようだが日印を結びしは単に宗教の関係ばかりでなく、斯く物質上にも及ぼしたは、復堂お手柄と謂つべきである。*13
まあ事実はそれほど単純ではないにせよ、実際の年代的経緯を見れば、そのように解釈できなくもない。野口善四郎の来印は新聞などを通じて広く報道されたというから、それをきっかけに日本への関心を高めたインド人士も決して少なくはなかったはずだ。キリスト教の浸透に危機感を抱き発憤した日本仏教によるひとりの宗教使節が、インドと日本の直接的な経済関係への呼び水ともなった……。復堂の我田引水の仮説には、どこまでも抗いがたい魅力があると思う。
南北仏教徒を結んだミッション
さてアディヤールで年越しした復堂。正月明け早々の明治二十二(一八八九)年一月十日、群衆に見送られながらマドラス港を出航しセイロンに戻った。
此時復堂の喜びは恐くは爾前爾後全生涯中の最大なるものである。何んとなれば日本出発前、京都栂の尾の送別会席上『復堂神戸に上陸せりと聞かば、オ氏は必らず来り居るなり、オ氏神戸に上陸せりと聞かば、復堂は必らず同道帰朝し居るなり、オ氏終に来らずとあれば、復堂は再び日本の土は踏まざるべし』と陳べ置いたからである。
オルコットの日本旅行には、若きダルマパーラも同行することとなった。復堂自ら、「彼こそ究極の人物だ」とダルマパーラを随行員に強く推した際、しかしオルコットは「彼は富者の子で、しかも体に障害があり病弱。両親はとても日本行きを許さないだろう」と難色を示したという。またオルコットは、南方仏教の代表としてスリランカの高僧を同行したいと考えていた。しかし戒律に抵触する行いを極端に忌諱する保守的な僧侶たちは、日本が遠方であること等を理由にして誰ひとり彼の要請に応じなかった。結局、復堂の口添えにダルマパーラの両親も納得し「この時期において、大佐への特別な献身が彼の人生のおもな情熱の一つであった」ダルマパーラ青年だけが、このミッションにつき従ったのである。
出発前日の一月十七日、オルコット訪日を記念した盛大な出発式が行われた。スマンガラ大長老はオルコットを仏弟子アーナンダになぞらえた感動的な演説をなし、歴史的なミッションを祝した。*14 おそらくこの時に撮影されたと思われるのが、下の写真である。紋付き袴姿の野口復堂の隣と、オルコットの右にそれぞれ写っている日本人僧侶は、吉連法彦師と、復堂がアディヤール滞在中にセイロン入りした東温讓師だろう。
オルコットはスマンガラ大長老(この写真ではオルコットからリードビーターの稚児扱いだったシンハラ人少年一人を挟んで中央に座している)よりサンスクリットで書かれた親書を託された。それは数百年の歴史的空白を経て、南方上座仏教の代表から北方大乗仏教の代表に向けられた最初の公式文書だった。その古い翻訳が残っているので、ここに引用したい。

スマンガラ大長老の公式書簡
《衆知の聖釈尊の祈念》
余はこの書簡を有名なる大日本の同縁の諸師および仏教信者たる我が同胞のために草せり
親愛なる同胞よ諸佛はこの現世に降りて無常の理を顕示せり
最後の仏なる釈尊はこの理に従って無常生死病苦の法を示し衆生を救う事を説けり
諸仏に従って往きし道は訓誨と究理を教えこれに従うて往く衆生は救わる可し
釈尊の楞迦山に三回降臨したまいその聖趾にてこれを潔め真理を吾等に明らかにしたまえり
釈尊入定後二百十四年においてダマリーカ王の子マハマヒンダラは六羅漢とこの楞迦山に来たり古えの仏道を説いてこれを国教とし以てその人民の救われたるを示せり
吾等はこの仏教の経文その注解等を釈尊の銘したまいしパーリ語にて現今なおこれを存せり
また仏教に尊守する僧侶ありて即ち潔白にその道を持せり
このゆえに日本同胞にしてパーリ語を学ばんとする人には尤も便益なる機会なり
この書を携える大佐オルコットと称する人は仏教の最も熱心なる信徒にして余は氏の日本同胞に大なる助力をなすを信じまた氏の日本国に滞在中は厚待を受くるをこいねがうなり
釈尊涅槃後五千三百三十四年ボッシ月の満月日楞迦山に於いてスウイバタノ大法師 スマンガラ書す
善良なる目的は成功するなるべし
世の善良なる人士は左の事を記せよ
高得なるコロネル・オルコットと名くる人は聖釈尊の忠節なる門弟にしてよくその訓誨を尊守せり故に下名等はいずれの国民にても三帰五戒を受け仏教拡張のため教会を組織する申請をなすときはこれを仏教信徒として承認記名することを依任す
この証として下名等セイロンに在るシャムラ宗及びアマラプラ宗の法師等は連書同人に渡すものなり
第一 スマンガラ・ナヤカ 第二 レリ・スマンガラ
第三 タッマランカリ・ナヤカ 第四 ザヒユチ
第五 アマラモリ 第六 グナラタナ 第七 デワーミッタ *15
書簡の内容はセイロン仏教の伝説上の由来と現状とを簡単に述べ、日本人のパーリ語習得のための留学を勧め、オルコットの紹介をしたうえで、氏の日本滞在中の厚待遇を望んでいる。またオルコットはスマンガラ大長老はじめセイロンの高僧たちから日本での仏教徒の組織・宣教のための委任を受けていた。
これは考えてみれば異様なことだ。上座仏教の教理において、在家信者に三帰依・五戒を授ける権限を持っているのは出家した僧侶だけなのだから。
「仏教世界の連合ユナイテッド・ブッディスト・ワールド」を目指す前代未聞のミッションにあたって、セイロン仏教の指導者スマンガラ大長老は「白い仏教徒」オルコットに僧侶の特権の一部まで手渡し、全面的な代表権を委ねたのである。オルコットとその従者ダルマパーラは、セイロン仏教界から日本仏教界に向けた、史上初の正式な使節ミッションとして訪日した。その事実は、何度でも強調しておきたい。
復堂・オルコット・ダルマパーラの一行は、コロンボでフランス船S. S. Djeninah号に乗り込むと、いよいよ同月十八日に日本への帰還の途に就いた。
ついに凱旋帰国
日本を発った翌年の明治二十二(一八八九)年二月九日、野口善四郎はオルコット大佐とダルマパーラを伴い、凱旋帰国した。神戸港の小野濱桟橋には僧侶七十人余りが待ち構えていた。復堂曰く、
神戸に着くや波止場は丸い頭の山、この間より毛のある頭が二つ来て復堂を抱えて泣いたのは平井金三氏と佐野正道氏であった。
これが明治における南北仏教交流の最初の成果であり、世界史の視座から眺めるならば、長く出会うことのなかった南北の仏教徒が、数千年のときを隔て、仏陀の名のもとに再会を果たした歴史的瞬間であった。
南国育ちのダルマパーラ青年はセイロンからの船旅の途上、上海で初めて雪を体験して縮み上がり、途端に体調を崩した(オルコットや両親の心配は、杞憂に終わらなかったのだ)。彼は寒さから来る強度のリュウマチ神経痛に苦しみ、日本に着くとまもなく、京都東山病院に入院する羽目となった。
ちなみに夫の帰国七日前、野口復堂の妻は無事女の子を出産した。その娘は、復堂に「三人迄も孫を拵えて」くれるのだが、それはまだまだ後の話になる。
電書版追記
本文中、「上座仏教の教理において、在家信者に三帰依・五戒を授ける権限を持っているのは出家した僧侶だけ」と記し、オルコットがスリランカ仏教界から授戒権限を委任されたことの特異性を強調した。しかし、これはテーラワーダ仏教の教学に照らすと、いささか乱暴に過ぎる断定だった。スリランカで西暦十世紀〜十二世紀頃に編まれた在家仏教論、Upāsakajanālaṅkāraによれば、「戒を授ける人(授戒者)には特別な資格はない。戒の相を知っている比丘や比丘尼、あるいは在家信者なら誰でも授戒者になりうる。またふさわしい授戒者がいない時には自ら心に誓って受戒すること、すなわち「自誓受戒」の方法も可能であるという。」(浪花宣明『在家仏教の研究』法蔵館、一九八七年、七〇頁)そういえば筆者も、日常生活の中では一人で五戒のパーリ文をとなえている。オルコットがスリランカ仏教界から正式な委任を受けたミッショナリーだったことは事実だが、「在家信者に三帰依・五戒を授ける権限」を強調したのはミスリードと思って追記した次第です。
註釈
*6 〝OLD DIARY LEAVES〟FOURTH SERIES 1887-92 H.S.OLCOTT p76
*7 同書 p81
*8 同書 p83
*9 同書 p86
*10 日本とインドの綿貿易の始まりと経緯については 山崎利男・高橋満編『日本とインド 交流の歴史』三省堂新書一七三、一九九三年、四十三頁に詳しい記述がある。当然、復堂の名前など出てこない。
*11 「這般死去せし『ダルマバラ』居士が始めて日本に入りし道筋」
*12 「四十年前の印度旅行」
*13 「這般死去せし『ダルマバラ』居士が始めて日本に入りし道筋」
*14 『浄土教報』一八八九年三月二十五日及び『仏教』第二号、一八八九年にスマンガラ大長老の演説翻訳が掲載されている。
*15 『浄土教報』一八八九年三月二十五日
*note注 復堂の手記で「パッチャパス・ホール」と記された施設をパッチャイアッパズ・ホール(Pachaiyappa's Hall)と同定するにあたって、赤井敏夫先生が神智学協会関係者への照会をしてくださいました。謹んで御礼申し上げます。
最後まで読んでくれて感謝です。よろしければ、 ・いいね(スキ) ・twitter等への共有 をお願いします。 記事は全文無料公開していますが、サポートが届くと励みになります。
