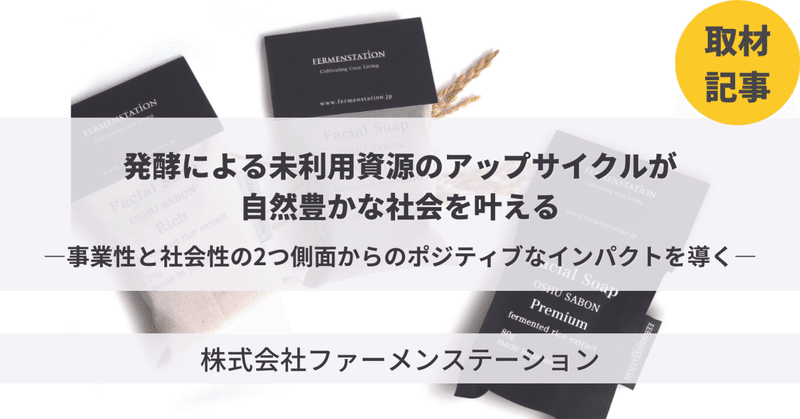
【取材記事】発酵による未利用資源のアップサイクルが自然豊かな社会を叶える ―事業性と社会性の2つ側面からのポジティブなインパクトを導く―
株式会社ファーメンステーションは、独自の発酵技術によって「循環型社会」を構築する研究開発型のスタートアップです。オーガニック米といったサステナブルなエタノールなどを用いた化粧品、雑貨などを世に送り出しています。今回のインタビューでは、発酵技術による未利用資源の有効活用の意義、これからの取り組みにフォーカスしてインタビューをしました。
お話を伺った方

株式会社ファーメンステーション 代表取締役
東京都出身、国際基督教大学(ICU)卒業。富士銀行(現みずほ銀行)ドイツ証券などに勤務。
発酵技術に興味を持ち、2005年に東京農業大学応用生物科学部醸造科学科に入学、
2009年3月卒業。同年、株式会社ファーメンステーション設立。研究テーマは未利用資源からの
エタノール製造、未利用資源の有効活用技術の開発。
世の中にポシティブな影響を与えたい思いで、農大で「発酵」を学び、そして創業

mySDG編集部:御社のホームページを拝見して、「発酵」をテーマとしたプロダクトに特化しているようですね。創業の経緯とサービス開始のきっかけを教えていただいてもよろしいでしょうか?
酒井さん:社名の「ファーメンステーション」とは、「発酵の駅」を意味します。弊社は、「未利用資源」という使われてない資源がたくさんとあることを知り、それを有効活用したいと思って始めた会社です。元々、私は、金融機関で働いていましたが、世の中にポジティブな影響を与えるような仕事をしてみたいと思っていました。そんなときに、たまたま東京農業大学(以下、農大)に生ゴミをエタノールにする技術があることを知りました。農大に入学し、発酵の技術について学んだのが創業のきっかけです。
mySDG編集部:普通に大学に入り直したということですか?
酒井さん:大学に入り直しました。
mySDG編集部:大学に入り直したのは、いつですか?
酒井さん:2005年に入学し、2009年に卒業しました。
mySDG編集部:4年間まるまる学んだのですね。今、発酵系のプロダクトが多いのですが、「発酵」に着目した理由はなんでしょうか?
酒井さん:昔から発酵技術に興味がありました。私たちが取り組んでいるものは、発酵食品の分野とは少し異なります。同じ発酵技術ですが、食品や飲料ではない原料や工業製品に関わっています。元々、発酵は微生物の力を使って、有機物を人間に有益なものに変えるということです。
お酒もそうです。環境の分野でも、発酵の技術がかなり使われていて、廃棄物になってしまうようなものがエネルギーになるなど、資源を活用する技術として長年研究開発されてきました。
特に私が注目したのは廃棄されてしまうものや有効活用されていないバイオマスなどを発酵させることでアルコールや変えられる技術、エネルギー利用も可能ですし、この技術を学びたいと思いました。
mySDG編集部:御社の創業はいつでしょうか?
酒井さん:農大を卒業直後の2009年に創業しました。
mySDG編集部:2009年からこれまで、環境問題が世の中にクローズアップされることが多くなりました。一番の大きなポイントは、SDGsです。御社がこれまで事業としてやっていたことが、SDGsとかぶっていたという認識でよろしいでしょうか?
酒井さん:私たちは国連によって「SDGs」が設定される前からこの事業に取り組んでいますが、「SDGs」という言葉を知ったきっかけはよく覚えています。国連大学の方に呼ばれたことがあり、私達も地元の仲間と一緒に地域におけるSDGsの実践事例を発表するような機会がありました。そのときにSDGsという大きな枠組みをみんなで設定しているグローバルなゴールがあることを知りました。元々私たちがやっていること、目指していることにもすごく近いと思ったのがSDGsを知ったきっかけです。
素材と生産環境の情報を見て、モノ選びをする人が多くなった

mySDG編集部:御社が取り組んでいらっしゃることのなかには、多分コロナ前とコロナ後で内容が変わってきていると思いますが、これまでのやり方を変えたのでしょうか?
酒井:弊社はコロナ前と後で、ほとんど事業のやり方を変えていません。ただ、自分が使ってるモノが、どこから来ているか、自分に「どういいか」だけでなく、「この商品が環境にどういいか」など別の目線を持って商品を選ばれる方が増えたと思います。そのときに弊社のプロダクトを選んでいただけることが多くなってきたという印象を持っています。
mySDG編集部:最近、確かにオーガニックとか「素材重視」でモノを選ぶ方が多いと思いますね。
未利用資源のプロダクトの認知度を上げ、より多くの方に良さを知ってもらいたい

mySDG編集部:事業を運営する上で、困難だったこと、続けてみたら結局良かったエピソードを教えていただいてもよろしいでしょうか?
酒井さん:弊社は、休耕田に限らず未利用資源といわれるものを、アップサイクルをして人々に使っていただくということを目指している会社です。最初のうちは、そのコンセプトが理解しにくいこともあり、苦労しました。
mySDG編集部:それは、対お客様ですか、対取引先の方ですか?
酒井さん:どちらもですね。10年前は、BtoCでもBtoBでも、由来のわかるエタノールという商品もありませんでしたし、私たちが取り組む、事業の中身や背景をご理解いただくのに結構時間がかかりました。
mySDG編集部:御社では、スキンケアなどのコスメを作っていらっしゃいますが、どの商品が一番先に出されたものなんでしょうか?
酒井さん:最初に出したのは自社ブランドの奥州サボン(洗顔石けん)です。洗顔石けんを最初に出した後、エタノールを使った商品を販売しました。私たちのオーガニックエタノールは、肌が弱い方でも比較的使いやすいと仰って下さることがあります。肌触りは評判が良いですね。
mySDG編集部:軸を変えずに新しいプロダクトを生産、提供するといった取り組みをされていると思いますが、今後、御社がチャレンジしたいこと、取り組みたいことについて教えていただいてもよろしいでしょうか?
酒井さん:これまで休耕田だったところで栽培したお米を使っていますが、それ以外にも色々な未利用資源を使っていきたいと思っています。色々な場所で、未利用資源からできたプロダクトが、多くの方の目に触れられるようにしたいと思います。
株式会社bajjiさんとご一緒に作った商品・アロマディフューザーがあります。こちらは休耕田を再生し収穫したお米・未利用資源を活用していますので、このような商品が増えるといいと思います。
mySDG編集部:酒井様からほかに伝えたいことはございますでしょうか?
酒井さん:SDGsに関連することで言いますと、最近、「B Corp」という認証を取りました。「B Corp」とは、環境や社会への配慮とインパクトの追求、地域性やダイバーシティへ配慮した従業員をはじめとするすべてのステークホルダーとの関係性構築、経営の透明性、事業の持続可能性などにおいて優れた、公益性の高い企業のみに与えられる国際的な認証制度です。こういった形のビジネスがあることを知っていただきたいと思っています。
mySDG編集部:例えば、ビジネスの広げ方としてオンラインなど色々なツールがありますが、酒井様が今考えていらっしゃる拡散のやり方はどういったものでしょうか?
酒井さん:インスタなどのSNSを使いながら、色々な情報提供をしています。私たちが考えていることをお伝えしながら、多くの方にプロダクトを手に取っていただきたいと思っています。。
mySDG編集部:本日はありがとうございました。
株式会社ファーメンステーションが運用しているSNS
ファーメンステーション公式インスタグラム
ファーメンステーションによる実験型プロジェクトPUKUPUKU POTAPOTAの公式インスタグラム
この取り組みが参考になりましたら、ぜひいいね・シェア拡散で応援をお願いいたします🙌
mySDGへの取材依頼・お問い合わせは mysdg.media@bajji.life までお気軽にご連絡ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
