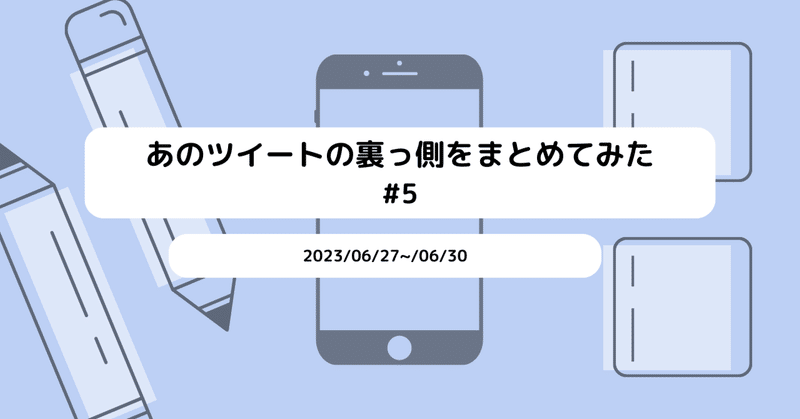
#5 あのツイートの裏っ側をまとめてみた
#5を投稿しました
こんにちは。ムーさんと申します。
『あのツイートの裏っ側をまとめてみた』の#5となります。
この記事は、私がTwitterで日々呟いているツイートについて、少し掘り下げたり、どんな考えが含まれているのかだったりをあーだこーだ書いてみる、というものになっています。
インプットよりは、「読み物」としてご覧いただければと思います。
日記の感覚で投稿していて、そこまで大袈裟に考える?というレベルのものもあるので、少しでも暇つぶしになれば嬉しいです!
※構成や書き方などに不慣れなところがあるかと思いますので、ご了承くださいませ・・・
※1週間全てのツイートではなく、いくつかをピックアップしたものになります(プライベートなものを深掘りしてもしょうがないので)
◎自分のキャパがフォロー数に見合っているか
最近フォロワーが減ってる。でも理由は分かっていて、フォロー数を整理したから。長期間ツイートがなかったり、自分の仕事や職種に関連してないと思うアカウントのフォローは外しました。仲良くなる機会もなく渋々整理しましたが、純粋に1400ものアカウントを見るのも不可能なので致し方ないかな🤔
— ムーさん(26)@Webディレクター4年目 (@yattoshussya) June 27, 2023
Twitterを始めてから2年ちょっと経ち、フォロー数を改めて見たら、
・こんな数のアカウント見切れてない
・これって運用としてどうなの?
と思い、フォロー数を少し整理した時のツイート。
整理自体は1ヶ月ほど前に粛々と進めていました。
それに伴い、少しずつフォロワー数が減ってきており、SocialDogで見てみると、私がフォロー解除したアカウントがほとんどでした。
本来、自分がフォローしている全てのアカウントの方々とちゃんとコミュニケーションを取っているのであれば、こんなことせずに済むのですが、実際のところはできていません。
(何千、何万とフォローされている方って、全てタイムラインを見ているのでしょうか?)
今回、なぜフォロー数がこんなに増えてから、後々整理するという行動に至ったか。
それは、自分がフォローされた後にリムられないようにフォロバをし、フォロワー数をキープするという、「とりあえず」という気持ちでフォローしていた背景があったからです。
つまりは、自分のフォロワー数に固執していたことが原因ですね。
これに気づき、なんとなく釈然としない自分がいました。
実際整理をしていると、自分の仕事の業界と全く関係ない方が多数いたり、「なんでフォローしたのか」が自分でもわからないということがありました。
加えて、全然ツイートが更新されていない方も多かったです(過去に仲良くさせていただいていた方は復活を願って、フォローしたままにしています)
こうやって見ていくと、フォローする意味について考えるようになります。
Twitterを見る時間は限られているので、やはり「この人のツイートを見たい」と思うアカウントでフォローをいっぱいにした方が、Twitterを見る時間に意味を持たせやすいので、そういう方向性が良いかなという結論になりました。
自分がフォローしたアカウントをしっかり見切れるかというキャパもありますからね。
ただ、整理したところで、いまだにやり取りにすら至っていない方々は数多くいます。
なので、今回のツイートをしたからには、「じゃあそのフォローした方々全員と仲が良いんだよね?」と言われかねないので、いいねだけに留めず、積極的にコミュニケーションを取ろうと思っています。
◎マニュアルは万能ではなく、口頭が全てでもない
おはようございます☀
— ムーさん(26)@Webディレクター4年目 (@yattoshussya) June 28, 2023
作業内容を口頭で細かく確認すると、やっぱりテキストにない情報が出てきたり、実は例外のパターンだったなんてことが発覚したりする。あとは1人じゃなく仲間の合意を得ることで不安がなくなる。テキストは楽だけど、楽な分しか頭に入らない。詳細は話をして理解した方がいい🤔
最近新しい案件業務がスタートしました。
マニュアルなどをたくさん読んで準備していたものの、手を動かそうとしても進まず、結局知っている人に口頭で進め方を確認して、ようやく手を動かせるようになったというツイート。
テキスト情報だけをもとに業務に入り込むのは限界があるということがよくわかった瞬間でした。
特定の用語や言い回し、大まかな流れといったものは、テキスト情報でもカバーできると思うので、わからない時の手引きとして活用することができますが、読むだけのインプットになり、理解は浅くなります。
背景にある意図を理解したり、応用につなげるということも難しくなりがちだと思います。
「結局やってみないとわからない」というケースが多いと思いますが、全てを一から手取り足取り教えてもらうのはとても効率が悪いので、マニュアルが存在します。
ただ、マニュアルを読んでもわからないからと言って何でもかんでも口頭で教えてもらうのも忙しい相手の時間を奪ってしまうことになります。
なので、そのような手間を極力減らすために、自分の力でインプットしたり、理解度を少しでも上げられるよう、努力して学ぶ姿勢はとても大事だと思います。
社会人ならこういう工夫はできるようにしたいところです。
仲間の合意を得ることができる、というのもとても大きなメリットだと思います。
相談をして「それでOK」という一言があれば、こちらも安心して業務を進めることができます。
初めての業務は誰しもが、「これで良いのか」という不安を抱くので、しっかり確認をして、合意を取った上で進めるというコミュニケーションはとても大事だと思いました。
◎誰もが同じ行動を取れるとは限らない
同じチームの人とお客さんも交えた30人くらいの規模の集まりに行ってきました。ただ知らない人がたくさんいたので当然のように人見知り。こういう場で仲良くなるように動いたり、話しかけたりするのやっぱできない。周りと違ってその場を楽しめない自分が間違ってるように錯覚してしまう🤔
— ムーさん(26)@Webディレクター4年目 (@yattoshussya) June 29, 2023
私の性格上、人見知りなので大勢の人がいるパーティーのような場があまり得意ではありません。
先日、ツイートの通りの場に参加してきたのですが、初対面の人が多すぎて人見知りを発揮しまくった日のツイートとなります。
立食形式のちょっとしたパーティーのようなものをイメージしていただければと思います。
こういう場の立ち回り(?)において、人それぞれ性格が出ますね。
どうして仲良くなるように動いたり、話しかけたりできないのか考えてみたのですが、失礼を承知で言うとわざわざこういう場で聞きたいことがないからです。
(誰とも話さないということは流石にしていないですし、お客さんへの挨拶もしています)
仕事を円滑に進めるために仲良くする会だろ!、という意見もわかるのですが、それは仕事内で工夫すれば、仕事は円滑に進むのではないかと思うのです。
こういう場では、積極的に話しかけることが正しいみたいな雰囲気が確立されている気がするのですが、誰もがそう易々と動けるわけではないのです。
でもそういう人が少数派となり、周りとの違いに直面することで、自分の在り方を自己否定するような感覚になります。
自分の肌で感じていることには素直でいたいですし、これまでに何回かこういう場はありましたが、それによって特に不利益があったこともないです。
結局どう振舞うのが正しいのかわかりませんが(振舞うという表現も等身大の自分じゃない感じがして好きじゃないのですが)、無理をする必要はないのかなと結論づけました。
人によって仲良くなる方法はそれぞれですし、こういう場は一切参加したくない派の人もいると思うので、他の人に無理して合わせず、自分らしさを保つことを最優先にしたいなと思いました。
◎「仕事は楽しい」と「仕事は面白い」、どっち派?
おはようございます☀️
— ムーさん(26)@Webディレクター4年目 (@yattoshussya) June 29, 2023
ずっと考えてるのですが、仕事が楽しいという感覚が僕にはよくわかりません。仕事と楽しいが結びつかないというか。いちいち楽しいか楽しくないか考えもしない。なので聞かれても回答に困る。ただ、強いて言えば仕事は面白いという感覚が圧倒的に強いです。ひねくれてるのかな🤔
正直、少し扱いづらい内容のツイートです。。
「仕事は楽しくあるべき」という考えの方が多い気がしますし、それはもちろん理解できますが、自分にはない感覚なので。
こういうことを言うと結構「えっ?」と思われそうでしたが、リプで共感していただけた方がいたので、間違っていないことは確信できました。
「楽しい」という感覚がないので、「仕事、楽しい?」という質問が苦手です。
「なぜその質問をするのか」がわからないのです(先日同じことを聞かれましたが、気を遣って「楽しいです」と答えました。笑)
個人的に思うこととしては、「楽しい」というのはワイワイやってる様子をイメージするのですが、そのワイワイが楽しいのであって、実際の仕事の中身とは結び付かない切り離されたものなのではないかと思います。
おそらくここに大きな違いのポイントがある気がしています。
一方で、ツイートにもある通り、私がこれまで3年ちょっと仕事をしてきて思うのは、「楽しい」という感覚ではなく、「面白い」という感覚が圧倒的に強いということです。
例えば「なるほど!」という発見があったり、スケジュール内の進行がちょっとしたゲームのようだったり、仕事を自分でコントロールしている感覚がある、といった瞬間に「面白い」という感覚が生まれます。
他にも、お客さんへの説明内容を考えたり、ツールを使って黙々と作業していたり、資料をどう作成しようか考えたりするのも「面白い」のです。
仕事をしている時の自分と言われると、このようなことを思い浮かべます。
逆に言うと、上に書いたようなそれぞれの瞬間に「楽しい」という感覚が入り込む余地がないようにも感じるのです。
だからこそ、「楽しい」という感覚がわからないのだと思います。
かといって、「仕事が楽しい」という感覚がある人を否定する気は全くないです。
一応、私も社会人になってそういう感覚は生まれるだろうなと思っていたのですが、蓋を開けてみると「面白い」に全てが集約されていたというだけのことです。
双方の考えの良し悪しを決めるのは難しいですからね。
もし同じような感覚を持っている人がいたら、お話を聞いてみたいです。
最後に
#5 、いかがでしたでしょうか?
何か一言でも頭に残ったり、読んでよかったなと思っていただけたらとても嬉しいです。
いつも読んでくださる方々もありがとうございます。
毎週投稿予定ですので、来週もぜひご購読いただければと思います!
もしよければ、私のTwitterアカウントもフォローしていただけると幸いです!
また、noteや記事作成に詳しい方、アドバイス等いただけると嬉しいです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
