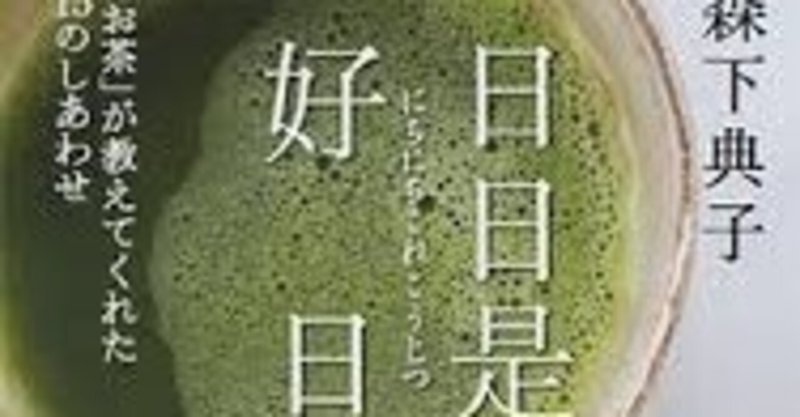
書評 茶道について書かれた小説。少し哲学っぽい。

樹木希林さんなくなられた時、映画を見た。
原作本があるのは知らなかった。
映画の内容は、半分くらい忘れたが、とても深く。
この小説も深い。
茶道について書かれた小説だ。
ある大学生が茶をはじめ、そして、ある感覚を掴む話し。
それは茶道の哲学のようなものだと思う。
それは禅にも似ていた。
まず、形を覚えなきゃいけない。
かなり厳格だ。面白くない。ちょっと抱いていたイメージと違う。
「わけ なんか、 どう でも いい から、 とにかく こう する の。 あなた たち は 反発 を 感じる かも しれ ない けど、 お茶 って、 そういう もの なの」
ものを学ぶとは・・・
もの を 習う という こと は、 相手 の 前 に、 何 も 知ら ない「 ゼロ」 の 自分 を 開く こと なの だ。 それなのに、 私 は なんて 邪魔 な もの を 持っ て ここ に いる の だろ う。 心 の どこ かで、「 こんな こと 簡単 よ」「 私 は デキ る わ」 と 斜 に 構え て い た。 私 は なんて 慢心 し て い た ん だろ う。 つまらない プライド など、 邪魔 な お 荷物 でしか ない の だ。 荷物 を 捨て、 からっぽ に なる こと だ。 からっぽ に なら なけれ ば、 何 も 入っ て こ ない。
やり続けているうちに、こうなってくる。
なじん で しまえ ば、 それ が 普通 に 思え た。
これが大切なのだ。
決まり どおり の お点前 が、 なんだか 着 なれ た 服 の よう に 見え た。 先生 が 服 を 着 て いる のでは なく、 服 が 先生 の 身 に 添っ て いる……。
お茶とは何か・・・
世の中 には、「 すぐ に わかる もの」 と、「 すぐ には わから ない もの」 の 二 種類 が ある。 すぐ に わかる もの は、 一度 通り過ぎれ ば それで いい。 けれど、 すぐ には わから ない もの は、 フェリーニ の『 道』 の よう に、 何度 か 行っ たり 来 たり する うち に、 後 に なっ て 少し ずつ じわじわ と わかり だし、「 別もの」 に 変わっ て いく。 そして、 わかる たび に、 自分 が 見 て い た のは、 全体 の 中 の ほんの 断片 に すぎ なかっ た こと に 気づく。 「お茶」 って、 そういう もの なの だ。
お茶をやっていると季節の感覚が違ってくる。
やる前は「暑い」と「寒い」しかなかった。
しかし、お茶を深めると季節がシャープになってくるのだ。
雨についての描写がおもしろい。
ど しゃぶり の 日 だっ た。 雨 の 音 に ひたすら 聴き入っ て いる と、 突然、 部屋 が 消え た よう な 気 が し た。 私 は ど しゃぶり の 中 に い た。 雨 を 聴く うち に、 やがて 私 が 雨 そのもの に なっ て、 先生 の 家 の 庭木 に 降っ て い た。 (「 生き てる」 って、 こういう こと だっ た のか!) ザワザワッ と 鳥肌 が 立っ た。
この言葉もおもしろい。
人 には、 どんなに わかろ う と あがい た ところ で、 その 時 が くる まで、 わから ない もの が ある の だ。 しかし、 ある 日、 わかっ て しまえ ば、 それ を 覆い 隠す こと など でき ない。
お茶の御馳走とは・・・・
「お 茶席 に 入っ たら、 まず、 床の間 の 掛け軸 と、 花 を 見 なさい ね。 お茶 の『 一番 の ごちそう』 は、 なんと いっ ても、 掛け軸 な ん です からね」 「…… ごちそう?」
お菓子でないところがいい。
今 という 季節 を、 視覚、 聴覚、 嗅覚、 触覚、 味覚 の 五感 ぜんぶ で 味わい、 そして 想像力 で 体験 し た。 毎週、 ただ ひたすら。 やがて、 何 かが、 変わり 始め た……。
本書のモチーフ。茶道はこれだと僕は思った。
道 は 一つ しか ない。 今 を 味わう こと だ。 過去 も 未来 も なく、 ただ この 一瞬 に 没頭 でき た 時、 人間 は 自分 が さえぎる もの の ない 自由 の 中 で 生き て いる こと に 気づく の だ……。
今、この瞬間を生きる。
このような考え方は禅に近い。
今、この瞬間の感覚を忘れずに生きよう。
2021 12 16
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
