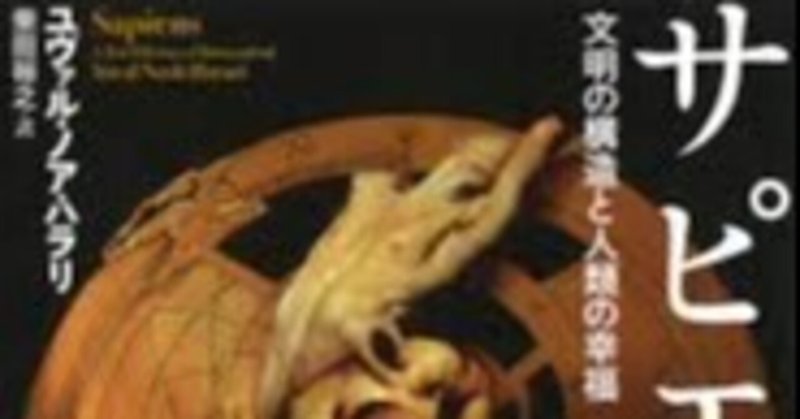
感想 サピエンス全史上 ユヴァル・ノア・ハラリ 人類史を新しい切り口で論じた歴史書、なかなかに興味深い内容でした。
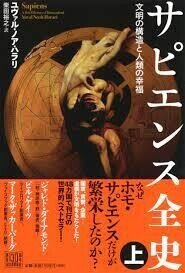
世界史や人類史についてかかれた本は無数にあるが、本書はこれまでとは違う切り口で語られているところが面白い。印象に残った部分だけ少し紹介してみたい。
我々、人類、ホモサピエンス以外にも人類はたくさんいた。ネアンデルタール人などである。しかし、たくさんいた人類の中で生き残ったのはホモサピエンスだけです。同化、つまり、婚姻によって吸収したという説もあるが、虐殺したという説も有力です。
さらに、著者は言う。アメリカ大陸やオーストラリア大陸で多数の動物が人類が辿り着いたことにより絶滅していると。
史上最大の危険な種
と人類のことを言っています。
生態系の大量殺人犯
とも言っています。それは現在進行系です。
一つの結論に必然的に導かれる。それは、サピエンス移住の第一波は生態学的惨事をもたらし、それは動物界を見舞った悲劇のうちでも、とりわけ規模が大きく、短時間で起こった、というのものだ。最大の被害者は毛皮で覆われた大型の動物たちだった。認知革命のころの地球には、体重が50キログラムを超える大型の陸上哺乳動物がおよそ200属生息していた。それが、農業革命のころには、100属ほどしか残っていなかった。ホモ・サピエンスは、車輪や書記、鉄器を発明するはるか以前に、地球の大型動物のおよそ半数を絶滅に追い込んだのだ。
初期の人類の話しで気になったのは、骨髄を食べていたことです。
つまり、肉とかは大型のライバルが食べ、残った残飯である骨髄を人類は食べていたのです。
さらに、もう一つ。火の発明。これは調理をすることにより、消化が良くなり腸が短くて良くなった。つまり進化した。=脳の巨大化。
もちろん、それだけで人類が 生態系の大量殺人犯 になれるほど強くなれたとは思えません。
そこに何かがあった。
仮説として本書で挙げられているのは 認知革命。
現実には存在しない虚構(フィクション)を信じ、語ることのできる能力を得たことで集団化が可能になった。前半のポイントはまさしくそこだと感じました。
この力の獲得により、人類は集団化が可能になった。ネアンデルタール人の集団は少数なのに対して、人類は大きな集団を形成できたとのことでした。
一対一で喧嘩をしたら、ネアンデルタール人はおそらくサピエンスを打ち負かしただろう。だが、何百人という規模の争いになったら、ネアンデルタール人にはまったく勝ち目がなかったはずだ。彼らはライオンの居場所についての情報は共有できたが、部族の精霊についての物語を語ったり、改訂したりすることは、おそらくできなかった。彼らは虚構を創作する能力を持たなかったので、大人数が効果的に協力できず、急速に変化していく問題に社会的行動を適応させることもできなかった。
猿から直線的に進化して人間になったというのは幻想です。実際は、様々な人類がいた中で、私達ホモサピエンスだけが生き残ったのでした。
認知革命がが発展し・・・。
神話とか・・・により。さらに集団が大きくなっていった。
貨幣の発明とか・・・。
目に見えない何かを信じる力。虚構を信じる力。貨幣などは、その典型例です。
貨幣は信用から成り立っていて、あれは虚構です。でも、共同主観的な存在でもある。みんなで信じる。だから、それは通用する。価値がある。
それが認知革命です。
農業革命についての僕たちの知識は、本書の内容と相反する所がある。
狩猟生活を辞めて農業を始めたことで、人は豊かになり集団を形成したと教科書にはあると思うが、それはいいことずくめだったのだろうか?。
作者は否と言っている。
むしろ、人は小麦の奴隷になった。
史上最大の詐欺
研究によって太古の生活が明らかになるにつれ、刺激的な仕事、短い労働時間、健康的な食生活、飢えや病気のリスクの少なさなどから、多くの専門家が、農耕以前の狩猟採集社会を「原初の豊かな社会」と定義するに至った。
狩猟生活の時のほうが人類は行動範囲も広く、知恵も発達した。いろんな知識がないと狩猟はできない。
農業は、狩猟に比べると頭を使わない。狩猟時代のほうが沢山の種類の栄養を摂取していた。
農業は河の氾濫や飢饉というリスクも内在している。
しかし、一旦、楽をすると元には戻れなくなる。人類は農耕生活をするしかなくなった。
サピエンスは「農業革命」の被害者でもあるが、数多くの動物たちを残酷な形で家畜化してきた加害者でもある
農耕による富の蓄積が、より大規模な「虚構」のネットワークを生み出した。
国が生まれる。
次に、階級の問題だ。
ヒエラルキーは秩序にとって重要な役割を果たし、それがあるからこそ見ず知らずの人々が効率的に協力し合える。人員が増えて社会が複雑になるほど差別が必要になる。
このようにして階級が生じた。
歴史には方向性があると著者は言っている。
世界は統一に向かっているのだそうだ。
地球上には異なる人間社会がいくつ存在したのだろう? 紀元前一万年ごろ、この星には何千もの社会があった。紀元前2000年には、その数は数百、多くても数千まで減っていた。1450年には、その数はさらに激減していた。
そこで、貨幣の問題が出てくる。
宗教的信仰に関して同意できないキリスト教徒もイスラム教徒も、貨幣に対する信頼に関しては同意できる。なぜなら、宗教は特定のものを信じるように求めるが、貨幣は他の人々が特定のものを信じていることを信じるように求めるからだ。
虚構の延長線上に、この貨幣はあり、貨幣は種族を超えてみんなに信頼されるものである。
貨幣により人はさらに統一される。
そして、帝国が出てくる。
中国の支配階級は、近隣の人々や外国の臣民のことを、自らの帝国が文化の恩恵をもたらしてやらなければならない惨めな野蛮人たちとして扱った。天命が皇帝に授けられたのは、世界を搾取するためではなく、人類を教育するためだった。ローマ人も、野蛮人に平和と正義と洗練性を与えているのだと主張して、自らの支配を正当化した。
外の集団を自らの内に取り込もうとする「帝国」は、過去2500年間、世界でもっとも一般的な政治組織だった
帝国主義や差別を若干、肯定するように述べている点は気になったが、それが歴史の必然として存在したのは事実であるのだから、そうなのだろう。
2022 10 8
* * * * *
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
