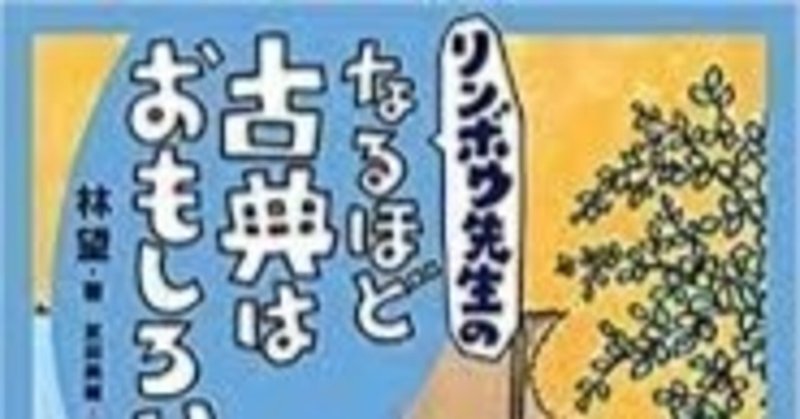
感想 リンボウ先生のなるほど古典はおもしろい! 林望 古典の魅力がダイレクトに伝わってきた。学校では教えてくれない古典の授業でした。

僕は古典が好きだった。その理由は、テストで点数が取りやすかったからだ。
歴史好きなので、古い文学も嫌いじゃない。
そんな僕が、本当の意味で古典は面白いと感じたのは、大学で 枕草子の講義を受けた時だった。
清少納言の感性に驚いたのを記憶している。
本書は、古典の入門書です。
学校の授業では教えてくれない古典文学の魅力を
有名な作品をダイジェストで紹介する形式で教えてくれます。
最初の歌に始まり
伊勢物語、源氏物語、平家物語、徒然草、土佐日記、枕草子、風姿花伝などなど・・・
まず、歌なのですが
これはSONGではなく 5 7 5 の百人一首とかに出てくる歌です。
もともと うた と うたう 歌う うったふ 訴ふ とは同族の言葉で、人が神様に思いを訴え、お願いし、祈る
だから、声に出さねばならないのです。
黙読では伝わらない。
和歌を、さっと二三秒で黙読してしまうと、子規のような批判が生まれる。しかし、平安時代風に、のどかにながながとうたいながら、その時間軸に沿って、一つ一つ理解し、味わいながら受け取っていくと、こういう歌の良さがふっと腑に落ちる
二つの歌を例にとって説明しているのですが、その説明が感動ものでした。
短い言葉の中に、見事にたくさんの気持ちや情景が凝縮されています
それは言葉だけでは理解できないし、京都の歴史やら風俗やら時代背景やらを理解して、初めて、この歌の本当の価値がわかるということなのです
この第一章だけでも、読む価値があると思います。
おもわず スゲー と叫びたくなりました。
いわば 歌 とは、詩をよく味わうための音楽装置であって、本質的に、美しい音楽的要素とゆっくり流れていく時間が必要なのである。
だから、和歌だって、文字に書かれたものを黙読するだけでは、その良さは、味わい、美しさ、悲しさなどが切実に感じられるはずがないのである。
僕が感じたのは、黙読は歌詞を読むのに似ていて
声に出してゆったりと読む行為は、音楽に歌詞をのせて聞く
部屋でCDを聞くみたいな感じで、文字だけでは味わえない感動みたいなのがある
それは和歌にもあるということです
土佐日記も面白くて、ただの旅行記ではなく、最初と最後が大切
この主人公は、土佐に赴任前に生まれた娘を土佐で無くしている
その悲しみの感情が伝わりました。
都の家に帰ると荒れ果てて、立派だった松も抜け落ちていて
その傍らで幼い松が・・・
たぶん、それに幼い娘を重ね合わせて・・・・
伊勢物語は、ある高級貴族と斎宮の女性との恋
斎宮は、伊勢神宮の神を奉る場所。そこに使える女性です。
つまり、修道院の女性みたいなもの
神様の女
どんなに好きでも 無理です。
そういう悲恋を描いた話しでした。
ここでも和歌が威力を発揮しております。
源氏物語が高く評価されている理由もわかりました
ただのモテ男の話しだけではなく、そのディテールの細かさがすごいのです
リンボウ先生の少し砕けた解説が面白く、古典作品を理解するきっかけの本になるのではと感じました。
2023 2 4
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
