
短篇小説『軀と歌だけの関係』
或る合唱団の公演に欠員が出て、その音域パートがどうしても足りないということで急遽、私は呼ばれた。
ながい病院暮しを終え、願ってもない仕事であった。
かつての仲間も聴衆も、私自身ですらも、私の音楽を忘却していた。
それでも。ハ長調のひとつも響かぬ、浮世より隔離された空間で、声だけは衰えぬよう、心がけてきた。
当日朝。
その県でいちばんの都市。
リハーサル。
まだ誰もいない客席が紫の扇となってひろがる、岩のようにごつごつとした白壁の、ホール。歌声をあてる。
♪モンゴルフィエモンゴルフィエモンゴルフィエ
とても心地好く実感を伴い歌っているのに、声は此方の腹からではなく、まるで天上の隙間より、極楽の光となって降るように感じ。
合唱は男声のようで、何か枠から外れた手触りのある、しかし混声とも明言し難い、不可思議なハーモニーだった。重厚ななかに、所謂ボーイだろうか、綺麗なソプラノが、たしかに、まざっている。それは透明な紗となって、空間を眠らせるかの如くつつみ、或は蛹より誕生したばかりの羽の如く瑞瑞しく舞い……いずれにせよ、融けこみもせず、分離もせず、ヴァーチャルの恋人みたいに絶妙な距離をたもつ。
合唱団は姿こそ、髪はみじかく化粧っ気もなく、髭を青青とさせたりシャツの胸もとを繁らせたり、喉仏を隆起させたり腹を膨らませたりした中年男、どう見ても男たちが、並んでいるのだが……
「『おてんば刑事は18才』シリーズのキリコ役、誰がいちばん好き?」
リハーサルを終え楽屋で、団員のひとりに話しかけられる。若い頃のニキビ跡が頬にはしる、おろした前髪、笑うとなくなってしまう眼、すこし並びのわるい歯に愛嬌のある男だった。どう見ても男。
質問からして、同世代だと悟ったのだろう、実際私はテレビドラマ『おてんば刑事は18才』を子供の頃ずっと観ていたし、ひさびさの歌仕事ながら声の調子も化粧台の鏡に映る顔色もよいことですっかり上機嫌になり、
「それは初代のアキカワアキエでしょう。僕は今なおファンですよ」
と返す。
楽屋では衣裳への着替えを、いったいいつ上も下も脱いだものやらわからない、まるで化けるみたいに済ませたひとが、ちょっと眼を離した隙に殖えてゆく。赤ネクタイに青スーツという、前世紀の面白げでいてさほどでもない漫才師を彷彿させる恰好。皆突っ立って身振り手振りまじえ喋っているから、よけいにそう映る。よく見ると狸顔と狐顔にわかれるところも。ボーイっぽい声は何処からも聴こえぬ。
私は衣裳を支給されていなかったので、どうしたものかときょろきょろしていたら、さっき『おてんば刑事は18才』の話題で和んだ男が、
「俺の予備あるから貸すよ」
と。顔や軀は狸だけど眼が狐かな、と男をぼんやり見遣る。おおきな背を猫のように屈め、やたらちいさな鞄から結び目のついた手拭みたいなものを出す。それを指でぴんっ、と天に弾くと、結び目が解け、ぱんっ、と、皺ひとつなく型の綺麗なジャケットがひろがった。ピンク地に、チェック柄。
「青の無地じゃないんですか?」
「パートによって色が違うんだよ。ほら、着せたげる」
福福しい狸のジャケットが病みあがりの痩せた私に合う筈はなかったが。男が私の肩を腕を、背を撫でると、布地も柄も嘘のように私に沿ってゆき。長過ぎる袖もちぢみ。
「似合うよ」
終っても未だ両肩を抱く、ジャケットごしにもつたわる掌の熱、鏡ごしの微笑みと視線は、『今日だけの同胞』では済まぬ空気を漂わせるが。果してそれはリアルな恋に似た好意か、もしくは化かそうとする悪戯心か。化粧台のあやとる光と影によって、ほんの1センチでもうごくと、男の印象はどちらにもころぶ。
ほかの狐や狸はまだ漫才をしつつ、此方もちらちら見ている。もはや青いスーツばかり。
私の歌のパートは何処らへんだったか? 楽曲は譜面のかたちでなく、幼い頃の記憶めいた顔をして海馬のメモリーチップへと送信されているので、わからない。それが理由なのかどうかさえ、わからない。
一旦ホールを離れ。
ビルの地下食品売場で買い物をする。冷凍ものをいくつか買い、それ用のロッカーへと仕舞いにゆく。
いまどきは鍵など要らず、国に登録された己の指紋でロッカーを利用できる、と退院前に看護師から聞いていたのだが。
たしかに触れれば扉はひらくが、どういうわけか使用中の他人のものばかりで、凍ったキャンディーやら凍った炒飯やら、凍ったテディベアやら凍った燭台やら凍ったコビトワニやら凍った離婚届やら凍った骨壷やらが溢れだし床に落っこち、あたふたする。私は現世の人間として認識されていないのか?
ホールへの帰り道がわからなくなった。迷うわけが、と高を括り、左顳かみのエレキバン電話も右腕の湿布モニターも剥がして来ており、連絡手段がない。
ビルの最上階かそこらへゆけばよいのはたしかだが、エレベーターやエスカレーター、階段さえも何故か見当らずに、気づけば駅構内へ入りこんでしまっている。道を尋ね易そうな地方色あふれる弛みきった顔をした割烹着のおばさん(どう見てもおばさん)に声をかけるも。何を聞いたか忘れてしまうほど時間をかけ、上から下までじろじろと見られた末に。
「窓を御覧なさいな、ほれ」
そう言えば、ホールはおろかビル内にひとつも見られなかった窓。今見廻してもクローンの御影石とおぼしき磨かれ光る壁しかないが。脇にある売店のさらに脇、飲み干した牛乳瓶の詰まれたケースをおばさんがよっこいしょと退けると、現れたのは城への侵入者でも迎え討つような三角の狭間(さま)。
外から、生れてはじめてうける気がする秋風。髪を煽られ頬をうたれつつ覗くと。青空だけを背景に、ブレザーの少女(どう見ても少女)が飛んでいる。まるで巨大な指でぴんっ、と天に弾かれた風に。学生鞄を片手に、トーストでなく御醤油のボトルを口に咥え、白眼を剥き隈をたくわえ。真上へ飛ぶのに、髪とスカートを壊れた傘の如くひろげ。
余韻もなく視界から少女が消えたその次に、定年を過ぎたっぽい干からびたおじさん(どう見てもおじさん)が飛ぶ。ひろげる髪の毛はないかわりに、競馬新聞をひらめかせ金色の尿を漏らし散らし、ときどき煙草、と思いきや風船、と思いきやコンドームを咥え膨らませ。黒眼と餅のような下腹だけはどっしりと据わっている。
それ以降もあまり間をあけず次次、老若男女(どう見ても)が三角の狭間のなか、飛ぶ。飛ばされる。
「……いいかい、フラフラしてたら足もと掬われて、引力重力も効かなくなって、飛んでっちまうんだよ。あんたもせいぜい、歩いて足腰鍛えな」
おばさんの、歯が抜け肉の詰まったような声、嗄れたアルトが、バックグラウンドに響く。ふりかえると、もういない。
声に敏感になった耳が、駅の喧騒とは別の音を拾う。いくつも。何処から?
「……ここからだ」
ふたたび三角に聴覚を澄ませる。筒状の空間が外からの風に吹かれリコーダーみたいにポーと鳴る。それにまぎれ聴こえるのは……歌だ。飛んでいる人人が皆で、歌を紡いでいる。対流圏を成層圏を突き抜け、膨らみ過ぎたコンドームの如くぱんっ、と弾けて死なんとする人人の涎たらす唇が、おんなじ歌詞を綴っている。
♪オーギュストピカールオーギュストピカールオーギュストピカール
あらゆる声質と音域のまざった、ほんとうの意味での混声。
私は牛乳とフルーツ牛乳とコーヒー牛乳を売店で購入し、腰に左手を添え飲みながら、それらの音を家で骨董のレコードかアナログラジオでも嗜むみたいに、しばし聴く。ボーイソプラノの音だけは、聴こえなかった。
飲み過ぎ、トイレにゆく。
淵までミクロ単位で極めて清潔な、タイル煌く空間ながら、そこには便器が、ない。
かわりに、等間隔で円い、闇のように黒い穴が空いており。数メートルほど底には水が揺れている。壁に貼られた電光マニュアルによれば、『天井よりさがったワイヤーに背を凭せ掛け、穴を足で跨ぎ、ほぼ直立の態勢で穴へ尿を放つ』ものであるらしい。すなおに従い、衣類が濡れぬよう下半身裸となり、小用を足す。背中を僅かながら反らせるかたちのワイヤーがつめたく心地好く、尿の流線は噴水の小僧よろしく存外に麗しく映る。存外にとまらぬ尿を穴の闇は永久に吸いこむかの如く呑みつづける。歌のホールへ間に合わずとも、もうこのブラックホールでも別に良いんじゃない? という心地に傾いてゆき、そして……
「キャアアアアアアアア」
ソプラノをも超えた4000ヘルツの悲鳴が耳をつんざく。入口から現れた若い女(どう見ても女)と、真正面から向き合う。私がトイレを間違えたのか? そもそもこのトイレに性別があったっけ? と心は逡巡しつつ、とりあえず服をきて、逃げる。女はその間、三編みの赤い髪を火の如く逆だて、息継ぎもなしに大口をあけ金切り声をあげつづけていた。腹からの、楽譜に記せぬ域の、幼きガールの日に海馬へプログラミングされた儘みたいな叫びを、少しのブレもなく、3分間。歌手としては羨ましい。
とりあえず犯罪者扱いされては堪らない。離れなくてはと歩きまわり。
「フラフラ歩くんじゃないよ、いいかい、腹筋と、内転筋を意識するんだよ。天に首吊られるイメージ。顎ひいて」
と、割烹着のアルトおばさんが云ったような云わないような、兎に角軀の軸をぶらさず、脚をひらかず内股で、トップモデルきどって……実態はおそらく天に首吊り死んだ眼と、1秒8枚のアニメのようなうごきで、歩いた。結果健康か不健康かトラックを一周しただけのようで、もとのトイレ入口へ。女がまだいる。
女はメルヘンチックな赤くゆるい三編みとパーマ、青のパフスリーブ、ハイウェストのワンピース。眉は完全に抜かれ、虫の触角めいた一本線が左右ひかれ。翡翠色の眸は先刻まで冷凍のロッカーにはいっていたように微動だにせず、しかし零れおち割れてしまいそうにつぶら。さっきの悲鳴はサスペンスの舞台劇などで見栄えがしそう。
いまは優雅にベンチに腰かけ、ワンピースを捲りあげ想像より肉感的な左腿に貼った湿布モニターで、愉快げにテレビ通話している。
「……そうなの。旧型の男性器をつけてたわ。いまどきアナタ、天然記念物よねぇ。……しかもよ、ピンク地にチェック柄のジャケット。ええもちろん、あの合唱団の」
モニターにもきれいな女(どう見ても女)がいて、まるで鏡像のように、顎に指を添えつつ微笑む。
「面白そうねぇ。今日は公演日でしょ? 私も支度するから、観に行きましょうよ。この眼でしかとたしかめなくてはね」
ストレートの黒い髪と瞳に金属粉を蒔いたような光が宿り。やや鼻にかかった声は棒読み気味……嗚呼なんと、あれは、往年のドラマシリーズ『おてんば刑事は18才』で、2代目の主役だったナツカワナツミではないか。どう見てもナツカワナツミだ。ブレザーを着て刑事キリコを演じたあの頃と、何ひとつ変っていない……不自然なほどに。修復だろうか。
『この眼でしかとたしかめなくてはね』とは、刑事キリコの決め台詞だった。懐かしさに胸を詰まらせつつ、彼女は何を、『この眼でしかとたしかめ』に来るのか考える。明白なようで不明。ともあれナツカワナツミが合唱団公演に姿を見せるらしい。初代のアキカワアキエでないのは惜しいが……それを知り歩みだした途端、壁に非常階段のドアを見つけ、潜りこむ。それまでの喧騒が墨汁となって紙に吸われるみたいに消えてゆき、私の革靴の音だけが、嬰ト短調を歌うようにこだまする。ホールが何階か忘れたけれど、これでいつかはたどりつける。ピンクのジャケットを貸してくれたあの男は待っているだろうか。男はたしか
「俺、二代目が好き」
と云っていた。ナツカワナツミが来る、と教えたら狂喜することだろう。あの男、どう見ても男のあの男には、旧型の男性器がついているだろうか。
靴音のほかに何やら変ホ長調でカサカサと音がして、ジャケットに触れると。右のポッケに再再再再再生紙の紙片があり、とりだす。いつ仕こんだものやら。指でぴんっ、と弾くとぱんっ、とひらき。そこにはきれいな手書き文字が、音符よろしく連なっている。手で文字を書くだなんて、『いまどき天然記念物よねぇ』と云われかねない、金も時間も費やす酔狂な趣味人だけの世界なのに。
「いま君がこの手紙を読んでいるということは、まだ君は戻ってきていないんだね。俺がいまどれだけ、悦びと淋しさを胸に秘め焦がしているか、わかる? 君が不審がっていたとおり、ピンク地にチェック柄のジャケットは、君と俺しか着ない。俺たちふたりだけが、担う声のパートがあるんだ。狸や狐が化かしたんじゃない、信じて。信じてほしい。やっと出逢えた。ボーイソプラノを失って、男声にもなりきれぬ儘この合唱団にはいって四半世紀、やっと、俺とおなじ音を歌う君に出逢えたんだ。なのに君は、何処にいるんだ? おなじ音、おなじスーツ、おなじ魂、おなじ性器をもつ運命の片割れ、はやく戻ってきておくれ。天より極楽の光降りそそぐ舞台へと、はやく。ふたりで立つんだ。ふたりで歓喜と悲痛の叫びをはなつんだ。旧型のセックスのように。旧型の君を知って旧型の孤独を知った俺は、もう君なしでは、歌えない。青スーツの連中とハーモニーを築けない。この儘舞台に出ようものなら、客席から一斉に鶏や鶉や駝鳥の卵をヴァーチャルで投げつけられるだろう。そうなる前に、嗚呼はやくいとしの」
私は最後まで読まず、まるめ、棄てる。左のポッケにも案の定はいっていた紙片と一緒に。カワリハイクラデモイルクセニ。面と向かって狸の太鼓腹に貼った湿布モニターで告白して貰う方が、まだマシだった。螺旋階段の渦の底へ消えてゆく。
眼の隅にカラフルなものが入った気がし、見れば。あの合唱団のポスターが、壁に貼られている。今日の告知ではなしに、相当昔のものだろう、おそらく天然紙による、ピクリともうごかぬ団員たちの像が、地方選挙をとっくに惨敗で終えた候補者たちも同然に、くすんでおり。
メンバーは、おそらく全員現在の儘だが、着ているスーツは青とピンクでなく、鶏や鶉や駝鳥の卵をリアルで被ったみたいな、オレンジとイエロー。
今より若くほそく、狸顔にも狐顔にも、漫才っぽさや人を化かす奸智にたけた風情はうすく、小動物的な愛らしさが薫る……
というだけでなく。『どう見ても男』っぽさを甚だしく欠いた、または元から存在しなかったと云わんばかりの人物が、ぽつぽつ見うけられる。顔のパーツをゴシック体のようにメイクした者、髪が肩よりながくのびメビウスリングのようにカールした者、スーツから毛のない綺麗な胸の谷間を剥きだす者、レザーのタイトスカートから蛇のように有り余る脚をのばす者……例の男に到っては、合唱団の名前がなければ凡そ誰だか判らないレベル。アキカワアキエでもナツカワナツミでもなく三代目のフユハラフユナにちょっと似ており。ニキビ跡でなくニキビがある。ボタンを外したジャケットの下はダンスコスチュームで、布ではなく金属のフリンジがキラキラと、バストトップや股間をかくしていた。
私はいま何階にいるだろう。手がかりとなる気配も匂いもない。感覚としては、どっちつかずの中間あたり。
音のしない儘に、底よりか、或は天よりか判然とせぬ突風が、何処の円三角四角の狭間から紛れこんだものやら知れぬ金の枯葉とともに、吹き、うねり、まわり、打ちつけ押し寄せ、あばれる。リコーダーの如き縦長の空間で、穴はかならず有る筈なのに、何故無音なのだろう。
無音であるかわりに、気流の層が虹のように、ありもしないステンドグラスから零れるように、半透明の美麗な色を纏い。
『おてんば刑事は18才』の刑事キリコが、『この眼でしかとたしかめなくてはね』と、真犯人に対峙する際、このような視覚効果がかならず使われていたのを、海馬データより昨日のことみたいに思いだす。冷凍ロッカーに有るような凛としたまなざしに虹を粧い、ストレートの髪をプリーツスカートを、オーロラの如く端正かつ艶やかに靡かせ……
今の私には、しかと向きあう敵も味方もいない。髪はもとの型を忘れるほど荒れ狂い顔にはりつき、今なお刑事キリコに憧れ穿いているプリーツスカートも只只不恰好に、風に四方八方振られ。散散弄ばれた挙げ句、壊れた傘の如く捲れあがり、表裏反対に。丸見せの毛糸ズロース。
「いやッ」
と、思わず出たボーイソプラノの声が、反響する。
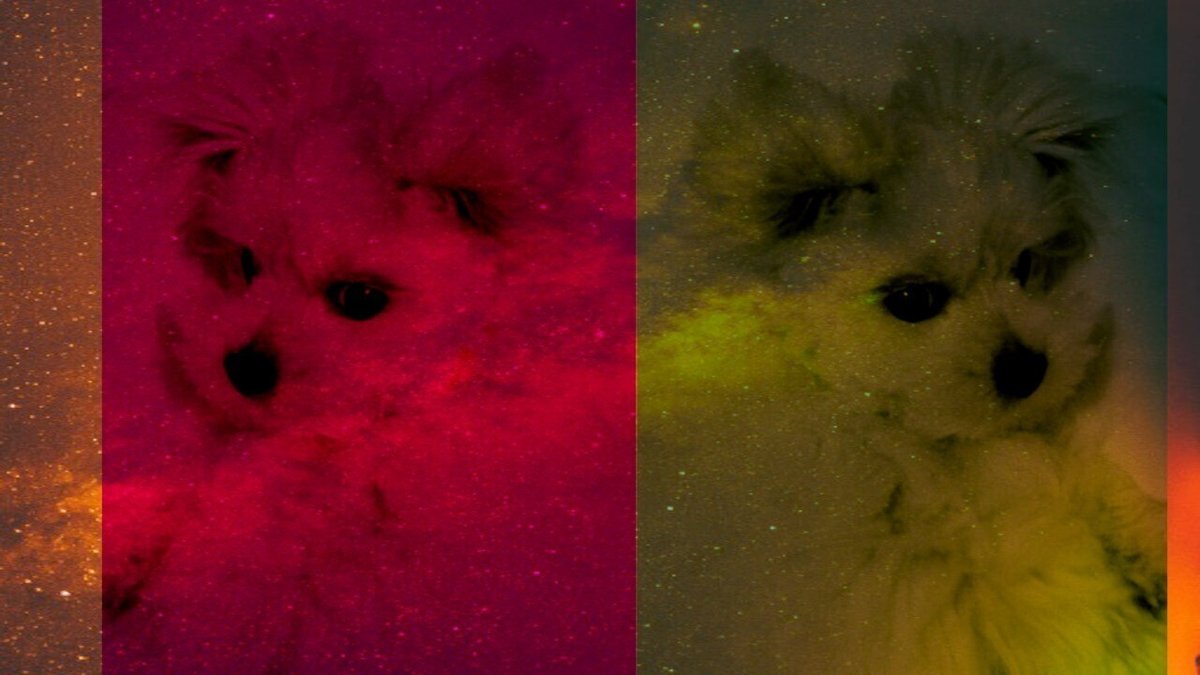
©2022TSURUOMUKAWA
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
