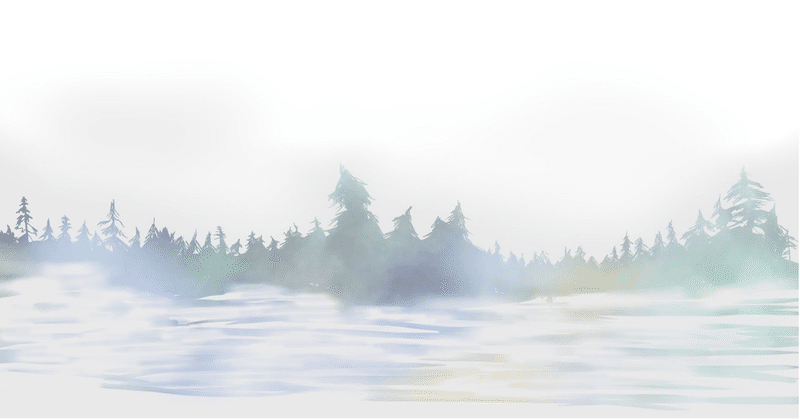
私に格差を語る資格があるか
ジェンダー学を学んでいると、ジェンダーだけでなく、国・地域、人種、階級、経済状況など、ありとあらゆる権力構造の結果として虐げられている人々のストーリーを垣間見ることになります。毎週毎週、授業の準備として課題文献を読むだけで、それまで思いを馳せたことすらなかった不正義を目の前に突きつけられます。その度に、この社会、格差、差別について何か言う資格があるのかと、苦しくならずにはいられません。こんなにも不正義に満ちているこの世の中のほんの片隅で、ぬくぬくと既得権益に包まれて生きている私に、社会について意見する資格があるのかと。
今月だけでも、ロシアによる侵略・占領地域で戦っていたウクライナの女性兵士のドキュメンタリーを見たり、リプロダクティブ・ヘルスに関する国際的取り組みの動向や、国連PKOに派遣されている女性ピースキーパー、気候変動で不均衡に影響を受ける女性やジェンダー・マイノリティについて読んだりしました。そのどれもが、私が想像できる社会環境からはあまりにもかけ離れていて、だからこそこうして学ぶことに意味があるとは分かりつつ、シャボン玉の中から違う世界を覗いているような圧倒的な距離と心もとなさと、無力感に苛まれずにはいられません。日本という経済的・物質的に非常に発達した国の、しかも東京で、「日本人」らしい名前と見た目の両親から生まれ、経済的余裕があり家族仲も良く、自分のジェンダーに違和感を持つこともなく育ち、東大を出て安定した職があり、私のキャリアをサポートしてくれる夫と親族がいて、今はロンドンで勉強している——これだけ恵まれているということを負い目に感じずにはいられないのです。白人の偽善的な自意識の高さが押し付けがましい'white guilt'として批判されるのも重々分かっている一方で、どういう態度で臨めばいいのかどうしても悩んでしまいます。
ジェンダー学の領域では、'Othering'と'appropriation'というのが不適切な態度の両極としてしばしば批判されます。'Othering'とは、あるグループの人々や社会・文化を「我々」として想像される側の対極におき、相容れない「他者 / Other」として疎外・理解を放棄すること。逆に'appropriation'とは、他人の状況や苦しみの一部を切り取って自分のものかのように「代弁」すること。どちらも紙の上で批判するのは簡単ですが、現実で気をつけようとするととても難しいのです。自分が恵まれていると自覚して「自分より恵まれない」誰かのために何かしようとすることはすぐに'Othering'や植民地主義的な「救済者 / saviour」のロジックだと言われかねませんし、どこかの誰かの苦しみを「自分も共感できる」と発信することは文脈の特殊性を無視した'appropriation'だと言われるかもしれません。じゃあどうすれば…?という気持ちになります。論文であれば、「理解しようと努める」だとか「寄り添う」だとかもっともらしい正解が語られますが、実際のところ、私たち一人ひとりは不完全な想像力とアナログな感情を持って特定の環境で生きている人間であり、そんな紙一重の適切と不適切の間を縫って感じることなんてできない気がしてしまうのです。見聞きしてすごく遠く感じてしまうストーリーの中に「それは分かる」「共感できる」と思える部分があって、その間を行ったり来たりしながら少しでも近づこうとする、そんなイメージです。
こんな雲を掴むような感覚で勉強しているので、発言するのはとても怖いです。私に見えていない部分があって、又はもっとひどい場合には潜在的な差別意識があって、気づかずに無神経なことを言ってしまうのではないか、不適切さを露呈してしまうのではないかといつも怯えています。教室は間違えを許す場とは言いますが、数学の問題や法律の解釈を間違えるのとは訳が違うと思ってしまうのです。自身がセクシュアル・マイノリティであったりトラウマを抱えていたり、人権状況が格段に悪い国から来ていたり、コースメイトたちにはジェンダーを学ぶ私よりも立派な理由があって、堂々と語る資格があるような気がしてしまうのです。不平等について語るのは誰が「より虐げられているか」の競争ではないし、あらゆる不正義の当事者である人も、全てにおいて特権者側である人もいないというのは分かっているのだけれど。だから、誰もが自分の悩みを語っていいし、他者の苦しみも理解しようとする権利と責任があると思うのだけれど。
ジェンダーを学ぶと後戻りはできない、というのはコースの初めに冗談混じりで言われたことですが、ジェンダーに限らず格差・差別について学ぶと、社会を分かっている気でいられた頃には戻れないなと思います。知れば知るほど、自分が何も知らない、小さなバブルの中で生きていることを思い知らされて、自分の感情にも視野にも意見にも自信が持てなくなっている気がします。それでも究極的には、少しでも「善い」人間に近づきたいと思って続けているのかもしれません——何が「善い」かなんて分からないのだけれど。直接仕事に結びつくとも思えないのに、なんで日々こんなに感情を揺さぶられながら真面目に勉強したり書いたりしているのかと自分で嗤いたくなる日もありますが、逆に言えば、これまで色々と勉強してきた何よりも本当の意味で学んでいるのかもしれません。中高、大学、一つ目の修士、どれよりも、私の頭に打撃をくらわせてくれています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
