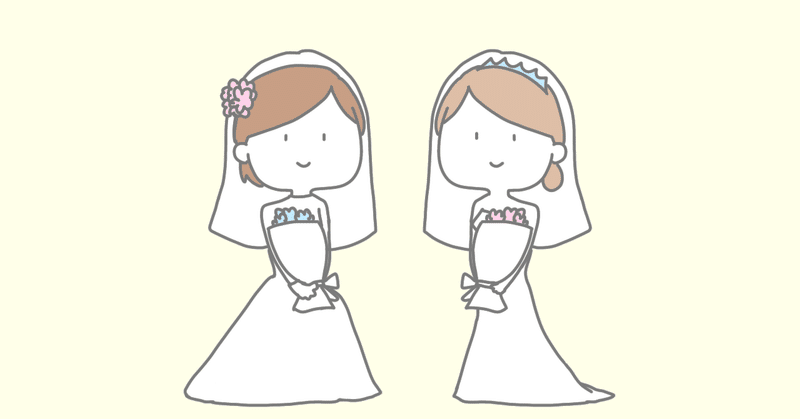
「同性婚」議論から考える結婚・家族制度の限界
首相秘書官がジェンダー・マイノリティに関する差別発言をしたというニュースを聞いて、日本の政治界はやはりまだそんなレベルなのかと気分が暗くなりました。その世代には、心の中で差別意識を持っている人がまだ多いかもしれないということは想像できますが、首相秘書官という立場にある人が、記者の前でそういった発言をしても問題ないと一瞬でも思えたという環境の閉塞さが何よりも信じ難いです。きっと、彼個人が周りと掛け離れた古い思想を持っているということではなく、秘書官室であれ国会であれ、日頃いる環境において差別を容認する空気があるのではないかと思ってしまいます。セクハラも、その他様々な差別発言・行為も、社会や組織として暗に許容する/真剣に咎めない姿勢が残っているからこそここまで蔓延しているのではないでしょうか。
直近の話題から始めましたが、同性婚について早く制度改正が進めばいいと思うと同時に、そもそも「結婚」という制度が真にインクルーシブなものになり得るのか、ジェンダーを学ぶ中で考えていることを書きたいと思います。
「Monogamyなの?」という質問
修士を始めた当初、コースメイトと自己紹介をし合ったりしながら話していた時です。私が結婚していると言うと、一人から、「それはmonogamyなの?」と聞かれました。当時 'monogamy' という単語を知らなかった私は別の人に意味を説明してもらう羽目になったのですが、'monogamy' は 'polygamy(複婚制、一夫多妻制又は一妻多夫制)' の反対で「一夫一婦制」という意味です。結婚していると言ってそれが一対一の関係なのかを聞かれたことはかつてなかったため、心の中で衝撃を受けたのですが、確かに世界的には(大抵一妻多夫ではなく)一夫多妻制が普通に存在している国も多くありますし、カップルと言っても 'open relationship' としてその他の人との性的関係を排除していない場合もあるので、的外れな質問ではないようです。「結婚とは異性間の関係であるべき」と同じように「一対一であるべき」という先入観を取り除けば、結婚と一口に言ってもそれが誰と誰のどういう関係なのかは聞かなければ分からないことになります。
「結婚は子どもを持つため」という幻想
同性婚に反対する人の中には、「婚姻した二人とは、その二人で子を成せる組み合わせであるべき」という価値観が残っているように思います。しかし、異性間カップルであっても、子どもを持つつもりがなかったり持てなかったり、DNA的には違う相手との子どもを連れての結婚だったり、養子や里子を迎えていたりと、生物学的に二人の間でできた子どもがいない例はいくらでもあります。人工授精の技術が進んでいる現在、精子バンクや代理母といった可能性も排除されませんし、生殖年齢を過ぎてからの結婚だって可能です。その上、「友情結婚」という言葉が聞かれるように、異性同士であれば別に恋愛関係になくても婚姻できます。こういった現状において、同性婚にまともに反対できる理由などないと私は思うのですが、それでは、重婚や近親相姦の禁止は正当な理由を保持できるのでしょうか?
近親相姦の禁止については子どもを持った場合に先天性障害が生じやすいからだと言われますが、遺伝性の病気を抱えている人だって子どもを持てますし、出生前診断で胎児に障害が見つかって、それを分かって産む方も大勢います。障害を持って生まれる子どもが悪いわけでは全くないのに、その確率が高くなるから親等が近すぎる人は結婚できないというのは差別的に取れますし、親等が近いからDNA的に近いとも限らず、そもそも二人で子どもを持つつもりはないというカップルだってあり得ます。
より根幹に関わると思うのは、重婚・複婚についてです。日本で一夫一婦制を当たり前のものと捉えていると、複婚と聞くと直感的に不誠実な気がしてしまいますが、特別な人は一人でなければいけないという掟はあるのでしょうか?伝統的な一夫多妻制だけでなく、'open relationship' や「友情結婚」というものまで生まれている時代、全員の合意の上で三人や四人で家族を形成することだって理論上可能な気がしてしまうのです。親友は一人とは限らず、親が離婚・再婚したり養子・里子になったりしていれば父親が二人、母親が二人いる場合だってあるのに、人生を共にする(という想定の)特別な相手は絶対に一人でなければいけないのでしょうか。日本での婚姻は、婚姻届にサインをし、誰でもいいので証人として二人からサインを貰えば成立するものです。宗教的なものでなくても結婚の儀式(シビル・マリッジと呼ばれます)をしなければならないイギリスなどの国と異なり、何の誓いも立てる必要はありません。「愛している」と宣言することなど求められないのに、戸籍上の「男」と「女」の一対一であれば婚姻できるというこの制度は何なのでしょうか。
それは果たして「結婚」である必要があるのか
外国人が配偶者としての在留資格を得る目的で行うとして取り沙汰されることのある「偽装結婚」は法的に罰され得る犯罪です。ですが、日本人同士で互いが了承していれば、恋愛感情がなかろうと、長年別居状態であろうと、単身赴任等で一年に一度しか会えない状況であろうと、行政や司法が介入してくることは考えにくいでしょう。法的な意味での婚姻とは、究極的に、戸籍上一つの世帯を形成し、世帯として扱われるということ以上ではありません。それにも関わらず、日本社会ではいまだに「結婚」することへの圧力が強く、セクシュアル・マイノリティであることを含む様々な事情から「友情結婚」を希望する理由の主なものの一つもそういった社会圧力であるようです。純粋に人生の一期間を共にすることを望むだけであればあえて婚姻という法的契約を結ぶ(そして改姓という非常に面倒な手続きを踏む)必要は本来ないはずなのに、私たちがここまで「結婚」という形を求めるのはなぜなのでしょうか。
価値観が多様化し、結婚しないという選択だけでなく多様な結婚のあり方が受け入れられるようになってきている今、「結婚」という形式だけが一人歩きして崇拝され、実態はとても歪んだものになってきている気がしてならないのです。本気で婚姻の「真正さ」を問うと言うなら、利益の一致で結婚した二人や愛の冷めた夫婦より、「結婚」を認められない同性カップルの方がよっぽど「真正」なのではないか?性的・恋愛関係に限らず大切に思っていれば/助け合っていれば/共に生活していればいいと言うなら、三人の親友が家族になってもいいのではないか?そうして三人親がいる状態で子どもを育てて何が問題なのか?そんなことを考えていると、この「結婚」というものは果たして何なのだろうという疑問に戻ってきます。
「結婚した」と言えば祝われ、会社でも「家庭」に一定の配慮をされ、「既婚者」だから節度が保証されているかのような扱いを受け、私もそういった恩恵に胡座をかいている一人なのですが、実際のところ紙一枚と付随する手続きだけなんです。法律や制度というのは公的な認証・認定の側面があるので、同性婚が認められるべき理由はその「公的なお墨付き」という部分にあると思いますが、この「結婚」という仕組みの定義を拡大していくことが社会の目指すべき方向なのかは正直よく分かりません。結局のところ、婚姻・世帯という制度は国家が国民を管理し、その母体の肉体的・精神的再生産を効率よく保証するために確立した制度であり、歴史を遡れば、娘や姉妹を「家」の間で交換することで血縁関係を広げ、争いを防ぎ勢力を拡大していったシステムだという学説もあります。そういった人工的な社会構築物であることを踏まえれば、むしろこの国家に都合の良い関係性だけが行政上・金銭上優遇される「結婚」という仕組みを問い直し、その過度な信奉を捨てていくべきではないか。性別や人数に関わらず誰もが大切な人と人生を共にし、一人を楽しむという選択も尊重され、そのことを堂々と話せる社会を目指さなければ、本当の意味でインクルーシブだとは言えないのではないか。今の日本社会はそんな理想よりは何十歩も手前なので、まずはこの機に同性婚を巡る議論が進めばいいと思いますが、突き詰めていくとこの「結婚」という概念がひどく不安定なものに見えてくるということも書き残しておきたいと思います。
関連記事はこちら↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
