
海洋プラスチック汚染
最近、「海洋プラスチック汚染」という本を読みました。
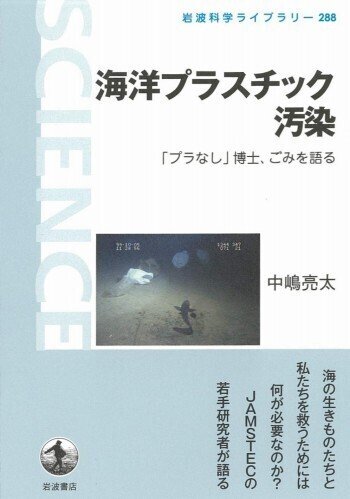
読みやすく、概要をつかむには良い本だと思います。
以下、読書メモと感想まで。
使い捨て文化――大量生産と大量廃棄
プラスチックの生産量は爆発的に増えている。1人あたりのプラスチックごみの量は米国が1位で日本が2位。その用途は大半が食品容器や包装等、一度きりの使い捨て用である。
プラスチックの91%はリサイクルされていない。その理由としてコストや品質低下の問題がある。そのため、繊維化して衣服用の中綿等に用いている(ダウンサイクル)。
日本のリサイクル率は82%とされるが、そのうちの67%はゴミ焼却炉で焼却し、生じた熱を火力発電等に利用することで、リサイクルとしてカウントしている。残りの25%が実際のリサイクルであるが、そのうちの約7割は海外に輸出し、輸出先でリサイクルされている。
輸出先は主に中国であったが、中国自身のプラスチック排出量が増えたこともあり、2018年に輸入停止。これを受け、東南アジアに輸出するも対応しきれず、自国内での滞留が増加している。ヨーロッパでプラスチックフリー政策が進展し始めたのも、中国の受入停止の影響が大きい。
海に漏れ出すプラスチック
毎年、世界で東京スカイツリー250個分の重さのプラスチックが回収されずに海に漏れ出している。流出量は中国を筆頭にして、アジアやアフリカの途上国が多い。
海に漏れ出す要因は(1)不適切な管理、(2)ポイ捨て、(3)不本意な流出の3パターン。(1)はゴミ回収時の散乱等、(2)は海や川等でのタバコや食品包装のポイ捨てや漁具の故意の投棄、(3)はタイヤや靴の磨耗、農業用具や漁業用具の紛失・劣化等。
海に流れ込んだプラスチックは蓄積し続け、2050年には魚の量を上回るとも予測されている。プラスチックは太陽光の紫外線や熱によって劣化・分解され、マイクロプラスチック化していく。
材質によって密度が異なり、海に浮くケースと沈むケースがある。沈む場合は海底に蓄積されるが、浮く場合は海流に乗って遠くまで運ばれる。世界には五つの大きな海流の渦があり、その渦の流れに乗って渦の中央部へと運ばれる。渦の中央で海水は沈むがプラスチックは浮いたまま滞留していく。
対策
海に流れ込んだプラスチックを人為的に除去するには莫大なコストがかかり、事実上不可能である。結局、排出を減らすしかない。
医療系は使い捨てにせざるを得ないが、食品・包装系はリユース等が試みられている。また、バイオプラスチックも研究されているが、バイオプラスチックと言っても生分解性のものと非分解性のものがある。また、生分解性と言ってもコンポストのような高温環境が必要で、海洋では分解されにくいプラスチックもある。
消えたプラスチック
これまで海に漏れ出たプラスチックの総計は約1億5000万トン。そのうちの4500万トンが外洋に流出したと推計されている。しかし実際に海上を観測してみると、流出したはずのプラスチックがほとんど見当たらない(実際に観測された量は、予測値の1%に満たない)。
その理由は明らかになっていないが、深海底から大量のプラスチックが検出されたため、微生物が洋上のプラスチックを体内に取り込む等して、マリンスノーとなって海底まで運んでいるという説も出てきている。

感想
マリンスノーの話を聞くと、ナウシカの腐海の話が思い出されます。人間の相知らぬところで、人間が好き勝手したのを尻拭いしてくれている。
日本という国は他国と比較しても、とても清潔で豊かです。
スーパーやコンビニには食材が個包装されて並んでおり、100円ショップには「これが100円?」と驚くような商品があふれています。
そういった清潔で豊かな暮らしが維持されているのを見て、「日本は素晴らしい国だ」「日本人の国民性は優れている」と思うかもしれません。
しかしそれは、地球と地球の生物たちによって支えられている生活だとも言えます。
そのことへの感謝を忘れてはいないだろうか。
また、日本人の丁寧さや潔癖さは、時に行き過ぎてはいないだろうか。それは誰かのためではなく、自分を守りたいという思いから来てはいないか。
そのようなことを考えさせられます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
