
グラーブ・ジャームン【3】 インド各地の菓子
インド食器屋「アジアハンター」の店主・小林真樹さんが、食器買い付けの旅や国内の専門店巡りで出会った美味しい料理、お店、そしてインドの食文化をご紹介します。
前回まではコーヤーとチェナーという乳脂肪由来のインド菓子についてご紹介したが、もちろん乳脂肪以外の素材を使った菓子もまたインド全土には存在する。今回はさまざまな素材で作られる、インド各地の菓子をご紹介していきたい。
まず「ジャレビー」。水で練って寝かせたマイダー(精白した小麦粉)を小さな穴の開いた布に入れ、油の中に細く絞り出すように揚げていく。ト音記号のような形状に揚がったら、どっぷりとシロップに漬け込んで完成。露店でよく見かけるポピュラーな菓子である。一見いかにもインド固有の菓子のように思えるが、あにはからんや語源はペルシア語の「ズールビア」で、インド化してジャレビーとなった外来の菓子である。ちなみにナーンやモモ、後述のハルワーなど、基本的にインドで見かけるマイダーを使った料理や菓子は外来のものが多い。

私のデリーの常宿のすぐ脇に、行きつけのジャレビー屋がある。朝8時半ぐらいになると店主がちょうど揚げたてのジャレビーをシロップにつけ込んでいる。揚げ物は揚げたてに限る。その時間帯を見計らって買いに行くと、手で持てないほど熱々のジャレビーが食べられる。ちなみに同店のジャレビーは中年男性の中指ほどの太さがある。店によってジャレビーの太さはまちまちだが、ある程度の太さがなければジャレビーがシロップを十分に吸わない、というのが私の持論で、カリッとした表面と中からドパッとしみ出るシロップのコンビネーションこそジャレビーの醍醐味だと思っている。このジャレビーを単体ではなく、揚げパンであるプーリーと合わせる食べ方が北インドやネパールで存在するが、摂取カロリーでいえば「甘さ世界一」と喧伝されるグラーブ・ジャームンをはるかに凌駕する。
小麦粉を原料とする菓子にはほかに「ハルワー」がある。ただしこのハルワー、地域によって著しく形状・材料が異なる。そもそもハルワーもまたペルシア発祥で、さまざまな経路でインドに伝わるうちに、どう見ても同じ菓子とは思えないものを幅広く包括する呼び名となった。
そのうち、今も北インド全域で広く食べられているのがスージー(セモリナ粉)を主原料にしたハルワーである。かなり古くから存在していた菓子だという記録があることから、もともと別の名称の菓子だったものが、ハルワーが伝わったことによって名称だけ「ハルワー化」したのかもしれない。そういう意味ではビリヤニときわめてよく似ている。なお、スィク教寺院で参詣後に配られる「カーラー・プラシャード」は同じ小麦粉でもスージーではなく、アーター(全粒粉)で作られるハルワーである。ハルワーはまた朝食としてプーリーと合わせることも多く、「プーリー・ハルワー」でワンワードになっている。

マイダーを使って作るハルワーも、味や製法は同じなのに食べられている地域によって「ボンベイ・ハルワー」、「カラーチー(カラチ)ハルワー」、「ケーララ・ハルワー」などさまざまな呼称がある。食感は名古屋名物ういろうを彷彿とさせる、甘くてネチっこいテクスチャー。ところどころ入っているナッツやドライフルーツがアクセントになる。基本的にグラムいくらで量り売りされていて、ケーララでは店頭に数キロ単位で山盛りにされている。唾液の分泌が抑えられない光景だ。ちなみにタミル・ナードゥ州タンジャウールには、このハルワーにミクスチャー(塩スナック菓子)を振りかけて食べる習慣がある。ハルワーの強烈な甘さが塩スナックでよりブーストされる、甘いものを知り抜いた人たちの食べ方だ。

「マイソール・パク」は南インドを代表する銘菓である。ベスン粉をベースにした、サクサクとした食感が持ち味。投入するギーの量でノーマルタイプと、よりオイリーさを増した「ギー・マイソール・パク」とがある。使用している食材はベスン粉と砂糖、ギーというたった3種。このきわめて単純な素材から、ここまでなめらかな食感とエレガントな後味を与えられることに驚く一品。大量のギーが含まれているのに不思議としつこさがなく、パクパク食べられる。ちなみに多くのインド菓子と異なり、マイソール・パクは発祥の店が同定されている。その名の通りマイソール(現マイスール)で独立前から続く由緒正しい老舗店グル・スイートマートがその店で、現在三代目店主が日々忙しく店頭に立っている。

インドの団子と称するにふさわしい「ラッドゥー」もまたハルワーのように、素材や製法により複数の種類を持つ菓子。ただしこちらはインド発祥である。「ブーンディー・ラッドゥー(ベスン粉の揚げ玉を丸めた団子)」「ベスン・ラッドゥー(ベスン粉の生地を丸めた団子)」「ココナッツ・ラッドゥー」などが有名で、積み上げるときれいな山状となって供物としてのビジュアルに優れているからか、ヒンドゥー神格との関係性が深い。ガネーシャ神が好む話はよく知られているが、ほかにもクリシュナ神も好むとされ、生誕祭(ジャンマー・アシュタミー)には山積みのラッドゥーが献上される。またベンガルでは、サンクランティの日(冬至)にゴマをまぶした「ティール・ラッドゥー」を食べるならわしがある。

ベンガルの甘味で忘れられないのがミシュティ・ドイである。ドイとはヨーグルトのことで、甘味の中に感じる程よい酸味は、甘味一辺倒のほかのベンガル菓子に比べ程よいアクセントになる。とりわけ素焼きの器の中で熟成された、グルを多用して甘味付けした老舗店のミシュティ・ドイは数日間、余韻を楽しめるほど。赤味(キャラメル色)を帯びるまでミルクを加熱して作るミシュティ・ドイはラール・ドイ(「赤いヨーグルト」の意味)とも呼ばれ、西ベンガル州ナヴァドヴィーパが発祥とされる。ラール・ドイだけを求めて、コルカタからナヴァドヴィーパまで鉄道で約2時間揺られてみるのも悪くない。

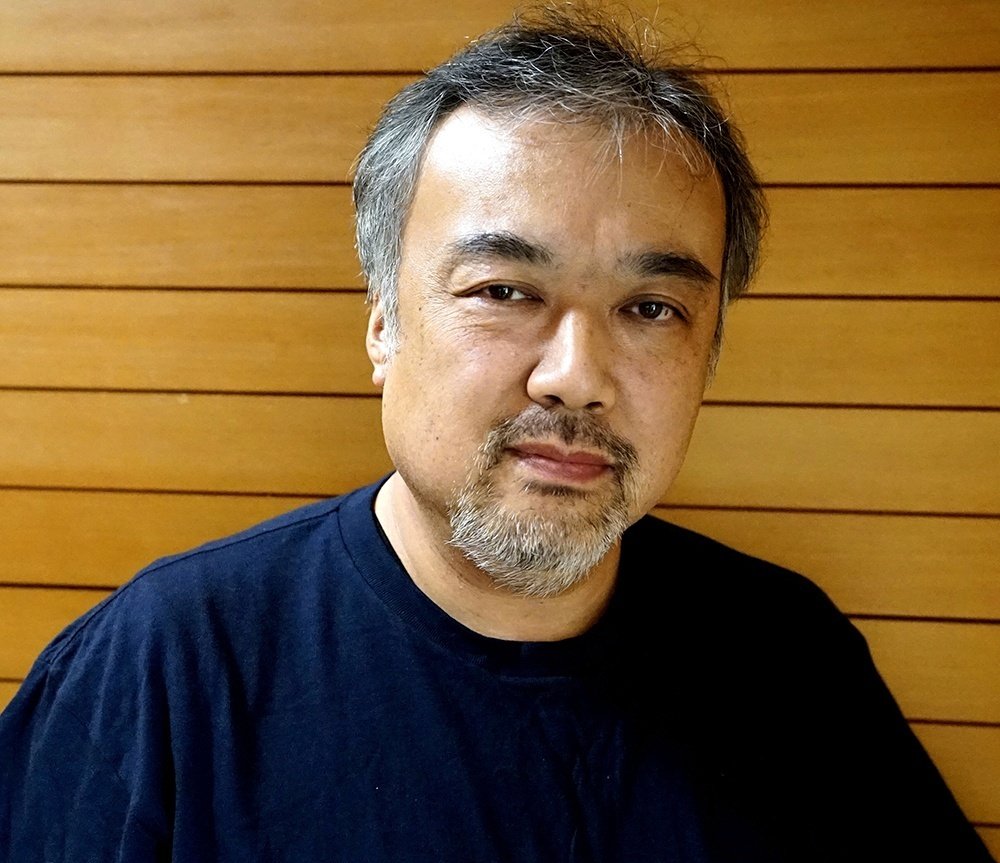
小林真樹
インド料理をこよなく愛する元バックパッカーであり、インド食器・調理器具の輸入卸業を主体とする有限会社アジアハンター代表。買い付けの旅も含め、インド渡航は数えきれない。商売を通じて国内のインド料理店とも深く関わる。
著作『食べ歩くインド(北・東編/南・西編)』旅行人『日本のインド・ネパール料理店』阿佐ヶ谷書院
アジアハンター
http://www.asiahunter.com
「インド食器屋のインド料理旅」をまとめて読みたい方はこちら↓
