
面白い本・好きな本|音楽と建築の進化史[ロマネスク、ゴシック、ルネッサンス、バロック、そして現代へ]
THE FIRST TAKEと日本建築って似てる。
THE FIRST TAKEは『一発撮りで、音楽と向き合う』をコンセプトにした音楽のYoutubeチャンネルで、、という説明が不要なほど有名なやつ。
その瞬間でしか味わえない緊張感
余白によって「間」をデザインする
ディテールを捉え、魅力を際立たせる
高音質と高画質
静謐、余白の美、ディテール、本物。
THE FIRST TAKEの特徴を挙げていくと、日本建築の特徴と実は同じでは?という気づき。音楽と建築のいい関係。
刻々と変化する自然を取り込み、
侘び寂びを追求した余白の美。
“手仕事や素材”の魅力を活かし、
静謐で凛とした本物の空間。
ということで、音楽と建築の歴史を、太古の昔から現代まで、大きな流れで振り返ってみるのもいいのでは、という話。
***
旧石器時代、古代ギリシャまでは遥か昔のことだけど、それ以降は300年の大きな流れで、音楽と建築が進化しているという“持論”。かなりざっくりとした年表ではあるけれど、これくらいが覚えやすくてちょうどいい。
6、9、12、15、18、21世紀。
3世紀ごとに変わりゆく音楽と建築の
アンサンブルとクロニクル。
旧石器時代|古代の洞窟壁画
音楽は洞窟で行われる儀式。音霊や言霊。

神の声を聴くことと、音楽を聴くことは同義。ミュージックの語源が聖なる女神(ムーサ)からきていることからも頷ける。
世界最古の楽器は4万年前の洞窟で見つかったマンモスの骨でつくられた笛。そこには壁画もあり、洞窟の中で最も音が響くポイントだったと。
BC 6世紀|ギリシャ
音楽は芸術で、科学。世界は数でできている。

弦の響きの美しさの背後に整数比が隠れていることを見つけたピタゴラス。音階の発見。オルガンを発明したのもギリシャ人。
音楽は円形劇場で楽しむ芸術。劇場の構造は、どの席からでも音がよく聞こえるように計算されたすり鉢状の円形劇場。
AD 6世紀|ローマ・カトリック
中世の教会音楽であり、クラシック音楽の源流

単旋律聖歌(モノフォニー)で、グレゴリオ聖歌とも呼ばれる。伴奏もなく、人間の記憶に頼って伝承される音楽。
グレゴリオ聖歌の名は、実質的な最初のローマ教皇であるグレゴリウス1世が、各地で歌われていた聖歌を1つに編纂した伝説に由来する。
AD 9世紀|ロマネスク
立体的で厚みのある音、彫刻的な修道院の美しさ

ハモりの源流であるオルガヌムの発見で聖歌がより豊かに。音の高低を表現する楽譜も発明される。
陰影と素材による、彫刻的で立体的な建築的美しさと、折り重なり厚みのある音楽の響きが、宗教的メッセージを音楽と建築で体現する。
AD 12世紀|ゴシック
大空間に反響する音楽と、多彩な光に包まれる

コードや和音が発明され、音楽はより重層的になる。楽譜ではリズムやテンポの表現も確立される。
ステンドグラスの彩り豊かな光が、ゴシック建築の大空間を包み込む。多彩な音色の宗教音楽が、石の反響で空間を満たす。
AD 15世紀|ルネッサンス
神から民衆の音楽へ。印刷の発明がすべて変える

神に捧げる音楽から民衆の音楽へ。数学的秩序が音楽や建築の美しさを規定する。
印刷の発明で、音楽が楽譜として広く普及して歌詞への関心が高まる。楽譜や図面の印刷が音楽家や建築家という概念を生み出す。
AD 18世紀|バロック
器楽と声楽の分離、音楽ビジネスの始まり

クラシック音楽とオペラの誕生。バッハ、モーツアルトの時代。豪華絢爛な宮廷や劇場で、貴族が楽しむエンターテインメント。
器楽と声楽の分離と自立。楽譜出版など、音楽ビジネスの構築も始まる。オペラと歌舞伎は同時代に生まれた音楽劇として類似性多数あり。
AD 21世紀|現代
録音による革命。音楽と建築が空間的に分離する

演奏家と聞き手が空間を共有する音楽体験が、レコードから始まる音楽メディアの登場で、時間的・空間的に分離する。
そして、ついに音楽はデジタル空間へ。
18世紀の音楽は今でいうクラシック音楽として芸術性を追求し、オペラは大衆音楽へと進化を遂げ世界に広がる。
300年後の24世紀、音楽と建築はどうなるか?
参考文献
138億年の音楽史|2016
「ビッグ・バン」からビートルズまで。すべての歴史を描きつくす。
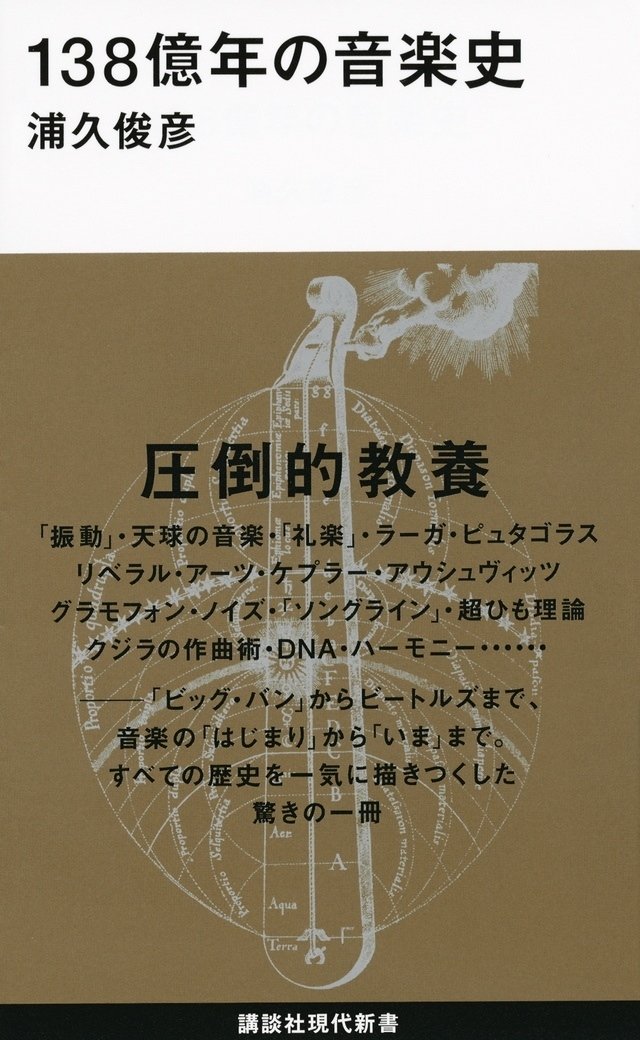
「われわれは、どんな過去にさかのぼっても音楽に出会う」。ビッグバンから始まった「宇宙の音楽」の歴史では、ベートーヴェンもビートルズもちっぽけな砂の一粒に過ぎない。「音」と「調和(ハーモニー)」をキーワードに壮大なスケールで描く、これまでにないユニークな書。
音楽の進化史|2014
旧石器時代から現代に至る4万年の音楽史を一望する決定版。

音楽はなぜ、どのようにより豊かで多様なものへと変化したのか? 楽器や楽譜、音階や和音の発明など、作曲家である著者が、旧石器時代から現代に至る4万年の音楽史を一望する決定版!
西洋音楽史|2005
「クラシック音楽」と、その前後の音楽状況をまとめた音楽史

18世紀後半から20世紀前半にいたる西洋音楽史は、芸術音楽と娯楽音楽の分裂のプロセスであった。この時期の音楽が一般に「クラシック音楽」と呼ばれている。音楽史という大河を一望のもとに眺めわたす。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
